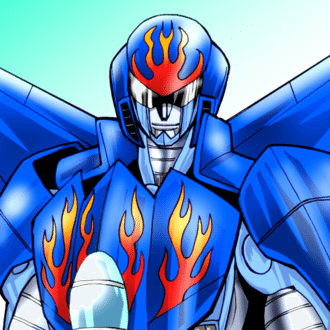ゆびさし夢子さん【事故】
バーのマスターがカウンターの壁際で縮こまっている青年を指さした。
「あいつなんですが」
マスターはかすれた、しかし魅力的な低い声で僕たちにささやいた。雰囲気を察したのか、青年がこちらを横目で見る。
「親戚の子供なんですが、昔から悪さばかりしましてね。本人に悪気があるというわけではないんですが、軽薄というか、浅慮というか……トラブルを起こしやすい性質なんです」
夢子さんは無言でうなずきながらピーナッツを一粒食べた。
「それで、この前はバイクでコケまして。運の悪いことに道端にあった慰霊碑を壊したそうなんですよ」
「あ、それ地方版で読みました」
ちょうど先月の地方版の記事を僕は思い出していた。『大学生、戦災慰霊碑壊す』というセンセーショナルな見出しと共に、石碑の基部が少し欠けただけのなんとも迫力にかける写真が載っていたのをよくおぼえている。
「お恥ずかしい話で……。それでなんですがね」
マスターは身を乗り出した。
「それ以来、あいつ、祟られたらしくて」
「祟られた、っていうと?」
夢子さんはグラスのウイスキーをすすり、空のグラスをカウンターに置いた。僕が止める間もなくマスターはウイスキーを注いだ。
「それがですね……」
「お、叔父さん」
青年が苦しそうにマスターを呼んだ。
「ああ、そろそろか」
マスターは2リットルのペットボトルを青年に渡した。ボトルの中身は水だった。青年は並みならぬ様子でキャップを回すと、大きなボトルに口をつけてそのままぐびぐびと飲み始めた。まるで口の中には食道も内臓もなく、ただ重力にしたがって水がこぼれ落ちているだけのようだった。
とうとうボトルは空になった。青年は「ふう」と息をついた。
「マスター……?」僕はマスターの方を見た。
「あれが祟り、らしいです。このぐらいの時間の夜中になると、喉が乾いて乾いて仕方ないそうで。いくらでも水が飲めるそうなんです。こう言っては馬鹿らしいですが、本人としては『死ぬほど苦しい』とか」
「叔父さん、ごめん」
「ああ……」
青年はまたボトルを受け取って飲み始めた。
「それで、私たちにどうにかしてほしいってわけね」
夢子さんはグラスをカウンターに乱暴に置いた。マスターがお代わりを注ごうとしたので僕は手で制した。夢子さんは口をとがらせて抗議したが、無視してマスターの話を聞く。
「あんなふらふらしてるやつでも馴染んだ親戚です。失礼を承知で、なんとかしてやってもらえないですか」
夢子さんはマスターの背後の棚に並ぶ酒瓶を指さした。その先には古ぼけたラベルのマッカランが置いてあった。
「あれを一杯で手を打とう」
青年が壊したという慰霊碑は、件のバーから十五分ほど歩いたところにあった。
空襲の犠牲になった人を悼むためのものだが、そこまで大きくはない。一メートル強といったところか。
見れば、隅のところが少し欠けたのを修復した跡がある。
夢子さんは青年と石碑を交互に見比べながら興味深そうな顔をしていた。
「ははぁ、そういうことね」
「ど、どうしたんですか」
青年がおずおずと尋ねた。手先は細かく震え、顔面は蒼白になっている。
「青年、君は確かに悪い。だが君は悪くない」
「夢子さん、意味わかんないよ」
「だってそうだもん」
夢子さんは青年を指さした。
「青年、ちょっと無理矢理やるから気を確かにね」
「えっ、ど」
どういうことですか、と問う暇もなく、夢子さんは指を青年から離れたところへ水平に勢いよく動かした。
「──う、ぐぶゲッ」
青年はその場に突然うずくまって嘔吐した。粘ついた胃液がアスファルトを叩く音がする。
僕は青年の身体から『もや』のようなものが出ていることに気付いた。その『もや』は夢子さんの指さした場所まで伸びている。そこには輪郭のぼやけた『何か』がいた。
「夢子さん、これが……」
「戦火で犠牲になった人の亡霊……じゃ、ないよ」
「え?」
「こいつはそのへんうろついてただけの霊。戦火の犠牲なんて大層なやつじゃない。普通に生きて普通に死んだくせして、うだうだと成仏せずにとどまって悪さしてる愉快犯。事故って慰霊碑壊しちゃったときの罪悪感に付け込んで憑りついたみたいね」
夢子さんは手をひっくり返して指を手前に曲げる。すると『もや』は夢子さんに吸い寄せられた。『もや』には男とも女ともつかない顔があった。
「で、どう? 楽しかった?」
肯定するように『もや』に軽薄な笑みが浮かぶ。夢子さんもにっこり笑って応えた。
「……クソ野郎」
夢子さんが指を振ると『もや』は虚空に消えた。
「終わったよ、お疲れ様」
夢子さんは青年の肩をぽんぽんと叩いただけで踵を返し、軽い足取りで去っていった。僕は肩を貸して青年が立ち上がるのを助けた。
「大丈夫?」
「は、はい……」
青年はふらふらしていたが脚には力が入っているようだった。一人でも大丈夫だろう。
「ゆ、幽霊、いなくなったんすか?」
「ああ、そうだよ」
「そっすか……」
へへ、と青年は笑った。
「ざまあみろ……」
青年がぽつりとこぼした。口元にはさっきの『もや』のような軽薄な笑みが浮かんでいた。
夢子さんがちらりとこちらを振り返った。
「……うまぁーいっ!」
後日、年代物のマッカランを一口すすった夢子さんは店の雰囲気も考えずに叫んだ。酒の味もさることながら、タダ酒ということがなによりのツマミだろう。
「マスター、その後彼はどう?」
「それがですね……」
マスターの眉が困ったという風に歪む。
「あの異常な喉の渇きはなくなったんですが、まだ何かがいるような気がするそうです。夜中に誰かの気配がしたり、鏡に人影が映ったような気がして振り返っても誰もいないとか……。まあ、あんなことの後ですから、考えすぎてしまってるのかもしれませんが……」
僕は夢子さんを見た。夢子さんはわざとらしく僕から目を逸らしている。
「夢子さん、まさか『やった』?」
「……どうでしょ」
夢子さんはまたマッカランの入ったグラスを傾け、うっとりした顔をした。
「まあ、ちょこっとビビらせる程度のやつだよ。ひと月もすれば消えるって。あの青年もいい薬になるでしょ」
「薬で済まなかったら?」
質問に答える代わりに、夢子さんはグラスを揺らしながらへらへらといやらしく笑った。それは人でない何かの笑顔だった。
いいなと思ったら応援しよう!