
極東書店ニュースNo.733 日本人著者・編者 日本関連テーマ 注目タイトル
極東書店ニュースONLINE、2024年10月15日に新着書誌情報を追加いたしました(No.733)。その中から日本人著者・日本関連テーマの注目タイトルをご紹介いたします。全て予約注文可能です!
*極東書店HPはこちら
*新刊学術洋書情報をお探しなら!会員制サイト「極東書店ニュースONLINE」についてはこちら
*「極東書店ニュース」について知りたい方はこちら
立花幸司編 キリスト教及び儒教の伝統と教育への日本の視点
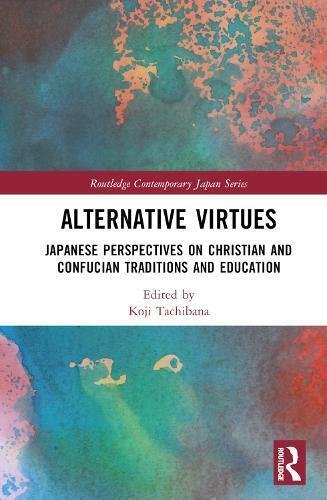
本書は、日本における「徳」Virtue の概念に関する様々な視点を取り入れながら、徳に関する現在の理解を調査・拡大し、徳に対する代替的なアプローチの基礎となる事例を提示するものです。
日本の歴史と文化というフィルターを通して、日本のさまざまな文脈に焦点を当てながら、道徳的美徳と認識的美徳の両方を調査、そのような代替的美徳が私たちの生活にもたらす実践的・教育的な意味合いについて論じています。
大塚啓二郎著 貧困者の経済を変える-農業と産業のための効果的開発戦略

著者は、貧困と飢餓を撲滅するために農業と産業がどのように発展してきたかを詳細に分析し、持続可能な開発目標(SDGs)の第1目標と第2目標を達成する方法に焦点を当てています。
最終的な成功の原動力は、海外からの学びに基づく技術革新と経営革新であり、農家や企業経営者のような主要な意思決定者がイノベーションを促進できるよう、人的資本に投資することが重要であり、これらの国々の生活を支援するための福祉プログラムの利用が変革的な影響をもたらす可能性は低い。だからこそ、農業と工業の発展が貧困削減につながることが実証されていると論じています。
友澤和夫、藤田幸一編 農業経済から工業経済への南アジアの移行-雇用と労働市場

本書は、農業と非農業の成長率格差の拡大、農民と都市住民の所得格差の拡大を伴う、南アジア諸国の農耕経済から工業経済への移行を分析しています。
貿易業者や加工業者を含む農民の闘争に関連する課題や、主に都市部、あるいは海外に出現したより洗練された農産物市場需要に、農業はどのように適応していくかを論じている。そして非農業部門の発展に焦点を当て、グローバル・バリュー・チェーン(GVC)の視点を導入。最後に、農業部門と非農業部門に密接に関連する労働移動と労働市場の動向を分析しています。
藤田典子著 変化する日本における転勤とキャリア管理

「転勤」、つまり日本の文脈における企業移籍は、その強制性と社会への埋没性によって特徴づけることができます。転勤は強制的な慣行であり、労働者に裁量がないことがしばしばです。労働者が共働きかつ小さな子供を抱えているとしたら、このような強制的な雇用慣行とどうやって折り合いをつけていったらいいのでしょうか?
当書籍では、大企業7社の人事部長、既婚のホワイトカラー労働者46人(うち男性6人)への質的インタビューと、いくつかの社会的イベントへの参加観察を通じて、この問いに答えようと試みています。
著者は、転勤の文化的規範性、ジェンダー性は、現代日本企業の資本家の論理とジェンダー化された家族の前提によって生み出され、再生産されているが、職場の多様化やインクルージョンを進めようとする企業もあることも明らかにし、日本で構造的な変化が起こるためには、すべての労働者のキャリア・マネジメントの議論のテーブルに、ケアという本質的な概念を持ち込むべきだと主張しています。
角田美穂子他編 リーガルイノベーション-技術、法曹、社会変化に関する会話

テクノロジーが法曹界と社会の変化に与える影響を探る一冊。
特に人工知能に焦点を当て、紛争解決やコーポレート・ガバナンスから金融サービスや規制監督に至るまで、幅広いトピックをカバーしています。各章は会話形式より成り、学術的な厳密さを保ちつつも親しみやすく読みやすい内容となっています。本書はCambridge Coreのオープンアクセスでもご覧いただけます。
河崎信樹、坂出健他編 米国のヘゲモニー、在外米軍、負担の分担-冷戦中・後の西欧と東アジア

本書は、西ヨーロッパと東アジアの事例を取り上げながら、第二次世界大戦後の米国と同盟国間の負担分担の歴史的展開を検証しています。
本書の寄稿者たちは、一連の事例研究を通じて、米国とその同盟国との間の負担分担関係の特徴と歴史的変容を明らかにし、外交的、安全保障的な懸念に加え、負担分担の経済的、財政的な側面、これらすべての要素がどのように絡み合っているのかにも注目。
1960年代までは西ヨーロッパ諸国がアメリカの政策を経済的・政治的に支援していたのに対し、1970年代以降は東アジア諸国からの経済的支援がより重要になったと論じています。
新井立志他編 社会政治的紛争における機能的共存

本書は、長期的な紛争介入と社会変革のための実践的戦略を構築するための文脈として、「機能的共存」の概念を紹介しています。
「機能的共存」とは、物理的暴力がない中で維持される、相互不認知の実際的な関係です。理論と実証、そしてビジョンと実践の架け橋となる本書は、持続的な紛争介入のための道標を提示、機能的共存の文脈における平和の可能性を示す事例を紹介し、それらの事例に共通する変化の道筋を明らかにしています。
本書の第3章は、クリエイティブ・コモンズ表示-非営利-改変禁止(CC-BY-NC-ND)4.0ライセンスの下、http://www.taylorfrancis.com、ダウンロード可能なオープンアクセスPDFとして自由に利用できます。
藤川健太郎著 紛争後の国民投票と和平プロセス

紛争後の住民投票は、近年和平プロセスの一環として行われることが多くなっています。政策立案者は、こうした住民投票が平和と民主主義に貢献することを期待していますが、住民投票には妥協のメカニズムがないため、特に領土問題に関しては住民投票の利用について大きな懸念を表明している研究文献が大勢を占めます。本書では、こうした住民投票が和平プロセスに与える実際の影響を測定するため、紛争後に中央政府の同意を得て実施された、エリトリア、東ティモール、南スーダンの3つでの住民投票を体系的に比較しています。
この3つのケーススタディを通して、住民投票の背景にあるさまざまな理由を明らかにし、住民投票が当初の紛争の解決に、肯定的ではあるが限定的な役割を果たすことをこの研究書は示しており、国民投票が和平プロセスに与える影響についての慎重、徹底的かつバランスの取れた記述を提供しています。
本書の第1章は、クリエイティブ・コモンズ表示-非営利-改変禁止(CC-BY-NC-ND)4.0ライセンスの下、http://www.taylorfrancis.com、ダウンロード可能なオープンアクセスPDFとして自由に利用できます。
佐野真由子著 江戸城で謁見する西洋外交官のための日本の儀礼 1857~67年

1857年、初代アメリカ総領事タウンゼント・ハリスが徳川13代将軍家定に江戸城で謁見し、日本と西洋諸国との正式な外交関係は幕を開けました。本書は、徳川幕府(1603-1867)がその治世の最後の10年間に行った17の西洋使節の江戸城での謁見を明らかにするものです。その過程で幕府は、自国の伝統に基づくとともに、西洋の慣行とも一致する儀式形式を完成させました。明治維新(1868年)に先立つ、当時の対外最前線における徳川家臣団の努力は、日本の国際社会進出の真の第一歩であったといえるでしょう。外交儀礼の形成は、より政治的な交渉とは別に進行しており、これまでの研究では見過ごされてきた幕末外交の別の視点からの歴史研究となります。
高橋優子著 日本における朝鮮人被爆者救済運動

原爆投下と日本の植民地支配からの解放後、朝鮮人原爆被害者は日本、韓国、北朝鮮に分散し、何十年もの間、救済も救済措置もないまま放置されてきました。
著者は、日本在住の朝鮮人原爆被害者に焦点を当て、彼らがどのように被害の認識と支援を得るために奮闘してきたかを徹底的に検証しています。徹底的な現地調査、資料調査、朝鮮人被害者救済運動の主要人物へのインタビューに基づき、彼らの運動が冷戦、日韓間の未解決の植民地関係、北朝鮮、韓国、日本間の民族主義的緊張、朝鮮半島と在日コリアンの国内分断によっていかに大きな影響を受け、制約を受けてきたかを分析。こうした困難にもかかわらず、在日韓国・朝鮮人核被害者の救済運動は、民族の「統一」という独自の理想と、韓国と日本の市民との共同の努力によって支えられてきたのです。
ご注文、お問合せなど、どうぞお気軽にご連絡ください。
〒101-0061
東京都千代田区神田三崎町2-7-10 帝都三崎町ビル
株式会社極東書店
