
初めてのラブレター
「初恋」とは、人生を彩る特別な一節である。保育園や幼稚園の頃から、それぞれの個性や環境によって異なる形で訪れるものであることを私は信じている。

私の偽初恋は中学二年生の時に始まった。

ささやかなエイプリルフールの冗談とサプライズのつもりで、友人に手紙を書いたのだ。しかし、その冗談が思わぬ展開を迎えることになった。

私は友人に「乙女心」と称する内容を含んだ手紙を書き、彼の下駄箱に忍び込ませた。本来であればすぐに気づかれるはずだったが、友人は手紙を真に受け、私の指示通りに返事を書いて下駄箱に入れ始めた。

私はその手紙を回収し、返事を書いて友人の下駄箱に返した。

友人の恋物語が始まった。

恋は盲目とはよく言ったものだ。

この男同士の文通は次第にエスカレートしていき、私は自分が一学年下の若林という架空の女子であることを装い始めた。

友人は若林という名前の存在を信じて、彼女とのやり取りに熱中していった。

友人は毎日のように若林さんのクラスに顔を出し、彼女にアピールを試みていたが、若林役の私の存在に気づいていた女子たちは彼を不気味に思っていた。

私自身も友人に対して罪悪感を覚えつつ、彼の可哀想さを感じた。
しかし、友人は全く気づかず、ますます熱心に男が読むと甘い、甘すぎて吐き気がするような手紙を書き続けた。

私は友人に対して「気づけアホ」と心の中で思いながらも、最終的にはヘドが出そうな手紙を通じて真実を打ち明けることを決意した。無論、どつかれる覚悟を持って。

しかし、その時には既に手遅れだった。友人は架空の若林さんから「もうやめてくいださい」と拒絶されてしまった。

自滅したのだ。

私は自分の愚かさと、友人に対する過酷な結末に対して、深い罪悪感を抱いた。

後悔もした。吐き気もこれで治る。

この愚かな文通によって、私自身が一番悲しくなった。男同士で嘘の女子役を演じ、架空の吐き気を催す恋の文通をしていたことに対して、私は自分自身の愚かさに嫌気がさした。

ただの時間の浪費と毎回手紙の返事を
書くことに飽き飽きしていた。

思い返せば、こんな馬鹿げたことをしている間に、大切な初恋の瞬間がいつ訪れたのか、私の記憶の中から消えてしまっていた。それが何とも悲しい現実であった。
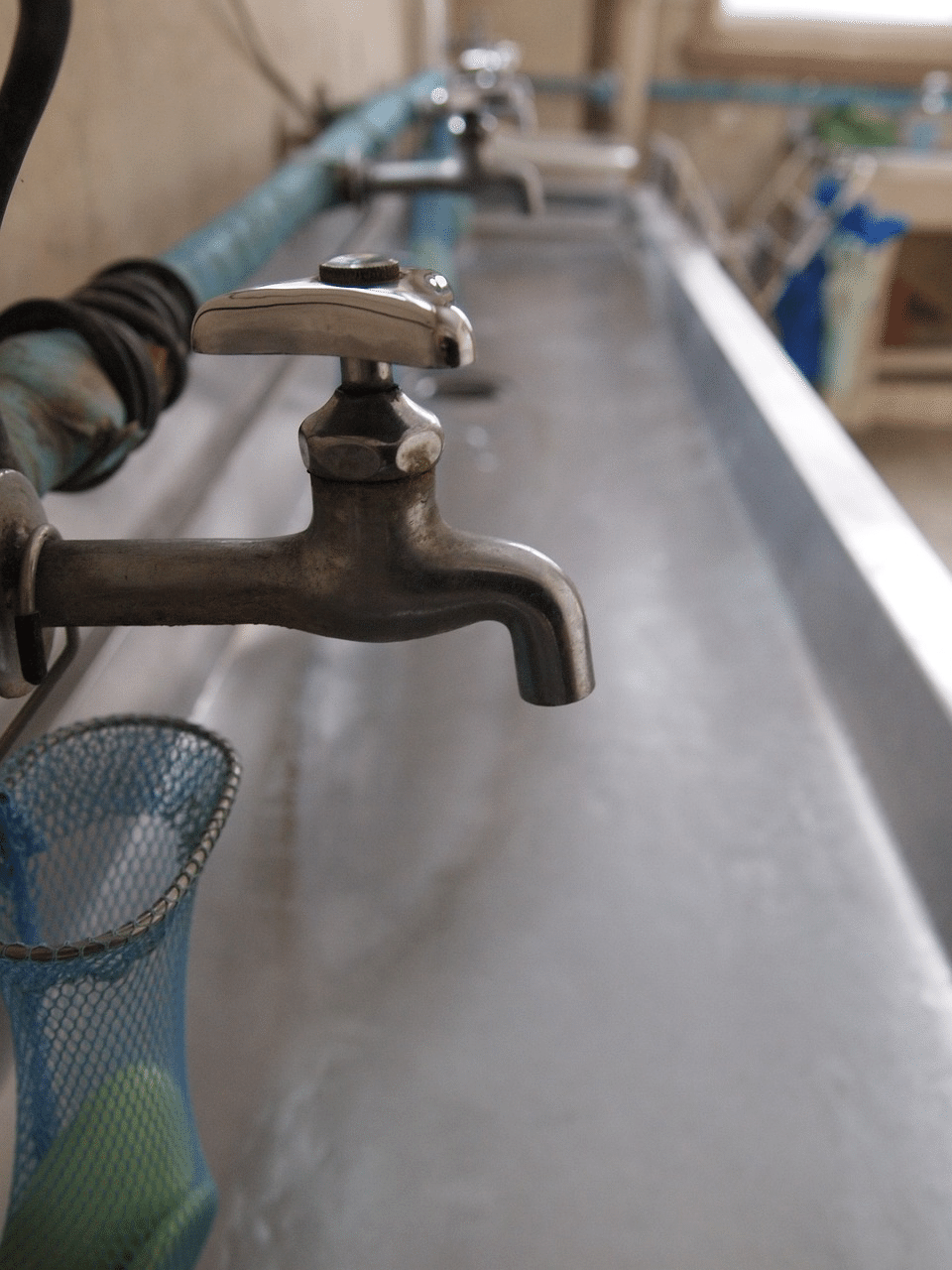
初恋は特別なものであり、真摯な心で迎えたいものだ。私はこの愚かな出来事を教訓とし、将来の初恋に向けて心の準備する決意を固めたのである。

事実を友人には今も伝えていない。

なのに毎年贈られるお中元を申し訳なく受け取っている。

「ごめんね坂下君」
そして「今年もありがとう」

