
田中庸介『モン・サン・ミシェルに行きたいな』を読みたいな
なにを隠そう、ぼくは田中庸介の筆跡フェチである。彼から郵便が届くたびに、封筒の宛名を眺めてうっとりする。それからおもむろに封を切るのだけれど、中身はたいてい詩の雑誌「妃」である。

ついこのあいだも「妃」の最新号が届いた。表紙に「一番高貴な詩の雑誌」と銘打ってある。ここからもう田中庸介の気配が滲み出ている。たしか前の詩集『スウィートな群青の夢』の帯には「当代最高の詩のスピリット!」と銘打っていたっけ。よう言うわ、と思うが嫌味はない。むしろ愉快である。

「妃」(それにしても銀座のバーみたいな名前だな。いったいどこから取ったのだろう)を開くと、まず彼の作品に目がゆく。「一月のコルカタ」というタイトルだ。
朝のドミトリーで目を覚ますと
コロニアル様式の窓の格子に
鳥が来た。
この遠方からのお客は誰であろうかと
窓辺にとっ散らかったスーツケースの中身をのぞいている。
水洗トイレには水のシャワーが欠かさずついて、
大きなバケツと小さな手桶のセット。
何となくトイレットペーパーを二巻き持ってきてほんとによかった。
インドに行っているのだな。詩のイベントだろうか、それとも脳細胞の研究だろうか。詩のなかの時間はそのどちらにも属さないぽっかりとした、エアポケットのような朝のひとときだ。
もう一羽、鳥が来た。
別の場所に止まって、
誘っている。あきらかに、
これは誘っている。
最初の鳥はどうしようか迷う様子だ。
きょときょとと、
落ち着かない雰囲気。部屋の中にも流れてくる。
だがはやり、誘いに負けてしまって最初の鳥も、
追いかけあうようにつつっと離れ、
こみあげてくる一月の、
遠くの空へ飛んでゆくのだ。
自分まで旅先にいる気分になってくる。コルカタは暦の上では一月だけれど、この詩の中の朝はなんとなく日本の初夏を思わせる。そういえば田中庸介の詩にはいつも初夏の風が吹いているような印象があるな。
「一月のコルカタ」は三篇からなっていて、二篇目の「チャイ」には屋台の食べ物が登場する。「ぱらぱらっと炒めた軽い、軽いビリヤーニ」「ベンガルの魚のカレー」「マトンのカレー」。庸介はストリートフードを書くのが上手だ。前の詩集でも美味しそうな食べ物が出てきた記憶がある。なんだっけ?ページから匂いが立ち上って、その途端詩の中の東京がエキゾチックな街に変貌した。そういえば現代詩にはあまり食べ物が出てこない。考えることに忙しすぎて、なにを食べたのかも上の空なのかな。
もっと庸介の詩にのって旅に出て、おいしいストリートフードを食べたいなと思っていたら、その願いが届いたのか、数週間後にふたたび田中庸介の筆跡の踊る茶封筒が届いた。開けてみると、
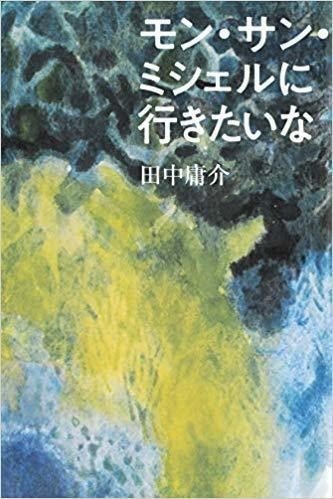
おお、新しい詩集だ。前作はスウィートな群青一色だったが、今度の表紙は青の上に黄色と黒が混ざっている。帯の謳い文句に、
軽く軽く時は流れていく、グランドデザインは変わっていく
このカーブを曲がりながら、詩人は精いっぱいの声を発するのだ
渾身の、10年ぶりの第3詩集!
そうか、あれからもう10年も経ったのか。その足跡を辿るように読んでゆく。そういう読み方の出来る編み方なのだ。
あれから一年が経って
急速に言葉が出なくなる。
夜である
冒頭に置かれた「黙る夜」の書き出し。ぎくりとする。巻末の初出を見ると、「あれから」が3.11のことを指していると察せられる(詩集の第二部へと読み進むと、それだけではないことも分かるのだけれど)。大丈夫かな、と(この詩が書かれたのがもう何年も前だとわかっていても)心配になってくる。さらに行を辿ると、
きらきら星がこぼれる夜に、
駅までいいひとを迎えにいこう。
というフレーズが唐突に出てきて、そうだ、彼結婚したんだっけと思い至る。数年前には赤ちゃんが生まれたっていう報せもあった。でもホッとした途端、次の行は
だが待つ人たちは
モアイのように並び、じーっと黙って
改札口に向き合って立っている。
と不穏な光景のまま断ち切られるように終わっている。
わかい恋人たちは抱擁しながら、
ディアゴナール、
ディアゴナール、
魅力的な地下鉄駅を過ぎ、海の方まで。
夏のバスが走った。
きちんとしたセックスがあった。
でもね。
時は軽く軽く軽く軽く流れた。
それから、
ビキニ、
(ビキニよ。
灰、
「バルセロナ」後半部分
キラキラ輝く若々しい言葉と、苦い喪失感、そして不気味な崩壊の予感が渾然と入り混じっている。うっとりと見惚れながらぼくは嫉妬する。もしもぼくが今中学二年生だったら、この詩を読んで、僕が初めて中也の「春の夕暮」を読んだときのような衝撃を受けるのではないか。
あるいはこうも言える。僕は中也的な叙情に惹かれながらも、それを継承することはできなかった。そうするにはまだ距離が近すぎた。だからもっと「現代的な」(あるいは実験的な)要素を探してきて、抵抗する必要があった。そうでないと自分の詩を書くことができなかったのだ。だが僕よりちょうど10年後にやってきた庸介にそんな韜晦の仕草は見当たらない。彼の詩は日本の近代詩における叙情を正統的に現代に敷衍していると思える。
第二部に入ると、言葉の背後からぬっと詩人の生身が姿を現す。
三月九日に母がなくなりました。
三月十一日に地震がきました。
三月十四日のお通夜と、
三月十五日の告別式との間に、
放射能が東京にきました。
これはほんとの話です。
「叫ぶ芋畑」冒頭部分
そうだったのか、と思う。と同時に、蘇ってくる記憶がある。ぼくは震災のすぐ後に彼と会っているのだ。近代文学館で開かれた、震災への鎮魂をこめた朗読会だった。和合さんもいたし、平田俊子さんもいた。亡くなる少し前の稲葉真弓さんもいらした。
おれ叫ぶから。
叫ぶから。おお、おれは
叫びますから。(大丈夫、大丈夫
ことばがきれないように、こときれないように、
わたしは精いっぱいに
叫ぶ人です。
あの時は知るよしもなかったが、彼はお母さんを亡くした直後だったのか。それにしては元気いっぱいで朗読していた印象が残っているけど…… あれ、ひょっとしてあのとき読んでいたのも畑の詩じゃなかったっけ?もしかしたらこの「叫ぶ芋畑」の詩だったのだろうか。
あれから七年半が経った。その間に彼は結婚して子供も出来た。
娘一歳は地蔵(傍点ふる)に似ている
非常に似ていると評判である
その娘も詩のなかに登場する。当代きっての表現者の磨き抜かれた表現を内側から突き破るようにして、表現者の存在が否応なく押し出されてくる。表現と存在の緊張感みなぎる関係性こそが、この詩集の醍醐味だ。
次に彼の詩集が出るのはいつのことだろう?彼の詩を通して、僕は食べたことのないストリートフードを味わい、行ったことのない初夏のカフェで潮風に吹かれてきた。その実感は自分自身の生の記憶にひけをとらない。それはほとんど奇跡的なことだけれど、同時に詩を読み、また書くことの本質でもあると思う。
どんな恥ずかしいことも
細胞の中で起きている
と言ってみる
だからと言って
決して何の
解決にもならないけれど
ここにある機械は
ここでしか働けないし
そこに持っていったら
こことは違う働きをしてしまう
それを見に行く、
あらゆる手段を使って
見に行くことが
闘いである
「それを見に行く」全篇
