
知らないと大損⁉️退職後、任意継続と国民健康保険のどちらを選ぶべきか?メリット・デメリットを徹底解説
退職後の健康保険の選択肢として「任意継続被保険者制度」と「国民健康保険」がありますが、それぞれには制度設計や保険料計算の違いがあり、退職後の経済状況や家族構成に応じて、どちらがより適しているかが異なります。これらの制度を詳しく比較・分析し、選択の際に考慮すべきポイントをより細かく解説します。
退職後の健康保険の選択肢とは?
退職後、企業が提供していた社会保険の資格を失うため、代わりに他の健康保険制度に加入する必要があります。この際、主な選択肢として挙げられるのが以下の2つです。
1. 任意継続被保険者制度
在職中に加入していた健康保険を一定期間継続することができる制度です。これは、退職した日をもって通常は失効する健康保険の被保険者資格を継続できる特例です。
2. 国民健康保険
すべての市区町村が運営している公的な医療保険制度で、主に自営業者やフリーランス、無職の人を対象にしています。会社を退職し、任意継続を選択しない場合、多くの人が加入する制度です。
この2つは、保険料の計算方法や扶養家族の扱い、加入期間、申請手続きなどに違いがあり、それぞれの詳細なメリットとデメリットを知ったうえで、自分に合った制度を選ぶことが重要です。
任意継続被保険者制度の詳細

任意継続とは?
任意継続被保険者制度は、会社の健康保険組合などに加入していた人が、退職後も一定期間その保険を利用できる制度です。具体的には、退職後でも最長で2年間は在職中と同じ健康保険に継続して加入することが可能です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
• 被保険者期間:退職する前に2ヶ月以上、その健康保険に加入していることが条件です。短期雇用や短期間の派遣社員であっても、この条件を満たしていれば対象となります。
• 申請期限:退職日翌日から20日以内に手続きを行う必要があります。手続きを行わなければ、この制度を利用することはできません。
任意継続の保険料の計算方法
任意継続では、退職前の健康保険と同じ保険を継続して利用できますが、保険料の負担額が変わります。在職中は、保険料の半分を会社が負担してくれていましたが、任意継続ではその会社負担分も自己負担することになります。つまり、保険料は全額自己負担となります。
• 保険料は退職時の標準報酬月額をもとに計算されます。この標準報酬月額は、在職中の収入を基に設定されており、退職後の収入減少に関わらず、一定額の保険料を支払う必要があります。
• なお、健康保険組合により、保険料の上限が設定されている場合もあり、その上限額に達することもあります。
任意継続で受けられる保障と制約
任意継続を利用することで、退職前と同じ健康保険給付を受けることができます。特に、企業の健康保険組合が独自の給付を提供している場合(医療費の一部負担軽減や特定の病気に対する給付金など)、これらの独自給付も継続して受けられることが任意継続の大きなメリットです。
ただし、いくつかの給付には制約があります。
• 傷病手当金や出産手当金は、任意継続では支給されません。これらは在職中に働けなくなった場合に支給される給付金であるため、退職後は対象外となります。
• 扶養家族の加入については、在職中と同様に家族も同じ保険に継続して加入することができます。そのため、世帯全体での保険料負担が抑えられるケースもあります。
任意継続のメリットとデメリット
メリット
• 保険の継続性:在職中の健康保険をそのまま利用できるため、使い慣れた保険で引き続き医療を受けられる。
• 扶養家族の継続加入:扶養家族も同じ保険に加入できるため、世帯全体の負担が抑えられる。
• 独自給付の継続:企業の健康保険組合による独自の給付を引き続き受けられる。
デメリット
• 全額自己負担:保険料が全額自己負担になるため、在職中よりも保険料負担が増える。
• 給付制限:傷病手当金や出産手当金が支給されない。
• 加入期間の制限:最長2年間しか利用できず、その後は別の保険制度に移行する必要がある。
• 申請期限が短い:退職後20日以内に申請しなければならないため、時間的な余裕が少ない。
国民健康保険の詳細

国民健康保険とは?
国民健康保険は、市区町村が運営する公的な医療保険制度です。対象は自営業者、フリーランス、無職の人などで、企業の健康保険に加入していない人が加入します。会社を退職後、任意継続を選ばない場合、原則として国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険の保険料の計算方法
国民健康保険の保険料は、退職後の収入ではなく前年の所得を基に計算されます。具体的な計算式は自治体ごとに異なりますが、一般的には以下のような要素で構成されています。
1. 所得割:前年の所得に応じて計算される部分。所得が高ければ高いほど保険料も上がります。
2. 均等割:加入者全員に均等にかかる部分。扶養家族の人数が多いほどこの部分も増加します。
3. 平等割:世帯ごとにかかる固定の部分。所得や家族構成に関係なく、1世帯あたり一定の金額が課されます。
退職後に収入が大きく減少する場合でも、前年の所得が高ければ高いほど保険料も高額になる可能性があります。しかし、国民健康保険には特定の条件を満たす場合に保険料を減免できる仕組みもあります。
国民健康保険で受けられる保障
国民健康保険では、任意継続と同様に基本的な医療保障を受けることができます。ただし、企業の健康保険組合のような独自の給付制度はありません。また、出産手当金や傷病手当金といった給与補償も存在しないため、病気や出産で働けなくなった場合の収入補償は期待できません。
国民健康保険の扶養家族の扱い
任意継続とは異なり、国民健康保険では扶養という概念がないため、扶養家族も個別に国民健康保険に加入しなければなりません。これにより、世帯全体で支払う保険料が大幅に増える可能性があります。扶養家族の人数が多い世帯では、この点が大きな負担になることがあります。
国民健康保険のメリットとデメリット
メリット
• 期間制限なし:加入期間の制限がなく、長期間利用できる。
• 所得に基づく保険料計算:国民健康保険の保険料は前年の所得に基づいて決定されるため、退職後に収入が減少した場合、翌年の保険料が下がる可能性がある。また、特定の事情がある場合には、保険料の減免や軽減措置が適用される場合もあります。
• 幅広い適用:自営業者やフリーランス、無職の人など幅広い層が対象であり、年齢や職業に関わらず加入が可能です。
デメリット
• 扶養家族の個別加入:国民健康保険には扶養家族の概念がないため、家族全員が個別に保険料を支払う必要があります。これにより、世帯全体での保険料負担が増える可能性が高くなります。
• 前年所得に基づく保険料:退職直後で収入がない場合でも、前年の所得に基づいて保険料が決定されるため、初年度は負担が大きくなる可能性があります。
• 給付の制約:任意継続と同様に、出産手当金や傷病手当金といった給与補償は国民健康保険にはありません。
任意継続と国民健康保険の比較ポイント
任意継続被保険者制度と国民健康保険を選ぶ際のポイントは、保険料や加入期間、扶養家族の扱いなど、さまざまな側面を総合的に考慮する必要があります。以下の比較表は、両制度の特徴をまとめたものです。

保険料の比較
任意継続では、退職時の標準報酬月額を基にした固定の保険料を支払うため、収入が減っても保険料が変わらないのが特徴です。一方、国民健康保険では前年の所得に基づいて保険料が決定されるため、退職後に収入が大幅に減少した場合、翌年度の保険料が下がる可能性があります。特に、退職後1年目の大幅な減収が予想される場合、国民健康保険の方が保険料を抑えられる可能性が高いです。
扶養家族の扱い
任意継続では、在職中と同様に扶養家族も同じ保険に加入できるため、家族全体の保険料負担を一元化できるというメリットがあります。しかし、国民健康保険では扶養の概念がないため、家族全員が個別に保険に加入する必要があり、家族が多い場合は負担が大きくなることがあります。この点は、特に扶養家族が多い世帯にとって重要な検討材料です。
給付内容の違い
企業の健康保険組合では独自給付(例:医療費補助や健康診断補助)を行っている場合があり、任意継続を選べば退職後もその給付を受け続けることが可能です。一方、国民健康保険にはそのような独自給付がありませんので、給付内容の差も選択の際の重要な要素となります。
加入手続きと加入期間
任意継続は、退職後20日以内に手続きを行う必要があり、期間内に申請をしないと加入できなくなります。また、最長2年間という加入期間の制約があるため、その後は別の健康保険に移行しなければなりません。一方、国民健康保険は加入期間に制限がなく、退職後の状況に応じて長期的に利用できます。
どちらを選ぶべきか?選択の際の具体的な判断基準
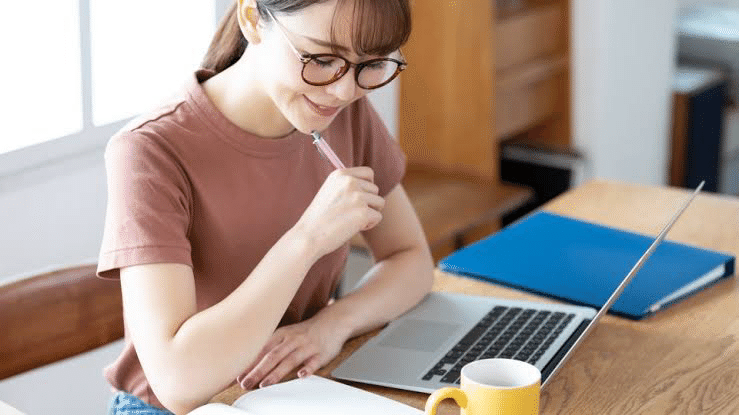
1. 保険料負担を重視する場合
退職後の収入見込みが大幅に減少する場合や、退職後に無職やフリーランスとしての収入が不安定である場合は、国民健康保険の方が保険料を抑えられる可能性が高いです。特に翌年度以降、保険料が減額されることが多いため、収入が少ない場合に有利です。
一方で、退職時点での標準報酬月額が比較的低い場合、任意継続でも保険料がそれほど高額にならないことがあります。加えて、扶養家族がいる場合は、家族全員を同一の保険にまとめられるため、任意継続の方が世帯全体としての負担が軽減されるケースもあります。
2. 扶養家族の有無を考慮する場合
扶養家族が多い場合は、任意継続を選択することで家族全員を同じ保険にまとめることができ、個別に保険料を支払う必要がなくなります。一方で、国民健康保険に加入する場合、家族全員が個別に加入し、個別に保険料を支払うことになるため、世帯全体の保険料負担が増える可能性があります。
3. 保障内容を重視する場合
企業の健康保険組合が提供している独自の給付(例:医療費補助や人間ドックの補助)が重要であれば、任意継続を選択する方がメリットがあります。これらの給付を引き続き受けることができるため、健康管理や医療費の補助を期待できる点が強みです。国民健康保険にはこうした独自の給付がないため、基本的な医療保障だけで十分かどうかをよく検討する必要があります。
4. 手続きのタイミングと加入期間を考慮する場合
任意継続は、退職後20日以内に手続きを完了しなければなりません。時間的に余裕が少ないため、迅速に決定する必要があります。また、最長2年間しか利用できない点も考慮する必要があります。一方で、国民健康保険は加入期間に制限がなく、長期的に利用可能です。
どちらが良いかの具体的なケースと保険料の差額

任意継続が有利な場合
ケース1: 扶養家族がいる場合
任意継続では、退職前に加入していた健康保険の扶養家族もそのまま同じ保険に加入できるため、世帯全体での保険料負担が抑えられることがあります。特に扶養家族が多い場合、個々に国民健康保険に加入するよりも任意継続で一括加入する方が安くなるケースが多いです。
• 例: 扶養家族が配偶者と子供2人の場合
• 任意継続の保険料: 40,000円/月(全額自己負担、会社負担分を含む)
• 国民健康保険の保険料: 被保険者の前年の所得と世帯の人数に基づき計算。扶養家族がいると、世帯全員が個別に加入するため、合計で60,000円/月以上になることもある。
ケース2: 独自給付がある場合
会社の健康保険組合が独自の給付(例: 医療費補助や健康診断の補助)を提供している場合、それを継続して受けられるのが任意継続の強みです。これが必要な人にとっては、若干保険料が高くてもメリットがあります。
• 例: 年に数回、健康診断や医療費の補助を受ける場合
• 任意継続の保険料: 35,000円/月(会社の給付が年間50,000円相当)
• 国民健康保険の保険料: 30,000円/月(給付は基本的な医療費のみ)
国民健康保険が有利な場合
ケース1: 退職後に収入が大幅に減少する場合
国民健康保険は、前年の所得に基づいて保険料が決まるため、2年目以降収入がないまたは少ない場合は保険料が大幅に減少します。特に退職後の収入がゼロに近い場合や、フリーランスとしての収入が少ない場合、任意継続よりも国民健康保険が大幅に安くなります。
• 例: 前年度の年収が300万円、退職後の収入がゼロの場合
• 任意継続の保険料: 35,000円/月(退職前の収入に基づいた金額で固定)
• 国民健康保険の保険料: 15,000円/月(収入がない場合は減額申請が可能)
ケース2: 加入期間が2年以上になる場合
任意継続は最長で2年間しか加入できませんが、国民健康保険は加入期間に制限がありません。退職後に長期間仕事を探す予定がある場合や、フリーランスとして安定するまでに時間がかかる場合は、国民健康保険の方が長期的に安定した保険料で加入できるメリットがあります。
例: 退職後3年ほど無職または低収入の場合
• 任意継続の保険料: 2年後には終了。終了後は国民健康保険に加入する必要がある。
• 国民健康保険の保険料: 2年目以降も前年所得が少なければ、15,000円/月程度に抑えられる。
具体的な保険料の差額
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額を基に計算され、全額自己負担になります(これまで会社が負担していた部分も自分で払う)。一方、国民健康保険は前年の所得に応じて決まるため、収入が少ないと保険料も低くなります。
【年収500万円の例】(扶養家族なし)
• 任意継続の保険料: 40,000円/月(全額自己負担)
• 国民健康保険の保険料: 35,000円/月(前年の所得に基づく)
【年収300万円の例】(扶養家族なし)
• 任意継続の保険料: 30,000円/月
• 国民健康保険の保険料: 20,000円/月
【年収300万円の例】(扶養家族が配偶者と子供2人)
• 任意継続の保険料: 35,000円/月(扶養家族も含む)
• 国民健康保険の保険料: 45,000円/月(家族全員が個別に加入するため負担が増加)
結論:どちらを選択すべきか?

退職後の健康保険選択は、個々の状況に応じて判断すべきです。保険料、扶養家族の有無、給付内容、加入期間など、各要素を総合的に考慮して、自分に最も適した選択をすることが大切です。
• 収入が減少し、翌年度の保険料負担を抑えたい場合は、国民健康保険が適している可能性があります。
• 扶養家族が多く、世帯全体の保険料を抑えたい場合は、任意継続が有利な場合があります。
• 企業の独自給付を引き続き受けたい場合は、任意継続を選ぶ方がメリットが大きいです。
最終的には、自身の収入状況や家族構成、保険料負担を見極めながら、どちらの制度がより自分に合っているかを慎重に判断することが求められます。
💰キャッシュバックキャンペーン
会員登録など簡単な作業でお金がもらえるお得なキャッシュバックキャンペーンを紹介しています!以下の記事をご覧ください!
