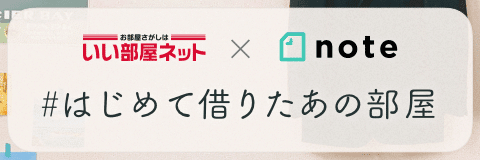さよなら、正しい街
母は過保護だった。
月々のお小遣いは多くはなかったけど、遊びに行くときにはいつでも多めにお金をくれた。
少しでも天気が悪かったりすれば車を出して駅まで迎えに来たし、どんなに遅く帰っても寝ずに待っていて、私が夕飯を食べていなければキッチンに立った。
母は過干渉だった。
私が見覚えのない服やカバンを持っていると、すぐに「それいつ買ったの」と訊いてきた。休みの日にどこに行って、誰と会って、何時に帰ってくるのかをいつも申告しなければならなかった。二十歳を過ぎてからもそれが続くので、たびたびけんかになった。
母は教育熱心で、安定志向だった。
私は中学受験をして、母の決めた中高一貫校に入った。
大学を決める時、文芸をやりたくて、専門学科があるとある大学に行きたいと言ったら、「あんたは頭がいいんだからもっといい大学に行ってほしい」と言われた。私はそれに従い、もっと偏差値の高い大学に入った。
就活は全然うまくいかなかった。
やっと内定が出た1社は、知りもしない、やりたいこともない会社だった。友達はみんないいところに決まっていて、そんななかでよくわからない会社しか内定が出なかった自分が惨めだった。
ただ、そこは大手企業の子会社で、安定という面では文句なしだった。このご時世に、問題を起こさなければ一生くいっぱぐれることはなさそうだった。
この会社なら父も母も安心だろうな。
就活に疲れ果てていた私は、最後はそれを決め手にそこに入社した。
振り返ってみれば、私は幼い頃から自分では何ひとつ決められなかった。
食べ物も、欲しいおもちゃも、その日着る服も、遊園地で一番最初に乗る乗り物さえ。
私はまずそれを母のところへ持っていって、母が「いいんじゃない」と言えば安心してそれを選んだし、反対に「なんでそんなもの」と言われれば、どんなに魅力的に映っても、もうそれを選ぶことはできなかった。
自分がどれが好きか、何がしたいかは二の次だった。
そんなことよりも、私はただ正解したかった。間違えたくなかった。
「なんでそんなもの」と思われることが何より怖かった。
そして、わたしにとって正しさの指標は常に、母だった。
*
私が社会人1年目の年、3歳上の兄が家を出た。
一生実家に住みつきそうな雰囲気だったのに、出ていくと決めたらあっという間だった。
出て行ってからは、兄は家にほとんど寄り付かなくなった。今では正月さえろくに帰ってこない。
「早く自立してほしい」と散々言っていたくせに、兄がいなくなって母は寂しそうだった。
冗談めかして口にしていた「あんたもいつか出て行くんだから」という言葉を、私に言わなくなった。
ねえ兄、先に出てったから知らないでしょう。
「変な時間に食べる人がいないから楽」なんて言い聞かせるみたいに言う母のこと。
あの家に一人「子ども」として残された私の気持ち。
先に出られてラッキーだったね。
少しずつ出口がふさがれていくみたいなあの感覚を知らずにすんで。
「子ども」が一人になった家で、私はその役目を果たそうとした。
それまでよりももっと意識的に、わがままで手がかかる「子ども」としてふるまった。母も、中学生の子のように私の世話を焼いた。
その時私、もう23歳だったのに。成人した身で必死にままごとをやる姿は、はたからみればただただ滑稽だっただろう。
このままこの家にいれば駄目になる。
「子ども」として振舞うその一方で、その感覚が心の奥で常にちらついた。
この、快適で安全で、自分では何も決断しなくていいこの家にい続ければ、私は駄目になる。何もできない人間になる。やってもらって当たり前の人間になる。決断を他人にゆだねる人間になる。そしていつか決定的な失敗を犯した時、それを母のせいにするだろう。
そういう、なりたくない人間になる。
それは確信に近い感覚だった。
*
日に日に強くなる「このままじゃ駄目になる」という感覚と、家にいる時の閉塞感に私は耐えられなくなっていった。
そして、ある休みの日、「友達と遊びに行く」と嘘をついて不動産屋へ行った。
母には言えなかった。「家を出たい」と伝えたとして、「まだいいんじゃない」と言われたら、私はそれに従ってしまうと思った。
物件探しについても同じだった。もしいいと思った部屋があっても、母が「それじゃないほうがいいんじゃない」と言ったら、私はもうそこを選べない。
でも、自分で決めたかった。そのために家を出るのだ。
だから何も言わないで、一人暮らしの部屋を探しはじめた。
「この条件でこの値段は無理ですよ」
独立洗面台、オートロック、築10年以内、7万以下。
私の希望する条件とエリアを見て、不動産屋の人は顔をしかめた。
条件に近い物件を数件ピックアップし、プリントアウトした紙を渡してくれる。どれもこれも希望からは遠くて、ぱっとしなかった。
しょっぱい私の表情を見て、現実を見せるしかないと思ったのか、「とにかく一度見てみましょうか」と、私たちは内見に向かった。
紹介された物件は、狭いか、暗いか、古いか、そのすべてかだった。
「どうですか?」
「はあ」
落胆が出すぎないようにそう答えるのが精いっぱいだった。
そこまで贅沢な条件を出したつもりはなかった。でも、なんだかんだ初めての一人暮らしに夢を抱いていた私は打ちのめされた。どの部屋も、思い描いていた生活とはかけ離れていた。
今の君が住めるのはこの程度。物件候補の紙束がそう言っていた。
結局、その日は物件を決めることができなかった。
夜、ベッドにあおむけになって、必要なものが全部揃った実家と、その日見た暗く狭い部屋たち天秤にかけてみた。何度量りなおしても、実家の皿のほうが重かった。
上京とか転勤とか、「絶対に引っ越さければならない理由」がない私に、快適さを捨ててまで家を出る決断はできなかった。そのことがまた、自分の甘えと中途半端さを見せつけられているようだった。
この家で引き続き暮らせばいい。出て行かなきゃいけない理由はないんだから。
家を出る気持ち自体が揺らいだ。
2週間ほど時間を空けて、私はまた不動産屋へ行った。
この間とは違う不動産屋に、新しく見つけておいたいくつかの物件と、希望の条件を伝える。
路線とエリアを、最初に考えていたものより少し郊外に変えた。それでもやっぱり最初の時と同じように「その条件だと厳しいですね」と言われた。
色々と話をして、3件まで絞って内見することになった。
ひとつ目とふたつ目は、やっぱりぴんとこなかった。エリアを変えたおかげで初回の時よりはいい部屋だったけれど、どれも個人的に譲れない条件が欠けていて、選べなかった。
車に乗って、最後の物件に向かう。
――わがままなのかな。
家を出ることが第一の目標なのに、あれこれ見ていると欲が出る。
こんな中途半端で家を出られるのかな。
「駅から徒歩9分って書いてありますけど、もう少し遠いかもしれません」
運転しながら不動産屋の人が言ったのをぼーっと聞いていた。
小さなマンションの前で、不動産屋の人は車を停めた。
そこは聞いたこともない駅の最寄りだった。住宅地の奥まった場所で、平日の夕方だったけれど車も人もほとんど通らなくて、静かだった。
鍵を開けてもらって、部屋の中に入る。
「おお」
不動産屋の人と二人して思わず声が漏れた。
「天井高いですね」
「そうですね」
ほとんどうわの空で、私はその部屋を見まわした。
窓が二面にあって、少しだけ天井が高くて、正方形に近い形をしたその部屋は、実際の平米数よりも広く、明るく見えた。
「こんな部屋あったんだ」と不動産屋の人が呟く。知らんかったんかい、と思ったけど、同じ気持ちだった。
この部屋好きだな、とはじめて思った。
「どうしますか?」
不動産屋が尋ねてくる。
でもすぐには決断できなくて、少し考えてもいいですか、と答えた。
不動産屋の人と別れ、私は地図を見ながら駅までの道を歩いた。なんの変哲もない、これといったランドマークもない、住宅が広がるだけの静かな街だった。
歩きながら、私の街だ、と思った。
*
家に帰ってから不動産屋に連絡をした。審査はすんなり通り、その部屋は私の部屋になった。
そこまできてやっと、私は母に伝えた。
「引っ越すから。家も決めてきた」
母が呆然とするのがわかった。その顔は見られなかった。
色んなものを呑み込んで、母は「そうなんだ」とだけ言った。
母が部屋を出て行ったあと、私はふとんに顔をうずめた。そして「もう決めたんだから」と言い聞かせた。そうでなければ、後悔と罪悪感で気持ちが揺らぎそうだった。
だって、「そうなんだ」という答えを聞いて初めて気づいたのだ。あれこれケチはつけることはあっても、母は私がやりたいと言ったこと、欲しいと言ったものを、いつも最後には叶えてくれたこと。
だって母は、子どもになんでもしてあげたい、過保護な人だから。
「子どものままでいてくれ」なんて、母は私に頼んでない。「家を出るな」なんて言われてない。いつも私が勝手に母の意図を汲もうとしてただけ。
母は過保護で、過干渉だった。
でも本当に、言っても伝わらない人だったのだろうか。一方的にコミュニケーションを諦めていたのは私じゃないのか。
どうしてこんな、引きちぎるようなやり方しかできなかったんだろう。
気持ちがおさまるまで、ずっとふとんに頭を突っ込んでいた。傷つけた私のほうが泣くわけにはいかなかった。
*
そこからひと月弱ほどで、家を出る日が来た。
家具家電は新しく買いそろえるのでほとんど荷物はなく、引っ越し業者を使わずに親に車を出してもらうことになっていた。それこそ親に甘えてるのだけれど、そんなこともうどうでもよかった。何より、父と母に新しい私と私の部屋を見せて、大丈夫なのだということを見せたかった。
兄はいないけれど、幼い頃家族旅行した時みたいに3人で荷物と一緒に車に乗り込む。
東京の端から端へ。電車でも車でも1時間程度。気が向けば帰れる、短い距離。果てしなく遠い距離。
私の選んだ部屋を見て、二人は「いいんじゃない」と何度も言った。
7.5畳の1K、2階。独立洗面台で脱衣所つき。西北向きだけれど二面採光。それが私が選んだ私の城だった。
部屋に置く家具もカーテンも、食器も雑貨もリネンも、すべて自分で決めた。
1日3食作るのは面倒くさかった。食材はしょっちゅう賞味期限を切らした。こまめに掃除しないとすぐ排水溝が髪の毛だらけになると知った。ゴミの分別の曜日がぜんぜん覚えられなかった。夏にゴキブリが出て、生まれて初めて一人で退治した。部屋の向きと窓が大きいせいで、冬は死ぬほど寒かった。
できないこと知らないことだらけの日々で、私はどうにかきちんと生活しようとした。探るように「大丈夫?」と連絡してくる母に心おきなく「大丈夫」と答えるために、面倒でも3食食べて、洗濯機を回し、こまめに掃除した。
住宅地にあるその家は、8時にもなると人通りがほとんどなくなる。電灯の数も少なくて、道はやたらと暗かった。遊びにきた友達からはよく「怖くない?」と訊かれたけど、気にならなかった。
初夏、夜に窓を開けると近くを流れる川の音が聞こえた。川には線路が渡っていて、昼間にはガタンゴトンという音も聞こえた。
その音を聞きながら気がついた。川の音が聞こえるところも、夜が暗くて静かなところも、実家の周りと同じだった。そこは確かに私の街だった。
実家に似たその街で、ひとつひとつ自分で決め、選びながら暮らした。失敗も、間違いも、そこでは全部私だけのものだった。
そうやって私は、自分のなかの歪な部分を少しずつ作り直していった。
その部屋で暮らした3年間、家族一人一人にも色々なことがあった。
どうしても編集の仕事をしたくて、私は新卒で入った会社を辞めた。不採用通知さえこないようななかで就職活動を続け、契約社員で編集者になった。
堅実で安定志向を溶かして固めたような人物だった父が、30年以上勤めた会社を辞めて転職した。
もともとアクティブだった母は、自分の自由な時間が増えたことで好きなバンドのライブのために全国どこへでも遠征に行くようになった。
たまに実家に帰ると、そこにはもう、私抜きの生活リズムが形成されていた。
母が『大丈夫?』とメッセージを送ってくる頻度も、少しずつ減っていた。
*
順応していく。
なんだってそうだ。取り返しがつかないと思った出来事も、時間とともに適した形へと変化していく。
いま振り返って思う。あの街の、あの部屋での暮らしは、私にとって正しいものでなければいけなかった。母を捨てるように振り切って得た新しい生活は、せめて正しくなければならなかった。
だけど、それと同時に、「正しさ」というしがらみを少しずつほどいていく日々でもあった。
いま、私はもう一度引っ越しをして別の場所で暮らしている。
来年には、還暦を迎える両親を祝うために、音信不通気味の兄を捕まえて家族旅行に行く予定だ。
相性の悪い母と兄が喧嘩しないかが心配だ。でも、部屋を分けようかと提案した私に、同じ部屋でいいんじゃないと言ってきたのは兄だった。
変わっていく。水が低いところに流れるように、あるべき場所に向かってゆく。
正しい子どもでなくていい。
正しい親でなくていい。
それでも、家族だ。
初めて一人で暮らした、あの正しい街。
地元によく似たなんのランドマークもないあの駅に降りることは、たぶんもうない。
いいなと思ったら応援しよう!