
絵の具で理想通りの色を生み出すコツ
こんにちは。
マジック:ザ・ギャザリングのアート大好き創作オタクのErinです。
TCGにおける「拡張アート」とは罪深く、不思議な遊びです。
以前、アクリルガッシュについての個人的How toを書きましたが、今回は第2弾となります。
今回のテーマは、「絵の具で理想通りの色をつくるコツ」。
アクリルガッシュ以外の絵の具にも通ずるところがあるかなと思います。モリモリと手懐けていきましょう。
理想通りの色とは?
拡張アートを嗜まれる方は、「色合わせ」というのを意識的に行うことが多いと思います。境目が目立たないような色を作る、アレです。
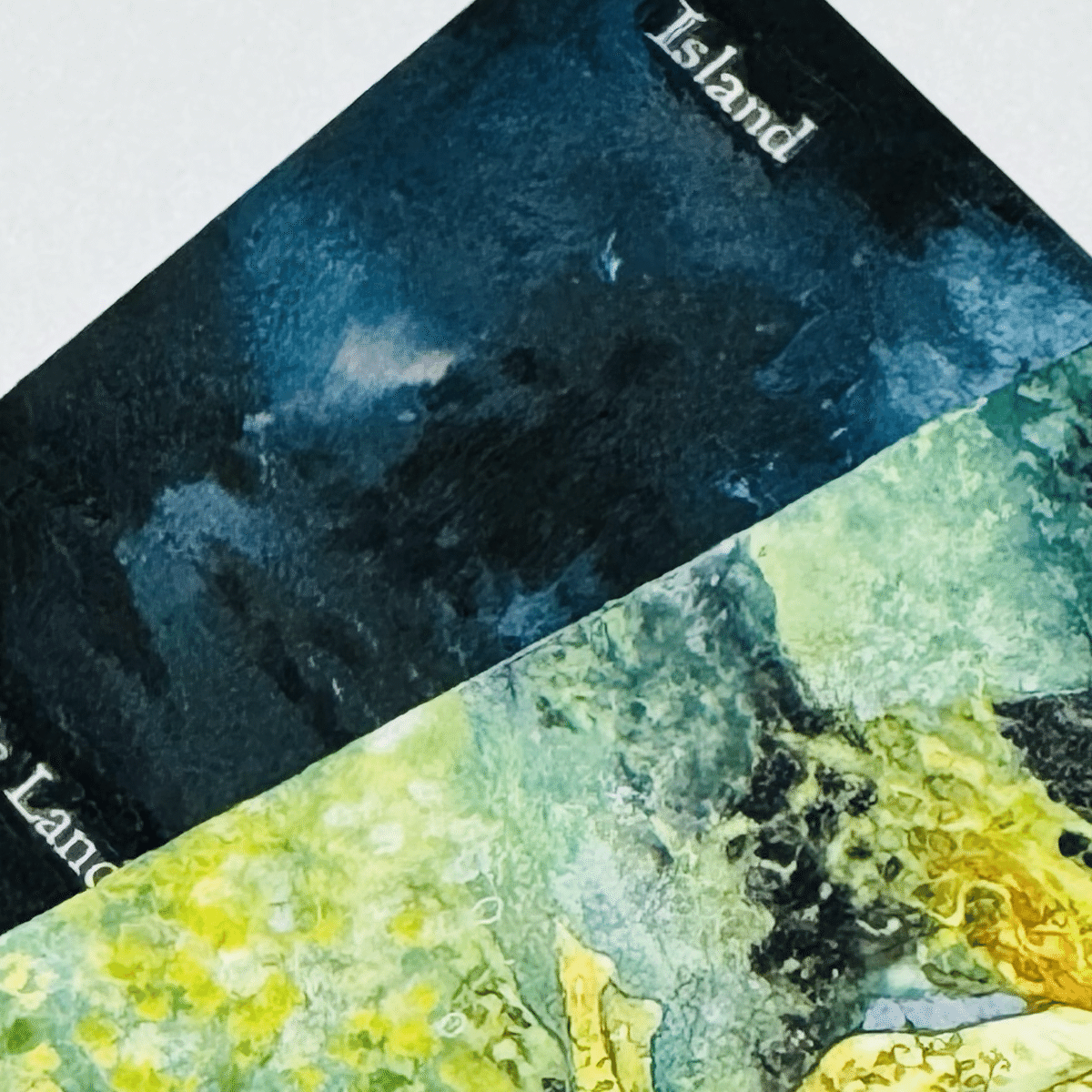
拡張アートをするにあたり、この色合わせは特に難しい要素な気がするので、自分なりのコツをまとめました。
よければ試してみてくださいね。
色のつくり方
では、拡張アートを行う流れで見ていきましょう。今回は実際に《興隆する木立/Thriving Grove》を塗っていきます。

極楽鳥が飛んでいそうな雰囲気が素敵。
南国らしい鮮やかな色も良いですね。
アーティストはJenn Ravenna氏。流れるような筆のタッチが印象的です。
今回は色合わせにフォーカスして書いていきますので、全体的な拡張アートの進め方については、過去記事をご参照くださいませ。
1.色を観察する
まず、塗りたい色を決めて、その色を観察しましょう。
今回は、ベースとして2色つくります。

では、その色が下記の図だと、どこに当てはまるか考えてみましょう。

理想の色が、この図で完全に当てはまらなくてOKです。この辺りの色かな、というのを見てみてください。

次に、その色の明るさを確認します。

色で明るさを表現するなら、白が明るく、黒が暗いと考えます。
このような白から黒の間で、つくりたい色がどの辺りにあるかを見てみます。

ここまで観察できればOKです。
続いて、実際に絵の具を混ぜていきましょう。
2.メイン色の絵の具を調整する
では、先ほど観察した色と図を参考に、絵の具を出していきます。
まずは明るい緑色からつくります。

手持ちの絵の具だと、シンプルに黄緑色が1番近いように見えるので、それをメインに使います。
では、ここから何色を混ぜれば理想に近くなるか?というのを見ていきましょう。

A.メイン色+三原色を混ぜ合わせる
まずは、色相を理想に近付けていく方法です。
不思議なことに、絵の具の場合は赤・青・黄の3色があれば、大体なんとかなります。(色の三原色と呼びます)
改めて、先ほどの図を見てみます。

赤・青・黄に★マークをつけました。
そして、つくりたい色に隣接するふたつの★を見ます。
それぞれの色を加えることで、色相の位置をずらすことができます。
今回の黄緑で考えると、隣接している★は黄色と青です。
メインの黄緑に黄色を加える、または
メインの黄緑に青を加える、ことで
色相を調整することができます。
実際にカードに試し塗りをしながら、近い色相に近付けます。

B.白・黒を混ぜ合わせる
続いて、明度を調整するために白または黒を混ぜます。
先ほどの図を見ながら、明るくする・暗くする目安をつけて、調整していきます。
明るくしたい場合は白を加えます。

暗くする場合は黒を混ぜますが、黒は人工的な色なので、無機質な印象もあります。
三原色など他の色も加えつつ暗くすると、自然物らしい色になりますので、題材に合わせて試してみてください。

3.ひとまず塗ってから考えよう
色々書きましたが、ひとまず試し塗りをするのが手っ取り早いです。
パレットの上で見える色と、紙に塗った色が違って見えることは、大変よくあります。
そして、カードの上にアクリルガッシュを塗った場合、塗った直後であれば水を含んだ筆ですぐ拭き取ることもできます。やり直ししやすいので、恐れず塗っていきましょう。

そのあと「あ、色合ってないな……」となることも大変よくあります。
そうしたら、何色を加えれば理想に近付くか、もう一度考えてみましょう。
・メインの色を追加で足すか
・理想の色に近い、別の絵の具を加えるか
・三原色で色相を調整するか
・白や黒で明度を調整するか
このあたりに慣れてくると、色合わせがぐっとラクになると思います。
まとめ

自分はよく「絵の具は基本色があればOK」と言っていますが、今回の話を踏まえると、「赤・青・黄、そして白・黒があればなんとかなりそう……」というのが伝わったでしょうか。
実際、三原色があれば全ての色相をカバーできますが、3色から全ての色を作り出すのは手間ですので、一般的な12色セットなどで十分活用していただけると思います。
大抵は基本色があれば十分ですが、塗りたい色が彩度の高い色(蛍光色のような鮮やかな色)だと、基本色では再現が難しいので、理想に近い色を用意いただくのが良いかと思います。
狙った通りの色が作れると、思わずニコニコしてしまう満足感があります。(主観)
楽しんで色塗りしていただくためのお役に立てれば、嬉しく思います。感謝。
個人的な創作How toをまとめています。
本記事はファンコンテンツ・ポリシーに沿った非公式のファンコンテンツです。ウィザーズ社の認可/許諾は得ていません。題材の一部に、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の財産を含んでいます。©Wizards of the Coast LLC.
