
ピアノ連弾作品を作曲しよう!②
●伴奏を作ろう!
大切なメロディーを支える、伴奏。
伴奏一つで、旋律が際立ったり、音楽の印象をガラッと変えたりしますので、丁寧に考えていきたいところです。
でも伴奏は、どうやって考えたら良いのでしょう。

今回も先生に相談してみましょう。「センセー。」

先生「まずは、和声を分散和音にしてみましょうか。」
●分散和音
「例えばハ長調の主和音があったとして…。」

このドミソの音を崩して分散和音にしてみましょう。

この分散和音の形を変えてみると…

そう。この形は、古典派音楽でよく見たことのある…
先生「はい。当時流行した伴奏※ですね。」※アルベルティ・バスと言います。

なるほど!伴奏の基本は、このように和声の構成音を分散和音にしてみると考えやすいですね。
先生「今回の曲は3拍子。いくつか伴奏形を考えてみましょう。」

いろんな形が考えられますね。ふむふむ。
①は1番シンプルな分散和音ですね。
②は分散和音を細かくすることで、音楽に推進力が出てきますね!
③は、各構成音を広めに展開することで、響きに奥行きが感じられますね。
一方、④の形はワルツの雰囲気です。

よーし。では早速、作ったメロディに伴奏をつけるぞ!
●メロディに伴奏をつけてみよう
今回作曲しているのはピアノ連弾。高音側に第1奏者=プリモ(Primo)、低音側に第2奏者=セコンド(Secondo)が座って、音域を分担して2人で演奏するピアノアンサンブルです。
音楽の冒頭なので役割をわかりやすく、メロディをPrimoに、Secondoに伴奏を書いてみます。

センセーできました!あれ?でも聴いてみると…

例えば1小節目の3拍目ですが、一瞬なのですが、PrimoのDの音と、SecondoのEの音のぶつかりが気になりますし(a)、裏拍のCisの音が同じ音なのも、せっかくメロディと伴奏の二つの役割があるのにもったいなく感じますね(b)。
先生「そういう箇所を少し補正して仕上げましょう。」

Aのように小さな休符を入れることで、音楽な息遣いを意識できるように工夫しました。
そして先ほどの場所、Bのようにぶつかる部分を補正しました。
音はコチラ↓(スマホの方はListen in browserをタップしてお聴きください。)
《POINT!》伴奏の書き方…伴奏は構成音を用いて、ハーモニーやリズムでメロディーを補佐する書き方を心がけます。
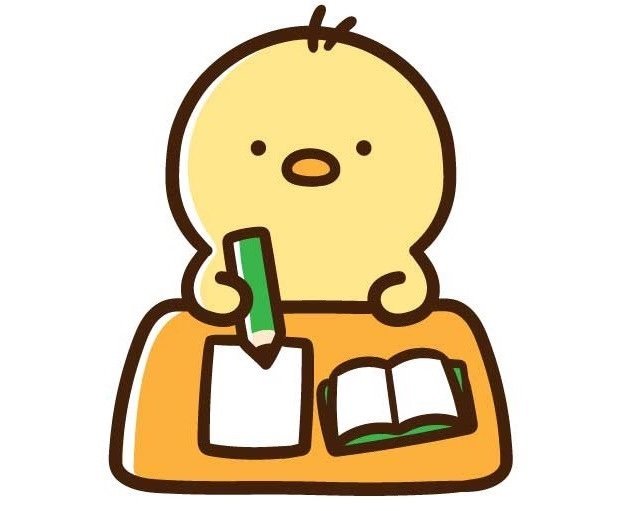
このような感じで、この先もどんどん書き進めていきましょう!
→次回もお楽しみに…
●最後に
私たちeqhor music labo Tokyoでは、今後も、珍しい切り口から音楽理論に関する記事、作品の配信と通して、音楽の魅力を発信していきます。
もしこの記事を気に入っていただけたら、ご支援いただけたら幸いです。
また私たちは、YouTubeで、聴音課題をはじめとする様々な音楽を公開しています。
ぜひご視聴いただき、気に入っていただけたらチャンネル登録をしていただけたら励みになります。よろしくお願いいたします。
https://www.youtube.com/@eqhor.musiclabo-Tokyo
○生徒:平田真里奈
《プロフィール》上野学園高等学校音楽科演奏家コースを経て上野学園大学演奏家コースに特待生として入学。現在4年次に在籍。合唱、器楽、声楽の伴奏及びソロのほか2022年「Pianoduoまなつ」を結成し演奏活動を行なっている。
第11回東京ピアノコンクール高校部門 審査員特別賞、第82回東京国際芸術協会新人演奏会オーディション、コンセール・ヴィヴァン新人オーディション(室内楽部門)合格、第25回万里の長城杯国際音楽コンクール優秀伴奏者受賞。
ソルフェージュと作曲を武澤陽介、室内楽を荒井伸一、声楽伴奏法を吉田伸昭、ピアノを佐古田彩子、安田正昭、星子知美の各氏に師事。
○Pianoduoまなつ
石川千夏 & 平田真里奈 (Piano)
出会いは幼稚園時代。音楽を通して繋がり、2022年第6回きらり鎌ヶ谷アーティスト発掘プロジェクトへの参加を機に「Pianoduoまなつ」を結成。
