
学術論文と国際会議0で学振DC1通った話
研究業績が無いけど何故か博士進学したい僕みたいな人の励みになれば。
申請書提出時の僕の状況は
・九州大学(旧帝大という括りのちょっといい大学)
・研究業績は国内学会3件のみ
・うち受賞1件
・学部/機械→修士/自動車工学→博士/情報で毎回所属が違う
・当然研究テーマもガラッと変わる
・新しい指導教員の研究室では初の博士学生
・当然学振を取っている先輩はいない
・学振締切2週間前に博士進学することを決める
です。みんなにきぼーをあたえたい。
申請時のプロフィール
東京の高校からはるばる九州大学の工学部機械航空学科に入学し、学部生の頃は鳥人間サークルに所属して飛行機を作っていました。修士課程ではそのまま工学府機械専攻を受験しましたが、無事院試に落ち、統合新領域学府オートモーティブサイエンス専攻という面接とToeicのみ(僕はToeic410です)で合否が決まる専攻に行くことになりました。進学後は研究をしておらず主にVR系の作品を作り、コンペや展示会へ作品を提出していました。また、僕が鳥人間サークルに上手く馴染めなかったため、自分で新しくものづくりサークルを設立し、代表としてサークル運営などを行っていました。
博士進学を考え始めた時期
僕は元々、進学するつもりはなく、冬まではみんなと同じように就活を行っていました(といっても自動車メーカーとデジタルアートをやっているベンチャーのインターン2個行っただけですが)。その結果僕が社会に適合できないことが判明し、とりあえずもう3年大学に引き篭もることにしました。
博士課程に行くにあたって、その頃に僕が趣味で作っていたVR系の研究がしたいと思い指導教員を変えることにしました。僕の研究グループ(https://app.ait.kyushu-u.ac.jp/)は人間のセンシング、解析、介入をそれぞれ行う3つの研究室が同じ部屋で研究しており、修士課程の僕は解析を行う研究室にいたので、介入をやっている先生にとりあえず連絡を取ってみました。

このslackの通りです。この後、あっさりと博士に行くことが決まり、院試のシステム(僕の場合、同じ大学からの進学だけど所属が統合新領域学府から情報理工学府に変わるから内部進学より結構だるい)とか、学振などの申請書のシステムとかを調べていたら5月になりました。僕の大学では学振の学内締切は5/7なので、あと1週間ですね。ちなみに他の研究室の学生がかなり前から学振を書き始めているらしいというのは後から知りました。研究グループからも学振出している先輩がほとんど(というより僕の知る限り全く)いないのでスケジュール感もわからなかったですね。
学振との戦い

5/7学内締め切りにも関わらず前日に初稿を上げています。無能です。この時期はDICOMOという学会への準備を行っており、かなりカツカツのスケジュール感でした。しかし、どうやら申請書の差し替えが5/24までできるという情報をゲットし、とりあえずこれをそのまま出しました。
学振に書くことは大きく
・やりたい研究の背景
・その分野の課題
・研究内容の着想の経緯
・研究計画
・その研究の特徴
・自分の強み
・自分に足りていないところ
・目指す研究者像
・それに向けた意気込み
の9個があります。
僕の場合は元々、趣味で開発していたプロダクトを研究内容にしようとしていたので、新しく考える内容は
・研究計画
・自分の強み
・自分に足りていないところ
・目指す研究者像
・それに向けた意気込み
の5つでした。
スケジュール的には、とりあえず1日でだいたい全部書き上げて、3日くらいで細かい修正や参考文献の吟味をしていました。
研究計画はやることさえ決まっていればほぼノリで書けるため、後ろ4つの内容を特に頑張って書いていました。普通の人は研究業績をたくさん書き、強そうなアピールをするのですが、僕の場合業績がなさすぎたので、趣味で行っていたものづくりの成果をいっぱい書いて強そうなアピールをしました。

また、自分の強みや足りていないところの欄も普通の人は研究で行った学会発表や論文投稿のエピソードを書くようですが、僕の場合、研究について書くことが何もなかったので、趣味の話でほとんど埋めました。

最後の2行を見て頂ければわかると思いますが、この男、研究成果がないのに何故かHCI分野で大きなインパクトを残せるという確信があるらしい。自身満々な雰囲気を出した方がこういうのは通りやすいのでは?と思ってもりもりで書いてました。
その後、5/9に本稿を書き上げ、約10日間の学振との戦いが終わりました。
意識して書いていたところ
僕の場合、研究はほとんどやっておらず、インターンや趣味のものづくり活動をずっと行っていたため、普通に学振を書いても落ちると思いました。そのため、自分の得意分野を押し付ける書き方を意識していました。おそらく、他の学生は研究一本で学生生活を過ごしているだろうと踏んで、サークル活動やインターン、コンペで実際にものづくりを行っていた、そしてその費用を自分で取ってきていた、ものづくりサークルを新しく設立したことなど、他の学生がやっていないであろうことを凄そうに書きました。
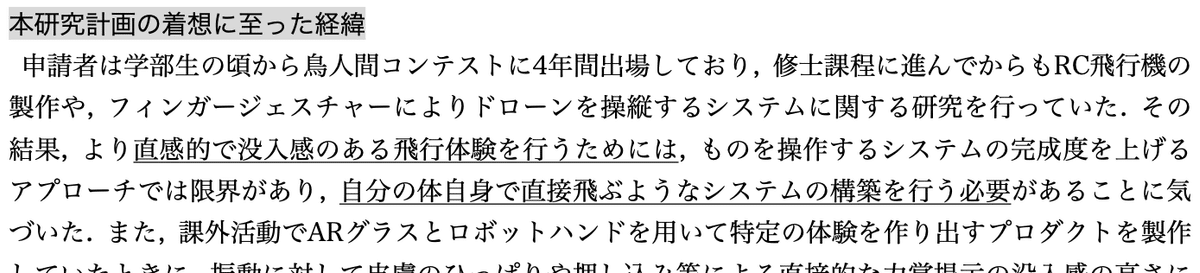

当然、申請書も社会実装寄り(というよりそうするしかない)。今まで色々やってたけどアカデミックの方面から社会実装したいです、の流れはすごく意識していました。書いている時は勝手に大事なのは一貫性だと思っていて、導入から研究内容、自分の将来像まで一貫して社会実装を推していました。
また、学振の書き方などまとめたサイトも一応見ましたが、基本的に無視して書いていました。みんなと同じように書いても落ちると思ったので。同様に書いた申請書を研究室の先生方に見てもらいましたが、そのフィードバックもあんまり申請書内に取り入れていません。全部入れたら僕の申請書ではなくなるので。自分の味を出しましょう
個人的な勝因
いくつかの要因があると思います。
一番の要因は申請書を提出したことです。提出することにより、審査員が申請書を読むことで内定確率が0%から一気に正の値に上がりました。僕の周りでも申請書を提出せずに学振に採択されている人を聞いたことがありません。
二番に大きい要素は運だと思います。運気を上げるために毎日善行を積みましょう。僕はたまたま学振の結果が出る前日に壁に挟まっている蝙蝠を外に逃がしてあげていました。おそらくこれが採択に繋がったと考えられます。恐らくDC1を提出する年齢は多くの人が24歳で厄年なので、全員運気が下がっています、つまり少しでも運気を上げることで差別化できます。
もう一つの要因として、僕が申請書を書き慣れていたことが考えられます。今まで福岡未踏(https://mitou-fukuoka.org/)やIPA未踏(https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/it/index.html)などに採択されており、この手の提案書を書くことで450万円くらいの資金を自分で調達していたため、その経験が活かせたと思います。その経験がなかったら1週間で学振の書類が書き切れる訳がありません。しかしながら、普通の人は申請書を書いたことがないと思うので、その分申請書を書く時間を多く取ることをお勧めします。
最後は自信です。最初に10ページの資料を書くことと倍率6倍の情報を聞いた時に、僕は「ああ、それなら取れそうだな」と思い申請書を書き始めました(当時は学振の難易度を知りませんでした)。このマインドで書いたことで、文字が覇気を帯び、審査員を圧倒したと考えられます。
つまり、申請書を提出して善行を積んで、提案書をいっぱい書く経験があり、自信に満ち溢れていれば研究成果があんまりなくても学振をとることができるかもしれません。
最後に
希望を与えられたでしょうか。頑張って学振通しましょう。
僕の申請書が欲しい人はtwitter(https://x.com/Emil_honmono)にDMください。僕のことなのでDMする時は可愛い女の子のフリをすると無料で申請書を渡すと思います。男は僕に焼肉おごれ。
