
内部受験 vs 外部受験|東京科学大学大学院に合格するための秘密の戦略!
〜内部生の圧倒的アドバンテージを覆す、外部受験生の勝ち方とは?〜
この記事を読むとわかること
✅ 東京科学大学大学院の内部受験と外部受験の決定的な違い
✅ 内部生の圧倒的なアドバンテージとは?推薦枠の実態を解説
✅ 外部受験生が不利にならないためにやるべき3つの戦略
✅ 合格者のリアルな体験談!外部受験成功者の勉強スケジュール
1. 内部受験 vs 外部受験|東京科学大学大学院の試験制度の違い

「内部生と外部生で試験内容が違うって本当?」
「推薦があるらしいけど、内部生はそんなに有利なの?」
東京科学大学大学院の入試では、内部受験と外部受験で大きな差があります。
特に、内部生には「推薦入試」があり、筆記試験を受けずに大学院に進学できる可能性が高い ことが最大のメリットです。
◆ 内部受験のメリット|試験なしで大学院に進学できる可能性も!
✅ 推薦制度があり、競争が少ない
✅ 試験なしで合格できることもある
(例:生命理工学院では150人中100人が推薦)
✅ 過去問や試験情報が手に入りやすく、教授とのコネクションもある
内部生は、受験において圧倒的に有利な状況にあります。
試験なしで進学できる可能性があり、例え一般試験を受けるとしても、試験の傾向や対策情報を入手しやすいため、圧倒的に有利な立場にいるのです。
◆ 外部受験生が直面する3つの厳しい現実
❌ 推薦による合格が期待できず、筆記試験で実力勝負を強いられる
❌ 試験の傾向や対策情報を内部生のように簡単には入手できない
❌ 身近に同じ目標を持つ仲間が少なく、孤独な受験勉強になりがち
「外部生は圧倒的に不利」と言われる理由はここにあります。
推薦がなく、内部生ほど試験情報を手に入れられないため、「どこから手をつければいいのか分からない」 と悩む人が多いのです。
しかし…
果たして、本当に外部生は合格が難しいのか?
外部受験でも合格する人は確実にいます。
むしろ、内部生にはない視点と戦略を持つことで、合格率を上げることが可能!
次の章では、外部受験生が不利になりやすいポイントを具体的に掘り下げ、「どうすれば不利を逆転できるのか?」 を詳しく解説します!
2. 知らないと落ちる?外部受験生が陥る3つの落とし穴とその対策

✅ 「内部生は有利」と言われるけど、外部生はどこでつまずくのか?
✅ 東京科学大学(旧・東工大)の院試は実力勝負と聞くけど、本当に情報格差はないの?
✅ 「勉強していて分からない問題が解決できない…」この状況、どう打破する?
外部受験生は、「推薦がないから厳しい」と思われがちですが、実は本当に問題なのはそこではありません。
多くの外部受験生が直面するのは、以下の 3つの“見えない壁” です。
① 試験の傾向や対策情報が手に入りにくい

内部生と外部生の決定的な違い
「内部生は試験の傾向を知っているから有利」と思われがちですが、実は内部生だけに極端に有利な出題傾向があるわけではありません。
しかし、内部生には試験対策を有利に進められる環境があります。
東京科学大学の学部生が受講している授業の資料と、大学院入試の出題範囲が重なっているため、対策がしやすい のです。
特に、昨年の試験では 学部の授業スライドと同じ内容の問題が出題されており、これを活用することで 過去問と照らし合わせながら院試の出題傾向を予測することが可能です。
また、過去問に取り組む前の 基礎固めとして、テスト範囲の復習がスムーズに進められる というメリットもあります。
解決策|外部受験生でも「内部生と同じ情報」を手に入れる方法
✅ 過去問は、大学の公式サイト+OB・OGネットワークを活用する
◆ 東京科学大学の公式サイトで過去問を収集(可能な限り過去10年分)
◆ SNSやX(旧Twitter)、研究室訪問を通じて、内部生や合格者から情報を得る
✅ 内部生が使っている授業資料を入手する方法
◆ 東京科学大学のシラバスを確認し、院試と関連の深い科目をリストアップ
◆ 研究室訪問時に「過去の院試で授業の内容が出題されたことはありますか?」と聞く
◆ 可能なら、内部生の知り合いを作り、授業スライドやノートを見せてもらう
👉 試験の出題傾向は、過去問+合格者の勉強法から逆算する
◆ 「どの分野が頻出なのか?」を過去問分析でチェック
◆ 合格者が使っていた参考書をリサーチし、無駄な勉強を減らす
外部受験生にとって 「内部生がどのように試験対策をしているのか?」を知ることが、最も重要な戦略になります。
情報戦を制し、内部生と同じレベルの対策を進めましょう!
② 「分からない問題を誰にも聞けない」状況が最大のハンデ

1人で勉強していると、必ず「分からない問題」に直面します。
しかし、外部受験生には、気軽に質問できる仲間や先輩がいない ため、分からない問題がそのまま放置され、理解が進まない という状況に陥りがちです。
「分からない問題をそのままにする」=「試験本番で解けない問題を増やす」 ということ。
これが積み重なると、合格点に届かなくなります。
解決策|学習の「壁」を突破する方法
✅ オンラインコミュニティを活用する
◆ X(旧Twitter)やDiscord、Slackを使い、同じ目標を持つ仲間を見つける
◆ 「東京科学大学 院試」「東工大 院試 受験仲間」などのキーワードで検索
✅ 合格者や内部生とつながる工夫をする
◆ 研究室訪問時に「受験勉強のコツ」を聞く
◆ 合格者が運営するブログやYouTubeを活用する
外部受験生は、「勉強仲間を作ること」自体が戦略の一つになります。
質問できる環境を作ることが、学力の伸びに直結する!
③ TOEICなどの英語試験対策に時間を取られる

◆ 内部生と外部生、B日程受験における決定的な差
B日程を受験する場合、内部生はすでに授業で担当教授の試験を経験しているため、短期間で筆記試験対策を進めることができます。
そのため、試験本番に向けての準備がスムーズで、専門科目の対策に集中できる環境 にあります。
一方で、外部生は 試験の傾向を一から分析し、専門科目の対策に時間をかける必要があるため、TOEICなどの英語試験を早期にクリアすることが必須 です。
特に、TOEICのスコア提出が求められる場合、英語対策をダラダラと続けるのはNG!
筆記試験対策に十分な時間を確保するために、遅くとも3月までにはTOEICの勉強を終え、スコアを確定させることが理想的 です。
解決策|TOEICを早期に終わらせ、専門科目に集中する戦略
✅ TOEIC対策は「短期間でスコアアップしやすいパート」に絞る
リスニング(Part 1, 2, 3, 4)を重点的に強化(短期間で点数が伸びやすい)
文法・単語は「TOEIC特化の単語帳+文法問題集」で効率的に学習
✅ 3月までにTOEICのスコアを確定させるためのスケジュール
1月〜2月:TOEICの基礎固め(単語・文法・リスニング)
3月:実践問題を解き、本番と同じ環境で模試を繰り返す
3月末までに目標スコアを取得し、4月以降は専門科目の対策に集中!
✅ TOEIC対策を早めに終わらせることで、専門科目にかける時間を最大化!
外部受験生は、英語対策のタイミングが合否に直結します。
TOEICは後回しにせず、早めに片付けてしまうことで、内部生と同じスタートラインに立つ準備を整えましょう!
まとめ|外部受験生が不利を乗り越えるためにやるべきこと

外部受験生は、確かに不利な点が多いです。
しかし、これらのハードルを理解し、事前に準備をすれば合格率は大きく上がります!
✅ 試験情報は「公式+OB・OG+SNS」から徹底収集!
✅ 「分からない問題を放置しない」環境を作る!
✅ TOEIC対策は早めに終わらせ、専門科目に集中する!
次の章では、さらに一歩踏み込み、「外部受験生が不利を覆し、内部生と同じ土俵で戦う戦略」 を解説します。
3. 外部受験生が不利を覆す最強戦略|内部生と対等に戦う方法とは?

✅ 「外部生は不利」と言われるけど、本当にそうなのか?
✅ 内部生と同じ土俵に立つために、外部受験生が取るべき行動とは?
✅ 「情報・試験対策・環境」すべてを武器に変えて、合格をつかみ取る!
前章では、外部受験生が不利になりやすいポイント を解説しました。
確かに、情報の入手難易度・勉強環境・試験対策のハードル など、内部生と比べて厳しい面はあります。
しかし、実際に外部受験で合格を勝ち取った人は少なくありません。
むしろ、外部受験生は正しい戦略を立てれば、内部生以上に有利な立場で合格を狙うことも可能 です。
この章では、外部受験生が不利を覆し、内部生と同じ土俵で戦うための最強戦略 を徹底解説します!
① 情報戦を制する!過去問・試験傾向を徹底リサーチ

「過去問を解けばいい」と思っていませんか?
確かに過去問は最も重要な教材ですが、単に解くだけでは不十分 です。
✅ 「試験範囲のどの部分を重点的に学ぶべきか?」を分析する
✅ 「この問題と類似した問題にはどんなものがあるのか?」を考える
✅ 「傾向は変化しているのか?」を年度ごとに比較する
過去問を「試験対策の指標」として活用し、どの分野に力を入れるべきかを明確にすることが重要 です。
◆ 情報収集の具体的な方法
✅ 過去問分析ノートを作成する
- 出題された問題の類題を探し、どの範囲から繰り返し出題されているかを記録する。
✅ 試験の難易度・問題形式を把握する
- 直近3〜5年分の問題を徹底分析し、「毎年出題されるテーマ」を特定する。
✅ 合格者の勉強法をリサーチする
- X(旧Twitter)や受験ブログ、noteで、合格者がどのように勉強したかを調べ、効果的な学習法を取り入れる。
過去問を「解くだけのもの」として扱わず、出題意図や関連する類題を見つけることで、より効果的な試験対策が可能になります!
② 「勉強の質」を上げる!内部生以上に効率的に学ぶ方法
外部受験生が内部生に対抗するためには、単に勉強時間を増やすだけでは不十分です。
むしろ、「どれだけ効率的に、質の高い学習ができるか?」 が合格のカギを握ります。
そのために、SNSや研究室見学を活用し、受験者同士で協力し合いながら学ぶ環境を作ること が重要です。
単独での学習では得られない 「アウトプットの機会」 を増やし、知識を整理しながら深めていく戦略 を取り入れましょう!
◆ 受験者同士で切磋琢磨しながら学ぶメリット
1. ディスカッションを通じて知識の定着率がUPする!
インプットだけの学習では、知識が浅いままで終わってしまうことが多いですが、他の受験生と議論することで、知識が整理され、より深い理解につながります。
例えば、過去問の解答について意見を交わしたり、出題範囲の重要ポイントをお互いに説明し合うことで、「分かったつもり」になっていた部分の穴を埋めることが可能 になります。
✅ 実践例
「この問題の解法は〇〇だけど、他にアプローチはある?」
「ここの分野、正直自信ないんだけど、どうやって勉強してる?」
「この単元の要点を3分で説明してみる!」
(自分が説明できれば理解度が高い証拠)
このようなアウトプットを積極的に取り入れることで、知識の定着率が格段に向上します!
2. SNSや研究室見学で「仲間」を見つけ、モチベーションを維持!
外部受験生の多くが抱える問題の一つに、「一緒に勉強する仲間がいない」「孤独な受験勉強がつらい」 という点があります。
しかし、SNSや研究室見学をうまく活用することで、同じ目標を持つ受験生とつながり、勉強を支え合う環境を作ることが可能 です!
✅ 仲間を見つける具体的な方法
→ X(旧Twitter)やDiscordで受験コミュニティを探す
◆ 「#東工大院試」「#東京科学大学院試」「#院試勉強仲間」 などのハッシュタグで検索
◆ 「院試勉強仲間募集」などのツイートをしてみる
※僕のX(Twitterのフォロワーさんは、東京科学大学志望の方が多いので、そちらから探してもらっても大丈夫です👍)
👉 研究室見学時に、他の受験生と積極的に交流する
◆ 研究室訪問で同じ志望の受験生と出会ったら、「一緒に情報交換しませんか?」 と声をかける
◆ 見学後に「試験対策の情報をシェアし合いましょう!」と提案し、SNSやLINEでつながる
「1人で勉強するのではなく、仲間と一緒に成長する」 という意識を持つことで、受験勉強が孤独な戦いではなくなり、モチベーションも維持しやすくなります!
◆ 効率的な勉強法を取り入れ、短期間で最大限の成果を出す!
ディスカッションやアウトプットの機会を増やしつつ、学習の質をさらに高めるために、以下の勉強法を組み合わせましょう。
✅ 「アクティブリコール」で記憶定着率を最大化
過去問を解く際に、「答えを見る前に、自分の言葉で説明できるか?」を意識する
✅ 「ポモドーロテクニック」で集中力を維持
25分集中 → 5分休憩のサイクル で、効率よく学習を進める
✅ 「スキマ時間」を活用し、学習量を最大化
通学中や食事の時間に、TOEICの単語や計算問題を解く
まとめ|「仲間を作り、アウトプットを増やすこと」が合格への近道!
✅ 1人で勉強せず、受験者同士で協力し合う環境を作る!
✅ SNSや研究室見学を活用し、勉強仲間を見つける!
✅ ディスカッションを通じてアウトプットを増やし、知識を深める!
内部生以上に「学びの質」を高めることで、外部受験生でも確実に合格ラインへ到達できます!
③ 外部受験生だからこそ使える“逆転の一手”|内部生に勝つための戦略
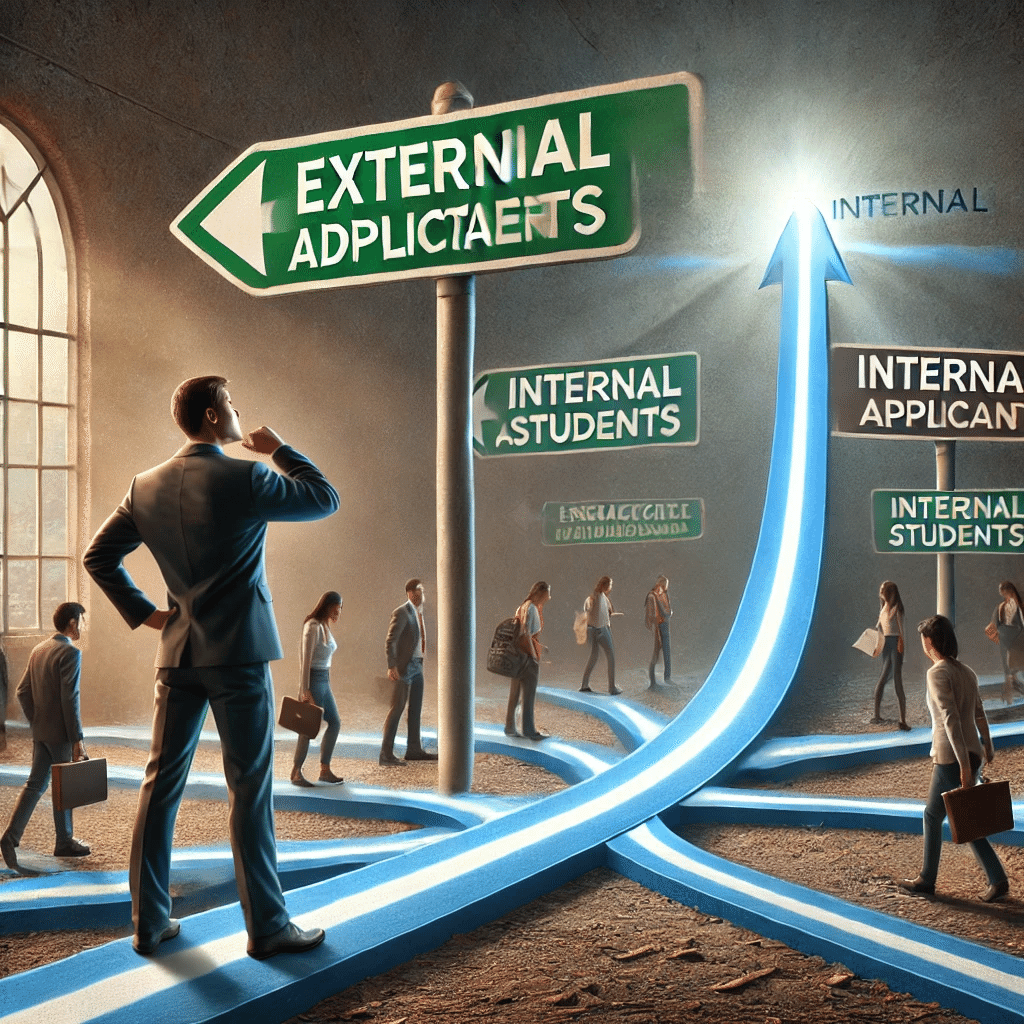
「内部生は有利」と思われがちですが、筆記試験の対策に関しては、むしろ外部生の方が本気で勉強しているケースが多い のです。
なぜなら、内部生は推薦で進学する人が多く、院試の筆記試験に向けて徹底的に勉強しているとは限らない からです。
また、内部生はわざわざ外部の受験予定者と交流する必要がない ため、情報交換や協力の機会が少ない傾向にあります。
しかし、実際に筆記試験を受ける受験生の大半は外部生 であるため、外部生同士でつながりを作ることが、試験対策において圧倒的に有利に働く のです。
🔳受験者同士で情報共有するメリット

1. 徹底した情報収集で、内部生以上に試験を攻略する!
内部生は、授業スライドや過去問と照らし合わせながら勉強できる ため、特に努力しなくても試験範囲の大枠を把握できます。
しかし、外部生は 自分で情報収集を徹底しないと、何をどこまで勉強すればいいのかすら分からない。
そこで、受験者同士で情報を共有し合うことで、試験の出題範囲をより正確に把握し、効率的な対策が可能になります。
✅ 実践例
「過去問でこの分野がよく出てるけど、最近の傾向はどう?」
「この科目の対策、どの参考書を使ってる?」
「〇〇さんと勉強会をやって、解法の確認をしたい!」
こうした情報共有をすることで、試験範囲の抜け漏れを防ぎ、より精度の高い試験対策が可能になります!
2. 受験者同士でつながりを作ることで、勉強のモチベーションがUP!
外部受験生は、周りに院試を受ける人が少ないため、モチベーションを維持しにくい という課題があります。
しかし、SNSや研究室訪問を通じて受験仲間を作ることで、「一緒に頑張っている」という意識が生まれ、継続しやすくなる のです。
✅ 仲間を見つける具体的な方法
◆ X(旧Twitter)やDiscordで受験コミュニティを探す
◆ 「#東工大院試」「#東京科学大学院試」「#院試勉強仲間」 などのハッシュタグで検索
◆「院試勉強仲間募集」などのツイートをしてみる
👉 研究室見学時に、他の受験生と積極的に交流する
◆ 研究室訪問で同じ志望の受験生と出会ったら、「一緒に情報交換しませんか?」 と声をかける
◆ 見学後に「試験対策の情報をシェアし合いましょう!」と提案し、SNSやLINEでつながる
一人で勉強するよりも、仲間と情報を共有しながら進めた方が、勉強の質もモチベーションも大きく向上します!
3. ディスカッションで知識を定着させ、試験本番に強くなる!
問題を解いて終わりではなく、他の受験生とディスカッションすることで、より深い理解につながります。
特に、以下のような勉強法を取り入れると、知識をアウトプットしながら整理できるため、学習効果が飛躍的に向上します。
💡 効果的な勉強法
✅「ファインマン・テクニック」
(人に説明できる=理解している証拠!)
- 「この問題の解法を3分で説明してみて!」
- 「この単元の要点をまとめるとどうなる?」
✅ 「グループ勉強会」
(他の受験生と試験範囲を分担!)
- 例:「〇〇くんはA分野を解説、僕はB分野を解説する」
✅ 「質問を通じて理解を深める」
(答えをもらうだけではなく、議論する!)
- 例:「この解き方で本当に合ってる?」
ディスカッションを取り入れることで、知識の定着が格段に上がり、試験本番でもスムーズに解答できるようになります!
まとめ|外部受験生は「戦略次第」で内部生より有利になれる!

✅ 内部生は推薦で進学する人が多く、筆記試験対策にそこまで本気で取り組んでいないことが多い!
✅ 筆記試験を受ける受験生の大半は外部生なので、受験者同士で情報共有することで試験対策の精度が大幅に向上する!
✅ SNSや研究室訪問を活用し、受験仲間とつながることで学習の質を高め、モチベーションを維持できる!
✅ ディスカッションを通じて知識をアウトプットすることで、理解を深め、試験本番での対応力を向上させる!
外部受験生は、不利ではなく”有利”になれる!
そのためには、情報戦略と仲間との協力が鍵を握る。今日から実践しよう!
4. 合格者の成功事例&勉強計画|東京科学大学大学院に合格するための具体的なステップ

✅ 「実際に合格した人は、どんな勉強をしていたのか?」
✅ 「いつ、何を、どのくらいやれば合格できるのか?」
✅ 「効率よく勉強するためのスケジュールと優先順位」
ここまでの章で、外部受験生が内部生に勝つための戦略 を解説してきました。
この章では、実際に合格した外部受験生の成功事例をもとに、再現可能な勉強計画を紹介 します!
🔳合格者の成功事例|何をどう勉強したのか?

実際に東京科学大学大学院に合格した外部受験生たちは、どのような勉強をしていたのでしょうか?
成功者に共通する3つのポイント を整理しました。
① 試験科目ごとに「優先順位」をつけ、ムダな勉強をしない!
合格者はみな、「何をどこまで勉強すればいいのか?」 を明確に決めて、時間を無駄にしない工夫をしていました。
💡 具体例:ある合格者の戦略
✅TOEIC(英語試験):
1月までに目標スコアを取得し、2月以降は専門科目に集中!
✅専門科目(筆記試験):
過去問を徹底分析し、頻出範囲から優先的に対策!
✅研究計画書(面接対策):
教授との面談を想定し、質問に的確に答えられるよう準備!
👉 「まずはTOEIC」「次に専門科目」など、段階的に学習を進めたことが合格の決め手!
② 「1人で勉強しない!」受験仲間と協力し、理解を深める
合格者の多くは、他の受験生と情報を共有しながら学習を進めていました。
特に、
「分からない問題をそのままにしない」
「過去問の解き方を議論する」
という習慣が、試験本番での対応力UPにつながっています。
◆ 具体例:合格者が実践した学習法
✅SNS(X, Discord)で院試仲間を見つけ、定期的に情報交換!
✅オンライン勉強会を活用し、お互いの理解度をチェック!
✅「問題を解いたら、人に説明する」ことで、知識の定着率を上げる!
👉 「一緒に受験する仲間を作る」ことで、モチベーションも維持しやすくなる!
③ 「過去問の徹底分析」が合否を分ける!
「過去問は解くだけではなく、分析して活用するもの!」
◆ 具体例:合格者が実践した過去問活用法
✅直近10年分の問題を解き、出題傾向を把握!
✅「どの分野が頻出か?」をリストアップし、対策の優先順位を決める!
「この問題の類題はどんなものがあるか?」を考え、追加で問題演習!
自分なりの「解答パターン」を作り、試験本番で迷わないようにする!
👉 「試験の出題傾向を分析し、効率的に対策を進めたことが、合格の決め手!」
🔳合格者に学ぶ!合格までのスケジュールと勉強計画

では、合格者がどのようなスケジュールで勉強していたのか?
実際の体験談をもとに、再現性のある勉強計画 を作成しました。
📅 半年前(1月~3月):基礎固め&TOEIC対策
✅ TOEIC対策を最優先!(遅くとも2月までにスコア確定)
✅ 専門科目の基礎復習&過去問分析で問題傾向を把握!
✅ 受験仲間を作り、情報共有を開始!
💡 ポイント
◆TOEICは、リスニングを重点的に対策!(短期間でスコアを上げやすいため)
◆過去問を眺めるだけでなく、「どの分野が頻出か?」を分析し、優先順位をつける!
◆SNSや研究室訪問を活用し、受験仲間を作って情報を共有し合う!
この時期は、「基礎を固めつつ、試験の全体像を掴む」ことが最優先!
特に、TOEICのスコアは専門科目の勉強時間を確保するためにも早めに決着をつけることが重要です!
📅 3ヶ月前(4月~6月):専門科目の本格対策&研究計画書の作成
✅ 専門科目の過去問演習を本格化!(最低10年分を解く)
✅ 重要な公式・理論を暗記し、解答のテンプレートを作る!
✅ 定期的に勉強会を開き、知識の整理&アウトプット!
✅ 研究計画書の作成を開始し、6月提出に向けてブラッシュアップ!
💡 ポイント
◆受験仲間と「過去問の解答解説をお互いに作る」ことで、理解を深める!
◆「自分が説明できるレベル」まで落とし込むことで、知識を確実に定着させる!
◆過去問を繰り返し解きながら、論理的に説明できる状態にする!
◆解答を覚えてしまい、勉強効率が落ちた場合は、参考書で知識を再確認し、理解を深める!
◆研究計画書は、まず全体構成を決め、5月中旬には一度完成させ、6月に向けて教授や先輩にフィードバックをもらう!
この時期は、「過去問を徹底的に分析し、解法パターンを身につける」 ことが最重要!
また、研究計画書の作成を並行し、6月の提出期限までにブラッシュアップを重ねることが不可欠!
📅 1ヶ月前(7月~試験直前):実践演習&面接対策!
✅ 試験本番を想定し、時間制限ありで過去問を解く!
✅ 専門科目の総仕上げ(頻出分野を中心に復習)!
✅ 研究計画書の内容を再確認し、面接での質問を想定して対策!
✅ 面接練習を受験仲間と実施し、的確に回答できるよう準備!
💡 ポイント
◆過去問演習は「本番形式」を意識し、時間配分を決めて解く!
◆面接でよく聞かれる質問をリストアップし、想定回答を準備!
◆受験仲間と模擬面接を実施し、伝え方や論理的な説明力を強化!
研究計画書の内容を深掘りし、面接時に説得力のある説明ができるようにする!
この時期は、「実践力を高め、試験と面接の両方に万全の準備をする」 ことが最優先!
特に、研究計画書の内容に関する質問に的確に答えられるようにし、面接での印象を強化することが合格の決め手になります!
最終まとめ|東京科学大学大学院 外部受験を成功させるために

この記事で学んだ重要ポイント
1️⃣ 内部受験 vs 外部受験|外部受験生が不利になりやすいポイント
◆ 内部生は推薦があるため、筆記試験対策にそこまで力を入れないことが多い。
◆ 外部受験生は情報が少ないため、過去問分析&受験仲間との情報共有がカギ!
◆ TOEICのスコアが必要なため、専門科目の対策を始める前に早めに終わらせる!
2️⃣ 外部受験生が不利を覆す最強戦略
◆ SNSや研究室見学を活用し、受験仲間を作る!
(情報共有&勉強のモチベ維持)
◆ 過去問を解くだけでなく、類題を考え、出題傾向を予測する!
◆ ファインマン・テクニックやディスカッションを活用し、知識をアウトプット!
3️⃣ 合格者の成功事例&勉強計画|戦略的に勉強を進める
◆ TOEICは遅くとも2月までにスコア確定し、4月から専門科目対策に集中!
◆ 過去問は最低10年分を解き、頻出パターンを徹底分析!
◆ 6月前に研究計画書を仕上げ、面接対策も並行して進める!
✅ 最後に|東京科学大学大学院に合格するために
外部受験生は、確かに情報が少なく、孤独な戦いになりがちです。
しかし、正しい戦略を持ち、計画的に学習を進めれば、内部生よりも有利な立場で試験に臨むことも可能!
1️⃣ 情報収集を徹底し、過去問を軸に効率的な学習を進める!
2️⃣SNSや研究室訪問を活用し、受験仲間と情報をシェアする!
3️⃣アウトプットを意識しながら勉強し、試験本番に強い実践力をつける!
「自分は外部生だから不利…」と諦める必要はありません!
戦略的に学習を進めれば、合格は確実に近づきます。
まとめ|東京科学大学大学院に合格するための最重要ポイント

✅ 外部受験生は情報戦を制することで、内部生以上に有利な立場になれる!
✅ 受験仲間を作り、情報を共有しながら効率よく学習を進める!
✅ 過去問を徹底的に分析し、頻出パターンを押さえる!
✅ 研究計画書・面接対策は早めに着手し、6月までに完成度を高める!
✅ 試験直前は「知識の整理」と「本番を想定した演習」に集中する!
ここまで読んで、「具体的に何から始めればいいの?」と感じていませんか?
✅ 「もっと詳しい合格戦略を知りたい!」
✅ 「具体的なスケジュールや勉強法を手に入れたい!」
✅ 「効率的に学習し、最短で合格を目指したい!」
そんなあなたのために、「東京科学大学大学院受験の基礎ガイドブック:ゼロから合格への手引き」 をご用意しました!
🔳 東京科学大学大学院受験の基礎ガイドブック:ゼロから合格への手引き
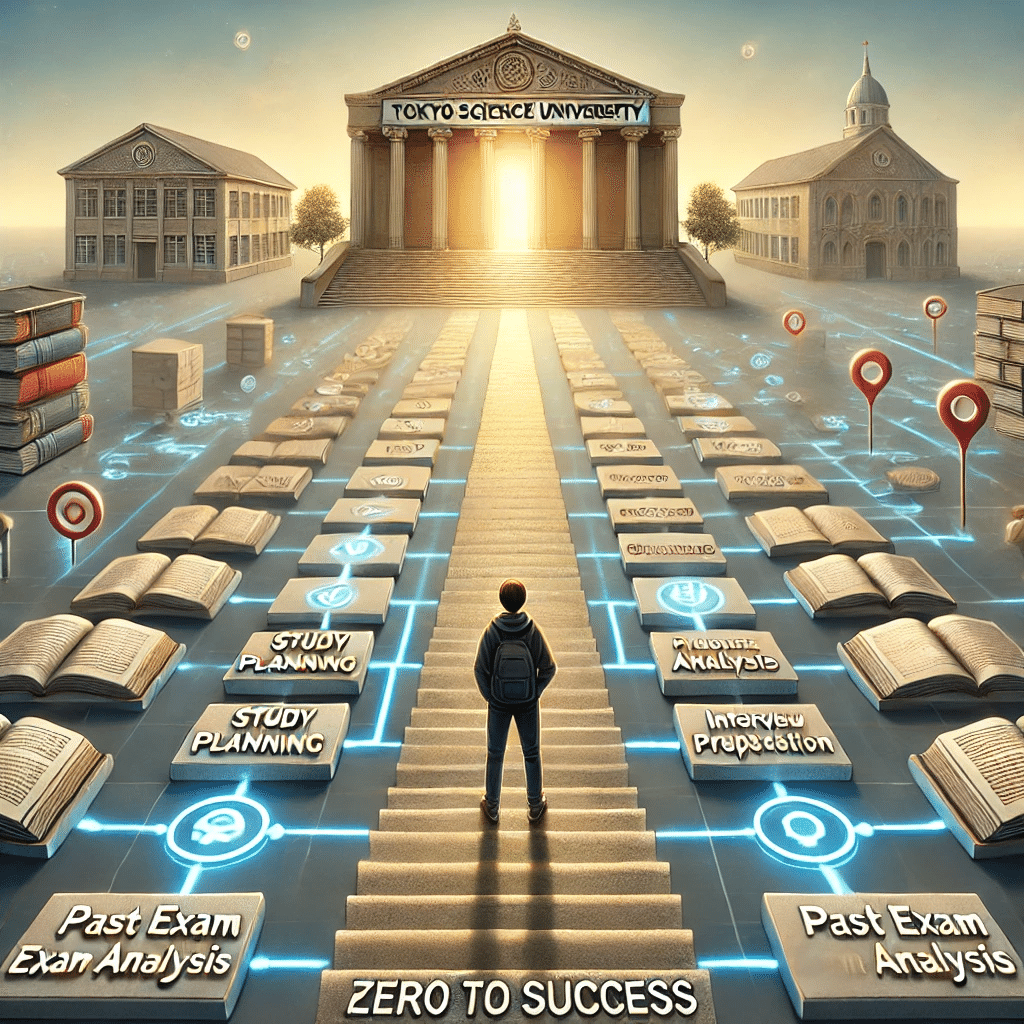
このガイドブックでは、「東京科学大学大学院に合格するためのすべて」 を詰め込みました。
📌 こんな悩みをすべて解決します!
✅ 「何から勉強すればいいのか分からない…」 → 合格者のスケジュールを完全公開!
✅ 「TOEIC・専門科目・研究計画書…やることが多すぎて不安」 → 優先順位を明確にし、最短ルートを解説!
✅ 「過去問を解いているけど、このままで本当に大丈夫?」 → 頻出問題&効果的な解き方を伝授!
✅ 「研究計画書や面接の対策方法が分からない…」 → 高評価を得るための具体的なポイントを解説!
このガイドブックで手に入るもの
✅ 合格者が実践した「半年間の勉強スケジュール」
✅ TOEIC・専門科目の勉強法&おすすめ参考書リスト
✅ 研究計画書の書き方と、合格するためのポイント解説
✅ 過去問や参考書の効果的な勉強方法を徹底解説
✅ 面接の流れ・頻出質問リスト&ベストな回答例
✅ 「一人でも受験仲間を作る方法」&効率的な勉強法
これさえあれば、「どこから手をつければいいのか分からない…」という状態から抜け出し、最短ルートで合格を目指せます!
今すぐ手に入れる!
「東京科学大学大学院受験の基礎ガイドブック:ゼロから合格への手引き」
このガイドブックは、東京科学大学大学院の合格を本気で目指すあなたのための最強のロードマップ です。
「もっと早く知りたかった!」とならないように、今すぐ手に入れてください!
いいなと思ったら応援しよう!

