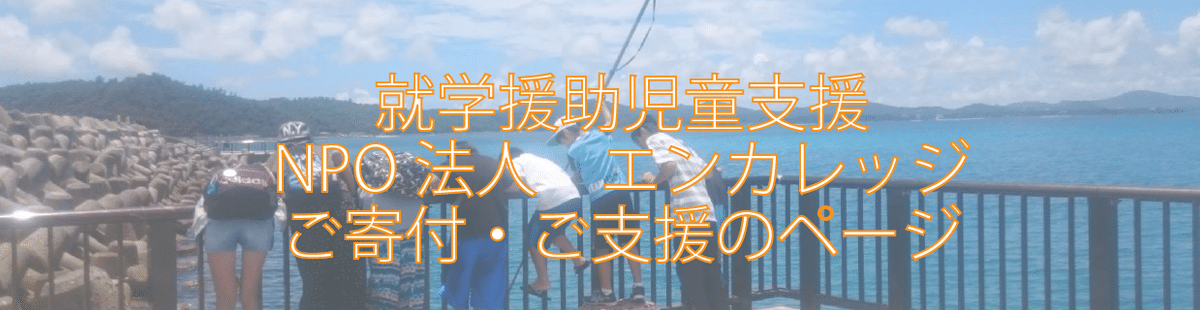応援メッセージ NPO法人バリアフリーネットワーク会議 親川 修 様
いつもご覧いただきありがとうございます。
エンカレッジ広報担当のシロです。
今回は、エンカレッジ設立当初からのアドバイザーであり、理事でもある、NPO法人バリアフリーネットワーク会議代表の親川修さんよりメッセージをいただきました。

社会が充実してきたからこその「就学援助」
いつの時代も、言葉は新しく生まれてくる。「就学援助」というのも、わかりやすく言えば20世紀にはなかったんですよ。
社会が少しずつ豊かになってきて、解決すべき課題が発見される。成熟した社会だから気づくことができる。
例えば発展途上国に「就学援助」という制度はないですよね。
ある程度のゆとりがあってそういった制度が生まれるんです。課題を発見して、その解決を図り、社会をもっとよくしていく過程。
制度自体、本当はない方がいいですけど。
「ヤングケアラー」という言葉も最近よく見かけるようになりました。
しかしそうしたことをしてきた人は昔からいる。そこに光がやっと当たったんです。
我々NPOは、こういったものにどう光を当てていくかを常々考えていかねばならない。
時代と共に問題はブラッシュアップします。それをいち早く察知して、支援をスタートする。
支援をする側は気づきがないといけないし、見る目、見る力、そして知恵がないと何もできない。常にアンテナを貼って、そして学ぶことが大事です。
気づきが早ければ早いほど、豊かな暮らしに繋がっていきます。
やり続ける責任と知識を
気づいて考えた人がやり続けなければいけない。
NPOや福祉だけでなく、全てにおいて、そこが一番大変で大切なところだと思います。
途中で投げ出すと、ダブルマイナス、より悪い方向になる可能性が大きい。そこまでの責任を持って、信念を貫き通さなければいけない。
エンカレッジも、坂(エンカレッジ理事長)の一代では終わらない社会課題解決に挑んでいる。我々は継いでいく人も育てていく必要があります。
そして支援するときは、困ってるときに一気に支援を開始することです。中途半端なお手伝いではなく、「今だ!」と思ったら一気に入る。
人は常にチャンスがあるわけではありません。それは支援する側の私たちも同じ。
時が来たら、百科事典から何から何まで全部持っていって、使える支援、制度を困ってる人に教える。
小出し小出しだと、結果として支援にならない。
「今日はこんな支援を紹介します・・」が続くと、支援される側は分からなくなって、「もういいよ」、ってなってしまう。
なのでやっぱり知識が大事です。助けてほしい、という人は、ワラをも掴む思い。知識という土台のもとにしっかり足をつけないといけない。
そして、私たちはジェネラリスト(広範囲にわたって知識を持ちアドバイスする人)になるべき、そして育てるべきです。
支援するにあたって、カードはたくさんあった方がいい。
ジェネラリストはすぐなれるものではない。普段から学び、問題意識の高い人たちがなれる。
制度そのものは我々では作れません。いかにその制度を使えるように知恵を絞る。それこそ屁理屈並べながらでも戦えるか、です。
本当に助けたいなら、とにかく勉強すること。中途半端ならやらない方がいい。戦うくらいの気合いがないといけない。
また、支援するカードがない人はある人に相談しにいったらいいだけ。最短の道です、わかる人に聞く。
「いつもこの子のことを考えてまして・・」と言っても、行動がなければ支援をやっていないのと同じ。自分が知らないことを恥じるのではなく、わからないことはとにかくわかる人に聞くこと。3人よれば文殊の知恵です。浅はかな知恵で支援にあたってはいけない。
学校でもエンカレッジでもどこでも、先生たちは一人で解決しようと思わなくていいんです。
子どもは「社会の子ども」
「就学援助」ってあったんだね、っていう世界になると思います。これは、解決ではなく、人口が減るから。
子どもを産み育てやすい社会とはなんなのか。
沖縄の子どもたちを単なる労働力として育てるだけでいいのか、未来を担う人材として育てていくのか。私たち大人は考えなければいけない。
そして子どもたちは生まれる環境を選べない。社会がどうにかしなければいけません。
子どもたちは障害があろうがなかろうが、どんな過程に生まれようが、等しく愛護されるべき存在です。
子どもは、「社会の子ども」。皆で育てていかねばならない。
エンカレッジに来ている子たちは、どうにかしたい、助けてほしいとサインを出した子たち。
いくら友人同士で「高校なんていかんでもいいよ」と話したとしても、本当は高校に行きたい。
この子たちに動機付けをしっかりすれば、そこからまだ繋がっていない、支援を必要としている子たちもついてくる。何か一つ引っ張れば、芋づる式に上がってくると思います。
なんでもきっかけです。例えば、オートバイに憧れる子へは、原付免許の試験勉強の本を渡せばいい。原付免許一つとるにも勉強しなければいけない。
そこから気づいていくんです。
メッセージをいただき、私たちが子どもたちへの支援を行う上で、大切なこと、忘れてはいけないこと、改めて実感したことと気づきがありました。
親川さん、ありがとうございました!
NPO法人エンカレッジのホームページでは、過去に親川さんを講師に迎え実施した職員研修のレポートも紹介しております。
そちらも是非ご覧ください。