
ヴァンパイア・レタスと
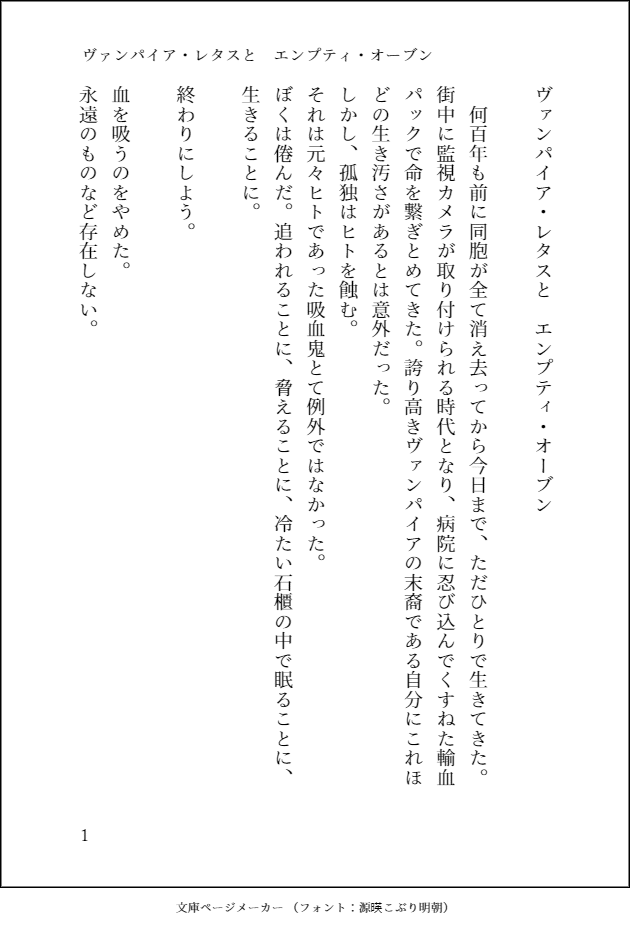
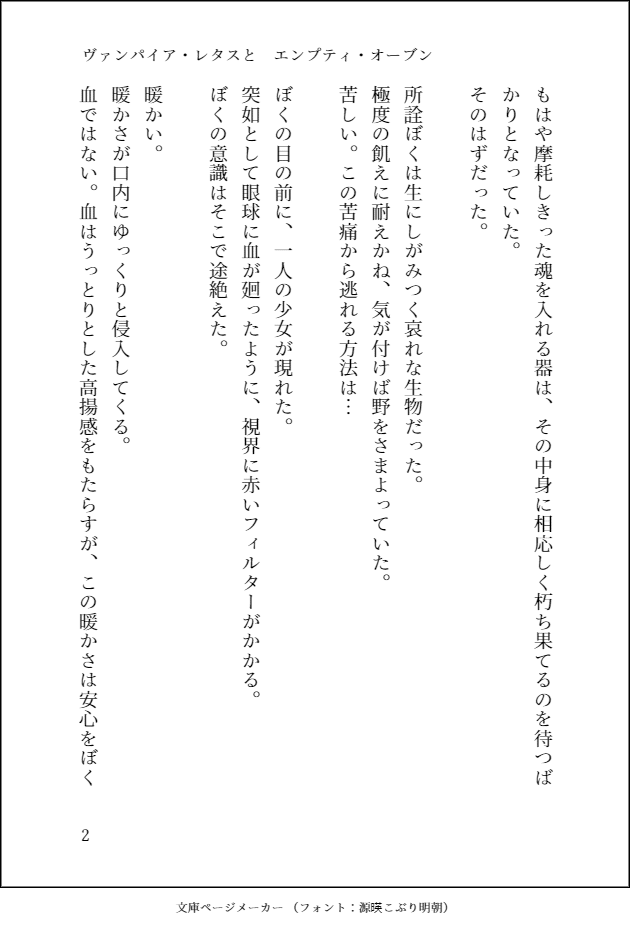






何百年も前に同胞が全て消え去ってから今日まで、ただひとりで生きてきた。
街中に監視カメラが取り付けられる時代となり、病院に忍び込んでくすねた輸血パックで命を繋ぎとめてきた。誇り高きヴァンパイアの末裔である自分にこれほどの生き汚さがあるとは意外だった。
しかし、孤独はヒトを蝕む。
それは元々ヒトであった吸血鬼とて例外ではなかった。
ぼくは倦んだ。追われることに、脅えることに、冷たい石櫃の中で眠ることに、生きることに。
終わりにしよう。
血を吸うのをやめた。
永遠のものなど存在しない。
もはや摩耗しきった魂を入れる器は、その中身に相応しく朽ち果てるのを待つばかりとなっていた。
そのはずだった。
所詮ぼくは生にしがみつく哀れな生物だった。
極度の飢えに耐えかね、気が付けば野をさまよっていた。
苦しい。この苦痛から逃れる方法は…
ぼくの目の前に、一人の少女が現れた。
突如として眼球に血が廻ったように、視界に赤いフィルターがかかる。
ぼくの意識はそこで途絶えた。
暖かい。
暖かさが口内にゆっくりと侵入してくる。
血ではない。血はうっとりとした高揚感をもたらすが、この暖かさは安心をぼくに与えてくれた。
これはまるで…そう。
記憶の彼方のその先にある記憶、覚えているはずのない記憶が立ち上がって姿を現した。
母の胎内、羊水の中に浮かぶ自分を認識したところで、ぼくは光に包まれた。
目が覚めると、質素な小屋のベッドに寝かされていた。窓がないので外の様子はわからない。
閉じられたドアの隙間から、朝日が差し込んでいるのが見えた。
本来であれば消滅の恐怖から全身が硬直しているはずだ。しかしぼくは起き上がってドアを開いた。
生まれて初めて見る朝だった。世界はこんなにも美しいものだったのか。
朝日が野を、遠くに見える山並みを、はばたく鳥たちを、そしてぼくを黄金の光で包み込んだ。
気づけばぼくの目からは、涙が溢れていた。
許されている。
太陽を忌み嫌い、明るい世界を拒絶したはずの吸血鬼が、昼の世界に存在を許されている。
ぼくは、ここにいていいのだ。
ぼくはようやく自分の状況を把握した。
あのとき行き会った少女。彼女は行き倒れていたぼくを見つけて看病してくれたそうだ。ぼくの命を繋いだあの安心は、彼女の住む牧場で採れた牛乳だった。
のちに知ったことだが、母乳とは母親の血液を元に作られているらしい。極限状態になっていたぼくの身体が、血ではないものを受け付けたのはそのためだろうか。
しかして、血ではなく牛乳を摂取して命を繋いだぼくは、それまでとは体質が全く変わってしまったのであった。
太陽の光が平気になった代わりに、夜目はすっかり利かなくなった。
人間を目の前にしても、あの乾くような吸血欲求は引き起こされない。
その代わりに、すっかり牛乳の虜になってしまった。この甘く香しい液体に比べれば、血液など鉄臭くてとても飲めたものではない、とまで思っている自身の変化に戸惑いもある。
血も吸わない、太陽も平気なぼくは、もはや吸血鬼を名乗る資格はないのかもしれない。だが、そんなことはもうどうでもよかった。
だってさ、人間の食べ物めっちゃうまいんだもん。何なのあれ!?
牛乳も最高だけど、牛乳からチーズとかヨーグルトとかできるって何それ魔法?甘くても塩辛くても合うなんて許されるのか?チーズは最初臭すぎて、ヴァンパイアなのがバレて毒殺されるのかと思ったが、ワインと合わせたら至高の食べ物と化した。本来のミルクの面影が戻ってきて、ワインの刺激をまろやかに包んでくれる。
トウモロコシの粉を煮たママリガは、最初は微妙だったが、続けて食べているうちになんだか癖になった。
肉も最高。なぜぼくの一族は肉には見向きもせず血だけを摂取していたのか。しかも調理の工夫もなしに。調味料がありさえすればヴァンパイアの食文化には革命が起きていたというのに。数百年を損していた気分だ。
住みこませてもらった牧場では、ぼくに関心を示す若い娘も何人かいた。それはそうだろう。記憶喪失(という体をとった)のミステリアスな美青年、モテる要素満載だ。
だが、もはや捕食対象が人間でなくなったぼくには何の意味も見いだせない。性欲とかほんとマジどうでもいい。そもそも生殖なんてその後子孫が恒久に続く保証も何もないただの博打ではないか。
その点食は素晴らしい。滅びることがない。他の命で自らの命を造り、また自らの命をもって他の命を造る。食べて、食べられることで己は永遠となる。
だから、ぼくは食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べて食べまくった。
いつの間にか青白い顔はすっかりバラ色の頬になり、レストランの看板に描かれたらすごく繁盛しそうな顔だな、と言われるようになった。こうなると言い寄ってくる娘はいなくなった。代わりにやたらと年配の女性から食べ物を貰うようになった。ぼくが食べている顔を見るのが好きだという。同じモテでもこっちの方が実益があって良い。
そのうち、料理のレポーターの仕事をしてみないか、という声がかかった。それなら古今東西の料理が食べられる。渡りに船と二つ返事で引き受けた。
そんなわけで、ぼくは今日もカメラに向かって幸せそうな表情で食レポを行う。
「うわー!レタスが輝いてまるで野菜の宝石箱や!」
いいなと思ったら応援しよう!

