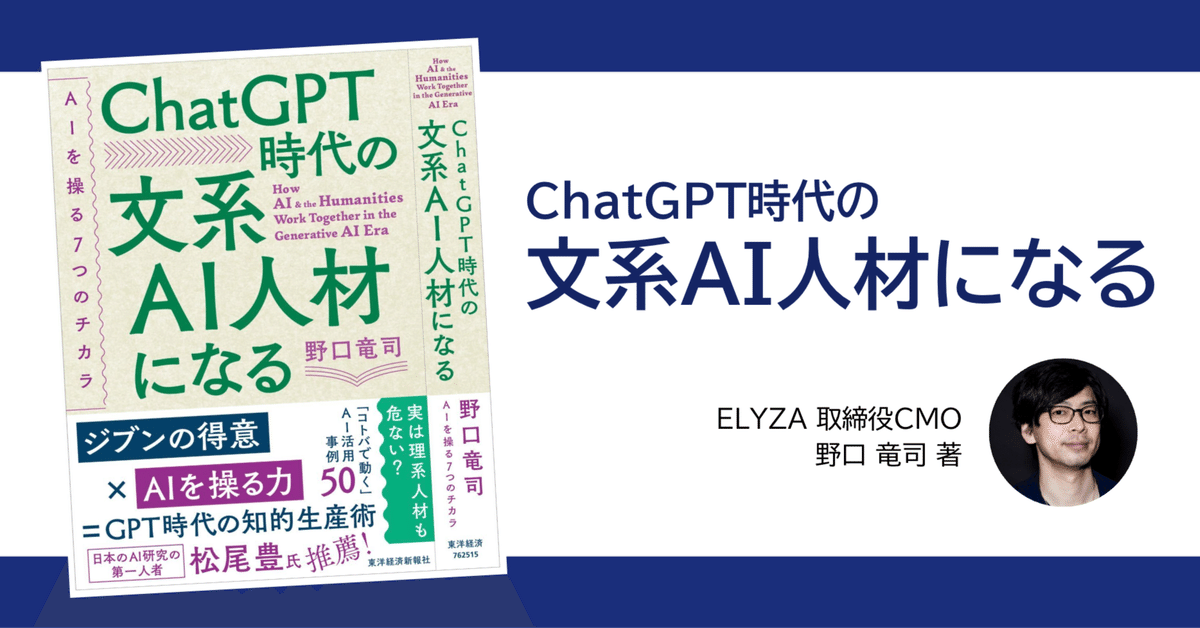
【教えて野口さん(前編)】新著『ChatGPT時代の文系AI人材になる』に込められた想いとは?
【Profile】野口 竜司 Noguchi Ryuji / 取締役CMO
ZOZO NEXT 取締役CAIOやZホールディングス Z AIアカデミア幹事を経て現職。カウネットの社外取締役、三井住友カードのHead of AI Innovationを務めるなど、大企業でのAI戦略/企画策定を多数リードしている。日本ディープラーニング協会 人材育成委員やDX MGR Club幹事も務める。新著『ChatGPT時代の文系AI人材になる』が2023年10月4日発売される。
経営者や企画人材に必要なスキルが大きく変わる
新著『ChatGPT時代の文系AI人材になる』はどのような内容ですか?
GPT時代のAIの基礎やプロンプト術、またAIのマネジメントやケーススタディを体系的にまとめた、非常に実用的な内容になっていると思います。前作『文系AI人材になる: 統計・プログラム知識は不要』の骨格は維持しつつ、内容はChatGPTなどの新しい技術に合わせてガラリと更新しています。
具体的には、AIの基本的な用語や仕組みを理解し、事例を知ることで、より多くの人がAIを活用できるようになると考えて執筆しました。ChatGPTなどの生成系AIに限らず、AIの基本から応用までを網羅しているので、まだAIにほとんど触れたことが無いという方はもちろん、より高度なAI活用を目指す方にも役立つと思います。
今回、執筆しようと思ったきっかけは何だったのですか?
ChatGPTが一気に普及したことで、経営者や企画人材に必要なスキルが大きく変わると思ったからです。個々人のキャリア、会社の事業、さらには日本全体に影響が及んできますので、書くなら今しかないと感じました。
前作の帯に「AIはExcelくらい誰もが使うツールになっていく」と書いていたんです。奇しくも今それが現実になろうとしています。AIは「つくる」から「使う」に変わる、まさにそのタイミングだと思います。

根底にあるのは新しい技術への感動、未来へのワクワク
野口さんとAIの出会いはいつですか?
AIとの出会いは大学時代です。ゲーム理論を専攻していたことから、機械学習やデータを扱うことに興味を持ち、Googleの登場をきっかけにビッグデータ活用へ関心がつながり、そこからAIへという流れです。
ロボットやヒューマノイドには高校生の頃から興味があったので、ルーツとしてはもっと以前からあったのかもしれません。SFが好きで、未来へのワクワク感が刺激されます。特に『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は影響を受けた作品です。あの作品で描かれた内容のかなりの部分が、いま現実になっていますよね。
ワクワクや感動が原動力になっているのですね。
その通りですね。技術に対するリスペクト、新しい技術に対する「感動力」のようなものがある気がしています。あとはそれをいち早く試して取り入れていくことが私の楽しみでもあり、現在の仕事にもつながっています。
AIについても、私自身がAIに早くから感動し、この技術をより多くの人に知ってもらいたいと思っていることが大きいですね。ELYZAに参画するきっかけとなったのも、『ELYZA Brain』の技術や、その技術と顧客に向き合う曽根岡さん、松浦さんらの姿勢に感動したことでした。
編集注:『ELYZA Brain』はELYZAが開発した日本語特化の大規模言語モデル(LLM)。2020年にはテキスト分類問題で人間超えの精度を達成した。

直接関わる人たちだけでなく、より多くの人へ「AI人材に」というメッセージを届けたい理由は何ですか?
AIは一部に独占されるものではなく、多くの人が使うべきだと考えているからです。今後のキャリアやビジネスを考えた際に絶対に必要だというロジカルな理由と、「こんなに楽しくてワクワクするものを使わないなんてもったいない!」という想いと、両方ありますね。
ビジネスパーソンの方だけでなく、これから社会人になる若い方にもぜひメッセージを届けたいと思っています。大学生、高校生の方にAIの授業をした経験があるのですが、若い方ほど新しい技術に対する吸収力が高いですよね。若い世代にこそ、早く、良い情報を提供したいですね。若い世代が変われば、社会全体が変わると信じています。
最後に、改めてメッセージをお願いします。
やはり私の根底にあるのは「この技術は素晴らしい、多くの人に使ってもらいたい」という想いです。書籍でも、AIという技術がもたらす新しい喜びや可能性に焦点を当てていますので、楽しむ気持ちで手に取ってもらえたらと思います。
この書籍が多くの方に届き、AIを使いこなす方が増え、AI実用化の流れを加速させる一助となれば嬉しいです。
編集より:
野口さんの新著『ChatGPT時代の文系AI人材になる』は10月4日発売予定です。ご興味いただけた方はぜひご予約ください。また野口さんに企業のLLM活用の現状や課題について聞く「後編」も近日公開予定です。
