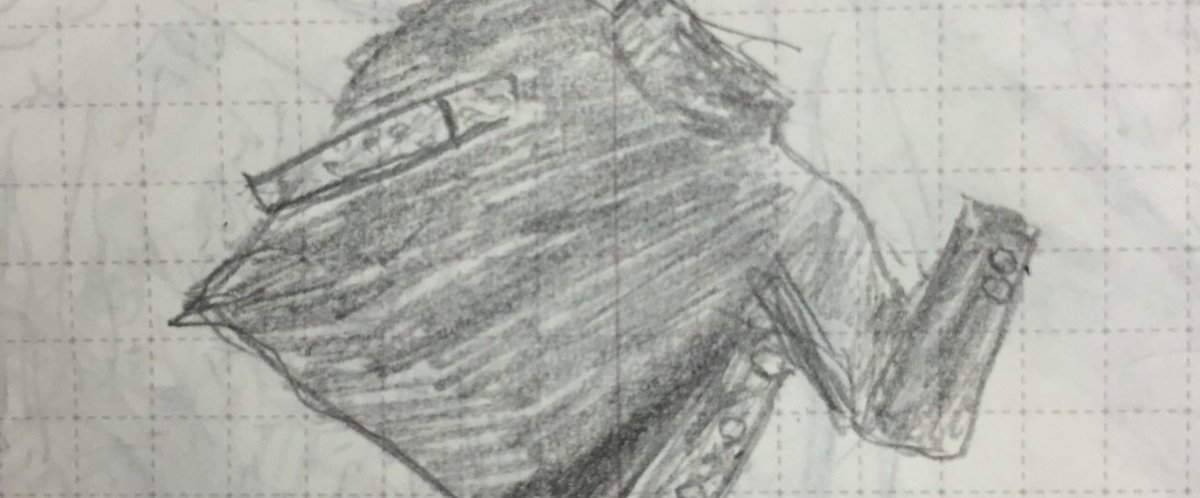
小説『これが僕のやり方』――⑫僕の最終回
「殺す?」
正憲の言葉は、脅しでもなんでもなく本気だった。先ほど僕に伸びてきた拳から、肌が強制的に反応してしまうような感じたことがない空気を感じた。それがたぶん、殺気なのだろう。
しかし、
「『僕が正憲に殺されるわけない』と君は思う」
正憲の微笑みが、僕の精神に少しずつ傷をつけていく。心まで読まれている。
「読まれとるんじゃない。僕が想像したんだよ。それに君はなぞっただけ」
考えないようにしても、僕の中で疑問が膨らんでいく。何も解決されない。刑事ドラマの中で犯人は、主人公の説明台詞でなぜ自分が逮捕されるに至ったか知ることができる。そんなのリアルじゃないけど、リアルじゃなくてもいいから犯人は説明してほしいと思うだろう。
僕はゆっくりと学ランを脱いで、卒業証書が入った筒と一緒に地面に置いた。
「まぁ、僕は捕まらんけど」
パチンと指を鳴らし、右足に力を込める。空いていた正憲との距離を一瞬で一歩で詰める。右手を正憲の喉に伸ばした。正憲は僕の視界から消えた。と思うと僕は膝をついていた。鳩尾がぐわぁぁっと熱くなり、吐き気に耐え切れず胃液が押し上がってきて吐いた。
あの一瞬で、僕の鳩尾に打撃を加えて移動したということなのだろう。それはつまり想像を超えた想像。
「砂にする力を僕の喉めがけてやるって……殺す気満々じゃん」
背後から正憲の声がする。
「ほんと強くなったよねー。ちょっと力使っただけじゃ倒れんもんなー。でも所詮我流だ。伸びしろがない」
僕の腰に正憲の足が乗っている。僕は抵抗しようにも、苦しくて動けない。
「よくドラマとかで止めを刺す前に説明するだろ。あれ、あんなん言う前に殺せばいいのにって思っとったけど、なんか言いたくなるなー」
足をグリグリと押し付けられている。
「段田くんみたいな興味本位でこういう能力を使われると迷惑なんだよ。僕たちの家系はね、君たち一般人には現実味がない職業なんです。これが世間にばれると生きづらくなる。だから、君みたいな突然変異を殺さないといけないんだ」
僕は口の中に残った胃液と唾を吐いた。
「僕がなんでこの能力に目覚めたか知っとる?」
「知らん。
ていうか無駄だで。君はもう僕の想像の中……え?」
僕は両膝を着きながら、上半身を起こし、正憲と対峙した。水溜りから両手で水を掬うように手の平を上に向けていた。その手の上には豆電球ほどの小さな光の玉が浮かんでいた。
正憲は僕を見下ろしている。
「出せるようになったんだ。きれいだろ?
誰かに見てほしかったんだ。技の名前も付けた。『光源』」
「そんなことのために……。
僕は腹が立っとる。
人間には生まれ持った能力がある。会社を立ち上げて雇用を生んでたくさん税金を収めて世の中を動かすような力じゃない。テクノロジーを進化させて人間を更なる高みへ導く力だ。優れた者はそれ相応の立場に立たなきゃいけない。それがやりたくてもできない人のために」
「大そうなこと考えとるんだな」
「お前にはわからんだろう。所詮ふつうの中学生だもんな」
視界が白くなったと知覚すると、瞬き1つで公園の景色が戻った。
正憲は右手に、僕が出したエネルギー波よりも大きくてまぶしい球体を浮かせていた。
「ちなみにその技の名前は『大陽』だ。
自分以外のエネルギーが体内に入ると、エネルギーは反発を起こして弾き合う。自分が磁石のS極なら、他は全部N極だ」
正憲はひざまずく僕に向かってエネルギー波を放った。シャボン玉のようにゆっくりと空気中を移動して、学生服をすり抜け、僕の胸の中に入っていく。
すべてが入り終わる前に、胸の中で何かが弾けた。胸を中心に破裂する箇所が広がっていく。今まで味わったことのない激痛が全身に広がろうとしていた。しかし、全身に回る前に僕は死んだ。

<了>
あとがき
これを書き始めたきっかけは、感じたことのない感覚を描写するためでした。それがエネルギー波だったというわけです。
好きで書いていましたが、スキが1つもつかないとやっぱりショックといいますか、書く意味あるのか、などと思っていました。
しかし、見切り発射すぎて構成も、展開もわかりにくくなってしまったのは否めません。それ以外にも、そのときのテンションで内容が作用されるということなどもあり、僕自身至らぬところがありました。すいませんでした。
3話で終わる、とかにしないとだめですね。
最初に思い描いていたのは、とうとう夜未知くんという不良を倒すためにエネルギー波を放った段田くん、を止めるために正憲がエネルギー波をうつみたいな流れでした。その後、全能感に酔っていた段田くんが打ちひしがれる、みたいな感じです。その後、高校生になって本格的なバトル展開に持っていくという。
僕が、ちょっとずつちょっとずつ変化していく、違和感がどんどん大きくなるような話が好きなので、助走が長くなってしまったかもしれません。
反省点はいろいろありますが、荒削りな作品の一部でも読んでくださった方々に感謝しています。
これからはできるだけ多く小説を読んでもらえるように工夫して取り組んでいきたいです。
最後が小学生の作文みたいになってしまいましたが、これが僕のやり方です。
おわり
