
現代の若者たちの孤独、不安、愛、セックスについて【次に観るなら、この映画】4月16日編
毎週土曜日にオススメの新作映画をレビューする【次に観るなら、この映画】。今週は3本ご紹介します。
①フランスの名監督ジャック・オーディアールが、デジタル化された現代社会を生きるミレニアル世代の男女の孤独や不安、セックス、愛について描いたドラマ**「パリ13区」(4月22日から映画館で公開)|bold**
②衣料品工場の過酷な労働環境と低賃金に立ち向かう女性たちの姿を描いたヒューマンドラマ**「メイド・イン・バングラデシュ」(4月16日から映画館で公開)|bold**
③かつて日本の山々に実在した流浪の民・山窩(サンカ)を題材に、孤独な少年とサンカの一家の交流を描いたドラマ**「山歌」(4月22日から映画館で公開)|bold**
劇場へ足を運ぶ際は、体調管理・感染予防を万全にしたうえでご鑑賞ください!
「パリ13区」(4月22日から映画館で公開)
◇リズム感あふれる瑞々しいモノクロの映像が織りなす、2020年代のヌーヴェル・ヴァーグ(文:フリージャーナリスト 佐藤久理子)
最近ギャスパー・ノエにインタビューをしたとき、彼が本作のことを挙げ、「自分は子供の頃、この地区に住んでいたことがあったけれど、映画でこれほど美しく描かれていることに驚き、感動した」と語っていて、深く同意せずにはいられなかった。
なぜなら、本作の舞台となっているパリの13区は、60から70年代の性急な都市開発のせいで、やたらニョキニョキと不揃いなコンクリートの団地が立ち並び、もっぱらパリらしからぬ景観を見せているからだ。さらに中華街をはじめ多彩な人種に溢れる点も、オスマン建築の並ぶクラシックなパリとは異なる。そんなエリアを選び、モノクロという選択を用いてここまで映画的な空間に仕立ててみせたジャック・オディアールの手腕にまず、脱帽する。

もっとも、ここに写し出されるのは特別な場所ではない。平凡な通り、よくあるカフェ、大学。そんな月並みな風景が、柔らかな光、挑戦的なアングル、俳優たちの生き生きとした佇まいにより、はっとするほど新鮮な風景に生まれ変わる。
ルームメイトを探していたエミリーは、応募してきた男性教師カミーユを見て、その晩すぐにベッドを共にする。ふたりの共同生活が始まるものの、エミリーにとって彼は「セックスもする」ルームメイトでしかない。

一方、社会人を経て大学に復学するため、地方からひとりパリに来たノラは、若い学友たちと馴染めず孤独な日々を味わううちに、ネットで知り合った元ポルノスターのセックスワーカーの女性と親密になっていく。そんななか、学友の悪戯が元で大学をやめることになったノラは、不動産会社の職に就くが、そこにはパートタイムで働くカミーユがいた。
個々のスケッチがやがて交差し、今を生きる若者たちの等身大の姿を描く鮮烈な絵巻となる。その瑞々しさは、脚本にセリーヌ・シアマ(「燃ゆる女の肖像」)とレア・ミシウス(「アヴァ」)という若手監督が加わっていることもあるのかもしれない。

さらにその滑らかな語り口を支えているのが、本作の音楽性だ。この映画の音楽はたんなる伴奏でも効果音でもない。音楽が物語のリズムの根幹を支え、カメラワークもまたそのリズムにのって躍動する。たとえばエミリーが中華レストランで踊り出すシーンのなんと自然で軽やかなことだろう。まるでゴダールの映画でステップを踏むアンナ・カリーナを彷彿とさせるようだ。
実際本作のところどころにヌーヴェル・ヴァーグへのオマージュを感じることは、難しくないだろう。そう、いまの若者はジャン=ポール・ベルモンドとジーン・セバーグが歩いたシャンゼリゼではなく、さまざまな人種が共存する13区を歩くのだ。2020年代のヌーヴェル・ヴァーグを生み出したオディアールの意匠を祝福したい。
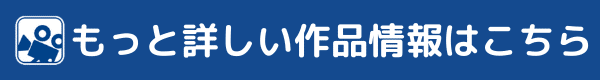
「メイド・イン・バングラデシュ」(4月16日から映画館で公開)
◇武器はもちろんスマホ。ブラック企業に反旗を翻した若き女性工員を応援しよう(文:映画.com編集長 駒井尚文)
バングラデシュという国の存在を初めて認識したのは、1970年代のことでした。きっかけは、ジョージ・ハリスンがシャンカールとともにニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで行った「バングラデシュ・コンサート」です。
公演が1971年8月で、同じ年の12月(日本では1972年)に3枚組のアルバムが発売されました。ジャケットにはひとりの飢えた子どもの姿が映っており「ロックのアルバムなのに、このジャケットは何なんだ?」と大いに驚いた記憶があります。バングラデシュ・コンサートは貧しいバングラデシュの人々を救済するための、チャリティーコンサートだったのです(映画として公開もされています)。

およそ50年の月日が流れた2022年、そのバングラデシュから「メイド・イン・バングラデシュ」という映画が届きました。かつて世界の最貧国のひとつで、多くのサポートが必要だったバングラデシュの人々も、今では立派に職を得て、女性たちも自立できるようになりました。この映画に登場する女性たちは、カラフルな民族衣装をまとい、日本製のミシンを使いこなしていて、とても誇らしく見えます。
しかし、まだまだ問題は山積み。彼女たちは低賃金で長時間労働を強いられていて、工場経営者や、そのクライアントであるファストファッション企業から搾取されている状態です。50年前よりは遙かにマシ。だけど、相変わらず生活は苦しい。映画の中で主人公シムが労働問題活動家に「5000タカ貸してください」とお金を無心する場面がありますが、ネットで調べてみると、5000タカは7250円(2022年4月現在)ほどで、それが彼女の月収相当の金額です。

低賃金にあえぐ女性工員シムは、活動家の協力を得て、労働組合の結成を決意します。工場で働く労働者みんなの力を合わせて、工場経営者に対して賃上げの交渉をするのが組合結成の目的です。しかし、シムの闘争はなかなか前に進みません。コンプライス違反を何とも思わないブラックな経営者は、卑劣な手段を講じてシムとその仲間たちを苦しめます。
バングラデシュの街並みや、主人公シムが勤める工場や、彼女の自宅の描写を見る限り、「この映画はいつ頃の話だろう?」「日本で言うところの昭和時代かな」という疑問を覚えるほど。そんなアナログでレトロなバングラデシュの風景にあって、この話が現代のものであることを示す唯一のツールはスマートフォンです。主人公シムがスマホを軽やかに使いこなすことで、ドラマをダイナミックに動かします。

女性監督案件にして、岩波ホール案件でもある本作は、今どきの若者案件でもありました。終盤、主人公シムが頭の固い役人に対して取った行動に、私は小さくガッツポーズをしました。話の展開に多少のストレスを感じることがあっても、我慢してシムを応援しながら最後まで見て下さい。

「山歌」(4月22日から映画館で公開)
◇山と共生する生命が伝える、大切なこと。(文:映画.com編集顧問 髙橋直樹)
笹谷遼平監督の「山歌」を観て、マーティン・スコセッシ監督の「ジョージ・ハリスン リヴィング・イン・ザ・マテリアル・ワールド」(2011)が思い浮かんだ。1974年に発表された同名アルバムのタイトル曲で、ジョージ・ハリスンは「物質社会で迷子にならないように、心に回帰しよう」と歌っていた。
舞台は1965年、山奥の田舎である。戦後から高度成長へ、誰もが豊かさの象徴たる“モノ”を求めてがむしゃらに働いた時代。東京五輪から大阪万博に突き進んだ日本にはビルが建ち並び、道路や鉄道が整備され、至る所にモノが溢れた。

東京オリンピックの翌年、進学を控える中学生の則夫(杉田雷麟)は東京を離れ祖母の家で受験勉強することになる。じっとしていても汗ばむ夏。勉強に集中できない則夫は芋泥棒に出くわす。「ちょっと待て!」と追いかけると、山道を悠々と歩く男に出会う。男が「返せ」と告げると少女は「腹が減った」と口を尖らせる。ふたりは父と娘だった。
ある日、山で道に迷った則夫は、その男、省三(渋川清彦)に導かれて、娘のハナ(小向なる)とタエばあ(蘭妖子)が暮らす、雨よけだけの簡素な住まいを訪れる。彼らは山に生きる人だ。“山窩(サンカ)”と呼ばれ、渡りを続ける鳥のように季節に応じて山から山へと移動していたとされる。

漂泊の民、日本のジプシーともいえる人々が存在していたことを僕は知らなかった。自然の営みに寄り添って生きる人=山窩を撮りたいと考えた笹谷監督は、改稿を重ねて「黄金」と題された脚本を仕上げ、伊参スタジオ映画祭で【シナリオ大賞】を受賞する。
歌うことは訴えること。伝えたいという監督の願いで「山歌」と名づけられた初長編は、ひと夏の特別な出会いを通して少年が人生の選択をする物語だ。日本人の価値観がモノに向かった時代、地域開発が豊かさをもたらすと信じる父(飯田基祐)は、学歴こそが人生を開くのだと息子に勉強を強要し、学もなく、経済にも頓着しない山窩を蔑み「もう会うな」と命じる。

何かが違う。これまで「正しい」と教えられてきたことに大きな疑問を抱いた主人公は、ある決意を胸に秘めて背筋を伸ばす。
朝の靄に浮かび上がる緑の山並み、渓流を泳ぐ魚たち、陽光に向かって木々が背伸びし、蜘蛛の巣で蜻蛉がもがいている。獣たちの道を歩いた先で大樹を抱きしめると、山の恵みが優しく全身を包み込む。僅か二週間、荒天下で撮影された自然、山と共生する生命たちは、何か大切なことを伝えようとしている。考えるのではなく感じるのだ。モノだけでなく情報が溢れる今だからこそ、心を穏やかにして向き合いたい作品だ。

