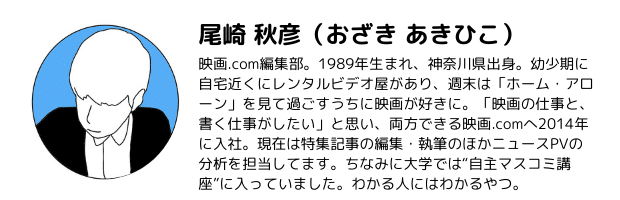魂をきしませる衝撃作 オススメの良作を紹介【次に見るなら、この映画】1月16日編
映画.com編集部が、毎週土曜日にオススメ映画をレビュー。
今週は、映画館で鑑賞できる新作から、見れば絶対に心に響く衝撃作・感動作3本を選んでみました。全国的に緊急事態宣言の発出が広がりつつあります。体調管理・感染予防を万全にしたうえでご鑑賞ください!
①少年院を出所したばかりの青年が、立ち寄った村で聖職者になりすましていた、という実際の事件を題材にした衝撃作「聖なる犯罪者」(公開中)
②勝手に救急車を運転し、勝手に救命活動をする“闇救急隊”を営む家族に密着したドキュメンタリー「ミッドナイト・ファミリー」(1月16日から公開)
③挫折した天才調香師が人生崖っぷちな運転手との交流を通して再生していく姿を、ハートウォーミングに描いた「パリの調香師 しあわせの香りを探して」(公開中)
週末に、どんな映画を見ようか……そう悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
「聖なる犯罪者」(公開中)
◇ヒリヒリする獰猛さと、祈りの静寂さと。観る者を釘付けにする衝撃作(文:映画ライター 牛津厚信)
久々に魂がきしむほどの映画を見た。冒頭からスクリーンに迸るのは、吹き溜まった感情を力の限りに吐き出す獰猛さと、真逆にある静寂のほとりで祈り続ける敬虔さだ。
たった一人の肉体を通じてこれほどの振れ幅を描き、なおかつ、生きとし生けるものが抱える原罪をヒリヒリするほどの感度で我々に突きつけるその筆致。信仰が一つのファクターではあるものの、これはむしろ、人は生きる上で何にすがり、いかなる存在のためにこの身を進んで差し出そうとするのかを炙り出した人間ドラマと言える。

本作は事実を基にしている。少年院で深い信仰心に目覚めた青年ダニエルは、聖職者になりたいと願うも、前科者にとってそれは叶わぬ夢だった。しかし仮退院後に訪れた村の教会でふと口をついて出た嘘をきっかけに、運命は思わぬ方向へ動き出す。彼は代理の司祭となった。型破りで真に迫った説教は次第に村人たちを惹きつけ、信頼を勝ち得ていくのだが――。
いわゆる偽りの存在が、本物以上に人の心を掌握していくプロットは、映画でもよく見かける。西川美和監督の「ディア・ドクター」もそうだったが、人の暮らしや生死に関わる職業であればあるほど、ある種のカリスマ性はよりいっそう厚みを帯びていくのかもしれない。こういった虚飾がボロボロと剥がれ落ちていく・・・という流れであったなら、他と変わらぬ凡作にとどまったことだろう。

しかし、本作は後半戦でさらにうねる。過去にとある悲劇に見舞われたこの村で、ダニエルは取り憑かれたように真相の蓋を開けようとするのだ。当然ながら彼には「真実とは何か」を語る資格もなければ、住民の心の傷に塩を塗る道理もない。だがあえてそうすること、そうせざるをえないことによって、本作はダニエルに、己の虚構性そのものと向き合う機会を与えているかのようだ。
これは「聖なる犯罪者」という物語が内包する一つのタイムリミットとも呼ぶべきものかもしれない。

なぜダニエルは二つの顔を持ち得たのか。彼はこの村で何を成し遂げたのか。本当の祈りとは、あるべき救いとは。青年の中で巻き起こるいびつな感情を活写し、村に影を落とす悲劇の顛末を描きつつ、人間の抱える原罪や信仰の意味すら問いかける。
かくも複眼的でありながら、それが暗闇を照らす光のように集約されていく様は実に力強く圧巻だ。ポーランドの若き鬼才ヤン・コマサの恐れ知らずの演出に、心も体も翻弄され続ける傑作である。
「ミッドナイト・ファミリー」(1月16日から公開)
◇家族経営の闇救急車に観客を誘う、刺激と企みに満ちた新世代ドキュメンタリー(文:フリーライター 高森郁哉)
予備知識なしに観始めたら、変わった設定のB級スリラーか、フェイクドキュメンタリーの類かと勘違いするかもしれない。何しろ、メキシコの首都で私設救急車を爆走させるオチョア一家のキャラが妙に立っている。
俳優でもいけそうなほどイケメンで切れ者の長男ホアンと、表情に憂いと諦念が相半ばする中年親父フェル、幼さの残る9歳だが大人びた悪態もつくぽっちゃり体型の次男ホセ。だが、本作がフィクションでもフェイクでもないことは、アカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞ショートリスト選出のほか、サンダンスをはじめ名だたる映画祭・映画賞のドキュメンタリー部門で多数受賞を果たしたことで証明済みだ。

人口900万人のメキシコシティで、行政が運営する救急車はたったの45台弱。そこで、専門訓練を受けず認可も得ていない営利目的の救急隊という闇ビジネスが広がりつつある。彼らは警察無線を傍受するなどして、負傷者の出た事故や事件の現場に駆けつける。
闇救急車とはいえ悪びれる様子もなく、前方をふさぐ車両に拡声器で罵声を浴びせて道を空けさせ、同業者と猛スピードで先陣を争う場面はカーアクション映画のシーンのようにスリル満点だ。

このファミリービジネスも相当に危うい。主な収入源は負傷した人やその家族からもらう搬送料だが、貧困者だと払いようがないし、公営病院よりも治療費の高い私立病院に搬送したと非難して支払いを拒む家族もいる。
無認可の商売ゆえ、取り締まる立場の警官が賄賂を要求してきたら渡すしかない。呼吸の止まった乳児に蘇生処置を施す場面では、命を預かる責任の重い仕事であることに改めて気づかされる。

1993年生まれのルーク・ローレンツェン監督は米スタンフォード大学で映画を学び卒業したのち、特に題材を決めないままメキシコシティ出身のルームメイトが帰国するのについて行き、滞在先の近くでオチョア一家に出会ったという。
家族から信頼を得た監督は、カメラを携えたまま空気のごとく親子に溶け込み、救急対応時の緊張した面持ちから、負傷者やその保護者とのやり取り、日常のリラックスした姿まで、彼らの素顔をありのままに伝えているように見える――ただし、途中までは。

えっ、と驚かされるのは、交通事故で負傷した母子を搬送した私立病院から、オチョア家が少なからぬ紙幣を受け取るシーンだ。おそらく、患者が払う治療費からのキックバックだろう(場合によっては患者と病院からの二重取り?)。
その前には、母子をいったん公営病院に搬送したが、「急患で混み合っている。ここからは見えないが救急車でいっぱいだ」と告げ、別の私立病院へ搬送することを了承させていた。その際、カメラは「救急車でいっぱい」であるはずの場所に向けられない。あの説得はもしかしたら…と思い返してしまうが、判断は観る者に委ねられる。
公的医療の限界や警察の腐敗といった問題を抱えるメキシコシティで、もがき苦しみながらも弱肉強食社会をしたたかに生き抜くオチョア一家に迫った本作には、並の倫理観や善悪論では太刀打ちできない力強さがある。その一方で、映像の先にあるものを“読む”よう観客に促す企みも感じさせ、新世代のドキュメンタリーという印象を受けた。
「パリの調香師 しあわせの香りを探して」(公開中)
◇優しい芳香に癒される、香水業界を舞台にした繊細な人間ドラマ(文:フリージャーナリスト 佐藤久理子)
パリの香水業界が舞台で、エルメスやディオールが協力している、と聞けば、いかにも洗練されたフランスの香り漂う、女性的な映画をイメージするかもしれない。だが本作は、そんなカテゴリーで括ってしまうには勿体なさすぎる。
もちろん、洒脱な雰囲気も魅力には違いないが、この映画の真のテーマは、異なる世界に住むそれぞれに困難を抱えた人間が支え合い、連帯することで障害を乗り終えていくことにある。それは世界が困難な状況に直面している今、ことさら本質的なこととして観る者の心に響くのではないか。

かつて天才調香師の名を欲しいままにしたアンヌは、4年前にストレスから嗅覚を失う悲劇に見舞われ、その後回復したものの、生き馬の目を抜く香水ビジネスの世界で、もはや以前のステイタスを得ることはできない。そんな彼女の元に新しく雇われた運転手がギョーム。彼もまた、失業や離婚を経験し、人生の立て直しを迫られている。
ディオールの名品「ジャドール」(シャーリーズ・セロンのCMでお馴染み)を生み出した、という設定のアンヌは、仕事に身を捧げてきたせいでいまも独身で、プライドだけは高く、わがまま。だがその内側には、孤独や不安を抱えている。

こういう役をやると、エマニュエル・デュヴォスは独壇場だ。もともとアルノー・デプレシャンやジャック・オーディアールの作品で評価されてきた彼女は名女優だが、いわゆる華のあるタイプではないだけに、同世代のジュリエット・ビノシュやエマニュエル・ベアールに比べると、いささか損をしている節がある。
だが、はっとするほどエレガントで美しい瞬間があるかと思えば、憎らしいほど傲慢で嫌味な女になるときもあり、ときには手を差し伸べたくなるような脆さを漂わせる。「ネ」(鼻の意味)とフランス語で呼ばれる、職人気質と芸術家肌の両方を兼ね備えた調香師の複雑さを、みごとに体現していると言える。

一方、「冴えないけれど中身はピカいち」なギョームに扮したグレゴリー・モンテルの、受けの演技も捨て難く、このでこぼこコンビのやりとりには、思わず微笑まずにはいられない。
もうひとつ本作がユニークなのは、男女の話の場合、かなりの割合で誘惑と欲望に結びつくフランス映画において、そんな紋切り型を粋なやり方でかわしていること。このあたりも、とても繊細で大人の映画だと感じさせられる所以だ。
優しい香りに満ちた本作に、ぜひ癒されて頂きたい。

――
編集した人