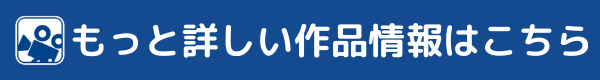怒りがわきあがる衝撃の実話 【次に観るなら、この映画】10月23日編
毎週土曜日にオススメ映画3本をレビュー。
①怒りがわきあがるような衝撃の実話をもとにした「モーリタニアン 黒塗りの記録」(10月29日から映画館で公開)
②半世紀以上にわたって続いたコロンビア内戦を背景に、ゲリラ組織の少年少女たちを描いたサバイバルドラマ「MONOS 猿と呼ばれし者たち」(10月30日公開)
③友だちの大切なノートを間違えて持ち帰ってしまった少年が、ノートを返すため友だちの家を探し歩く姿を生き生きと活写した「友だちのうちはどこ?」(10月16日から映画館で公開)
劇場へ足を運ぶ際は、体調管理・感染予防を万全にしたうえでご鑑賞ください!
◇グアンタナモ収容所での不当拘禁 「これは真実の物語である」という言葉があまりにも重い(文:映画com編集部 岡田寛司)
「モーリタニアン 黒塗りの記録」(10月29日から映画館で公開)
「This is a true story.(これは真実の物語である)」。実話をベースにした作品では、大抵の場合、このような意味合いの文言が挿入される。ジョディ・フォスター、ベネディクト・カンバーバッチの共演によって描かれた「モーリタニアン 黒塗りの記録」も同様だ。鑑賞後に、この文言を思い返す。「そんな話があったのか」と驚くだけに留まらない。この事実、あまりにもヘビーだ。
2015年、1冊の本が発売された。アメリカ政府による検閲で多くが黒く塗りつぶされた「グアンタナモ収容所 地獄からの手記」だ。そこにつづられていたのは、当時、キューバ・グアンタナモ米軍基地に収容されていた著者モハメドゥ・ウルド・スラヒの“壮絶な体験”。映画では、モーリタニア出身の青年モハメドゥがグアンタナモ収容所で体験する地獄の日々に、人権派弁護士ナンシー・ホランダー(フォスター)と軍の弁護士スチュアート中佐(カンバーバッチ)の奔走を絡めていく。

モハメドゥの身に生じたのは、9・11に関与した人々を勧誘した“リクルーター”という疑惑だ。悪名高き収容所に収監されてからの日々は、スタンダードサイズで描出。その画面の狭さも相まって、囚われの身の息苦しさが伝わってくる。不当な拘禁は“正義の鉄槌”を望む政府によって正当化されていく。確固たる証拠「自白」を引き出すために行われたのは、精神と肉体を抉る尋問という名の拷問。この描写があまりにも強烈で惨い……。思わず目を伏せたくなるだろう。

「モハメドゥを守る」「モハメドゥを死刑にする」という両極の立場に身を置くホランダーとスチュアート中佐。2人の行程は、まるで登山のようだ。別々のルートを辿り、霧のかかった山頂へ。理性的で落ち着き払った彼らの呼吸は、頂上に隠された“真実”に近づくほど、荒くなっていく。国民感情、隠ぺい、上層部の圧力、仲間とのすれ違い――立ち塞がる数多くの困難。まるで酸素が徐々に薄まっていくかのような、緊迫のストーリー構成に引き込まれた。

第78回ゴールデングローブ賞では、フォスターが最優秀助演女優賞を受賞。モハメドゥ役のタハール・ラヒムは、惜しくも最優秀主演男優賞の受賞を逃しているが、その迫真の演技には是非注目してほしい。また、本作では、とある現実が「This is a true story.」ど同じく、テロップとして明らかになる。僅かな尺を割いて伝えられる情報は、かなり衝撃的だ。これによって“物語の重み”が、飛躍的に増していることは間違いない。
◇集団と暴力をめぐる埋もれた記憶を顕在化させる、圧倒的な“共振力”(文:フリーライター 高森郁哉)
「MONOS 猿と呼ばれし者たち」(10月30日公開)
圧倒的な共振力を備えた衝撃作だ。雲海が眼下に広がる高地などの光景が醸し出す異界感。登場人物を介して視点を緩やかに移す叙述法で没入感を増すドラマ。オーガニックな楽器音とノイジーな合成音を精妙に配置したサウンドトラック。これらの要素が手練れの演出により共鳴し合って交響曲のごとき荘厳な世界を構築し、その重層的な響きが観客の深い部分を揺さぶって共振させるのだ。
アンデスの4000m超の高地で集団生活を送る十代のゲリラ兵8人、通称モノス(猿)。組織上部との連絡係である“メッセンジャー”が時折赴いて彼らを厳しく訓練する。モノスは米国人女性の人質“博士”を託されてもいる。15歳になった“ランボー”を祝うシーンが象徴するように、若者にとって遊びと暴力は隣り合わせだ。支給されたアサルトライフルを玩具のように無駄撃ちする(それが悲劇の引き金にもなる)。

物語は南米のコロンビアで1964年から半世紀続いた内戦を下敷きとする。ただし、そうした歴史的背景を知らなくても鑑賞にはほぼ支障がない。ブラジルに生まれ米国で報道と映像制作のキャリアを積み、本作が長編劇映画2作目となる監督のアレハンドロ・ランデスは、国や世代を超え多様な観客に響く仕掛けをいくつも施した。
監督はウィリアム・ゴールディングの小説「蠅の王」へのオマージュを公言しているが、隔絶された若い集団の中で暴力が支配的な力になるという展開も近い。変容した兵士らがボディペイントでカモフラージュして標的に迫るシーンは「地獄の黙示録」を思わせもする。

「2001年宇宙の旅」を想起させる要素も。スペイン語のmonoは「猿」のほかに「単一の」という意味もあるが、セメント鉱山の名残だという巨大建造物が山頂近くに屹立する様はまさにモノリスのよう。かのスタンリー・キューブリックの傑作は、猿人が放り上げた骨が人工衛星に変わるマッチカットでも有名だが、本作にも、高地のゲリラ拠点内にいた博士が出口の覆いを開けるとジャングルに移っているという鮮やかなマッチカットがある。
観客の目となる登場人物の視点を緩やかに切り替えていく叙述のスタイルも効果的だ。モノスの隊長と付き合う“レディ”、独裁的な傾向を強める“ビッグフット”、脱出を試みる博士、ある決断をするランボーといった具合に、シークエンスで主体となるキャラクターが移り変わり、各人物への同化を促すかのよう。

それにより喚起されるのは、観客自身の体験と創作物で見聞きした情報が混然一体となった“集団と暴力”をめぐる古い記憶を、夢を見ながら思い出して追体験する、震えるような感覚だ。「アンダー・ザ・スキン 種の捕食」でも音楽を担当したミカ・レヴィによる、瓶に息を吹き込んだホイッスル音や雷鳴のようなティンパニの連打といった自然に近い音と、電気的に合成し加工した人工音を組み合わせたスコアも、そうした埋もれた記憶の顕在化が生み出す共振に一役買っている。
◇少年の焦燥感や友だちへの思いが胸に迫るキアロスタミ監督の傑作(文:映画.com 和田隆)
「友だちのうちはどこ?」(10月16日から映画館で公開)
イランを代表する巨匠、アッバス・キアロスタミ監督の生誕81年、亡くなってから5年を迎えたということで、7作品をデジタルリマスター版で上映する特集「そしてキアロスタミはつづく」が、10月16日から東京・渋谷のユーロスペースで開催されている。
懐かしくなって、20数年ぶりに「シネマ映画.com」で「友だちのうちはどこ?」を見直すと、あの時の感動は色褪せることなく、新たな発見まであった。1987年製作のイラン映画で、日本で初公開されたのは1993年。当時、全盛の都内ミニシアターで初めて見た時の衝撃が甦る。それまでハリウッドや香港などの娯楽作やアクション作品を数多く見てきて映画好きを自負していたが、「友だちのうちはどこ?」には、自分の中の「映画」というものの概念が覆された。

フィクションの物語映画でありながら、その作品世界は真実のようで、それまでの映画で味わったことのない映画表現の領域に入り込んだような感覚に陥り、特にラストシーンの感動でしばらく立ち上がれなかったのを覚えている。キアロスタミ監督は、職業俳優を使わず、撮影地の村の住人や子どもたち、実際の家や学校を使用して撮影し、フィクションとドキュメンタリーの間の絶妙なバランスを保つスタイルを確立した作家だが、「友だちのうちはどこ?」はそんなスタイルを象徴する傑作である。
物語は、イラン北部の小さな村を舞台に、同級生のノートを間違って持ち帰ってしまった少年アハマッドが、ノートを返すために遠く離れた友だちの家を探し歩く姿を描いたとてもシンプルなもの。だが、イランののどかな風景の中で、アハマッド少年の不安げな表情やつぶらな瞳、困り切った焦燥感、そして勇気を出して小さな冒険に踏み出し、大人たちに翻弄されながらも友だちのうちを見つけだそうとする姿が真に迫っており、観客はいつしか作品の中に入り込んで一緒になってその焦燥感や友だちへの思いを味わうことになる。

この映画は、あなたのその後の人生観や映画の見方を変えてしまうかもしれないほど、映画的な力を持っている。そして、世界には異なる文化や習慣を持った民族がいて、映画表現も国によって異なるという、未知の領域を教示してくれるに違いない。しかし、この映画で描かれているのは普遍的なもの。国や人種、文化が異なっても共感できるテーマであることが、今なお世界中で愛されている所以なのだろう。
純朴なアハマッド少年が何度も駆け抜ける「ジグザグ道」の風景は、キアロスタミ監督のその後の作品「そして人生はつづく」「オリーブの林をぬけて」に受け継がれ、“ジグザグ道三部作”と言われている。キアロスタミ作品は続けて見ていくうちに、キアロスタミ監督が影響を受けた監督や作品の映画的な系譜まで浮き上がってくる面白さもあるので、是非この機会に、追悼するとともに作品と出会って欲しい。