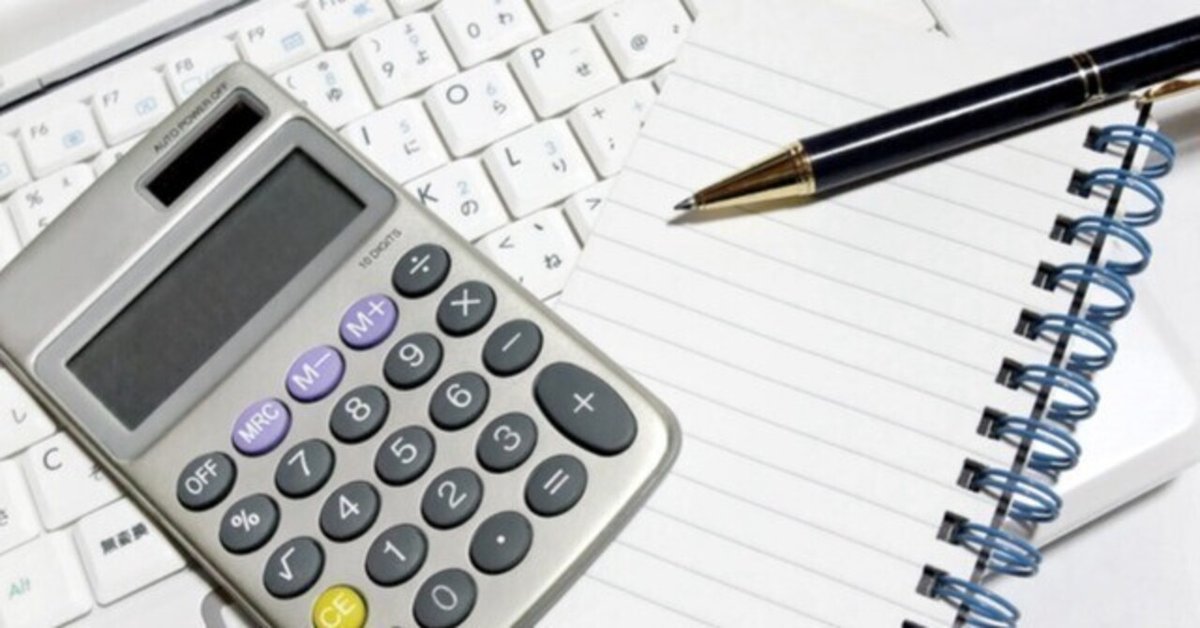
発信について経営学から学べる事
経営学の本を読んでいて、SNSでの発信について応用できることがあるなぁと思い、こちらに簡単にまとめます。
➀合理性は限定されている
これは、個人で合理的に選べる範囲は限定されている、ということです。
確かにそうで、まずは➊個人が選択肢として想定できるものの範囲が限定されていますし、➋選択肢を並べたとしても、それぞれの選択肢について関連した知識や経験が限定されています。
もちろん、日頃から広くアンテナを張り、情報を取り入れるように気をつけるべきではありますが、それでも限界はありますね。
発信に引き付けて言うなら、特に➋が重要で、日頃から多くの方の発信に注目し、うまくいっているところは模倣するなどの工夫が大事だと思います。
あとは、自分がやってみたいと思っていることと似ていることをしている発信者(先達)を見つける、ということも大事ですね。
➁作業をしながら閃いた戦略
継続的に作業を行うためには、ルーチン(定型的な作業)を確立してスムーズに作業が流れるように様々な障壁を減らしたり低くする必要があります。
そうして確立した継続的作業には、ある種の惰性が生まれます。
この惰性をどう見るかについてはいろいろあると思いますが、例えば継続しさえすればいいという局面もあると思いますし、そういう場合はこの惰性を利用するのもアリです。
他方で、作業がマンネリ化して面白くないとやる気がなくなってしまう…ということもあると思います。
そういう場合は、適宜新しいやり方や内容に挑戦してみたらいいと思いますし、そうして新しく行ったこととこれまで行ったことが化学反応を起こして、新しいコンテンツが生まれる可能性もあります。
経営学では、プロジェクトを実現する道筋において、計画通りに進めていくよりも、柔軟に適宜修正して行うべき、という話があります。
ルーチン作業の話では惰性ということがポイントになっていましたので、すこし内容が異なるかもしれませんが、計画通りに行うかどうかという意味では似た問題です。
シンプルに考えると、➊前もって考えられたもの(計画)は、実行中の出来事を認識したうえでつくられたものではないので、その点不十分である、➋しかし、前段階の状況下で可能な限り合理的に計画されたものなので、その点では配慮すべき、➌実行過程で状況が変化することもあるので、その変化の影響を勘案して修正していく必要がある、ということであると思います。
➂参考にした本
参考にした本です。
こちらのシリーズは、大学の教科の内容をざっと学べるということで、とても便利です。
SNSなど発信する個人にとって、経営学からも参考にできる内容が多くあると思います。
