
オンライン MEET UP! レポート#17
こんにちは。インターンのよねくぼです!
全国どこからでも参加できる「オンラインMEET UP!」は毎回、テーマについてホストと一緒に話す会です。第17回のテーマは、「ローカルカルチャーの面白さ・長浜いいね!」。今回は、東海圏内のローカルカルチャーを発掘、発信するWEBマガジン”LIVERARY”を立ち上げた武部敬倰さんと、滋賀県長浜市役所に勤務しながら、「長浜くらしノート」と「長浜ローカルフォト」というローカルメディア・団体を運営している川瀬智久さんをゲストにお迎えしてトークを展開しました。

1人目のゲストの武部さんは、出版・編集、また本の装丁デザインの会社を経て、現在はフリーランスとしてWEBマガジンやイベント運営、デザイン制作またPOP UPショップの開催など、多方面で活躍されています。
武部さんが活動の中心にしている”LIVERARY”は、名古屋の本セレクトショップ「ON READING」店主の黒田義隆さんと2013年11月に立ち上げたWEBマガジンです。名古屋で開催されるイベントの情報発信を主に、「LIFESTYLE 」「MUSIC」「ART」「CINEMA」などさまざまな切り口から名古屋のローカルなカルチャーを発信しています。東京にはない、ローカルならではのカルチャーをもっと外に発信したい!という思いで始まった”LIVERARY”は、単なる情報発信に留まりません。
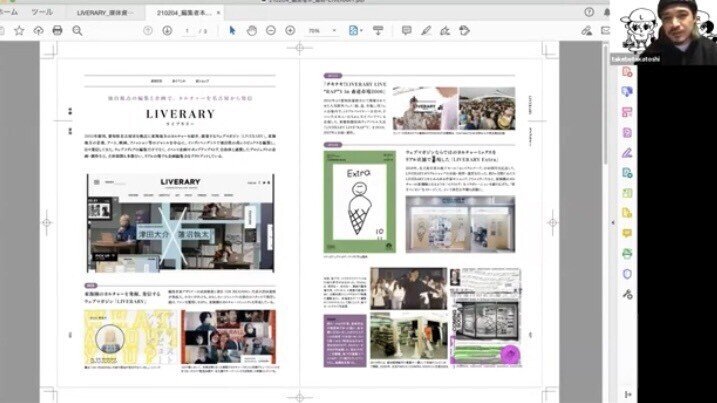
コロナ禍では、飲食店や娯楽施設が休業したことで、”LIVERARY”の情報発信の要となるイベント自体が中止になる状況に。そんな中武部さんは何かできないかと思い、空になった場所でアーティストのライブを行い、それをYouTubeで生配信しました。連日地域内外の多くの方が視聴し、最終日までには20万円程の投げ銭が集まったそうです。
このように、武部さんは、単なる情報発信だけでなく、メディア発のイベントを自ら作っていくことにも尽力し、名古屋という“場所”と地元のアーティスト両方をフューチャーする活動を行っています。
行政からの依頼も多いといいます。「名古屋の若いアーティストが表現できる場を。」ということで、おじいちゃんおばあちゃんが経営している個人のコンビニを半分間借りしたPOPUPでは、普段コンビニには絶対置いていないようなファッションブランドのグッズやイラストレーター平山さんとのコラボ作品を展開しました。コンビニのレジにあるタバコ売り場は、左半分は普通にタバコ、右半分ではステッカーやマグカップを販売するというカオス状態。元々、そのコンビニ自体も孫のおもちゃやおじいちゃんの趣味のバイクが飾ってあるなど、東京のコンビニにはないカオスさがありました。元々あった場のカオスさと今回のPOPUPがうまくマッチしたというのが面白いなと思いました。

元々武部さんは、会社員時代にも自分でZINEやイベントを開催していたこともあって、自分の好きなことをやるなら、赤字が出るのは当たり前というスタンスでした。それが今お金になっている事自体が武部さんにとってはラッキーなんだとか。
ディスカッションでは、コロナ禍でYouTubeやネトフリなどの映像メディアの台頭によって、「WEBマガジンが読まれなくなってきているのではないか」について話し合いました。“どれだけ多く読まれたか”というPV数は、WEBマガジンの価値を図るうえで重要な指標だと捉えられがちですが、媒体の”ブランド”自体がしっかりしていれば、PV数はそれほど気にしなくてもいいと影山さんは言います。「EDIT LOCAL」自体が3か月に1度ほどのペースで更新するスローペースなWEBメディアですが、特徴的なのは、1つ1つの記事の長さ。以前までは、WEBは情報の”鮮度”があってこそ重宝されると考えられていましたが、今では、それほどスピード感が無くても、長くてしっかりした文章は、長期的に読み継がれていく可能性があります。つまり、以前は紙媒体が担っていた“アーカイブ性”は、今後、WEBに求められてくると言えます。今後のWEBの在り方を改めて考えさせられました。
この”LIVERARY”については影山さんの新刊『新世代エディターズファイル~越境する編集――デジタルからコミュニティ、行政まで』にも掲載されているので、ぜひご参照ください!
2人目のゲスト、川瀬さんは滋賀県の長浜市在住の市役所職員で、市民活動を応援する「ながはま市民協働センター」に勤めています。(※4月1日から生涯学習文化課に異動)
長浜市は滋賀県北部に位置しており、人口11万人の美しい自然と豊かな歴史・文化が息づく都市です。中心市街地は、豊臣秀吉が最初に構えたお城「長浜城」があり、城下町として栄えた古い歴史があります。中でも、「黒壁ガラス館」を中心に行われた商店街の復興事業は、全国的に話題になり、観光客は市全体で年間800万人(県内2番目に多く)訪れているそうです。その他にも、ユネスコ無形文化遺産に登録されている「長浜曳山まつり」や地場産業の「浜ちりめん」を活かした着物の祭典など様々な取り組みが行われています。

そうした長浜市で、川瀬さんは長浜市の”くらし”にスポットにあてた「長浜くらしノート」というローカルメディアを運営しています。「長浜くらしノート」の大きな特徴は、“MEDIA”(WEBマガジン、紙冊子)דTOURISM”(記事にしたものを体験)דSTORE”の3つを掛け合わせ、「ヒト」「モノ」「コト」を発信し、読者との関係性を構築しているという点です。

例えば、「山のいのちに心を向ける」という特集では、“ジビエ”についての知識や狩猟体験、ジビエ料理人の思いなどを取材し、記事にして紹介しました。さらに、ジビエの解体やジビエ料理の試作や試食など、記事にした内容を実際に体験していただきました。このように記事と“体験”を上手く組み合わせることで、読者の方により多くの魅力を伝えようと挑戦しています。

川瀬さんは他にも、長浜市の住民を中心に、”写真”というツールを用いて長浜市のヒトや暮らしぶりを発信する「長浜ローカルフォト」という団体の運営にも携わっています。最初ローカルフォトの第一人者である写真家MOTOKOさんを講師とした「ローカルフォトアカデミー」にて3年間みっちり指導を受け、カメラ技術だけでなく、まちの人とコミュニケーションできる力、まちを分析する力、そしてそこからまちの魅力を伝えられる力を身に付けていったそうです。主な情報発信はFacebook。外からのファンを増やすだけでなく、住んでいる人が改めてまちの魅力に気づき、誇りを持つことによって地域の活力をあげていくことを目的としていています。
大きなプロジェクトの1つが、長浜の限界集落の1つ”菅並集落”を元気にしたいという思いで始まった「SUGAMANI PHOTO PROJECT」。主に集落に住んでいる“ヒト”にスポットを当て、写真を撮影しました。撮影当初は、やはり集落の方との距離はありましたが、何度も集落に通い、コミュニケーションを撮るうちにだんだん打ち解け、自然体の写真を撮れるようになったとのこと。そうやって撮り貯めていった写真を使って、最終的には“まち全体を写真展会場にする”イベントを開催しました。

こうした“集落”を対象としたプロジェクトは他にもあり、「KANEIHARA PHOTO PROJECT」で開催された写真展は、市街地で開催しました。そこでは、集落を出ていってしまった人が住民の元気な様子を見て涙を流したり、さらに、金居原集落の魅力に惹かれ、空き家を使って何かしたいという人も現れたそうです。

今後の展望として、川瀬さんは、400年以上続く「長浜曳山まつり」などの地域の祭りの継承に貢献していきたいと言います。祭りといえば、男のイメージが強いですが、女性も縁の下の力持ちとして祭りを支えています。そうした裏側を写真で伝えることで、地元の人に愛着や誇りを持ってもらえればと考えていらっしゃるそうです。
メディアのかたちがWEBであれ、写真であれ、まちに住んでいるヒト、またかつて住んでいたヒトが地元を見つめ直すきっかけとなっているのはすてきなことですね~~
次回もおたのしみに!
文:よねくぼひなこ
