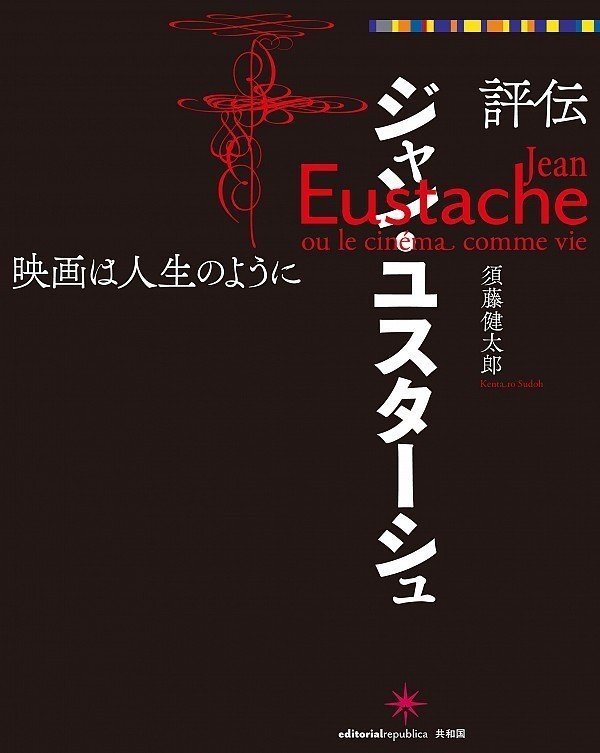ジャン・ユスターシュとは誰か? 人生は映画のように [前篇]
須藤健太郎 × 廣瀬純
『ママと娼婦』(1973)や『ぼくの小さな恋人たち』(74)などでポスト・ヌーヴェル・ヴァーグの旗手として活躍しながら、1981年11月5日、パリの自室で拳銃自殺を遂げた映画監督、ジャン・ユスターシュ。本年(2019年)4月に小社から刊行された須藤健太郎『評伝ジャン・ユスターシュ』は、その作品と生涯とに本格的に向き合った、世界で初めての1冊となった。
本書の刊行にあわせて4月~6月に都内で開催された特集上映は異例の好評を博したが、今回のトークイベントも、著者の須藤さん、そしてゲストに映画批評家の廣瀬純さんをお招きして、このしばしば「幻の」「伝説の」と形容される映像作家の実像に肉薄する稀有な機会となった。以下のふたりの発言によって、また新たなユスターシュ像が切り結ばれているのではないだろうか。前篇/後篇の2回にわけてお送りする。
[2019年10月19日(土) 於:エスパス・ビブリオ]
|映画とは人生なのか?|
廣瀬 今年の4月に須藤さんの『評伝ジャン・ユスターシュ』が刊行され、特集上映もありました。世界で一番ジャン・ユスターシュに詳しい研究者が日本で生まれ育った人だというのは、たぶん偶然ではない。ユスターシュ作品のDVDが出ているのは日本だけなんですよね。
須藤 フランスにもないのに、なぜか日本版のDVDがある。
廣瀬 その日本版DVDの謎についてもおいおい訊いてみたいんですが、まずは、ジャン・ユスターシュとはそもそもどういう人なのかということから話を始めたいと思います。『評伝ジャン・ユスターシュ』には「映画は人生のように」という副題が付いています。須藤さんにとって、ユスターシュは「映画は人生のように」の人なのだと理解してよいのでしょうか? そもそもなぜこういう副題を付けたのか。本を読んでいて、ひょっとすると、彼の人生もまた、映画のようであったのかなと想像したのですが。
須藤 実は、書いている時は「ユスターシュ伝(仮)」とだけタイトルを付けていました。ただ、編集を担当してくださった共和国の下平尾直さんと相談するうちに、本として出版するにはそれでは不十分だと理解し、より読者に親切なものを考えて、いまのかたちになりました。
はじめに考えていたのは、あまり情報を出したくない、先入観を与えたくない、タイトルから内容が想像されるようなものにしたくないということで、「ユスターシュ伝」くらいでいいと。本当はこの本は「伝記」とか「評伝」ではないんですけど、「伝」という漢字はいいなと思っていて、序文で「伝統」とか「伝承」という「伝」のつく熟語がいくつも出てくるのはその名残です。
もともとは、章題っていうんですか、第1章、第2章とあるところにもタイトルはなくって、数字しかなかった。それで、第1部、第2部、第3部のタイトルが全部「映画は○○のように」と揃っているんですが、これだけがはじめから付いていたものです。だから、副題を付けようというときも、ここであらたに情報を付け足して、新たに意味を増やさないようにと考えて、その同じ言い回しを全体にも持ってきたという感じで、そこで「映画」と「人生」という単語が選ばれたのも、むしろ新しい情報を出さないためだったんです。要するに、「評伝ジャン・ユスターシュ」とあれば、それは映画監督の話なので「映画」のことだとわかるし、評伝であればそこにはその監督の「人生」について書かれていると想像されるわけで、この副題は何も説明していない。丁寧に副題を付けるふりをして、もっとも意味しない言葉を付け足したつもりだったんですけど、結果的には大きな言葉を選んでしまったようで、逆に過剰な意味を喚起してしまったかもしれない。それは、あとになってから気付いたことです。
廣瀬 でも、ユスターシュは映画を人生のようなものとして捉えていた、須藤さんはそう考えているわけですよね。
須藤 うーん、そういうふうに訊かれると答えにくいですね……。もしかすると、「人生」ではなく「人」を抜かして「生」といったほうが正確なのかもしれないですけど、彼の中では映画と生が区別されることなく、ほとんど同じものとして捉えられていた、そういうふうに書いたし、たしかにそう考えてはいるんですけど、廣瀬さん的にはそれは違うんじゃないかということですか。
廣瀬 いやいや、そんなことないですよ。一般的にも、ユスターシュは自分の実人生を作品の題材にした監督だということになっています。彼の作品で特に有名なのは『ママと娼婦』(1973)と『ぼくの小さな恋人たち』(1974)の2本ですが、どちらについても、ユスターシュ自身の実人生が描かれていると、通常は理解されています。
自分の生きた人生を作品で問題にする監督は、映画が誕生したときから存在していたわけでもなんでもなく、映画史のある時点で出現した。ぼくは、ジャン・ユスターシュとともに出現したと考えています。もちろん、反論はあり得ます。すでにフランスワ・トリュフォーがいただとか、さらにそれに先立ってサミュエル・フラーがいただとか。確かに、フラーは、戦場での自身の経験や、新聞記者としての自身の経験に基づいた作品を撮りましたが、しかし、彼にとっての問題は、あくまでも、映画を「戦争」という超越性から解放し、映画に「戦場」という内在性を返すことであって、そのために自身の体験の具体性が必要になったに過ぎません。トリュフォーは、フラーが米国でそうした試みを行なっていたのと同時期に、フランスで批評活動を開始した人ですが、批評家としての彼の問題は「映画とは何か」であって、監督になってからも、この問題を追求し続けました。確かに『大人は判ってくれない』(1959)は、彼自身の経験にそれなりに忠実なものなのかもしれませんが、その後のドワネル諸作では、そうした「自伝」路線からどんどん逸脱していきます。こうした脱線は、ユスターシュだったら、あり得なかったでしょう。「映画とは何か」はヌーヴェル・ヴァーグ全体に共通する基本的な問いでした。ユスターシュは、そのヌーヴェル・ヴァーグに、わずか数年かもしれませんが、それでも決定的に遅れてしまった人です。問題はすでに立てられてしまっていた。だから、ユスターシュは、問題の重要性をヌーヴェル・ヴァーグの人々と共有しつつも、彼らと同じ天真爛漫さをもってその問題に取り組むことを自分に許すことができなかった。そうしたなかでユスターシュが導入したのが「人生」だったのではないか。
これに似たような例は、青山真治にも見出せます。青山は、立教大学の出身ですが、彼に先立ってすでに黒沢清や万田邦敏がいた。黒沢や万田は、ヌーヴェル・ヴァーグに比し得る存在で、まさに「映画とは何か」の人々です。無論、日本映画史における真のヌーヴェル・ヴァーグは日活ロマンポルノに他なりませんが、青山真治その人にとっては、黒沢や万田がゴダールやトリュフォーのような位置にあった。青山もまた、「映画とは何か」という問題を黒沢たちと共有していますが、しかしやはり、その問題に彼らと同じ天真爛漫さで取り組むことができず、『Helpless』(1996)以来、自分がどこで生まれ育ったかといった問題を導入することになる。黒沢清は神戸で生まれ育ったらしいけれど、彼は、そうしたことを作品にはけっして持ち込みません。青山自身は、自分をフィリップ・ガレルにたとえていますが、以上のような観点から総合的に見れば、ユスターシュにより近いでしょう。
|自殺とダンディズム|
廣瀬 「自殺」についても、須藤さんの本を読んでみて、その重要性を再認識しました。ユスターシュは1981年に自殺するわけですが、これも、ぼくからすると、「映画は人生のように」という副題と響き合う何かであるように思えます。
ミシェル・フーコーというフランスの哲学者が、ユスターシュとほぼ同時代のドイツの映画監督ヴェルナー・シュレーター(1945—2010)との対談で、自殺を問題にしています(『ミシェル・フーコー思考集成IX 1982—1983 自己/統治性/快楽』筑摩書房、2001)。人生を芸術作品にすることと芸術作品で人生を描くこととは同じことであり、自殺は人生を芸術作品にすることかもしれないとフーコーが言ったのを受けて、ヴェルナー・シュレーターがすぐに話題にするのが、まさに、ユスターシュの自殺なんです。あれは酒のせいだとか鬱になったからだとか言われてるけど、おれはそう思わないと。むしろ健康そのものといったような状態で自殺したはずだと言うわけです。これは「テロリスト」などについても同じでしょう。どうでもいいような人生をずっと生きてきたなかで、ある日、そんな自分の人生を一瞬でも輝かせたい、芸術作品にしたい、うまくいくかわからないけど、できるだけの準備をして、一瞬に賭けてみたいと思うようになる。「自爆テロ」と一般に呼ばれているものは、そんな欲望の下で実行されるものなのではないでしょうか。
須藤さんの本では「ダンディズム」というのも重要なキーワードになっていますが、これも、言うまでもなく、同じ問題に属するものです。須藤さんの本には、ユスターシュがダンディたちに囲まれていて、彼らから多大な影響を受けていた様子が描かれています。ダンディとは、要するに、自分の存在や振る舞いを芸術作品にする人のことです。ユスターシュは、作品では自分の実人生を描き、実人生については自殺に至るまでその作品化を推し進めた。映画=人生、人生=映画ということです。
須藤 でも、「映画は人生である」とはしなかったんです。「映画は経験のように」とか「映画は反復のように」という部ごとのタイトルは、博士論文の時からすでに付いていたもので、「Le cinéma comme expérience」を訳して「映画は経験のように」としたわけですが、ある時期までこれを「映画は経験である」と訳していたこともあった。ただ、最終的にはこんなにはっきりとイコールで結びつけないように、両者を等号で結びはしないけれども、なにかしらの関係がそこに結ばれるような、そういう曖昧な関係を導入することにした。
いま廣瀬さんのお話を聞いていて思い出したんですけど、『シネマの大義』(フィルムアート社、2017)の中ではユスターシュの名前が最後に出てきて、ぼくの名前も一緒に出てくるので読んでいて驚いたんですが、そこで問題にされているのは「映画監督」か「作家」か、あるいは「シネマ」か「フィルム」かという話でした。廣瀬さんとは実際に似たような問題について話したことがあって、その時にぼくは執筆中だった博士論文の第1部のタイトルのことを話題に挙げている。
廣瀬 まったく覚えていません(笑)。
須藤 大文字の「シネマ」を相手にするのか、それとも個々の作品である「フィルム」を問題とするのかという話題の中で、ぼくはそういうつもりではなかったけど自分の博論の第1部は「Le cinéma comme expérience」と名付けていて、各部のタイトルに全部「シネマ」という語が入っていますと言ったら、「じゃあ、その博論良さそうだね」って(笑)。廣瀬さんの整理だと、ユスターシュを境に、「シネマ」ではなく自分の人生を問題にしてしまう「作家」が増えた。
|2つのあいだにいる|
廣瀬 ユスターシュ以降、映画を撮る人、撮りたい人のうちの一部は、「人生」のほうしか見なくなってしまう。これは須藤さんの本でも特に強調されている点ですが、ユスターシュ自身は、つねに2つのもののあいだにいたわけです。『ママと娼婦』というタイトルがそれをこの上なく雄弁に語っている。どちらが「ママ」でどちらが「娼婦」なのかは判然としませんが、とにかく女性が2人いて、そのあいだに男が1人いる。ユスターシュは、「映画」と「人生」という2つを共存させ、そのあいだに身をおいていた映画監督なわけです。しかし、後続の作家たちは、ユスターシュの登場によって、「映画」を忘れ「人生」だけを問題にしても許される道が拓かれたと、とんでもない勘違いをしてしまった。
2つのものの共存、そして、その「あいだ」という問題は、無論、映画/人生だけに限られるものではありません。『ママと娼婦』には、ジャン゠ピエール・レオー演じる主人公が女性をレストランに誘うというシーンがありますが、そこで行くことになるのは、パリのリヨン駅にある有名なレストラン、トラン・ブルーです。リヨン駅はターミナル駅で、すべてのプラットフォームの突き当たりのところにレストランは位置しています。そのレストランで主人公は、一方には田舎へ出発する列車が見えて、他方にはパリの街が見える、それが好きなんだと言う。田舎と都会とのあいだに自分を位置づけるわけです。田舎と都会の並置はユスターシュの作品群全体にも見いだせるテーマで、『ぼくの小さな恋人たち』は田舎で展開され、『ママと娼婦』は都会を舞台にした話になっています。さらに、『ぼくの小さな恋人たち』の内部でも、ペサックという田舎とナルボンヌという都会が併置され、そのあいだを主人公の少年が行き来します。
須藤 本当は、ナルボンヌはそんなに大きな街じゃないんですけどね。
廣瀬 でも、作中だとそういう位置づけになる。
須藤 2つの別のものを同時に扱っていくっていうんですかね。異なる2つものを出してきて、それらをどうやってつなげるか。それは、ユスターシュの作品群を貫いている大きな主題になっている気がします。それを確認するために、いくつか抜粋を見ながら、お話ししてもいいでしょうか。まずは、一番初めの作品を見てみたい。
廣瀬 ユスターシュはもともと国鉄の職員だったんですよね。そのころの作品ですか?
須藤 国鉄の職員で車両を洗っていて、それを辞めてテレビの研修生みたいのを始めるんですけど、このままいても映画は撮れないと思ってそこも辞めて、それで自分で作った『夜会』という作品です。未完なんですけど、なぜかYouTubeで見られる。
廣瀬 ユスターシュ作品は、実は、ほとんどすべてYouTubeにアップされている(笑)。
須藤 ユスターシュの作品は権利関係が複雑になっていて、なかなかDVD化されないままで、それはボリスっていう次男がかたくなに守っているからなんですけど、彼はネット上に流出することはまったく問題にしていない。
廣瀬 別にいいよっていう感じですか?
須藤 そういうのに神経質に反応しそうなところなんですが、著作権違反だと訴えたり、削除の要請を出したりはしない。
廣瀬 なぜ日本ではDVDが出てしまっているのでしょうか?
須藤 日本では1996年に『ママと娼婦』が公開され、2001年にその他の作品もユーロスペースで特集上映されたんですが、たぶんそのときにDVD化の権利が一緒に売られているんですね。で、ユスターシュには息子が2人いて、そのときは次男のボリスじゃなくて長男のパトリックが権利を管理していたらしい。長男はあまり父親の仕事に関心がなかった。
廣瀬 ボリスさんのほうは助監督をやったり、ユスターシュに生前から付きっきりですよね。
須藤 そうなんです。でも、ことの真相はよくわからなくって。長男のパトリックはもう亡くなっていて、ぼくはボリスからしか話を聞いていない。あまり兄弟仲も良くなかったみたいで、ボリス側の言い分では「兄貴は映画に関心がなかったから、状態の悪いフィルムをそのまま日本に売りつけたんだ」と怒っている。
廣瀬 じゃあ、ボリスさんは日本でDVDが出ていることを苦々しく思っていると。
須藤 「海賊版」と呼んでいました(笑)。正式に発売されたものなんですが。
では、準備できましたので、そろそろ抜粋に移りますね。『夜会』というのは未完で、音も入っていない8分くらいのものですが、これが何者かによってYouTube上にアップされている。編集もされているように見えるので、おそらく本人がここまで手を加えたうえで放棄したんだとぼくは考えています。
お見せしたいのは冒頭の部分。異なる2つのものをどうつなげるか、それがよく表れていると思います。舞台となるアパルトマンはメゾネット形式で、2階建てになっています。アパルトマンの中に階段があって、1階と2階がある。カメラを初めて回した若きユスターシュは、1階の空間と2階の空間という別々の空間をどうやってつなげるかをまず考えたんだろうと思います。
抜粋上映 『夜会』(1963年、未完)0:00—0:40
須藤 いきなりキスシーンから始まるわけですが、まず1階でキスする2人が映されて、こういう感じで場面が2階に移っていきます。面白いのは、1階を映して、次の瞬間にいきなり2階を映したりしない。カメラがものすごく不自然にぐねぐねってパンをして階段を捉える。で、1階から階段とその奥にある絵を撮って、そのあと今度は2階から階段を見下ろし、その奥にある絵を捉えたショットにつないでいく。
どうやって1階と2階をつなぐか、おそらくそれが彼が一番初めに立てた問いだったと思う。そうすると、キスシーンから始まるのも意味深で、2人の異なる人間がつながる瞬間というか、それに続く階段はあたかも一種の唇であって、1階と2階のキスシーンのようで……。
廣瀬 その比喩、少し気持ち悪いですね(笑)。
須藤 まあ、でもそういう連関を見つけたくなるような始め方ではある。で、ユスターシュは別々のものをつなげると言っても、これは逆の言い方もできて、何かと何かをつなげようとするのは、それらを別々のものとして捉えているからだと思います。いつも丁寧につなげようとするわけではなく、異なるもの同士だと考えているからこそ、そういうときにつなぎが導入される。
|儀式とかたち|
廣瀬 1階と2階とでは、起きていることも全然違いますよね。1階ではキスしていて、2階の人たちはみんなで打ち合わせのようなことをしている。
加えて興味深いのは、冒頭のキスが純粋な「かたち」「身振り」でしかないという点です。好きだとか、愛し合っているだとか、そういう「気持ち」は画面にはまったく映っていない。これも『評伝』を読んで再確認したことですが、ユスターシュ映画は「身振り」の映画であって、これを須藤さんは「儀式」という表現で論じています。
たとえば『ぼくの小さな恋人たち』でも、主人公の少年は、田舎では、幼い友だちと遊んでいるわけですが、都会に来たら、思春期から20歳過ぎぐらいまでの青年たちと付き合うようになる。青年たちの仲間となっていく過程で重要なのは、見ること、そして、反復することです。主人公は、青少年たちの様々な身振りを観察し、それをひとつずつ模倣する。カフェでたむろするだとか、女の子に触るだとか、映画館で女の子に後ろから息を吹きかけるだとか、いずれの行為も、欲求や気持ちから生じているものではなく、見たことをそのまま自分でもやってみたというものです。自分のなかに原因がないそのような行為や身振りを、須藤さんは「儀式」と呼んでいるわけです。
ユスターシュ映画が「現代映画」に属すると言えるのは、まずは、この「儀式」という点においてのことです。古典的な映画では、まず、登場人物たちに何かやりたいことがあって、それに応じて身体が動かされる。ユスターシュは身体の動きをやりたいことに結びつけません。彼の関心は、欲求や有用性から切り離された身体の動きにあるわけです。『豚』もそういう映画です。
須藤 1970年に撮られたドキュメンタリーですね。
廣瀬 屠殺の話なのだけど、別に殺さなくてもいいというか、どうしてもこの豚が食べたいから殺すとか、豚肉を売ってお金を得なければならないから殺すといったことではまったくない。欲求や有用性とは無関係に、今日は豚をさばく日だということがまず決められていて、過去にも同じような日に繰り返されてきたであろう同じ手順、同じ手捌きで、淡々と豚の解体作業が進められてゆく。問題になっているのは、身体のそうした儀式性なんですね。
須藤 職人の自動化された身振りというか。
廣瀬 人々の身体の動きは、空腹から屠殺を経て満腹へといったような欲求充足的なフローの外にあり、そうしたフローに対して過剰なものとなっています。
須藤 そうですね。いま紹介していただいたように、この映画は養豚の農家のところに取材したもので、そこでは職人たちの反復されてきた身振りが捉えられている。
また、これはユスターシュとジャン゠ミシェル・バルジョルの共同監督作なんですが、バルジョルの企画だったものをユスターシュが奪い取ったというあたりが本当のところだろうとぼくは考えています。そういう意味では、さきほど話題にあがった2つのものを組み合わせるという主題に沿った映画でもある。ユスターシュ組とバルジョル組の2つの撮影班があって、屋外を撮っているのがユスターシュとそのカメラマン、一方バルジョルの方は解体されたものを屋内でソーセージなどに加工していく人たちを撮っている。当日は別々に作業していて、最終的にユスターシュが編集で2つの素材を一緒にした作品です。
またちょっと抜粋をお見せしながらお話した方がわかりやすいと思うのですが、だいたい半分くらいのところで、それまでは屋内と屋外が別々に映され交互に見せられるだけだったのが、2つを編集でつなげるということをやる。
抜粋上映 『豚』(1970年)26:55—28:30
須藤 ここは屋外で豚を解体しているところですが、ここもこうやって同軸で寄っていくので、なんかアメリカ映画みたいな編集ですね。で、こうやって外で解体したものを中に持っていき、中では中の人たちが作業をしている。ここで、中の人が外側に運んでいきますが、この人が入り口を通るタイミングで外のカメラに切り替わります。この人の動きを使って、つなぐわけです。
|『ママと娼婦』冒頭のつなぎ|
須藤 ついでにもう1つ抜粋をいいでしょうか。『ママと娼婦』の冒頭近くで、アレクサンドル(ジャン゠ピエール・レオー)が自分のもとを離れた元恋人のジルベルト(イザベル・ヴェンガルテン)に会いに行くくだりです。「もう一回やり直そう」みたいなことを言うところ、そこまでの流れをちょっと確認してみたいと思います。アレクサンドルが車に乗って、その車が道に入ってくる。いまカメラは道から車を撮っていますが、カメラが1回車の中に入ります。
抜粋上映 『ママと娼婦』(1973年)2:20—4:00
須藤 彼が車でやってきて、道を歩いてくる彼女のところに向かう。それだけなんですけど、ユスターシュは何度もカットを切り替えて撮っていく。路肩に駐車する車を撮り、そこから出てくるアレクサンドルを見せる、それで十分なのに、なぜカメラを車の中に入れる必要があるのかと思いますよね。しかも、カメラを車内に入れるために、アレクサンドルに振り返るという動作をやらせ、そのアクションを使って、ものすごく丁寧にアクションつなぎでつないでいく。
ぼくが思うのは、1つは彼が車から「出て来る」姿ではなくて、そこから「出て行く」姿を撮りたかったのだろう、と。彼は車内という私的な空間から、路上という公的な空間に出て行く、そういう関係をはっきり見せたかったのではないか。さっきの話で、ユスターシュがつなごうとしているときは、むしろそこに対立する2つのものを作りだそうとするときだと、異なる2つのものというふうに捉えるからこそ、両者につながりを設けようとするという話をさきほどしましたが、ここもそういう箇所だと思うんです。私的空間と公的空間の対比、そして私的空間から出て公的空間で2人が出会い、会話が始まると路上という公共空間の中にきわめて私的な空間が作られていく、そういう展開になっている。
廣瀬 『夜会』でも、まず、1階と2階という2つの空間があって、次いで、それらの空間をつなぐロジックが見出され、最後に、そのロジックに沿って、2階にいた人たちが1階に降りてくる。『豚』でも同じです。まず、屋外と屋内が並置され、次いで、それらのつなぎが見出され、最後に、そのつなぎを利用して、屋内にいた人が屋外にやってくる。
『ぼくの小さな恋人たち』も大きな作りとしては同じです。ペサックの田舎での幼い子どもたちとの木登りが一方にあって、ナルボンヌの街での青年たちとのナンパがもう一方にある。しかし、最後には、主人公が、街でのナンパのようなものを、田舎の子どもたちのところに持ち込んでしまうわけです。ここでは、一方の空間から他方の空間へと移されるものがまさに「身振り」であるという点で、よりいっそう興味深いように思われます。
|正しいつなぎ、間違ったつなぎ|
須藤 映像をどうつなげるかというのは、ユスターシュの中にずっとあった関心だと思います。彼は自作は自分で編集していますが、ほかの監督の作品の編集もしたりしていて、編集技師としても周囲から大きな評価を得ていた人物でした。興味深いのは、遺作になった『アリックスの写真』(1980)が「つなぎ間違い」のさまざまなヴァリエーションを試してみるといった具合になっている。最終的に、そういう方向に向かっていくんですね。
廣瀬さんは、たとえば「切り返し」のような映画のテクニカルなタームを一種の概念にまで練り上げ直し、その概念でもって作品を論じていきますよね。ただ、そのなかでも「つなぎ」というか、それに付随して「つなぎ間違い」みたいなものはこれまで大きく取り上げてこなかったように思います。
廣瀬 「つなぎ間違い」は、批評の用語としてよく使われてきたものですが、ぼく自身は、須藤さんがおっしゃるとおり、基本的に、その語の使用を自分に禁じています。「間違い」という表現に疑念を抱いているからです。「つなぎ間違い」は、当然、「正しいつなぎ」の存在を前提にしているわけですが、「正しいつなぎ」というのは、それ自体、「映画の文法」のようなものの存在を前提にしています。しかし、「映画の文法」に則った「正しいつなぎ」で編集された作品に、重要な作品が1本でもあったでしょうか。「正しいつなぎ」は、映画を撮ることのできない自称映画監督が、それでも自分の作品を映画にみせかけるために用いる装置に過ぎないのではないかと、ぼくは考えています。小津安二郎もどこかで同じようなことを言っていたはずです。
たとえば、これはすでに論じたことがありますが(「『ダゲレオタイプの女』問題、あるいは、黒沢映画の唯物論的転回」、『シネマの大義』フィルムアート社、2017)、山田洋次は「寅さんがまた旅に出ちゃった」というのをどう見せるのか。まず、寅さんとさくらが団子屋の軒先で話している様子を捉えたショットがある。次いで、タコ社長の声が画面外から聞こえてきて、同じショットのなかで、さくらが声の方へと振り返る。ここで、山田洋次は、店裏の勝手口から顔を覗かせているタコ社長を示すショットを挿入する。その後、もう一度、最初のショットに戻すんだけど、そのショットからはすでに寅さんが消えている。これがいわゆる「正しいつなぎ」です。
他方、黒沢清だったら、寅さんをどう消すのか。『岸辺の旅』(2015)の終盤近くで、浅野忠信が消えてしまいます。まず、浅野と深津絵里が海辺に2人で座っている様子を示す固定のロングショットがある。次いで、同じ場面を別の角度から撮り直すんだけど、この2つ目のショットにはすでに浅野忠信はいない。寅さんに言わせれば、これは「つなぎ間違い」です。沖合にたこ八郎の亡霊を召喚し、深津絵里をそちらに振り向かせなければダメじゃないかということになる。
須藤 たしかに「正しいつなぎ」といっても、それこそが大きな「間違い」とも言える。そもそも編集自体が不思議なものですよね。本来は別々だったものが、なぜかつながって見えてしまう。
廣瀬 ただ、ユスターシュには奇妙な欲望も感じられます。彼には、正しいつなぎをしたがっているような側面があるわけです。これも、ヌーヴェル・ヴァーグとの関係によって説明できるかもしれません。ジャン゠リュック・ゴダールを筆頭に、ヌーヴェル・ヴァーグの人たちは「間違っても、正しいつなぎなんてしませんよ」という立場だったわけで、ユスターシュは、自分はこれとは違うことをしなければならないと思っていたのかもしれません。ユスターシュは「人生」を映画に導入することでヌーヴェル・ヴァーグと距離をとろうとした。しかし、それだけではなく、つなぎにおいて正しくあることでも、一線を画そうとしていたということです。この点については、「現代映画」において長らく禁じられてきたズームを再導入してみせたホン・サンスと比較してみることもできるかもしれません。
須藤さんの本では、「おれは反動なんだ」というユスターシュの発言が度々引かれています。「反動的になることによって革命的になる」とユスターシュは言うわけだけど、しかし、まさに「正しいつなぎ」こそ、反動の最たるものでしょう。ジャンプカットなど、斬新な編集技法が数多く開発されていたなかで、「正しいつなぎ」を顕揚するなど、保守反動以外のなにものでもない。
須藤 ちなみに『ママと娼婦』にヴェロニカが一瞬消えるところがあるんですけど、いま説明していただいた寅さんと同じ消え方です。アレクサンドルがカフェのテラスにいるヴェロニカに目を付けるのですが、いったん通り過ぎて、やっぱり気になって振り返ると、席からいなくなっている。それで、急いで道を追いかける。
廣瀬 ユスターシュは左翼の批評家たちから批判され続けた監督です。それは作品に描かれていることに問題があったというだけではなく、友だちが悪い奴らばかりだったからでもあるでしょう。彼を取り巻いていたのは、先にも述べたとおり、ダンディたちですが、彼らは、保守反動、右翼のダンディでした。好きな作家からして、ルイ゠フェルディナン・セリーヌです。須藤さんの本では、エリック・ロメールやクロード・シャブロルのために脚本を書いていたポール・ジェゴフに憧れていたとも指摘されています。シャブロルは、ヌーヴェル・ヴァーグのうちで最も徹底したマルクス主義者ですが、ジェゴフ自身は極めて反動的な人です。ユスターシュの最初の中篇は『わるい仲間』(1963)と題されていますが、彼自身、悪い仲間に囲まれていた。
『ペサックの薔薇の乙女』(1968)というドキュメンタリーは、1968年の4月と6月に撮影されています。まさに68年5月の時期です。ユスターシュは、68年5月に見向きもせず、それどころか、わざわざパリを離れて、地方のお祭りを撮っている。68年5月とは無関係に盛り上がっている田舎の若者に、彼はカメラを向けたわけです。須藤さんの評伝でも、68年5月はその語すら出てきません。ユスターシュにとっては、68年5月は起きなかったわけです。
ユスターシュが68年5月を撮ろうとしなかったことは、しかし、肯定的にも理解可能です。68年5月ほど、そこでカメラを回しさえすれば何かいい映像が撮れてしまうに違いない出来事もないでしょう。ユスターシュはその容易さを自分に禁じたのかもしれません。東日本大震災後の福島には日本国内外から多くの作家が殺到し、競ってカメラを回しましたが、その同じ時期、堀禎一という映画監督は、浜松の山間村落に行って、茶栽培のドキュメンタリーを撮っていました。ユスターシュにとってのペサックは、この意味では、堀にとっての天竜区だと言えるかもしれません。
須藤 ヴェロニカが消えるくだり、ちょっと確認してみましょう。
抜粋上映 『ママと娼婦』(1973年)14:05—15:00
廣瀬 でも、これは正しいつなぎへの「擬態」のようにも見えますよね。先の『夜会』の場合もそうだけど、ぎくしゃくしている。連続性を無理に見つけ出そうとするその過剰さが、逆に、不連続性を際立たせてしまっているとでも言うべきでしょうか。
[後篇につづく→*]
須藤健太郎(すどう・けんたろう)
1980年生まれ。パリ第三大学博士課程修了。博士(映画研究)。専門は、映画史、映画批評。現在は、首都大学東京教員。訳書に、『エリー・フォール映画論集 1920-1937』(ソリレス書店)、ニコル・ブルネーズ『映画の前衛とは何か』(現代思潮新社)などがある。
廣瀬純(ひろせ・じゅん)
1971年生まれ。パリ第三大学博士課程中退。専門は、映画批評、現代思想、フランス文学。現在は、龍谷大学教員。著書に、『シネマの大義:廣瀬純映画論集』(フィルムアート社)、『資本の専制、奴隷の叛逆』、『暴力階級とは何か:情勢下の政治哲学2011-2015』(以上、航思社)、『アントニオ・ネグリ:革命の哲学』(青土社)など、訳書に、アントニオ・ネグり『未来は左翼』(上下、NHKブックス)など多数がある。
*
評伝ジャン・ユスターシュ 映画は人生のように
この稀有な映画作家に魅せられた批評家が、その生涯と作品を取材や調査によってあきらかにし、伝説化された実像に肉薄する世界初の本格的な評伝。
詳細なフィルモグラフィ、ビブリオグラフィ、人名索引を附す。
須藤健太郎 著
菊変判並製412ページ 3600円+税 共和国 刊
978-4-907986-54-4
小社通販サイト(クリック→*)より送料無料で発売中。