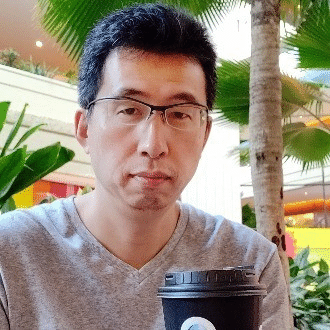【shopify #018 注文管理編】
主要機能のひとつ、注文管理機能を確認していきましょう。shopifyはあくまでも業務をカートに合わせていくことを前提としています。既存の自社基幹システムに合わせようとすると大きな改修が必要。
どちらに合わせていくのがいいのか?今後の主流はクラウドなので、やはり基幹システムもクラウド化し軽くしていくことが望ましいと思います。
当社では、ベースとなる基幹システムが34歳と高齢で今後保守管理をしていくことが難しくなってくる=エンジニアがいなくなるので、そろそろ本気でリプレイスを考えているようです。
話がそれましたが、今までのことが出来ないと嘆く前にどのようにして合わせていくか?を考えて取り掛からないと、ストレスがたまります。要・不要をしっかりと切り分けて進めていくことをお勧めします。
1.受注情報検索/一覧
受注情報の検索、一覧表示が行えます。
これが出来ないカートはないですよね(笑)
2.受注情報・配送情報のCSV出力
受注内容のCSV出力が行えます。
配送情報のCSV出力が行えます。
標準のCSV掃き出しでも良いのですが、データの出し入れはアプリを使ってやり取りしたほうが楽だと思います。文字コードの違いにより、そのまま開いてしまうと文字化けだらけ。それを回避するためにはスプレッドシートかアプリの利用となります。
やはりおすすめはこちら!?226件の評価で5.0ってすごくないですか?
3.新規受注情報登録
電話やFAXで発生した受注情報の登録が行えます。
これ皆さん対応されていますか?いたずら等の注文を避けるために行っておりません。あくまでもご注文主さんがご自身の責任で行っていただきます。
請求書の発行とかがshopify上からできるのは良いですね。当社はロジレスを利用するので、マイページから請求書・納品書・領収書が自身で取得できます。これにより、ペーパーレス化でき領収書の対応業務から解放されます。
4.出荷登録
出荷日時や問い合わせ番号(出荷伝票番号)を登録することができます。
5.受注情報編集・対応状況一括変更
受注情報の編集が行えます。受注の対応状況を一括で変更できます。
6.出荷メール送信機能・問い合わせ番号入力機能
出荷メールを送信することができます。
問い合わせ番号(出荷伝票番号)を受注詳細画面から入力(追加・変更)することができます。
この部分はロジレスの機能を使って行うので特に必要性は感じていませんが。。。問い合わせ番号をひとつの注文に対しては入力できないので、アプリを使うと便利かと思います。
日時指定という概念をShopifyが持ち合わせていないため、日本のエキスパート企業さんが沢山アプリを開発してくれることを願います。
その中でもトランスコスモスさんからリリースされたこちらのアプリで対応できます。
7.対応状況設定・各種メール送信
支払い確定、配送中などのステータスの設定が受注詳細画面から行えます。注文されたお客様に任意のタイミングで「商品発送済みメール」などのメールを受注詳細画面から送信できます。
発送済メールをバッチ処理でやっていると、必ず配信直前でキャンセルの依頼がやってくる(笑)現在は、朝9時ごろに作業が完了したものも17時の出荷案内メールとなります。実はこれって昼の便ですでに出荷済となっています。これらを解消するためにも、ロジレスで出荷明細突合せが終わったタイミングでデータを流し込むとその場で出荷案内メールが配信できる。
ロジレス押しとなっていますが、ロジレスのおかげで受注から出荷までがスタンドアローンで可能。基幹システムを介せずに完了するので基幹システムに依存しないオペレーションが可能。これにより、センターの作業効率も格段に上がり、バズって注文過多となっても作業のコントロールができるのでお互いにwin-win。
8.納品書PDF出力 +app
納品書のPDF出力が行えます。一括出力することも可能です。
ここも、ロジレスマイページ内より、購入者がDLできるので特に必要がなくペーパーレスとなります。
9.ショップ用メモ登録機能・ 配達用メモ登録機能
ショップ運営者が確認する用のメモを登録することができます。
出荷作業者や、配送業者に対するメモを登録することができます。
アプリでShipandcoを紹介していますが、日本向けではないですね。越境をされている方にはいいかもしれませんが、、、、
おそらく日本でも空前のshopifyブームなので、たくさんのアプリが開発されることを願っています。
10.注文管理のさいごに
今回、何度も出てきたロジレス。私たちがやりたかったことを解決してくれたのは、shopifyではなく実はロジレスです。shopifyのブームによる、簡単だから!ランニングが安いから!流行っているから!という理由で選択したのではありません。
現状抱えている問題が、ロジレスによって解消されました。その際にどのカートを利用するのか?
そう、Shopifyとロジレスはアプリで連携が容易で特に開発費用が発生しない。だからShopifyを選択。何が何でもshopifyありきではなく、スマートに利用できるのがshopifyだった。
今までのカートは、すべてを自社のルールに合わせてカスタマイズしていましたが、今回はいかにshopifyのルールに自社のルールを合わせられるか?のせめぎあいです。このnoteも、業務に漏れがないかを合わせて確認するため、チェックリストをもとに少しづつ書いています。
shopifyに飛びつくのではなく、まずはshopifyを理解して自社のルールを合わせられるかを検証してください。
いいなと思ったら応援しよう!