
所さんも目がテン! 楽天の劇的ビフォーアフターな某成績の改善劇。匠の正体は今季試験導入のVR打撃練習だった?!
こんにちは。@eagleshibakawaです。
故郷の英雄・真田幸村の赤備えがクリムゾンレッドに見える信州上田在住の楽天ファン、ブログや有料メルマガ、noteの運営と合わせて、「週刊野球太郎」や「ベースボールチャンネル」など野球専門メディアにも寄稿しています。
みなさん、先週の金曜深夜、NHK BSで放送していた『スポーツデータ・コロシアム』、ご覧になりましたか?
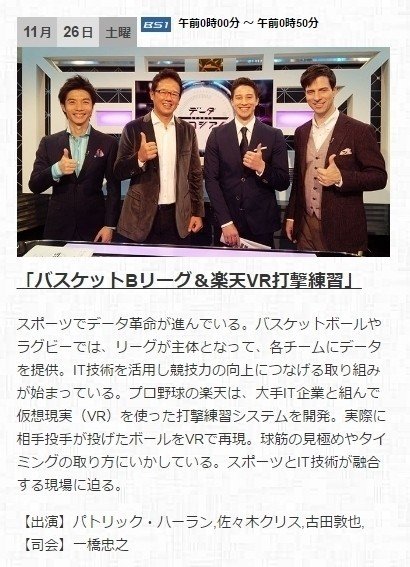
11月26日の放送回は、楽天のVR打撃練習が取り上げられていました。
各種報道で、みなさんもすでにご存じでしょう。今年、NTTデータ(三上弾、高橋康輔、馬庭亮太の3氏の研究チーム)が開発し、楽天に持ち込み、1軍監督、コーチ、全選手の意見をもとに共同で改良に取り組んできた「IT時代の打撃トレーニング・システム」です。
選手は特殊ゴーグルを装着して打撃練習を行います。
その特殊ゴーグルの中には仮想現実、ヴァーチャル・リアリティの世界が広がります。バッターボックスに立ったときの球場のリアルある風景が再現され、実際に投げられた球をデータ解析し、18.44m先から忠実に再現。
選手たちは、例えば則本昂大投手のスライダーなど、当該投手の球筋・軌道を事前にチェックできるのです。
番組内では、実際、今年、銀次選手がこの新型システムで相手投手の球筋を確認して試合に臨んでいたと紹介されていました。
また、イーグルスのチーム打率が昨年.241から今年.257に上がったのも、このシステムのおかげであるかのように紹介されてもいました。
このVR打撃練習、球団から正式発表されたのが9月5日でした。しかし、番組内では半年にわたり改良を重ねたと紹介されていましたので、シーズン開幕時にはすでにプロトタイプがあり、秘密裡に楽天に持ち込まれていたのでしょう。
その試作品がようやく本格運用できうる品質に達したため、満を持して9月5日の発表になったものと思われます。
実際、このVR打撃練習のおかげで、どの成績が劇的に向上したとか、大きく改善されたとか、外部であるぼくらからズバリ指摘するのは、大変困難なことになります。すでに運用されているトラックマンによるトラッキングデータの活用例も、具体的にはどうなっているのか?なかなか見えてこない。
MLBでは低迷ピッツバーグ・パイレーツをビッグデータで立て直した再建劇を描写した『ビッグデータ・ベースボール』が話題になりました。
邦訳本を読んだ読者の方もいると思いますが、ああいった形で外部に出てくることはないかと思います。
MLBと比べてNPBというか、特に日本は企業秘密やマル秘情報を隠したがるので(まあ、企業秘密なのだから隠すのは、当前なのかもしれませんが)、今後もその辺りのピンポイントな具体例は、あまり表に出てこないでしょう。
この点は、昨年12月、「スポーツアナリティクス・ジャパン2016」に登壇した、楽天のデータ解析に携わる山本一郎氏もそのようなことを述べていました。

しかしですよ。推測することは可能ですよね。
(まあ、、、推測することぐらいしかできないのが、外野のぼくらなわけではありますが)
実際、この番組を見ながら、
(´-`).。oO(この劇的すぎる成績改善は、ひょっとして、もしかするともしかして、VR打撃練習の恩恵も大きかったのかなー)
と思ったりもした、V字回復の成績がありました。
それはですね。
こちらです!
じつはですね。このぼくの予想、かなり精度の高い、ズバリなところを突いていることが判明しました。
※ここから先は有料エリアでお楽しみ下さい。セブンイレブンの淹れ立てコーヒーと同程度のお手頃価格でお楽しみ頂けます。
※なお、本稿はnote単価200円ですが、まぐまぐメルマガでも配信中。本稿を含む月十数本の連載で月額514円。読者数は、「中村紀洋の野球マガジン」を上回る支持をいただいております。noteで全コンテンツをバラで購入するよりも断然お得。さらに新規読者登録初月は無料購読のサービスも。まぐまぐでのご入会はコチラでどうぞ。銀行振込をご希望の方はtan_5277アットマークyahoo.co.jpまでご連絡下さい。
※見やすさで言えば、とにかくnoteがお薦め。スマホアプリでの閲覧が良いです。本稿はこちらのお得なバリューマガジンに所収されています。→「オフも語り尽くすshibakawaの鷲応援マガジン冬季版」。現在10名様に御購読頂いております。
読者の皆さんにいただいたサポートで、さらなる良い記事作りができるよう、心がけていきます。
