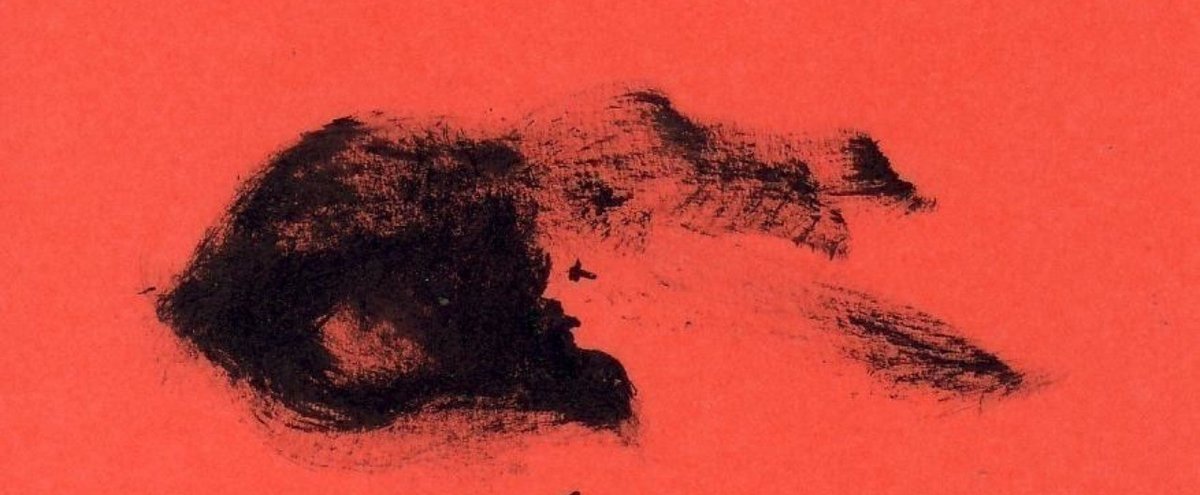
ラディカル・ゾンビ・キーパー 七
高校の同級生に青白い肌の女がいたことをラドは思い出した。白い肌にうっすらと浮かんだ青い血管が童貞の小僧にはあまりに刺激的だった。
その女はクラスで浮いた存在だった。顔や性格が悪かったわけではない。笑わないのだ。あれだけ楚々とした顔立ちの女はいないだろうとラドは今でも思った。背も高かった。肩甲骨まで伸びた長い髪、きりっとした切れ長の瞳、化粧品の広告モデルでもしたら世の中は必ず大騒ぎになるだろうとまで思った。もしかしたら本当にモデルとして活躍しているかもしれない。生きていたら。
ホンダCB750F、それを手に入れて浮かれていた。酒を飲み、その女を後ろに乗せて埠頭で事故った。女は即死だった。それで高校は退学になった。小さい頃にアメ玉の取り合いで喧嘩になった話をしたが、女は死ぬまで一度も笑わなかった。
ラドは煙草を押し潰した。女の名前が思い出せなかった。当然か、顔を見るまですっかり忘れていたんだから、ラドは路肩にアウディを停めた。そしてその女を思い出させた顔をしたグレージュのコートを着た女に声をかけた。歳は二十歳前後だろう。
女はあっさりと車に乗り込んだ。よく見るとあまり似ていないかもしれない。でも雰囲気は似ている気がする。成長したらこういう具合に変わるような気もする。
「今時の子は、警戒心ってもんがないのか?」
女は無言だった。ラドは車を走らせた。
しばらくして女が口を開いた。月を見ているような感覚になる声だった。あの女はどんな声だったかな、思い出せない。
「何処へ行くの?」
「いや、別に決めてないけど」
「何で声をかけたの?」
「何であっさり受けたんだ?」
女はまた黙り込んでしまった。セブンイレブンの看板を見つめている。
ラジオが演歌みたいな歌詞のレゲエを流し始めた。ラドはアメ玉の話をしてみたくなった。今度は笑うかもしれない。女との会話に困ったらこれだ。そういえばニナにはしたことがないな。
「……バター味とヨーグルト味のアメ玉の取り合いで喧嘩になったんだ、友だちと、小さい頃に」
そこまで言ってラドが女の顔を見ると、一応聞いているようではあったが、表情は変えなかった。この女も笑わない女なのか。
「俺はバター味を食べたかったのに、ヨーグルト味とどちらを食べるかを決める前に友だちがそれを全部食べてしまって、それで取っ組み合いの喧嘩になったんだ、確か公園で、通りかかったオバサンが止めに入った、俺は納得がいかなくて、すぐに家に帰って小遣いを握り締めて、スーパーにバター味のアメ玉を買いに行った、走って帰って、よし食べよう、ぱく、うん、まずいんだよこれが、馬鹿だよなあ、ヨーグルト味の方がさっぱりしていておいしいんだ、バター味はこってりしていて甘ったるい、確か二百円ぐらいしたんだ、いっぱい食べようと思って大きな袋のを買った、二百円、子供がアメ玉に二百円も出すのは勇気がいったぞ、その時の月の小遣いが五百円だからな、馬鹿だよな子供って、そのアメ玉は全部お袋にやった、それからバター味のアメ玉は一切食べなくなった」
そう言い終えてすぐに事故るんじゃないかという気がラドはしてきた。なんだか分からないが急に強い焦りと後悔が襲ってきた。信号は青だ信号は青だ信号は青だ。手に汗が滲み出した。女を見やった。笑っていた。叔父ではないが、秘書のような人当たりの良い笑顔だった。真っ直ぐ前を向いて笑っていた。それを見てラドはこの話をしたからあの女が死んだような気がしてきた。そして分かった、この女もあの女も心がないんだ。
「……笑ってるけど、面白かったのか?」
「え、うん」
ウソ、という顔になった。分かりやすい女だな。おっと赤だ。
「名前ぐらい、知っておこう、俺は、ケン、だ、ケン、でいいよ」
「……ナオミ、ナオでいいよ」
「心がないだろ?」
「え?」
「先に、何で俺を無視しなかったのか、教えてくれ、そしたら俺も何で声を掛けたか話す。普通、女の子は声を掛けてもすぐには誘いに乗らない、何を考えている?」
ナオは高層ビルのレストランから夜景を展望するような目つきを一瞬してから、自然な笑みをこぼした。ラドは後続の車にクラクションを鳴らされるまでその笑顔に見惚れていることに気がつかなかった。
「……なんか、どうでもよかったていうか、別に自暴自棄じゃないけど、見知らぬ男に連れ去られる女を演じたかった、のかな、よく、分からない、自分でも、もしかしたら、ケン、に、何か惹かれたのかもしれないし、一目見て、でも、よく、分からない」
「何か、あったのか? 言いたくなけりゃいいけど」
「……」
「俺は、昔の女を、ナオを見て思い出したんだ、死なせてしまったんだ、俺の不注意で、でも、そんなことすっかり忘れてしまっていた、でも、よく分からない、なんか、その時間を取り戻したかったのか、声を掛けたくなったんだ、俺もよく、分からないけど、なんとなく気になるっていうの、あるだろ?」
「うん、ねえ、その人、可愛かった?」
「生きていたら、モデルになっていただろうな」
「心がないって、なに?」
不思議な女だとラドは思った。声のトーンが変わるだけで心に溜まった水に波紋を起こすような感覚を与えてくる。さっきは月で、今は砂漠をゆったりと歩くラクダを思わせる。
「その死んだ女は笑わなかったんだ、何を話しても、まったく、さっき、ナオが見せた笑顔、不自然だった、機械みたいだった、だから心がないと思った、心がない奴ってのは表情がない、だけど、その後に綺麗な自然な笑みを見せたから、俺の誤解みたいだ、すまん」
「悲しい心は殺したの」
「え?」
「悲しい心は必要ないから殺したの」
今度は凍った竜巻みたいな声になった。ふふ、と笑って、ドラマみたいなこと言っちゃった、とナオはうつむいたが笑顔だった。あの女もこういう笑い方をしただろうか、薄い水溜りだと侮っていたら底なし沼だった、みたいな笑い方だとラドは思った。
「そんなこと言われるの初めて、でも、当然かな、言わない方が鈍感だって、お母さんも友だちも誰も何も言わないし、私に関心がないんだろうな」
「そうか? 笑顔は特に、心があるかないかが出ると俺は思う、機械みたいな愛想笑いは目の奥に光が射してないんだ」
「光?」
ラドは眼球に疼きを感じた。左目だけだったが、急ブレーキを踏みたくなるほど痺れるものだった。どしたの? アクアマリーンのベッドシーツが左目の前に浮かんではっきりと具現化した。奇妙な光景だった。この前、想像を自主的に促すと、考えると気持ち悪いが、心地よい快感に変わることが分かった。だが、これが何の映像なのかは分からない。そのシーツにゆっくりと滴る赤い血は、いつかの夏にナンパして孕ませた女のものだ。腕にしがみつき産んでもいいかと迫る女の腹を友人は思い切り蹴飛ばした。小川のせせらぎのような曲が聞こえてくる。ねえ、どうしたの? アスターパープルだった。アスターパープル、小さい頃、テレビショッピングでオバサンがそれを連呼するのがおかしかった、真似をしているうちに口癖になった、マフラーの紹介だった、アスターパープル、アスターパープルの、腕だ。それは血だ。バイクで事故った時に後ろに乗っていたあの女の腕がちぎれかかった、その時の血だ。左目に記憶されていたのか、左目が脳みそから引き出してきたのか、リアルにボンネットにあの女の腕が乗っかっている。右目はシルバーなのに左目はアスターパープルのボンネットだ。
「ねえ、どうしたの?」
「ホテルに行ってもいいか? 休みたい、何もしない、そんなつもりで声を掛けたんじゃない、話がしたかっただけだ、何もしない、行ってもいいか?」
ナオは頷いた。それはラドには見えなかった。車はホテルへと入っていった。
シティホテルの七階の部屋は狭かった。明かりはテーブルライトだけで、少し湿気った匂いがする、窓からは道路を走る車しか見えない。
ナオはパックの紅茶を入れてくれた。眼球くんは疲れて少し落ち着いたようだ。
「なにか、病気なの?」
「ああ、ちょっとな」
「……笑っちゃダメだけど、あのまま事故を起こしそうで、ちょっと、ハラハラして、面白かった、ジェットコースターとか好きじゃないけど、どうなるか分からないっていうの、面白かった」
「そうなってたら、俺は笑えないよ、さっき言った女も、俺がバイクに乗せて死なせてしまったんだ、ナオと重ねてた、自分でもよく分からないけど、思い出してから気になってしょうがなかった、バチがあたったんだよ、ナオはナオだ、すまん」
ナオは聞いていないような感じでテレビの番組表を眺めている。リモコンを手に取ったが、すぐにテーブルに戻した。すると今度はデスクの引き出しを開けて新約聖書を取り出して、パラパラと捲り始めた。
「悲しい心を殺したって?」
ナオはゆっくりと振り返った。
「さっき、そう言ってた、話の途中だった」
「……心を無くせばなんでもできるの、知ってる? 心を無くせば誰とでも話せるし誰とでも付き合えるの」
「……」
「自分を意識すると何も言えないし誰とも付き合えないの、今、こうやってケンとお話してる、さっき会ったばかりの知らない人とホテルで二人っきりでお話してる、心を無くすと何も感じなくなるの、だから何でも話せるし何でもやれるの、だからといって、心を全て無くしちゃダメよ、それは廃人、だから、悲しい心だけを無くすの、そうすれば嫌われても悲しくないし、ケンカしても悲しくない、嫌味を言われても悲しくないし、無視されても悲しくない、腹は立つよ、でも、悲しくないの、悲しいって、悲しみが強すぎると、死にたくなるの、心を込めると、すごく揺さぶられて、死ぬところまで揺れてしまうの、自分は何のために生きてるのかっていう夢を何度も何度も見るの、生きる意味はない生きる意味はないって繰り返し呟くの、私が、自分で、夢の中で、今、私は生きてる、何のために? 確かめたくないのに、そう確かめるの、心が勝手に、そして気がつくの、私は仕方なく生きてるって、だけど分かったの、私はお金のために生きるんだって、お金を稼ぐために生きるんだって、でもお金を稼ぐことは悲しいことばかりなの、だから悲しい心を私は殺したの、心を殺せばなんだってできるの、体だって売れるの、ビデオにだって出られるの、バレて怒られても平気なの、悲しい心なんてとっくに殺したから、私はなんだってできる方法を手に入れたの」
「……似たような夢を、見たことがあるよ、自分は死んだ人間じゃないかって思う夢だ、ここはあの世じゃないかって、そしてそれを、いつしか現実でも思うようになってしまった、今でも思うことがある、だけど、現実が本当に苦しい人は、夢は見ないんだとさ、夢の中でまで苦しめられたら精神がおかしくなるかららしい、睡眠は肉体ではなくて精神を休めるためのもので、夢は苦しめるもんじゃない、現状への警告なんだってさ、だから、ナオが思うように、俺もなぜ自分が死んでるんじゃないかって夢を見るのか、それが何を暗示しているのか、気になってしょうがない、それは、本当に死んでいることに気がつけよ、ということなのかもしれない、俺は今ナオと話してる、あの世でかもしれない、天国や地獄は、こういう、現実とまったく同じものなのかもしれない、だけど、生きる意味はないの答えが、お金は、違うと思う」
「……どうして? どうしてそう言えるの?」
悲しい目だった。この子は悲しい心なんて殺してない、ラドは抱きしめたくなって、それがニナに抱いた感情と同じだってことに気がついて、それはただ、自分が自分と同じように傷ついて弱っている人間が好きなだけなんだと気がついて、それを今になってなんで冷静に気がつくのだろうと自分に腹が立った。頭のいい犬は飼い主の些細な心の変化も感じ取って吠えたりする。自分が頭がいいと言っているわけではない、自分はそういう犬と同じように自分と同じ匂いのする人間の感覚を鋭く吸収することができるのかもしれない。それは本能か、自己崩壊を抑止する同じ性質の仲間を見つけるための本能か。
「どうして?」
「……金を稼ぐことは生きる目的にはならないと思う、そこには何の意味もなくて、ただ、お金というオールマイティな物々交換のアイテムを手に入れなければ生活できない、ただそれだけだと思う、多くの金を持っていれば多くと交換ができる、ただ、それだけだ、それは生きてきた意味になり得るのか? 今、宝くじを当てたとする、それが生きてきた意味か? 辛いことも嫌なことも堪えて堪えて生きてきて、そこでポンと大金が手に入って、それが生きてきたってことになるのか? 確かに、宝くじじゃなくて働いて得た金なら、そういう実感は湧くかもしれない、でも、その場合は働いたことが生きてきた証だろ? お金を得た額じゃないだろ? 俺は、俺の父親は社長で、実は俺はそこの役員で、毎月、何百万って金が入ってくる、だけど、そこに俺の歴史はないんだよ、スタートを切ったこともないしゴールも用意されていない、あるとすればバトンタッチだけで、またそのバトンタッチが繰り返される、人間はその環境で器が測られる、俺は金を持ってる、だけど俺はただの金の管理人だ、ナオ、心を殺して金を稼いで、そこに何が残る? 心を殺さないと付き合えないような人間と付き合っているナオも心を殺さないと付き合えないような人間の一人なんだよ、自分を悲しい思いにさせる人間が嫌だから心を殺したんだろ? それと自分は同じなんだよ、それ、誇れるのか? それで生きてきたっていうのか? それが生きる意味か?」
「私は他人に誇るために生きてない」
「他人じゃない、自分にだ」
「……お金がないと何もできない、自分も見つけられない、子供の頃、私も、妹のミオも、才能の芽でいっぱいだったはず、だけど、うちは貧乏ではないけど極平凡な家庭だから、大した才能なんて伸びなかった、お金があれば違ったはず、もっと色んな習い事も出来てプロとかにもなれたかもしれない、お金があればミオを大学にやれる、私は行かなくてもいい、行きたくないから、だけどミオは行かなきゃダメ、中学や高校と大学は違う、もっと自由、ミオもそこならうまくやれる、合唱コンクールに出たり、修学旅行、バイトしたり、友達と笑って少女漫画やドラマの話をしたり、ひきこもって何もできなかったミオが花開くチャンスなの、お金があれば大学にやれる、お金なの、お金でチャンスは買うの、だってそうでしょ? そうでなければ、教育は無料のはずでしょ、お金を払わないと成長するチャンスがもらえないの、お金でチャンスを買うの、チャンスはお金で買うの、そうでなきゃ、何もないミオはどうなるの、私はどうなるの」
「ナオは、妹が好きなのか」
「好きよ、大好きよ、ミオが大好きよ、なのに小さい頃のミオの記憶が全然ないの私には、写真もないの、ミオは、私なんかよりもよっぽど辛くて悲しくて寂しい思いをしてるの、私はミオの幸せのためなら何でもする、心だって殺す、体だって売る、お金を稼いでミオを幸せにするの、ミオに比べたら私なんて平気なの、ミオも将来、一人で生きていかなくちゃいけない、なのに、あの子は何も出来ないままなの、勉強したいって思ってもその時にお金がなかったら何にもならないの、そうでしょ? 可愛そすぎるでしょ? だから私は悟ったの、私の生きる意味は、ミオを幸せにするためにお金を稼ぐことなんだって、私は悟ったの、だって、親にも見捨てられてるんだから、あの子は、私がなんとかするしかないじゃない」
「うまく言えないけど、違う気がする、ナオは、お金のためじゃなくて、妹のために生きているんだよ、それは間違いない、お金のためじゃない、妹のために生きている、それは素晴らしいことだと思う、自分以外の人のために自分の身を削るなんて俺にはできない、だけど、それは妹の人格を否定してる、ナオが妹の人生を決めてしまっている、ナオは妹のサポートを決めた、それを妹は望んだのか? 無理強いしようとしてないか? そんな風に聞こえたよ、妹への深い愛情は感じた、だけど妹を人間だとは思っていない、自己投影した人形みたいに感じたよ」
ラドは煙草を取り出して咥えたが、火をつける前に紅茶を口にした。するとなぜか、冷めた紅茶がニナの顔を思い出させた。無邪気な笑顔だった。
「……本人が望まない限り、他人は手を差し伸べちゃいけない、それが不幸にすることもある、自分で立ち上がるのを待つのも助けることだ、他人にしてやれることは基本的には何もない、人一人の一生を背負うだけの覚悟があるのか? 俺にはできない、そんな無責任なこと」
「私にはできる、ミオは私が育てる」
「それじゃ妹は変わらない、ナオが本当にやらなきゃいけないのは、ナオが楽しく生きてその姿を妹に見せることだろ、泣いて、笑って、叫んで、人間は、ナイフ一本で一生を終えられるんだよ、人間は儚すぎるんだよ、明日死ぬかもしれないんだよ、ナオは、心を殺したまま、自分を殺したまま、死んでいいのか? 後悔しないか? 心を殺して過ごすナオを見て、妹は、心を殺さないと生きていけない世界なんだって思うだけだろ、ナオも妹も、このままじゃ後悔と寂しさしか残らない」
煙草を吹かす自分の手が震えることにラドは気がついている。心臓の慟哭も増すばかりだ。ナオに言いながら、同時に自分にも言っていた。自分はナオを責められない。自分にはモーションすらない。今死んで、一番後悔するのは自分だった。ナオは妹のために覚悟を決めている。自分を殺すという覚悟を決めている。なのに自分はなんだ。自分のためにすら覚悟を決めていない。父親の金を拒むこともしない。尾も振らない。何がしたいんだ。自分で言ったとおり、後悔と寂しさが付き纏っている。寂しさはニナで紛れても、後悔は自分で拭うしかない。ニナがいなくなったら、きっと別の女で寂しさを埋めるだけだ。ニナは道具でしかなかった。自分は最低だ。ニナに謝ろう。帰りにすぐに謝ろう。そしてお別れしよう。自分にはニナと一緒になる覚悟なんてない。自分の一生も覚悟できないような蛆虫だ。本当は生きてちゃいけないような人間だ。そのとおりだ。自分は死んだ人間だ。やっぱりここは死後の世界じゃないか。そして永遠に苦しむ地獄じゃないか。
「……泣いてるの?」
頬を伝ったのは汗じゃなかった。ラドは拭うことはしなかった。涙を零せば零すほどニナの顔が浮かんできた。別にニナが好きなわけじゃない、ニナを思い浮かべると寂しさが紛れるんだ、だから涙を拭わないんだ、そうすればニナが沢山浮かんでくるから、そうすれば寂しさが紛れていくから。
「雨が降るたびに温かくなる、人も同じ、そう、言ってた人がいた、有名人じゃない、偉い人じゃない、その辺にいる普通のおじさん、でも、私はこの言葉が好き、泣いたら、その後は少し、温かい人になれてるって思えるの、私は悲しい心は殺してしまったけど、寂しい心は残っているから、たまに泣く、その時にこれを思うの、泣きやんだら前よりも少しだけ温かい人になってるの」
そう言ってナオはやさしく肩を抱いてくれて、やさしく髪を撫でてくれた。自分はどうしようもない奴だとラドは思った。ナオに抱きつきたくなった、唇を合わせてセックスしたくなった。本当にニナじゃなくていいんだってことに気がついてしまった、どうしようもなくなってしまった。ニナは温かかった。ナオも同じくらい温かい。二人の温かさは共通している。誰かのために生きている。
月の明かりが綺麗よ、私、月、見るの好きなの、ラドが目を覚ますと窓から銀色の光が射し込んでいた。ナオはナオで、あの女でも、ニナでもなかった。ナオの笑顔で起こされたのだ。
「もう少し、科学が進歩した世界に生まれたかったって思うことがたまにあるの、ドラえもんまではいかなくても、もう少し、月に行けるくらい、私、月に行きたいの、真っ赤な月に、誰の絵だったか忘れたけど、学校の課題で美術館に行ったことがあって、そこで真っ赤な月を見たの、綺麗だった、甲子園の土を持って帰る気持ちが分かる、月の赤い砂がほしい、赤い月の土で湯飲みとかお茶碗を作ったら素敵じゃない?」
紅茶、飲む? ラドは首を振った。頬に当たったナオの肉が温かくそして柔らかかった。
「今よりも科学が発展した世界ってどんな感じかな、砂漠とかなくなってるのかな、空とか飛べたりして、でもあれだな、きっと、環境とか戦争とか、問題は今と何も変わらないんだろうなあなんて」
この子は心なんか殺してない、ラドは改めてそう思った。悲しさと寂しさはたぶん同じだ、言葉が違うだけだ、この子はきっと人一倍豊かな心を持ってる、それが馬鹿馬鹿しくなってくる世の中なんだ、悲しい心を殺したんじゃなくて、それが周りに受け入れられないことが単純に悲しいんだ。
ナオは口を尖らせて、紅茶に立った湯気を遊んだ。
「この前、寝る前に思ったんだけど、私、なかなか寝つけなくて、色んなこと考えちゃうの」
あの女の名前は思い出せなかった。ナオミ、だったらなとラドは思い始めている。偶然や運命に微笑む自分はどうしようもない弱虫だな。あの女も、きっと、笑いかけて、笑いが返ってこないことが、怖かったんだ。
「この前、思ったの、極端だけど、人間の利便のみを追及したら地球が死ぬ、地球の環境を第一に考えたら人間の存在が最大の悪害、でしょ、だから、双方がバランスよく、良いところも悪いところも抱えて、上手に、その均衡を保たないといけないんじゃないのかなって、思ったの、人類は自身のために科学を発展させるんじゃなくて、その均衡を保つために科学を発展させないといけないんじゃないかって、大量の排気ガスを吐き出すなら同時にその排気ガスを処理するものを開発しないといけないってどっかの偉い学者さんが言ってた、それ、なんだかすごく分かったの、それだ! って分かったの、それが人類の使命じゃないかって、そのために人類はいるんじゃないかって、だから、地球に巨大隕石が衝突する前に、人類のためじゃなくて地球のために破壊する、そういう関係でないといけないんじゃないかって、思ったの、人類と自然を守るための科学、だから、神様って偉いと思うんだ、試してるのよ、人間を、だから、自分が人間だから人間のために人間として生きるというのが、私はあまり好きになれない、大津波や大地震で人がいっぱい死ぬでしょ、その中には子供もいて、野球選手になりたい、サッカー選手になりたい、って思ってた子もいて、叶えることなく死ぬでしょ、でも、それって、いいと思うんだ、地球がそうしたかったなら、いいと思うんだ、仕方がないって、私は受け入れちゃう、私は人と動物と植物と地球とで生きてるんだしなあって、これって、人間もそうだと思うの、良いものと悪いものがあってバランスが取れてる、だから、本モノの自分と偽モノの自分がいていいの、そういう、バランスなの」
「……人間の完全体は、たぶん、良くも悪くも、全てを受け入れられる人間だろうな、人間ってのは、多かれ少なかれ、何かを他人に願ってる、自分の理想を無意識に他人に押し付けてる、それって、ナオが今言ったように、地球にも押し付けてるよ、神って、地球のことだと思うんだ、地球は全てを受け入れてる、人間も、その業も、体を痛めて、全てを受け止めてる、人間も地球から生まれたんだから、そこに到達できるはずなんだ、だけど生きている内は無理な気がする、生きることそのものが地球に負担を掛けているから、今、俺が言った、人間の完全体、人間が神や仏になるのは、死ぬ瞬間、コンマ一秒でのみ、その領域に達することができるんじゃないかって、これは皮肉だけど、土に返る瞬間、もしくはその時、地球と一体となって人間は完成する、考えようによっちゃ、死ぬまで理想を追う、苦しい人生だ、ってことだけど、な」
「ううん、私は好きよ、その考え方」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
