
ChatGPTとの対談(その13:「時間経過」について)
今回は、「時間経過」について、対談してみました。以下、対談内容です。
私)続きの対談です。数学の証明を解くために、論理学は有力な手段であり、人間の思考に関しても大きな役割を果たしている。しかし、論理学では、一般的に、時間的な変化を考慮しない。考慮するために、そのための条件を、燐る式として付け加える必要がある。この違いを悪用して誤った論理的な結果導き、世界に不幸に追いやったこともあったようです。いわゆる、三段論法の欠陥とも言われています。悪用じれとしては、例えば、今日、命題「AならばB」であることが真であることが証明されたとして、明日も、その命題が真であるかどうかは、本来、不明である。つまり、明日には、その命題が偽になることを知りえる人間が、明日も、その命題が真であると口外し、自分の都合の良い結果を論理的に導きだし、第三者へ誤った判断へ誘導する事例になります。命題「AならB」において、Bは、必要条件たるAの集合によって、定義付ける手法もある。これは、昔のAIで使われた、フレーム理論の基礎となっている。ここで、時間経過の影響が問題になる。Bが時間とともに変化する。例えば、「B」=「美人」とした場合、Bの基準は、人間の時代によって、異なっている。丸顔が美人とだった時もあり、細顔が美人だった時もある。Bの時間的な変化で、その必要条件たるAも、必然的に変化します。論理学の派生に、時相論理学というものもあり、時間経過を含めた論理学のシステムを提唱していますが、それが専門的意で、一般の人間が思考で、採用することは、まず、ないようです。それゆえ、三段論法の欠陥で詐欺にあうなどの人がいなくならない訳です。AIシステムにおいて、時間経過を、どのような情報として学習するのか、教えて下さい。
ここから先は
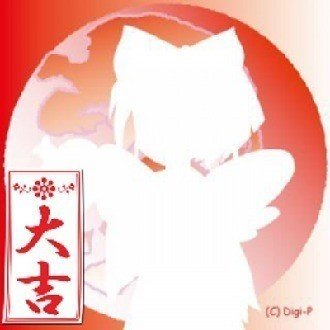
人類の不安を煽るChatGPTとの対談
人類の不安を煽るChatGPTとの対談と銘打って、人類が不安になりそうな、テーマで、ChatGPTと対談した内容を、記事にしていきます。
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
