
宇宙ステーションの超低温気泡が、量子研究の新たな道を拓く。

NASAのカリフォルニア州パサディナにあるJPL研究所(Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif.)が公開している「NASA's Jet Propulsion Laboratory Day in Review」は2022年05月18日に、NASAの「コールド・アトム・ラボ(Cold Atom Lab)」で製造された気泡は、エキゾチックな物質の状態を実験する新しい機会を提供する。
NASAのアポロ計画の時代から、宇宙飛行士は微小重力下での液体の挙動が地上とは異なることを記録し、そして論争し、底の重い液滴ではなく、浮遊球に合体していることを明らかにしてきた。このたび、研究者たちは、物質が到達できる最低温度である絶対零度(華氏マイナス459度、摂氏マイナス273度)まで冷却した気体という、よりエキゾチックな物質を用いてこの効果を実証した。

研究者たちは、ISS(International Space Station/国際宇宙ステーション)に設置された史上初の量子物理学施設であるNASAの「Cold Atom Lab」を利用して、絶対零度より100万分の1度高いところまで冷却した原子のサンプルを採取し、非常に薄い中空の球体に成形することに成功した。冷たいガスは、卵の黄身のような小さくて丸い塊から、薄い卵の殻のようなものに成形される。地球上では、同様の試みは失敗に終わっている。原子は下に向かって溜まり、泡というよりコンタクトレンズに近い形になってしまう。
https://time-az.com/main/detail/76931
この画期的な成果は、022年05月18日水曜日にNature誌にオンライン掲載された新しい論文に記載されているが、宇宙ステーションの微小重力環境でのみ可能なことなのである。

それがなぜ重要なのか?
材料をさまざまな物理的条件にさらすことは、その材料を理解する上で重要なことである。また、その物質の実用的な用途を見つけるための第一歩となることも少なくない。
宇宙ステーションで「Cold Atom Lab」を使用してこの種の実験を行うと、流体の運動や挙動に影響を与える主要な力である重力の影響を排除することができる。そうすることで、液体の表面張力や粘性など、他の要素をよりよく理解することができる。
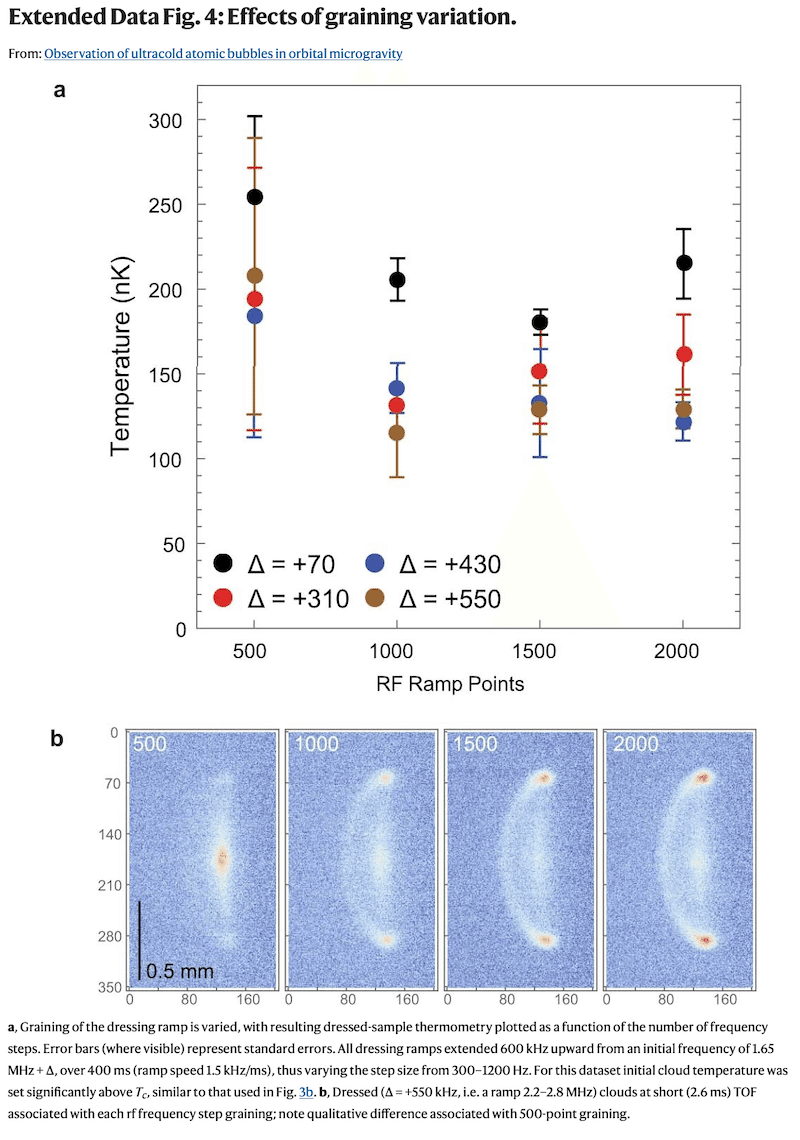
超低温の気泡ができたので、次のステップは、気泡を構成する超低温の気体をBEC状態に移行させ、その挙動を見ることである。
メイン州ルイストンにあるベイツ大学の物理学教授で、この新しい研究の主任研究者であるネイサン・ランドブラッド(Nathan Lundblad, a professor of physics at Bates College in Lewiston, Maine)は、「いくつかの理論的研究は、BEC状態にあるこれらの気泡の1つを扱うと、量子物質中に渦(基本的には小さな渦巻き)を形成できるかもしれないと示唆しています。」「これは、BECの特性をより良く理解し、量子物質の本質をより深く洞察するのに役立つ物理的構成の一例です。」と語っている。
量子科学の分野は、トランジスタやレーザーのような現代技術の発展に繋がっている。地球周回軌道上で行われる量子研究は、宇宙船のナビゲーションシステムや、地球や他の太陽系天体を研究するためのセンサーの改良につながる可能性がある。地球上では何十年も前から超低温原子施設が稼働しているが、宇宙では重力の影響が少なくなるため、超低温原子やBECを新しい方法で研究することが可能になる。このため、研究者は定期的に低温に到達し、地上よりも長く現象を観察することができる。
JPLのCold Atom Labプロジェクトサイエンティストのジェーソン・ウイリアムズ(Jason Williams, project scientist for Cold Atom Lab at JPL.)は、「Cold Atom Labの主な目的は基礎研究であり、宇宙ステーションのユニークな宇宙環境を利用して、物質の量子的な性質を探求することです。」「新しい形状の超低温原子を研究することは、その好例と言えるでしょう。」といっている。

