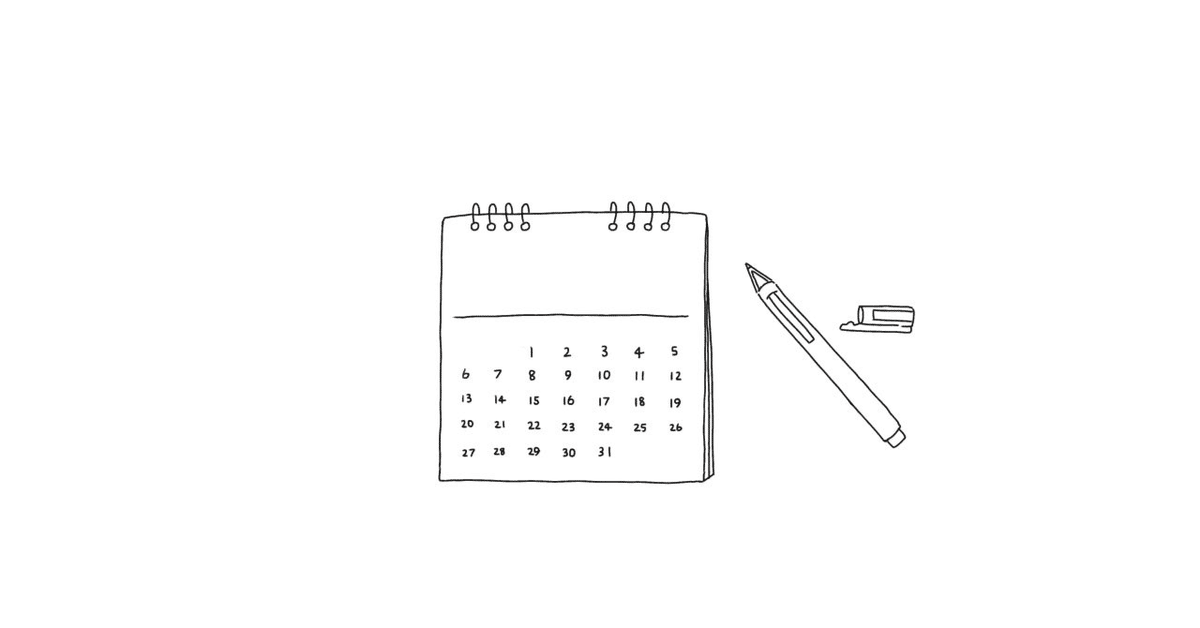
読書メモ|目的=未来を描いて実現する方法|目的ドリブンの思考法
今日は「戦略コンサルタントが大事にしている 目的ドリブンの思考法」をご紹介します。
こんな人におすすめ
以下にあてはまる方におすすめの本です。
・なんのために働いているのか分からない
・取り組んでいることに意味が見出せない
・チームの方向性がまとまらない
・仕事で適切な指示が出せない
・叶えたい夢がある
取り入れたい3つのポイント
私が本書を読んで、特によかったなと感じたポイントをご紹介します。
❶目的は「使命」や「意志」をエネルギーにする
目的を設定する際には「できる・できない」の話はひとまず脇に置き、まずは「〜すべき(使命)」「〜したい(意志)」というゼロベースの思いから出発すること。
そのように目的をセットしてから、次に「どのようにそれを実現するか」考える、と本書にはあります。
能力はあくまで目的を実現するための「手段」でしかありません。
現時点で能力が不足していても、目的に応じてそれを強化したり、外部から補強したりすることができるし、能力は、目的に従ってあとから高められるものなのです。
腹落ちする目的を見出す方法は「何のためなのか?」と問い続けることです。
❷目的と現状の間にあるギャップを埋める
目的を達成するというのは、すなわち、目的と現状の間にあるギャップを埋めることです。
目的と現状の間にあるギャップを埋め、目指す姿の実現を可能にさせるもの、それが「手段」です。
抽象的な目的を実行対象として具体化したものが「目標」、目標をさらに具体化すると「手段」になり、実行につながります。
❸それそのままで学ばない
「学校の勉強は重要なのか?」という議論に対して、著者は「それは学びを使う人次第」であり「使いこなせれば学校で得た学びは仕事で生かすためのアナロジーの宝庫である」と答えています。
アナロジーとは?
「既知」の内容を「未知」にあてはめて新たな理解を得ようとする試みのこと。
重要なのは何事も「それそのままで」学ばないこと。
国語なら「相手の主張を読み解き自分の意見をつくるための方法」として学ぶ。数学なら「論理的に正確な主張を組み立てる方法」として学ぶ、など。
上記のように「〜として」学ぶことで、テキストに書かれた情報以上の大きなものを学び取ることができるようになるというのは、私にとって新しい発見でした。
まとめ
私は普段から目的や目標を考えるのが好きなのですが、改めて目的と目標の違いや達成の仕方を学ぶことができました。
そして何より、本書の中で紹介されていたマハトマ・ガンディーの「目的を見つけよ、手段は後からついてくる」という言葉に私はとても励まされました。
そのほかに、本書の中でいいなと思った部分をメモしておきます。
・リーダーは目的を成し遂げ、目指す未来を実現するために存在する
・アフリカのことわざ「早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければ皆で行け」
・備えは最悪に向け、希望は最良に向けよ。
・大切なのは最悪の事態に備える「冷めた目」と最良の結果を期待する「明るいまなざし」を持ち合わせること。
定期的に読み返したい一冊です。
