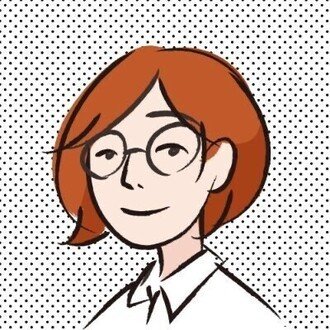ユーザーインタビューはみんなで「共感」するためにある?#01 THE GUILD勉強会レポート
THE GUILD主催の勉強会へ参加してきました!
今回、せっかくnote枠で参加させて頂いたので、良質な内容や詳細はたくさん上がると思い、できるだけ私なりのレポートをお届けします!
【この記事を書いている人:スズキアユミ】
デザインメモというブログを運営している、今年7年目のデザイナー。Webやアプリなどのデザインから、最近はUXまで手を伸ばしてます。ユーザーインタビューは未経験です。
(1)なぜユーザーインタビューをする必要があるのか?
■ 同じ視点からプロダクトを評価する
■ ユーザー中心の価値判断をする
私たちは自分のバイアスの中で生きているものです。
でも、みんな普段からそのことを意識して生活はしていません。なので、何かサービスやプロダクトを作ったときも、客観的な視点で判断ができないんですね。
とはいえ、異なった視点を持った者同士で、作ったモノを分析して改善・改良していく必要があります。
登壇者の金子さんがあげていた例:

金子さん「視点によって見え方が変わるのは、価値観・境遇・知識の違いからなるのではないか?」
(2)必要なのは「共感」=相手を知ること
では、私たちはサービスやプロダクトに対して見え方が異なってしまうことに、どう対処していけば良いのでしょうか?
それは「共感」すること。
金子さん「共感と同情は違う。共感は相手を知ることであって、同情は”自分だったら‥”となる。」
金子さん「例えば、自分がAさんだったらどう思うか?相手のバックグラウンドを知ろう。」
(3)みんなを巻き込んで「共感の解像度」を上げる
登壇者の金子さんは、多種多様なメンバーで直接インタビューすることも大事だとおしゃっていました。それは、組織やチームとしての「熱量」を上げることにつながる。
共感は、いわば体験ですよね。その体験が直接かそうでないか、そこの距離が出てくれば出てくるほど、金子さんが表現していた「共感の解像度が落ちてしまう」のです。
金子さん「自らユーザーインタビューをやらずとも、インタビューに特化した人をメンバーに入れるのも手。」
→ つい、ユーザーインタビューも自分でやらないと‥!と思いますが、得意・不得意もあるので、たしかに自分で無理にやらなくてもいいかもしれません。ただ、自分でやらなくても、距離の近さが大事。というところでしょうか。
(4)一人でもまずはやってみよう
金子さんが紹介していたデレク・シヴァーズ氏の有名なTED動画「社会運動はどうやって起こすか」。私も好きなTED動画です。
なぜ、この動画が突然出てきたのかというと、なかなかユーザーインタビューを組織やチームで導入するのが、ハードルが高く感じたり、億劫になってしまう。ならば、この動画のような最初にダンスし始めた人になって、たくさんのフォロワーを増やしていこうというメッセージが込められているのではと解釈しました!
─────────────
【さらに詳しく】
一人目の登壇:金子 剛さん(弁護士ドットコム株式会社 / デザイン・マネージャー)のより詳しい登壇内容については、ご本人がnoteにまとめていらっしゃるので、ぜひ下記の記事を熟読あれ。
─────────────
(5)相談が来てから完了までのプロセス
ここからはDMM.comラボの西部さんと伊藤さんの登壇内容から、より具体的なプロセスでとくに気になった・なるほどと思ったものをご紹介します。
【DMM.comラボでのプロセスの流れ】
STEP1:ヒアリング
STEP2:インタビュー設計
STEP3:実査
STEP4:分析
プラス1
■ バイアスをかけない方法
・質問の「抽象度」を上げると良い。機能ベース(「お気に入り」など)で尋ねるとバイアスがかかりやすい。
■ ユーザーへの接し方(アイスブレイク・ラポール形成など)
・話し相手になるように意識する。ユーザーによっても変化。
・時事ネタを用意して、共通の話題で打ち解ける。
・尋問にならないように注意する。
・専門性が高いと嘘も見抜けないので、事前のインプットが大事。
・ノンバーバル情報から読取る。ユーザーの反応をよく観察して、ベースラインを知る。表情の変化や一瞬の動作を見逃さないように。
■ 分析手法
・ユーザーの発言を鵜呑みにしない。ユーザーが「赤いボタンがいい」と言ったときに、どうして赤い方がいいと思ったのか?など。
■ 施策への落とし込み方
・カスタマージャーニーなどで、ユーザーのペインポイントを洗い出す。
■ 社内でライブ配信
・ユーザーインタビュー時にリアルタイムで社内にライブ配信している。こうすることで、例えば別の部屋でディスカッションができる。
・事業部長を巻き込みたいときも、ライブ配信にきてもらうと◎。
■ インタビューの練習
・最初は社内でひたすら練習。そうすることで、様々なパターンを設計できるので、未然に取りこぼしも防げる。
─────────────
(6)その他
登壇者3名と深津さんの質疑応答・パネルディスカッションで、とくに気になったものを取り上げます。
■ ユーザーが意見しやすい雰囲気づくり
・謝礼を一番最初にあげる。(深津さん)
・サービスの悪口を一緒に言っちゃう。(深津さん)
・自分たちが作ったものじゃないと言ってしまって、ユーザーが遠慮なく発言できるようにする。(伊藤さん)
■ 言ったこと・やったことが混ざらないように!
・例えば、スプレッドシートを3つに別けて進める。(深津さん)
■ 報酬だけが目的ではないユーザー
・既存サービスのユーザーだと、そもそもそのサービスが好きで協力してくれている場合があり、決してお金だけが目的とは限らない。(深津さん)
・来てよかったなと思ってもらえることが大事。(こばかなさん)
─────────────
(感想・まとめ)共感しづらくなっていく世の中
ユーザーインタビューってそもそもどんな目的でやるのでしょうか?
この問いは、じつはユーザーインタビューに限ったことではなく、今回の登壇内容を聞いていて、UX(ユーザー体験)に関わるすべてのことに言えることのように思いました。
サービスやプロダクトには、いろんな立場や職種・背景を持った人たちが関わります。そんな人たちで、一つのモノを作り上げようとしているのです。みんなで同じ方向を目指しているはずなのに、バラバラになっていては、改善も改良もありませんよね。
今回の勉強会では「共感」「価値観」「バイアス」というキーワードが多く飛び交いました。
逆に、私たちはユーザーインタビュー設計までしないと、ネットが無かった時代よりもずっと「共感しづらくなっている」のかもしれません。
それほど価値観が多様になりつつある世の中で、サービスやプロダクトを提供してビジネスにしていくこと。
こうやって考えていると、「組織やチームで誰もやろうとしてくれないから・・」と、手をこまねいてはいられない気がしてきます。
深津さんもおっしゃっていましたが、すぐにでも、まずは隣にいる人にユーザーインタビューやってみよう・・!
いいなと思ったら応援しよう!