絵を見る技術を読んだった。#1
どうも。秋田麻早子さん著の絵を見る技術という本を拝読させていただいたので、そのまとめを章ごとに殴り書きで書いていく。
複数の軸で描かれてる本あので分ける
なんの本なのか
今まで絵の見方は、美大など美術に関わる人たちしか得られなかったものらしく、絵画の分析の仕方も体系化されておらず理論としても深ぼられていることが少なかったようです。
この本は、誰でも絵画を理解できる、見るのではなく観察するようになれる理論的なことが書かれた本です。
この絵の主役はどこ?
絵を理解するためには、さまざまな要素に関して理解していく必要がある。主役のことであったり、絵のバランスだったりがその要素だ。それらを一つずつ見ることで絵を理解できるという。
まずは、主役を見つけるところから始まります。
絵の顔を見つけるためには、フォーカルポイントを見つけることが重要です。主役は必ずと言っていいどフォーカルポイントが存在する場所にいるのです。
フォーカルポイントの差が仕方は、いくつかあって、
普通にみているだけでこれ主役だなと思える絵は、絵の中でど真ん中に配置されていたり、大きく配置されていたり、画面位それだけしかない場合などはすぐに主役を見つけられるのですが、やっぱり少し思考を凝らした絵画も存在しておりその時に使える探し方は大きく分けて以下2つです
コントラストが高いところを探す
リーディングラインを探す
コントラストが高いところを探すのは結構簡単で、基本的にどの絵にもあるので見分けがつきやすいのですが、絵画の中には大袈裟に「これが主役です!」と伝えていないものもあってこのときにリーディングラインを探すことでフォーカルポイントを見つけることができます。
リーディングラインとは、目線を誘導する線のことで、はっきりした線だけでなく、線を示唆するものにも同じ効果が見られます。リーディングラインの種類は、
似たものを並べて
身振り手振りで
グラデーションや筆遣いで
大きい方から小さい方への運動で
一点透視図法の消失点
があります。他にもあるかもしれませんがこの本には5つかかれていました。
で、先ほど言ったように主役が丸わかりのものと、そうでないものの2種類があると言いましたが、それを集中型と分散型という分け方をしており、
集中型は、一眼で主役が何かわかることが特徴で、そういう目的につかうといいのですが、分散型はより全体を見てほしいときに使われる手法で主役以外の周りの物も書き込まれているものをさしたり、逆にどれも書き込まないものを指したり、どれが主役なのかわからなくさせる時に使われるみたいです。
これまでの絵画の歴史には、集中と分散を行き来しているらしいので、歴史的背景と併せて絵を見るのもいいかもしれないですね。
で、分散型の話をもう少し深ぼるのですが、基本的にリーディングラインは主役に繋がるもの多いのですが、中には主役につながらないラインもあって、それが準主役と言われるものなんですね。主役とその他だったものにもう一つ役を追加することで、絵の中に関係性を持たせることでストーリーを伝えらるメリットがあります。
また、W主役を演出してる物もあって頭おかしくなりますよね。その場合フォーカルポイントが二つになるのですが、2つの関係をうまく繋がないとストーリーを伝えることができません。「アダムの創造」という絵は、神とアダムのあのふれそうで触れない手が関係をつなげストーリーを伝えています。

「アレオパゴス会議のフリュネ」という絵では、裸と着衣、人と神、など対概念を連想させることで関係を生む方法や、同じくらいの大きさ、同じ立場、似た形、と言ったようなところで関係を作る方法を使っています。
芸術家頭使いすぎやろって思うねんけど、ここら辺身につけられればグラフィックの技術力めっちゃ上がるんじゃないかなと思いました。

アレオパゴス会議のフリュネ
このようにフォーカルポイントの探し方を身につければ、どうしてココに注目したのだろうかとわかるようになってきたのではないでしょうか。僕もです。画家さんのテーマ絵の姿勢が伺えますね。
ところで、リーディングラインはフォーカルポイントの見つけ方以外にも役割があるらしく、それを次の章で書いてくれんやって。
人の目をとらえて離さないのはなぜか?
で、第二章は、リーディングラインのもう一つの役割の話やねんけど、
いままで言ってたリーディングラインの役割って、主役を示しすいがいに、もう一つの主役や準主役を指すものっていうのを言ってたんやけど、それだけでは説明がつかないリーディングラインがあって、主役も準主役も咲いてないものがあるらしいねんな。今回はそのリーディングラインはなんなんやっていう話から、それの種類・特徴まで書かれてた。
で、もう一つの役割とは、絵を見る順路・経路らしくて、画家たちは当然隅々まで絵を見て欲しいからそんな工夫があるらしいねんな。ここらへんの考え方なんかしたことなかったからマジで嬉しいい。ありがとうございます著者。
で絵を見る順路にも大きく3種類あって、周回型・ジグザグ型・放射型があるらしい。
まず周回型から話すねんけど、これは主役から出発して絵を一周して主役に戻る仕掛けの順路で、特徴はできるだけ角は避けて描かあれてるらしいです。つまり、角を見て主役を指さないリーディングラインがあればそれは毛色の可能性が高いらしくて、不自然なポーズ取ってたりするらしい。
ほんでな、なんで角を避けるのかというと、もともと画角の中では真ん中と角の引力が強くて何もなくても注意がいっちゃううらしい。確かにギブソンもそんなこと言うてたな思った。角に注意がいっちゃうとそのまま外に目線がいってしまうので避けてる足しい。
周回型の形はただ丸く一周してるのもあるねんけど、8の字型とあドーナツ型とかもあるらしい。特にドーナツ型は、真ん中が空の状態になってしまうから必然的に分散型の絵になってしまうやって。
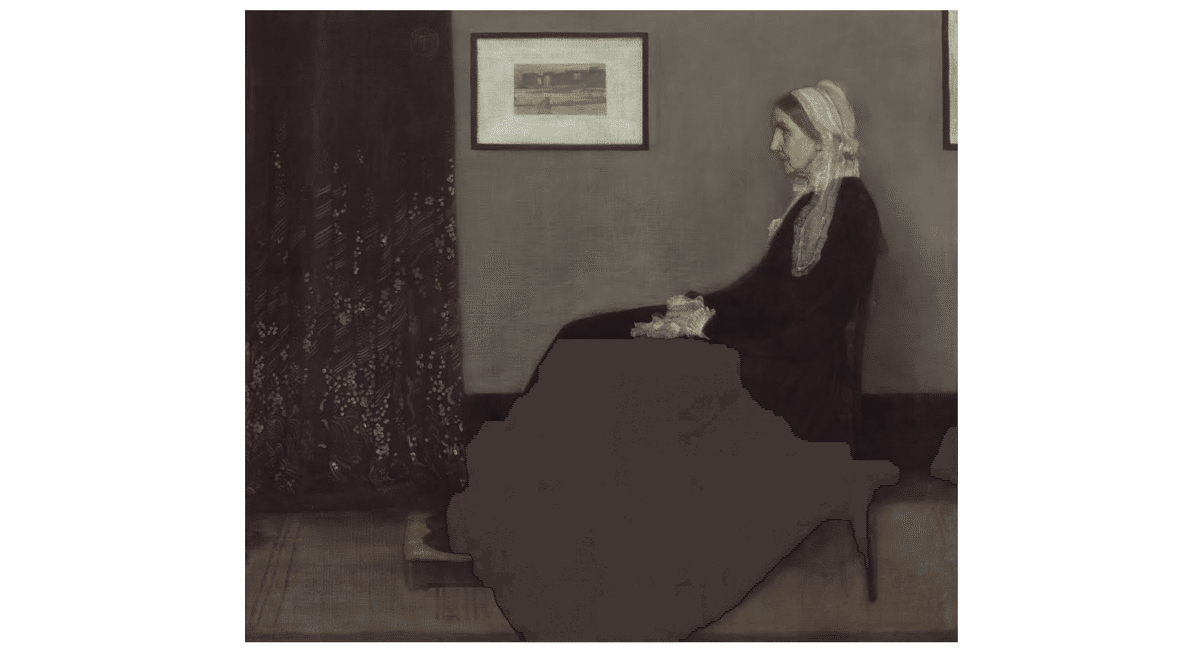

2つめのジグザグ型の経路の話をするで。
この経路は、左右または上下にジグザグさせるから、結構フォーカルポイントが複数になる傾向があって分散型の絵に向くねんて。
でこれも周回型とにて外に目がいくリスクがあるものなのでそうされないような工夫がある。でこの経路は、折り返しってんが辺に近づいてしまうことが問題でうまくストッパーを置かないとあかんらしい。で、これ上下よりも左右にジグザグさせた時につまり左右の辺の方が注意を引く傾向があるらしくて、左右ジグザグで描く方がむずいんやって。
まぁでもジグザグを置かんくていい方法もあって、さっき言ったように上下にジグザグさせる方法とS字カーブにする方法がある。
上下ジグザグはさっき書いたとおり、左右と比べて注意をあまり引かないらしいので、ストッパーを置かなくてよくて、
S字カーブは、ジグザグをS字にすることで角を避けつつ画面を蛇腹に巡れるからめっちゃ使えるんやなって思ってんけど、やっぱりデメリットもあって、丸くなる分、どうしてもエレガントでしなやかな印象・女性的になってしまうから、厳格な絵にしたい時には使わん方がええんやって。うん。



で最後に放射型は、フォーカルポイントから放射状に経路がのびてて、フォーカルポイントと周りを行ったり来たりする仕掛けがあるん。
3つくらい形があって、集中型・十字型・クラッカー型がある。もう型型うるさいねんほんまにぼけ。とかおもってますけどね。
で、この放射型ってフォーカルポイントを起点にしてるかしてないかでちょっと役割違ってきて、起点がフォーカルポイントでない場合は絵にまとまりをもたらすために使ったりもするらしい。
やから、画面にまとまり持たせながら周回型で経路を示す合体技かましてる絵とかあったりする。それぞれ合わせて使ったりできるんかな?ジグザグと円を利用するのもできるし、それぞれ合体はできそうなんか。



まぁこんな感じで絵は複雑なんですが、この考え方があれば、もっとデザインを論理的に組み立てられそうだなと思いました。
昔の人すげぇっておもってる。
以上
