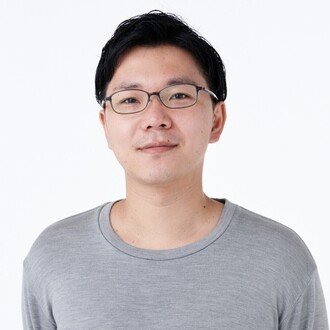FinTechの発展的解消
「FinTech」という言葉はこの5年間で使い古された。
僕自身が「金融イノベーション」と名の付く部署に移動を出したのは、FinTechという言葉が日本でバズワード化しはじめていた、ちょうど5年前。
当時はFinTechが最も大きな産業トレンドの一つとして注目されていた。
そのため日経FinTechのような重厚なレポートが発刊されたり、ありとあらゆるところで「FinTech」と名のつくイベントが世界中で開催されていた。
そういえば、2017年には、FinTechについて語ったこともある(笑)
しかし、2019年頃から、FinTechは、発展的解消のステージに来ているように感じる。
結論を言えば、FinTechではなく、テクノロジー・ドリブン・ファイナンスだということに、世の中が気づき始めている、ということだと思う。
FinTechというと、どうしても金融機関が主語に見える。
しかし、FinTechと呼ばれる領域で最先端を行く企業は、決して金融機関とは限らない。むしろテックを生業を持つ企業が多い。
上記の「分かったつもりにさせない金融トレンド」でも一部書いているが、「FinTech(と呼ばれていたものの)」の本質的な目的は、テクノロジーの力によって、より金融サービスが便利になる、そして、生活者の不安が和らいだり笑顔が増えるということだ。
であるならば、金融機関が主語になる必要はない。造語をつくるならTechFinだろう。
いやむしろ、下記のような金融における基本的な機能を、テクノロジーの力でより便利にできるのであれば主語は誰でも良い。
お金を送る(送金)
お金を払う(決済)
お金を管理する(預金・保険)
お金を繋ぐ(投資・調達)
分かりやすい事例がある。
2019年11月、SOMPOホールディングス社とピーターティール率いるテック企業Palantir社の提携が発表された。
さらに2020年6月、SOMPOホールディングスがPalantir社に540億円の出資と、「安心・安全・健康のリアルデータプラットフォーム」の立ち上げを行う新会社への共同出資(50:50)を発表した。
Palantir社は、PayPalの創業者でもあるピーター・ティール氏らが2004年に立ち上げたビッグデータ解析に特化した企業である。金融をメイン領域としない、純粋なテックカンパニーだ。
とはいえ、クライアントには金融機関は多い。
しかしその理由は「大量の顧客に関するデータを保有しており、そのデータを整理し有効活用することで多くの人がハッピーになる」からだ。
ピーターティールの有名な言葉がある。
Monopoly is the condition of every successful business.
(独占は、すべての成功するビジネスの条件である。)
孫子の兵法の「戦わなければ、負けない」という意味も含んでいるとは思うが、それ以上に、圧倒的に誰かを幸せにしているテクノロジーがあれば、そこに競争相手はいない、という考え方だ。
PayPalがそうであったように、今回も、テクノロジーの力で人類を幸せにするというチャレンジをしている。
そんな中、日本にSOMPOと組んで日本に進出した理由をこう述べている。
①同社が欧米で実績を重ねたように、日本でも同社のテクノロジーで企業や組織が成功する支援をするため。
②高齢化社会としてアメリカより先を行く日本から、学ぶため。どうこの社会を生き抜くか、テクノロジーを有効活用するのか、挑戦したい。
③日本とアメリカのパートナーとしての関係を国家レベルでも、強化していくため。
SOMPOホールディングスの社長自らの記事(有料記事)を読んでも、②の理由が最も大きいように思う。
日本は世界に先駆けて超高齢化社会に突入する。
そこにはまだ見ぬ不安や課題が数多く存在しているだろう。
そんな中、日本には国民皆保険制度があり、今後の改革次第で国民の健康情報をデータを蓄積しやすい環境にある。
ピーターティールは、今後のデータ蓄積、有効活用によって、世界に先駆けて到来する超高齢化社会でも人類が幸せに暮らせる環境づくりにチャレンジしようとしているのだろう。
話をもどす。
ここに、FinTechという言葉は必要ない。
テクノロジーの力で人類のまだ見ぬ不安を解消しようとする起業家と、それを加速させることができるデータをもった保険会社が、ビジョンを共有して解決策を探しているだけだ。
SOMPOホールディングスは保険会社なので、保険という切り口のソリューションは当然出てくるだろう。この分野に関しては、テクノロジー・ドリブン・ファイナンスだ。
いまでも100円からはじめられる超少額のLINEほけんをサービス提供しているが、こういった個人個人によりカスタマイズされた保険商品も増えていくだろう。
そして、重要なことは、決してSOMPOホールディングスとPalantir社が取り組む領域は金融に閉じないということである。
「安心・安全・健康のリアルデータプラットフォーム」が事業領域であり、同社並びにプラットフォームへ参画する企業が、そこに蓄積されたデータを活用することで、介護やヘルスケア、その他様々なソリューションが世の中に生まれてくるだろう。
金融機関主語のFinTechという言葉が発展的解消を迎えた背景には、「テクノロジーで誰かを幸せにする」という信念をもつ起業家・大企業の取り組みが具体化してきた、という素敵な理由があったりする。
余談
ブロックチェーンやAIといったテクノロジーが金融領域でより活用されることで、少額の保険や投資、調達が可能になる、つまり生活者に恩恵がある状態にするには、金融諸制度への理解が必要不可欠であり、まだまだ面白い分野でもある。「金融がテクノロジーを活用する」ではなく「テクノロジーが生活者を幸せにするために、金融面から貢献する」という、言い回しの問題なのかもしれない。
いいなと思ったら応援しよう!