
QUEEN + ADAM LAMBERT THE RHAPSODY TOURから1年
1年前、QUEENのライブを見た。もう遠い昔のようだ。Covid-19の感染拡大によって、しばらく私たちは大規模なライブを見ることはできず、ミュージシャンはライブの興業ができなくなってしまった。ライブのない世界になってしまった。そう思うと、あのQUEENのライブを目撃できたのは、なんという奇跡だろう。
その感想を文章にまとめることができないまま、1年が過ぎてしまった。
あの日、ようやく私はQUEENを観たと思った。ポール・ロジャース時代を見て入るのだけれど、ごめんあれは違うんだ…。で、まごうことなく圧倒され感動した。そして、長年の私の思いである「QUEENって、なんだ?」をまた考えることにもなった。
親子の世代衝突
映画「ボヘミアン・ラプソディ」は、映画作品だったということは前にも書いた。
が、何がどう「作品」だったのか? 個人的に、あれはQUEENの3人がフレディと自分たち4人を使って作り上げた「作品」なのだ。何を伝える作品だったのか?それは、1960年代に花開いた若者文化の中での彼らの苦悩だったのではないか。
映画を見るよりずいぶん前に、テレビでブライアン・メイがインタビューで亡くなったばかりの父について話しているのを見た。その中で、父に理解されずに悲しかったと語っていた。ブライアンは父ととても仲が良かったと思われている。おそらく一緒にギターを作ったエピソードがそう思わせてきたのだろうし、それまでにブライアンが父について悪く言っているのを聞いたことも見たこともない。しかし、普通の思春期男子として反抗期もあっただろうし、それがSwinging Londonの時代だ。若者文化(音楽、ファッション、アートなどのサブカルチャー)が大きな成功に繋がるビジネスになるという、世の中がとてつもない変化をし始めた時代。おそらく親子の衝突はいたるところで見られただろう。
「高学歴なメンバーが作り出したバンド、QUEEN【5】」に書いたように、私は親と子のジェネレーションギャップが特別に激しい時代だったと考えている。QUEENの4人の親たちはおそらく1910年から30年の間に生まれた人たちだろう。
親たちが生まれ育った時代
1910年代初頭は世界の4/5がヨーロッパ列強諸国の占領下にあり、そのヨーロッパは普仏戦争以来40年間戦争がなかった。多くの若者が戦争を知らない世代であった。1912年の4月15日、タイタニック号が沈没する。1914年の6月にサラエボ事件、7月には第一次世界大戦がはじまり、1918年に終わる。そして、スペイン風邪が大流行した。1919年にはイギリス領インドでガンジーが独立運動に加わり、8月にはアフガニスタンがイギリスから独立した。イギリス政府は、植民地に対し戦争に協力する代わりに自治権の拡大を約束し、インドは自治を獲得した。イギリスは、続々と植民地を失い始めるのだ。
1920年代はアメリカが「黄金の20年代」と呼ばれる空前の大繁栄をとげ、大量生産・大量消費の生活様式を確立し、自家用車やラジオ、洗濯機、冷蔵庫等の家電製品が普及する。アメリカがぐんぐん伸びていくいっぽうで、イギリスはどんどんしぼんでゆき、ヨーロッパではファシズムが台頭する…海外ドラマ「ダウントン・アビー」の時代だと言えば、ぴんとくる方も多いだろう。イギリスは大英帝国の栄光を失い、貧しくなっていった。手に職を付け、お金を稼ぐことが非常に重視される時代になったのだ。

QUEENのメンバー4人の親たちは、そんな時代に生まれ育った実直で勤勉な中産階級(中流とは違う)だった。30年代に経済は好転するが、第二次世界大戦でイギリスは戦勝国ではあったもののやはり貧しく、親たちはそんな中で青春時代を送った。
親の「まとも」から外れる子どもたち
子どもであるブライアン、ロジャー、ジョンたちは、アメリカの文化的な豊かさを目の当たりにし、グラマラスな消費社会へと突入していく。大衆音楽のミュージシャンはイギリスでは立派な職業とは思われていないし、ましてやロック音楽は生まれたばかりだ。それが一生食べて行ける職業だとはとても思われなかっただろう。不安定で、尊敬されるかどうかわからない。経済的にもどうなるかわからない。実直な中産階級の彼らとしては、子どもたちの進路や夢をとても容認できなかっただろう。親たちは子どもになるべく良い教育を受けさせようと努力し、子らも期待に応えるべく大学に進学した。しかし、非常に少数しか到達できない場において、新しいグラマラスな文化を体験してしまったのだ。
現在、ユーチューバを職業とすることに反対する親は少ないかもしれないが、初期の頃はうさんくさく思われていたのを覚えている人はいるだろうか。40年を遡ればタレントやアイドルを目指すのだって、「まとも」から外れる進路だった。筆者が高校生や大学生の頃、日本でも大卒のロックバンドがいくつかあったが、やはり非常に珍しく特別な存在だったものだ。70年代のイギリスは階級社会の文化が根強かった。階級の中で成功すること、あるいは移動するにしても下に降りることなど考えられない。
ブライアン・メイはインタビューの中で亡くなった父について、ロックミュージシャンになることを大変に反対していたと語った。ブライアンはとても優秀な学生だったし、将来を嘱望されていたから、一人っ子の彼がその期待を退けて突き進むのは並大抵ではなかっただろう。そして、成功することで親を安心させよう、あるいは認めてもらおうと必死になっていた事は想像に難くない。インテリというかさすが大卒だなと思うのだが、成果を出すことで理解が深まるだろうと考えたブライアンは、79年のアメリカツアーで初めて両親を招待した。飛行機はファーストクラス、一流のホテルを手配して、きらびやかなステージ、満員の観客を目の当たりにしてもらおうとしたわけだ。そして父はやっと「わかった。お前は成功したんだな」と言ってくれたと、ブライアンはぽろぽろ涙を流しながら語った。彼にとって父に認められることがどんなに重要なことだっただろうか。

(photo:Uwe Matezki, Wikipediaより)
尊敬し愛する親との分断が対立がどれほど辛いことだったのか。それはクイーンの他の3人にも言えるだろう。細かいエピソードはわからないが、ジョン・ディーコンも優秀な成績で大学卒業し、QUEENは副業だと思って大学院の進学した。「とても成功すると思えなかったからね」と語っている。ロジャー・テイラーは母に甘やかされていたエピソードが有名だが、まだ幼いうちに離婚した母は、躍起になってロジャーによい教育を受けさせようとしていた。きっと長男の彼には、大きな期待と重圧ががのしかかっていたに違いない。フレディ・マーキュリーはイギリスに来る前はザンジバルで使用人付きの屋敷で贅沢に暮らし、インドではイギリス式のパブリックスクールに通うエリートの、豊かな生活を享受していた。そこから移民としてやってきたイギリスで、貧しいマイノリティ生活になってしまう。イギリスの中産階級としてのあるべき姿をと言うプレッシャーはなかったかもしれないが、移民とはいえ大英帝国の民であること、そのためにきちんと生きること、宗教的な背景など、セクシュアリティの問題がなくともやはりプレッシャーは大きかったに違いない。
親と違う体験を持った世代の孤独
ファッションデザイナー、ヴィヴィアン・ウエストウッドは、2011年のドキュメンタリー映画「永遠の反逆児 ヴィヴィアン・ウエストウッド」の中で、こう語っている。
「私たちは親に対してNoと言える、最初の世代だった」

ヴィヴィアン・ウエストウッド
https://www.afpbb.com/articles/-/3060451?pid=16460228
1941年生まれのヴィヴィアンは、1971年に自らのブティックをオープンし、パンクバンドのSEX PISTOLSをプロデュースした。彼女のファッションがパンクを産み育て、70年代イギリスの若者文化をけん引した。
新しい時代、大きな声で(あるいは控えめに)親(旧い世代)にNoを突きつけることが許された。しかし、何もかもが親の愛と期待に答えられず、わかり合えない世代とも言える。どんなに社会的経済的あるいは歴史的に成功したとしても、埋められぬ孤独や後ろめたさを残したのではないだろうか。
映画「ボヘミアン・ラプソディ」は、親との衝突はフレディのバルサラ家だけのものとして描かれていた。もちろんゲイであることをも大きく取り上げるべきテーマだけれど、私は先述のブライアンのインタビューを強烈に覚えていたので、ブライアンが自分の経験も大いに反映させているのではないかな、と思った。もちろんバルサラ家で起きた実際のことだったかもしれないが、きっとテイラー家でもディーコン家にもあったことだろう。あの時代、新しい文化に飛び込み、作り上げていった若者たち誰にもあったことだろう。親を裏切り、捨てたと言う罪悪感を告白できたとしても寂寥感は心から去り得ない。その悲しげな思いは親たちが他界するまで語り得なかったのではないか…。ちょうどライブでのブライアンのギターソロを聴いた時、だから家に帰りたいのだろうな、今でも帰る家を求め続けているんじゃないか…と思った。
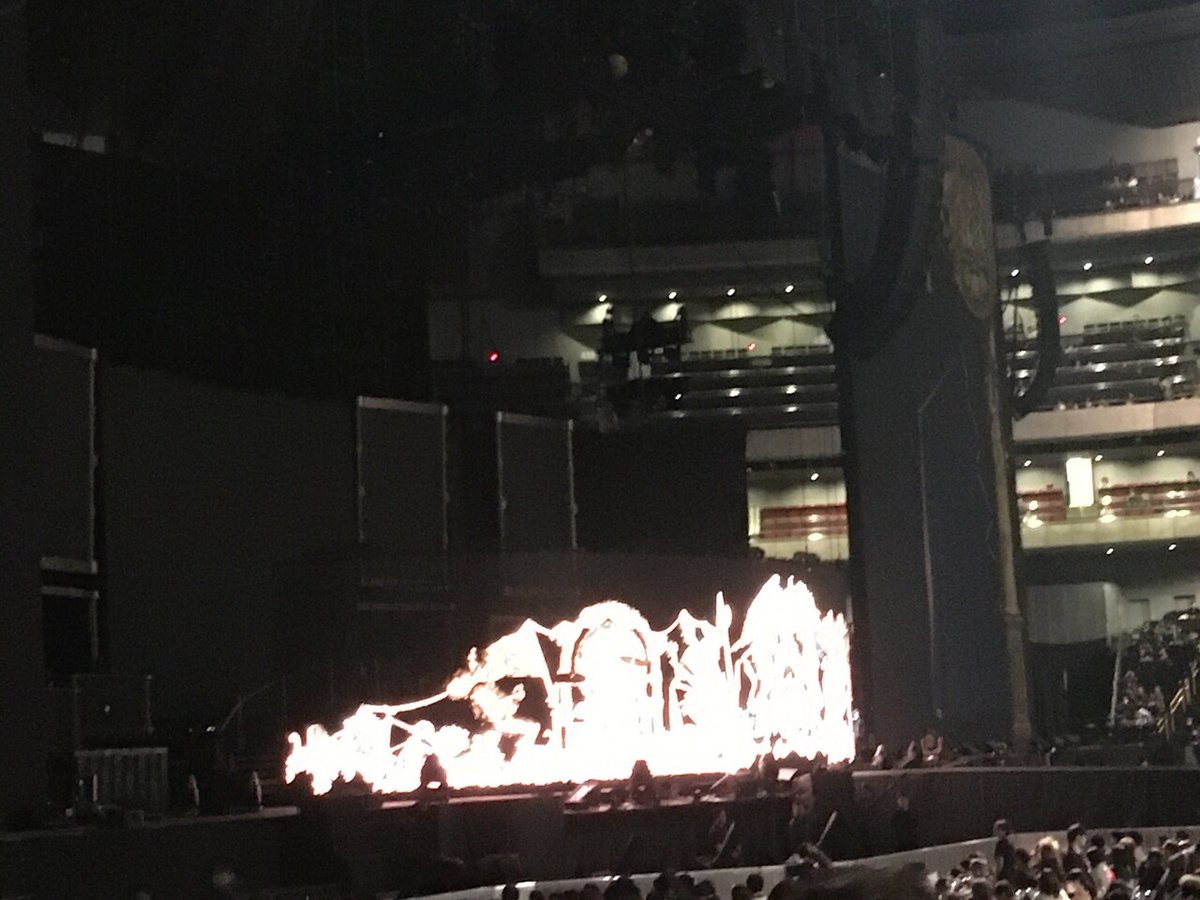
2020年1月26日さいたまスーパーアリーナ、筆者撮影
ブライアンのギターソロは、ホルストの「惑星」からドヴォルザークの「新世界」第2楽章にいたる。これは『A Night At The Opera』収録のブライアンの曲「39」で、宇宙へ旅立った男が帰ってきたら長い年月が過ぎてしまって帰る家も家族も無くなっていたという世界での描き直しなのかと思った。親のもとに帰りたい。家に帰りたい。許されたい。そんな孤独を抱きしめたまま、帰る家をずっと探し続けているのかしらとと思ったのだ。
この来日公演のテレビインタビュー(下記リンクの「news23」)で、70年代の来日後、ブライアンたちがすっかり日本に魅了されてしまったことについて父に話すと、やはり意見の相違があったことを語っていた(この時は笑顔で話していた)。彼らは日本文化をエキゾチックで素晴らしく、新しい異文化体験としてとても気に入っていたわけだが、父は第二次世界大戦の記憶から日本を好きになることなんてできない、日本人なんてと話したらしい(大島渚監督の「戦場のメリークリスマス」を見たら、戦争の記憶が生々しいイギリス人が日本人を憎む一端が垣間見えるかも)。インタビューではだいぶマイルドに話していた記憶があるが、ここでもジェネレーションギャップは大きく出る。戦争の記憶のある親との埋められない溝もあっただろう。その溝に戸惑いながらも父を否定することができない苦悩がやはり垣間見えた気がした。インタビューでは、父がだんだん理解してくれて受け入れられたのだと話している。
Bohemian Rhapsodyの歌詞
Bohemian Rhapsodyの歌詞の意味は、誰にもわからない。あの歌詞を書いたフレディが話さなかったからだ。現在では彼がゲイであることを告白すると言うストーリーだと言う理解が一般的だが、親子のジェネレーションギャップと言う分断のことだとも考えられるのではないだろうか。ブライアンもロジャーもジョンも、多くの子どもたちが、大人を殺してママ(家)に別れを告げたと考えられないだろうか。
親と子が生きる時代はどうしても20年、30年といったギャップがある。時代の出来事、経済状況、技術的背景何もかもがお互いの育った環境と違った体験をしていく。私の両親は第二次世界大戦前に生まれ、戦争を体験した。そして高度経済成長期を必死に生きてきた人たちだ。その彼らは右肩上がりの果てであるバブル時代は理解できても、その後の失われた10年や就職氷河期といったデフレ時代にに生まれ育つ世代を理解できないだろう。私ですら、親世代との大きな分断を感じている。
孤独を胸に抱きしめながら、ただひたすらに歩んできたQUEENの曲は、50年の長きにわたって2021年の現在でも世代を超えて愛されている。これは、やっぱり希有なことなんだろうと思うし、音楽がなしえる奇跡なので「QUEENって、なんだ?」は永遠の心地よい謎のままでいい。
余談
ブライアン・メイがWe Will Rock Youで「和」のTシャツを着るのは、歌詞中のOld manがget you some peace somedayにかけているのかしら、と思いました。自分がOld manになり、peaceを得たのだと。まあ「感謝」を着てることもあるから、関係ないんだろうけど(^^;)。

