
“鬼軍曹” 大坪清隆
⚠️この記事にはインターネット上には無い、埋もれた情報(新情報)が含まれています。引用・参考にする場合は私のXのDMかこの記事のコメント欄にて事前の連絡をお願い致します。
また、記事中の全ての写真は全て私の所有する雑誌・書籍からの引用です。その中には稀覯本も含まれているため、無断使用は厳禁です。
今回は猪木さんの師匠の一人でもある、大坪清隆(飛車角)さんについてまとめてみました。
大坪さんに関しては、ネット上に間違った情報も流布されています。今回、それを正すためにも、色々な参考文献から大坪さんの生涯に迫ってみました。

プロレスデビュー以前
大坪清隆(飛車角)は、1927年7月10日に鳥取県八頭郡智頭町で生まれる。
父親は材木関連の仕事をしており、清隆は10人兄弟の7番目、男4人の三男だった。
また、一部資料に東京都出身と表記されているが、それは間違い。
鳥取工業高校(当時は鳥取工業学校、鳥取第一工業学校)で柔道の二段を取得。
一部資料に都立工業高校出身と表記されているが、これも間違い。

卒業後、東芝に就職し、川崎工場に勤めながら、東芝の柔道道場で練習を積む。師範代でもあった。また、戦時中に三段に昇段。
1948年まで東芝にいたが、同年富士電子に転職。
この頃は、昼休みには東芝道場、午後4時ごろには講道館、夜8時ごろには川崎の高木道場(柔剛館)で練習を行っていた。
ちなみに、この頃にはボクシングにあこがれて、
大森の京浜拳闘クラブへ通って、プロボクサーになったりもしている。
後輩に田中昇さん(元日本フェザー級チャンピオン)がいたようだ。大坪さんはウェルター級の六回戦まで勝ち進んだことがあるらしい。
1949年、全関東実業団柔道選手権大会に出場し、優勝(『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』に神奈川県の大会で優勝との記述があるが、この大会が上記の大会かは分からない)。
しかし、現時点で1949年にこのような大会があったことを確認できていないため、他の大会を優勝した可能性がある。
また、ご家族の方からの情報より、1955年にトロフィーを持って家族と家の前で撮った写真があるようです。
このトロフィーが関係しているのか…?
1950年に牛島辰熊、木村政彦、山口利夫らの『国際柔道協会』(いわゆるプロ柔道)に参加したとされるが、真偽は不明(途中から参加したともされるがそもそも参加していない可能性がある。理由は後ほど)。
また、上記書籍に木村政彦、山口利夫らの新団体『全日本プロ柔道家協会』に大坪が参加したとの記述があるが、これも詳細は不明。
プロ柔道崩壊後は柔挙(柔道対ボクシングの興行)を一年半ほど経験した。
1952年1月には四段になる(後に五段に昇段)。
昭和の巌流島以前
大坪清隆は、1953年12月8日の大阪府立体育館での試合でプロレスデビューしたとされる。
ダイアンに15分56秒(15分16秒と記載されている資料も)フォール勝ち。翌日には同会場でヘンリー・ジョニーに5分21秒、フォール勝ち。
ちなみに、身長は172cm程度、体重81〜88kgほど(年齢により変化)だった。
1954年4月14日から5月4日まで行われた、全日本プロレス協会の『日本対駐日米軍プロ・レスリング試合』のシリーズに参加。
このシリーズには木村政彦も参加していた。
在日米兵や柔拳ボクサーと対戦していたが、中にはキラー・マイク・ユセフ(ユセフ・トルコ)もいた(4月16日 大阪府立体育館大会、4月24日 蔵前国技館大会。どちらも時間切れ引き分け)。
最終日には、立ノ海松喜に14分21秒、試合放棄で敗れる(5月4日 阪急西宮球場大会)。

同年9月25日、26日に行われた、全日本プロレス協会の『日米土対抗水上プロレス』シリーズにも参加。大阪の扇町プールで両日行われ、25日はヘンリー・ジョニーに13分3秒、試合放棄で、26日はタムエス・ゼノウラに12分35秒、体固めで勝利。
同年11月3日に岐阜市民センターで行われた、国際プロレス団の旗揚げ戦に参加。
5月10日が旗揚げ戦となっている記述があるが、これは間違い。
ジム・グラッシュと対戦し、時間切れ引き分けとなっている。
12月18日まで旗揚げシリーズは続いた。
最終日は、熊本市内の白川公園で大会が行われ、メインで大坪は木村政彦と組んで、ゼントルマン・ジム、ジム・コジンスキー組と対戦。

昭和の巌流島
1954年12月22日に、日本プロレスリングコミッショナー設立準備委員会主催の蔵前国技館大会に参戦。勘違いしている方も多いと思うが、主催は日本プロレスではない。
この大会は、かの有名な『昭和の巌流島』(正式には日本選手権大試合)が行われた大会である。
大坪清隆は、この大会で駿河海と対戦。時間切れ引き分けとなる。
後に、この試合を回想して大坪はこのように語っている。
あのときは、ぜがひでも勝たなくてはという気構えで、両方の協会の選手が闘った。ぼくも体力的なハンディなど眼中になくやった。結果は引分けだったが、あのときほど、気力が必要ということを、感じたことはない
また、この大会は柔道対相撲の構図となっていたため、木村政彦からは、『どんなことがあっても相撲出身に負けるな』と言われていたようだ。
昭和の巌流島以降〜ウェイト別日本選手権まで
その後も国際プロレス団所属だった。
1955年12月10日の大阪府立体育館大会から、翌年1月3日の神奈川体育館大会までの国際プロレス団のシリーズ(全3戦)に参加。
このシリーズでは参戦していた、ボブ・マンフリー、ジェロニモ・クアネイドらと対戦した。
また、1956年4月17日の大阪府立体育館大会から、5月4日の広島大会までのシリーズにも参加。
名古屋、岐阜、熊本など各地を転戦しながら、ラウル・ロメロやラモン・ロモ、ヤキ・ローチャたちと対戦。
4月17日の試合はラモン・ロモに2対1で敗れる。
4月20日の名古屋 金山体育館大会では、ロメロ、ローチャ組に2対1で敗れる(タッグパートナーは木村)。観客は約3000人だった。
他にも、清美川梅之ともタッグを組んでいる。
同年5月15、16日の国際スタジアム(旧メモリアル・ホール)大会でも両日試合をしている。

同年7月9日大阪府立体育会館で、国際プロレス団と大同山又道の東亜プロレスの団体対抗戦が開催される。国際プロレス団が4勝3敗で東亜プロレスを下し、対抗戦に勝利するが、木村、清美川は7月22日にメキシコ遠征に出発。
この遠征中に、大坪たち団体全メンバーは国際プロレス団を辞め、大阪に新団体 アジア・プロレスを設立する(なぜか清美川もアジア・プロレス のメンバーだった)。
このことについて、大坪は雑誌インタビューでこのように答えている。
ほくはフリーになりたかったんですよ。で、木村さんとは一番仲が良かったんですが、悪いと思ったけど、やめたんです。そして、しばらくしたら、今のアジアから引っ張られて入ったわけです
同年10月15日に行われた、『ウェイト別日本選手権』の予選に参加。
一回戦は、山口道場(旧全日本プロレス協会)の三山三四郎と対戦し、4分19秒、足鋏固め(足ばさみ極め、ボディシザース)で勝利。
二回戦は、東亜プロレスの白頭山稔と対戦し、34分15秒、負傷棄権で勝利。
この日の試合は浪花町のプロレス ・センターで非公開で行われた。

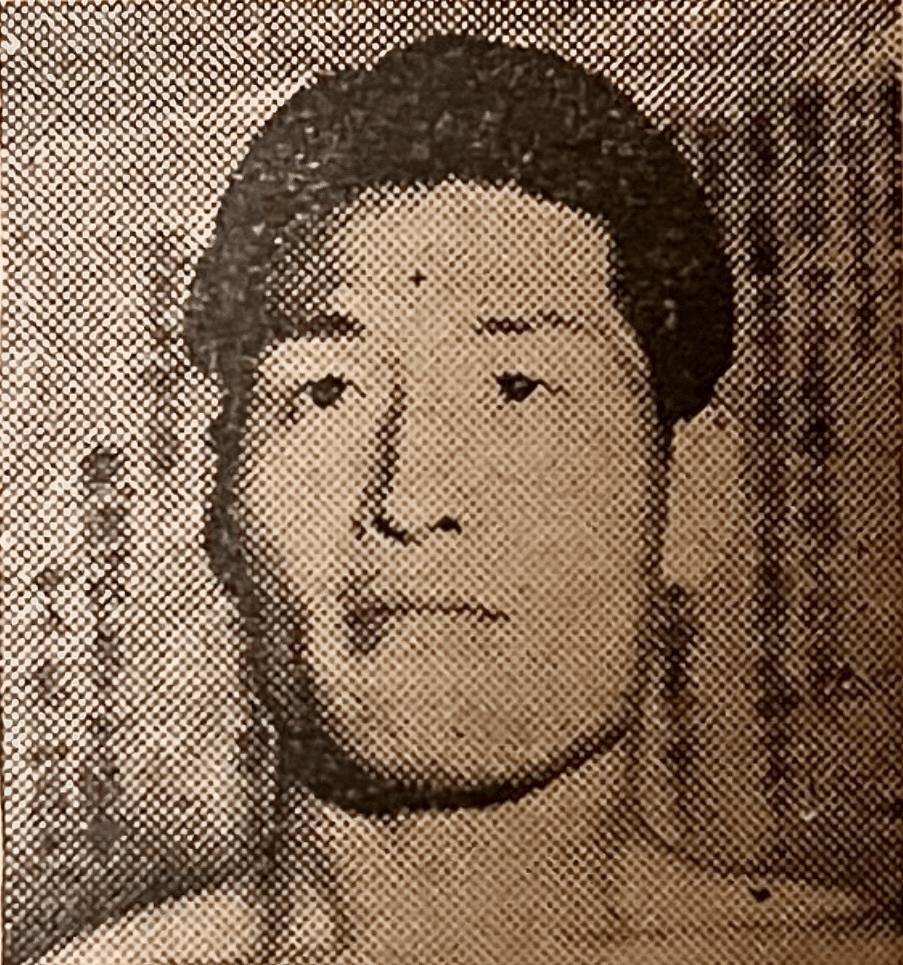
準決勝(本戦)は、10月23日夜に国際スタジアム(旧メモリアル・ホール)で行われ、日本プロレスの芳の里に17分42秒、片エビ固めで敗れる。


翌日には、同会場で2、3位決定戦が行われ、山口道場の樋口寛治(後のジョー樋口)に23分8秒、体固めで勝利し、ライト・ヘビー級2位となる。

最終的にライト・ヘビー級は、
王者 芳の里(日本プロレス)
1位 吉原功(日本プロレス)
2位 大坪清隆(アジア・プロレス)
3位 樋口寛治(山口道場)
4位 比嘉敏一(日本プロレス)
5位 金子武雄(日本プロレス)
という順位となる。

日本プロレス〜引退以後
ウェイト別日本選手権が終わった、1956年11月30日の山口道場(旧全日本プロレス協会)の大阪府立体育館大会にアジア・プロレス所属として参戦。東日出雄(当時東亜プロレス、後フリー)と対戦し、7分20秒、戦意喪失で敗れる。

1957年にアジア・プロレスが解散し、同年日本プロレスに移籍。
詳しい日時は不明。
同年1月5日の日本プロレス 大阪府立体育館大会で、芳の里の持つ、日本ライト・ヘビー級王座に挑戦。2対1で敗れる。
8月21日の日本プロレス 大阪府立体育館大会では、宮島富男に勝利。

その後は、日本プロレスの前座、中堅レスラーとして活躍。
1960年9月30日台東体育館大会で、日本ライト・ヘビー級王座決定トーナメントが行われる。
大坪さんも出場し、1回戦で竹下民夫と対戦。4分53秒、腕固めで勝利。
同日2回戦(準決勝)が行われ、ミスター珍に5分29秒、エビ固めで勝利。決勝進出を決める。
周知の事実だが、この日の試合で馬場正平(後のジャイアント馬場)と猪木完至(後のアントニオ猪木)はデビューした。
10月19日の台東体育館大会で決勝が行われ、吉原功と対戦。試合は吉原が2対1で勝利し、吉原が第2代日本ライト・ヘビー級王者となった。
同年10月22日の岐阜市民センター大会(国際プロレス団旗揚げの地)では、猪木完至(後のアントニオ猪木)と初対決。12分36秒、逆腕固めで勝利。
1961年5月14日の鹿児島県立体育館大会で、猪木完至と対戦し、初めて黒星をつけられる(11分30秒、体固めで敗れる)。

試合と並行して、馬場、猪木といった若手レスラーたちの指導もしていた。
この話は後ほどします。
1968年頃にレスラーを引退。
現役最後の試合は、1967年11月17日 後楽園ホール大会でのミスター珍戦だった(試合は大坪の勝利)。
引退後は日本プロレスのコーチとなった。
この話も詳しくは後ほど。
ちなみに、日本プロレスの役員も務めていたようだ。
1972年にプロレス界から去ると、東京渋谷に、地元鳥取の名所である鳥取砂丘から名付けた、『砂丘』という喫茶店を開店。
横浜市鶴見区に住んでおり、川崎で麻雀屋(雀荘)を経営していた。
また、時おり全日本プロレスや新日本プロレスの試合に顔を出していたという。
喫茶店の場所が青山学院大学に近かったこともあり、多くの青学生が来ており、その学生たちとも将棋を指していた。
その中に後にサザンオールスターズとして活躍する、桑田佳祐がいたのは有名な話だ。
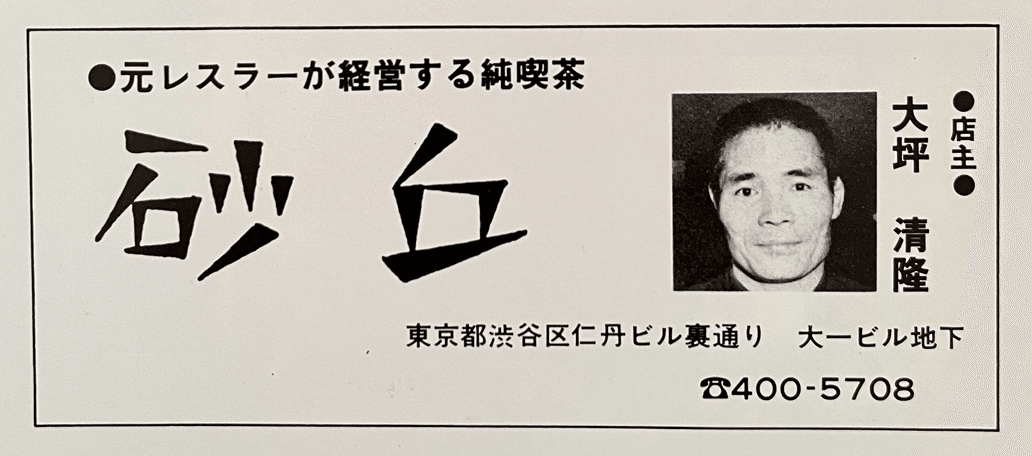
1982年7月29日、海で溺れた少女を助けようとして、助けに行くも自らが溺れてしまい、死去。
この事故については、別冊ゴング 1982年9月号に詳しく記載されている。一部引用します(名前や年齢といった個人情報は隠しています)
それは29日の出来事だ。大坪さんはこの日、近所の友人、Iさん一家ら七人で神奈川県湯河原町吉浜海岸に出かけ、午後2時40分ごろ、Iさんの長男、T君、長女・Hさんが乗っていたゴムボートが沖合約40メートルのところで転覆、高波にさらわれておぼれそうになった。
これを見た大坪さんは助けに泳ぎ出し、T君は自力で泳ぎ助かったが、Hさんを助けたあと力尽さておぼれたもの。
享年55。
また、この悲報を耳にしたかつての仲間や、プロレスの関係者は「ツボさん(愛称)らしい事故死だね。あの人の人柄、性格からいって納得する部分がある」と話していたという。
また、猪木、馬場は「骨のある人だったのに・・・」とその悲報に感無量だったようだ。
こわい人だったが、話せばわかる思いやりのある人、というのが後輩たちの大坪評で、同期の仲間たちは一本気で曲がったことが嫌いな人、骨っぽい男と評していた。

エピソード
エピソードでは大坪さんにまつわる、数々の興味深いお話を紹介します。計9つのエピソードです。
現在8つしかありませんが、残り1つの話(猪木さんたち若手の指導の話)は、また後ほど追加します。
楽しみにしておいて下さい!
①木村政彦との話
part.1
プロレス&ボクシング 1965年10月号に大坪さんのインタビュー記事が載っています。
題名は、61分3本問答⑳ 力道山・木村戦の秘話 大坪飛車角選手の巻であり、聞き手はプロレス・相撲ライターの小島貞二さんです。
ちなみに、私の今回の記事は、このプロボクの記事からもかなり引用しているので気になった方は是非に手に入れてみて下さい。

この記事を一部引用します(原文のまま)。
──木村さんとの出合いは。
「出合いはズーッとあとですが、24年に浜町国技館で、全日本(戦後第2回目)があったとき、木村さん(政彦七段)と石川さん(隆彦七段)が、優戦をやり引き分けたでしょう・・・」
──ボクも見てました。
「ボクもあの試合を見に行った。そのとき木村さんをはじめて見たんです。鬼の木村という名前は、もちろん、前からきいていた・・・」
──やったことは。
「やったことなど、当時はないですよ。講道館で醍醐さん(敏郎六段)とやり、捲き込みを喰って、肩の骨を折っちまったことがある。ボクより年が一つ上で、向こうはもう六段、こっちは四段・・・とてもじゃないがいけませんと、あのときはなかば柔道をあきらめた。木村さんってその醍醐よりひとけた強いんだから・・・」
(中略)
──木村さんの話はまだですか。
「木村さんとは、シャープ兄弟のとき(29年2月)からです。あのときはボクのところへも、酒梅さんから、こんどこういう試合があるから、よかったら出場してくれというような手紙が来たようにおぼえているから、大阪から山口さん、清美川さん、それに長ちゃん(長沢)九州から木村さんなどが、同じように招集されて、東京へ出て来たのだと思いますね。何でも凄いですよ。一回のギャラが3000円から4000円とか・・・」
(中略)
──シャープ兄弟が帰って、大阪に全日本(山口、清美川など)、九州に国際(木村など)の二つのプロレス団ができましたね。
「ええ、29年の9月か10月ですよ。九州にいる木村さんと連絡とって、六ノ海(もと立浪部屋の幕下力士)と戸田(武雄・柔道六段)と、ボクというメンバーで国際プロレス団というのをつくり、岐阜で旗あげ記念興行をやった」
(中略)
──木村・力道山、世紀の決戦は12月22日だったから、ひと月足らずでしょう。その間、木村さんは物凄いトレーニングをしたそうですが。
「凄いというのか、超人的というのか、ともかく、あのときのけい古は殺気立っていましたよ、熊本に尚武館といったかな、柔道の道場があるんですよ、そこのタタミの上で、レスリングをやるんだが、ボクと六ノ海と戸田と三人がこっち側にいて、つぎからつぎへとかかっていく。
真剣ですよ。一人が参ったというまでやり、つぎがすぐぶつかっていく。いくら頑張ってもすぐ逆を取られてしまう。休みなしに二時間半から三時間半やって、終ると熊本城まで走ってのぼりおりする。これで心臓がなんでもないんだから、本当に人間ばなれしてると思いましたねえ」
──東京では、力道山のトレーニングも、かなり熱っぽいもんでしたよ。
「そりやァそうでしょう。あのときの木村さんに、きっと、戦前のあの無数をほこったころの元気を回復してたと思いますね。一本背負いなど喰うでしょう。あのひとの投げは、ピタリと体へ吸いつくようで、逃げることなんぞ絶対にできないです。そんなことをいっちやァなんだけど、あとになって、ボクはリキさんにもけい古つけてもらったが、迫力の点では、木村さんのほうが上だと思いましたねえ・・・」
──その木村さんが、決戦で、どうして、ああもろく軍門に降ったんでしょう。
「さァ、そいつはねぇ・・・」
──さしつかえない程度の、裏話とか秘話みたいなものを、どうです。
「うん、知っていてもいえないこともあり、ほんとうに知らないこともあるねえ・・・。推理小説みたいなものとちがいますか・・・」
ここ出てくる、六ノ海はおそらく立ノ海だと思われます。
このエピソードからも大坪さんと木村さんの関係性、木村さんの強さや凄みが伝わってきますね!

part.2
木村さんと大坪さんのエピソードは他にもありますので紹介します。
木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのかの頁435から一部引用します。
巌流島決戦のとき新聞記者に「あんなふうに負ける木村先生ではない。力道山のやり方はひどい・・・」と泣いて語った大坪清隆(中略)
木村さんと大坪さんの絆を感じますね。
この文章の中に『木村先生』という言葉が登場しますが、本当に大坪さんが木村さんのことを『先生』と呼んでいたのかについては疑問が残ります。
この疑問と関連して、ネット上に、アントニオ猪木は木村政彦の孫弟子である、という情報があります。
この『木村政彦は大坪清隆の師匠』ということについて、私的には違うように感じています。
理由としては3つありまして…
1つ目は大坪さんは木村さんと呼んでいることです。先ほど引用したプロレス&ボクシングの記事を見てもらえれば分かりますが、終始大坪さんは木村さんのことをさん付けで呼んでいます。私が知る限り、大坪さんが木村さんを先生付けで呼んでいる記事は見たことがありません。
2つ目は大坪さんがプロ柔道に参加していない可能性があることです。
これも後から紹介しますが、大坪さんは木村さんのプロ柔道(国際柔道協会)に参加していない可能性が高いです。
こうなると、初めて知り合ったのは、1954年4月14日から5月4日まで行われた、全日本プロレス協会の『日本対駐日米軍プロ・レスリング試合』のシリーズということになりそうです。
最後の3つ目が最大の理由ですが、大坪さん本人が木村さんには弟子がいなかった、持たなかったと証言しています(その当時までの話だと思います。柔道の指導者時代はいたと思います)
また、この情報は有識者の方から教えて頂いた情報のため詳細は伏せますが、1959年のプロレス&ボクシングの記事に記載されてあったようです。
以上、この3つの理由から、『木村政彦は大坪清隆の師匠』ではなく、仲間 or 先輩・後輩の関係性だったのではと私は考えています。
ですけど、二人の心の中に絆や信頼が生まれていたことは確実です👍
②家族の話
大坪さんには、奥さんと子ども(長女、次女、長男)がいました。
下の写真は最初の夫人 正子さんとの一枚です。

また、家族について大坪さんはこう話しています(プロレス&ボクシング 1959年1月号より)
二人の子供と女房。ぼくはそれを養っていかなければならないし、そのためにも生活・・・レスラーとして、真剣やらなくてはならない
家族思いのいい父親ですね!
大坪さんの堅実さが伝わってきます。
正子さんとはその後離婚され、大坪さんは数年後にみつ子さんと再婚しました。
再婚した後には長男も生まれました。
ちなみに、W★INGプロモーションなどで活躍した徳田光輝さん(柔道三段、元オリンピック強化選手)は大坪さんの甥らしいです。
あと、大坪さんの地元、鳥取県智頭町に大坪姓の方がいないか調べていると、下のサイトが!
名前が載っていないので確定できませんが、おそらくご主人の名字が大坪なのだと思います。
調べてみると、大坪姓は鳥取県にまぁまぁ多く存在しているようです。
なので、ご主人が大坪さんの親戚の方かは断言できません…
③プロ柔道出身か?
先ほども述べましたが、大坪さんは牛熊、木村さんのプロ柔道(国際柔道協会)に参加していない可能性があります。
プロレス&ボクシング 1965年10月号のインタビューをまた引用します(原文のまま)。
──あなたもプロ柔道やりましたか?
「いやァ、ボクはそうじゃないです。木村さんと一緒にやったのは、そのあとです」
(中略)
──なるほど、それじやァ、プロ柔道は知らないわけだ。
「知らんですよ。見たことはありますがね」
このように大坪さんは自らのインタビューでプロ柔道への参加を否定しています。
しかし、聞き手である、小島貞二さんの著書、力道山以前の力道山たち(1983年)の頁175には大坪清隆はプロ柔道出身であると記述されています。
下の写真がその頁を撮ったものです。

聞き手である、小島さんは大坪さん本人からプロ柔道に参加していないと聞いているはずなのですが…
おそらく、年数が経っているので忘れていたのだと思います。
現在、この本をきっかけかは分かりませんが、大坪さんがプロ柔道出身であるとの情報がネット上に流れています。しかし、少なくとも、本人は否定しているので、プロ柔道出身ではないと考えた方がいいと思います。
④力道山と木村政彦への思い
1959年のプロレス&ボクシングに、大坪さんの記事がありました。
その記事の中に、力道山と木村政彦、二人への思いが書かれていました。
一部引用します。
ぼくは力さんに感謝しています。体の小さいぼくが、大きな連中にくらべて体力のないことは、自分でわかっている。だが、そのぼくを力さんは大きな連中と同じように、待遇してくれるんだからありがたいことです
木村さんとは、いまは別れ別れになってしまったが、あの人の勝負師としてのものの考え方は、他人ではわからない。ぼくは古今独歩の最強の柔道家といまでも思っている。木村さんはどんなときでも、勝っということだけしか考えていなかった。あれが本当の勝負師ですね
大坪さんは、力道山と木村政彦という二人のスーパースターと一緒に行動した、数少ないレスラーの内の一人です。
大坪さんが長らくプロレスで活躍できたのも、二人へのこんな思いがあったからなのかもしれませんね!
⑤大坪さんの強さ
上記のプロレス&ボクシングの大坪さんの記事には、大坪さんが自身の強さについても語っています。一部引用します。
ファイトじゃ負けませんよ。試合でカッとなって、セメント(この社会では、相手をさんざんに痛めつけることをこういう)してやろうと、リキむと、たいてい相手がファイトをなくすんで拍子抜けしますよ
自身のセメントの強さを語っているのは貴重ですね!
また、月刊ゴング 1969年6月号の大坪さんの記事には、下の写真のような記述がありました。

やっぱり稀代のシュートレスラーだったようです。大坪幻想が膨らみますね!
⑥将棋の話
リングネームが飛車角であることからも分かりますが、大坪さんは将棋がかなり強かったことでも知られており、アマチュア四段を取得していました。
ちなみに、飛車角は豊登と九州山が命名したようです。下の写真は将棋を指す大坪さんです。
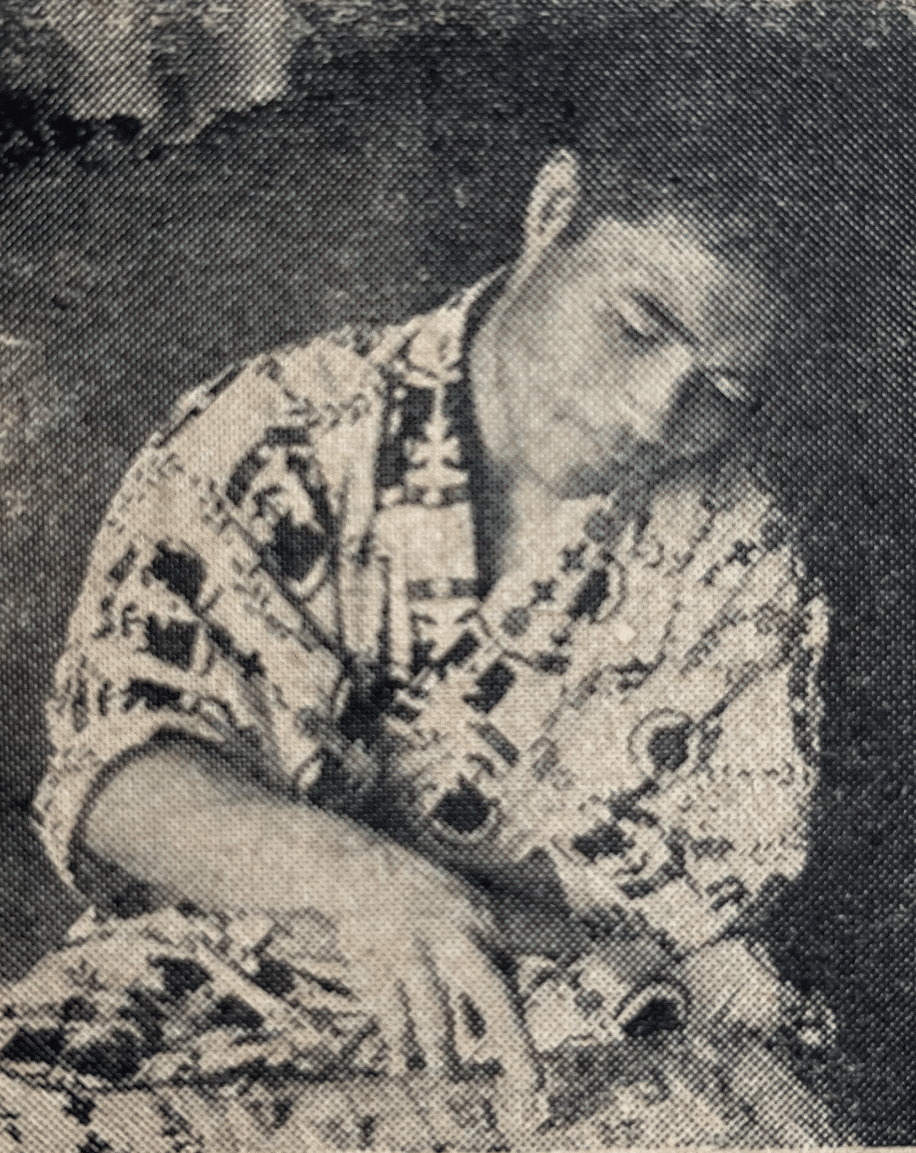
また、将棋とプロレスの関連性はあるのかと質問された大坪さんは、このように答えている。
ありますね。昔からよく“歩のない将棋は負け将棋”なんていうでしょう。ボクは自分で“オレはプロレスの歩だ”と思っている。それでいいんですよ。ボクみたいのもいないとこまるでしょう。そのかわり、歩は金になる。飛車でも王手でもつめてみせる。そう思っています…
プロレスと将棋を重ねて考えていたのは興味深いです🤔
将棋が強い大坪さんならではのエピソードですね。
⑦カール・ゴッチとの話
皆さんも知っておられるように、大坪さんはゴッチ教室の補佐役を務めていました。
ゴッチと大坪さんの関係性について、色々な記事から紹介致します。
まず、二人の出会いについて書いておきます。
二人はゴッチ(当時はクラウザー)が初来日した、1961年の第3回ワールドリーグ戦のシリーズで初めて出会っています。
この時の貴重なゴッチへのインタビュー記事がプロレス&ボクシング 1961年8月号に掲載されています。この記事の中に、大坪さんへのコメントもあったので、一部引用します(原文のまま)。
──日本に来てからも大坪選手あたりにいろいろならっていたようですが・・・
「控室が同じなので、いつもトレーニングを一緒にやる。彼はすごく柔道がうまいのでいろいろ教った。ボクもレスリンクのワザをいろいろと教えた。とにかく彼はすごいファイトの持主だね。さすがのボクも驚ろいたよ。もし彼に体力があったら米国へ一緒にいくところだが残念だよ」

この記事から6年後、日本プロレス内にゴッチ教室が開校します。
このゴッチ教室について、大坪さんのコメントが月刊ゴング 1969年6月号のインタビュー記事にありましたので、一部引用します(原文のまま)。
ちなみに、このインタビュー記事で大坪さんは「わし」という一人称を使っていますが、ご家族の方からの情報より、大坪さんの一人称は「ボク」か「オレ」だったようです🤔
雑誌側が変えたのか…?
──ゴッチ教室のサブ・トレーナーになったのはいつ?
「そんな質問には答えられんね(と、はなから撫然たる面持ち・・・やや、あって)
わしはサブでもなければ、トレーナーでもない。トレーナーてえのは調教師・・・わしはコーチだ。日本プロレス界で第1号のコーチだ。コミッションからはヘッド・コーチのライセンスを貰っちょる・・・」
──では、ゴッチは?
「彼は特別コーチさ・・・(と一息入れて)実のところは、サブ・トレーナーだってヘッド・コーチだって、わしの内容はちいーとも違わんが、きみの聞き方がちと気にさわってね(と、坪やん、にんまりと笑う)」
──ゴッチ教室が開かれたのは?
「正式には去年の8月15日」
──第二次世界大戦が終わった日だ。これあ因縁話だな。ゴッチは親日家のドイツ人。練習は?
「朝10時から午後の2時まで休みなしがっちり4時間。この10時に1秒でも遅れた者はドアを閉められて入れない」
──入れない日がつづくと。
「いくら素質があってもリングに上がって試合をやれんようになる。ミスター・ゴッチは(と、人生劇場ならぬゴッチ教室の飛車角はミスターとのたまった)
一にも練習、二にも練習、三なく四なく、五も練習・・・ちょっと変だな・・・いずれにしても猛練習で不撓不屈の根性を養う。これが目的」
──どんなトレーニングを
「腕立て伏せが、500回、脚の屈伸運動・・・」
──脚の屈伸てえと、立っていて、腰をぐっと落として、ウンチング・スタイルになり、そして立つのを繰り返えす・・・例のやつだな・・・。
「それが4000回・・・1日にだよ・・・それに縄とびが1分やって休んで2分、次が3分、そして
2分やって、最後に1分・・・計9分というやつを繰り返す。ブリッジも不動スタイルのやつが3分がワンセットで・・・」
──いやあ、わかりました。大変なノルマ。音(ネ)をあげる若手は多いでしょうな。
「音(ネ)をあげている暇も度胸もないよ。ミスター・ゴッチが先頭にたって実際にやってみせるんだから、嫌もおうもない。」
大坪さん曰く、ゴッチ教室の開設は1968年8月だったようです!
練習内容にも触れられていて、興味深い内容ばかりですね🤔
他にも、月刊ゴング 1970年12月号に大坪さんのインタビュー記事がありまして、この記事にもゴッチへのコメントが記載されていました。
一部引用します(原文のまま)。
──レスラー15年と経験豊富なことは、わかるけど、170センチ、80キロと一番の小兵で、大男をコーチしていくのはさぞ難儀なこと・・・
「一昨年、リングを降りたとき、カール・ゴッチが日本に来ていて若手をしごいていた。降りたこのわしがコッチのアシスタントに起用されて、びっくりしたね。ゴッチが新入りレスラー同様、わしをしごいた」
──リングを降りてやれやれという気持だったろうに・・・
「その通り、その通り・・・・・・15年もレスリングをやってきたこのわしに何を今さら・・・と思ったが、しごかれているうちに、だんだんとレスリングがわからなくなった。号令をかけているコッチが先に立ってがんがんやるんだからいやだ!と、いうわけにはいかん!」
大坪さんもゴッチ教室の補佐役を任命されたのは驚きだったようです。
この記事には、練習内容についても詳しく紹介されているので、次の稿で紹介致します。
⑧練習内容について
大坪さんの練習内容についても、月刊ゴング 1970年12月号の本人のインタビュー記事に記載がありました。
一部引用します(原文のまま)。
──率先垂範てえヤツだ。プロレスのトレーニングというのは、どのくらいやるの?
相撲の場合だと午前5時に起きて、まず四股(しこ)それから鉄砲、それから柔軟体操をやって若い順から土俵で申し合い、ぶつかり稽古、それから足腰の運動、受け身、四股、整理体操をやって終わるのが午前11時・・・
「相撲は部屋の人数によって違うだろうが、プロレスの場合は、みた通りだし、人数も少ないし、サボることは一切できない。がっちり3時間半から4時間、時間をかける」
──どんな要領で?
「スクワット・・・そう、まず足の屈伸運動を500回やる」
──力道山時代は足の屈伸運動を1000回、ぶっつづけにやらせていた・・・時間にして3時間から3時間半はたっぷりかかった・・・北沢幹之の新海など、第一試合が始まる前からこのスクワットをやらせられ、力道山がメイン・エベントを終えて控室に帰ってきたとき、まだ2500しかいっていなくて、力道山にひどく怒られた─と、いう話がいまでも残っている。
「スクワットをやることはいいことだが、あまりオーバーすぎると膝を悪くするし、ほかの運動とのバランスがとれない・・・このスクワットが終わると、ベンチプレス、10回ワンセットを10セット、腕立て伏せ200回、腹筋運動30回ワンセットのを3、4回、それではじめてリングに上がってフリッジ3分を5回以上、それから格闘競技・・・実戦用の格闘競技をね」
── 一歩誤まれば大ケガを招くというような厳しいトレーニングだそうね。
「鍛えぬいた腕、足が極められて、どこまで耐えうるかという耐久訓練などは、レスラーがおのおの自信をつける意味で大事なこと・・・これとアマチュア・レスリングの合法的攻めと、スピード養成・・・どこからでもこいという一丁前のレスラーをつくるのには、今までは10年はかかった。それを1年でも2年でも短縮して仕上げるの
が、わが輩の勤め・・・」
猪木さんたちが習った柔道の技術こそが、大坪さんの言う、『実戦用の格闘競技』だと思われます。どんな練習をしていたのか、想像が膨らみますね!
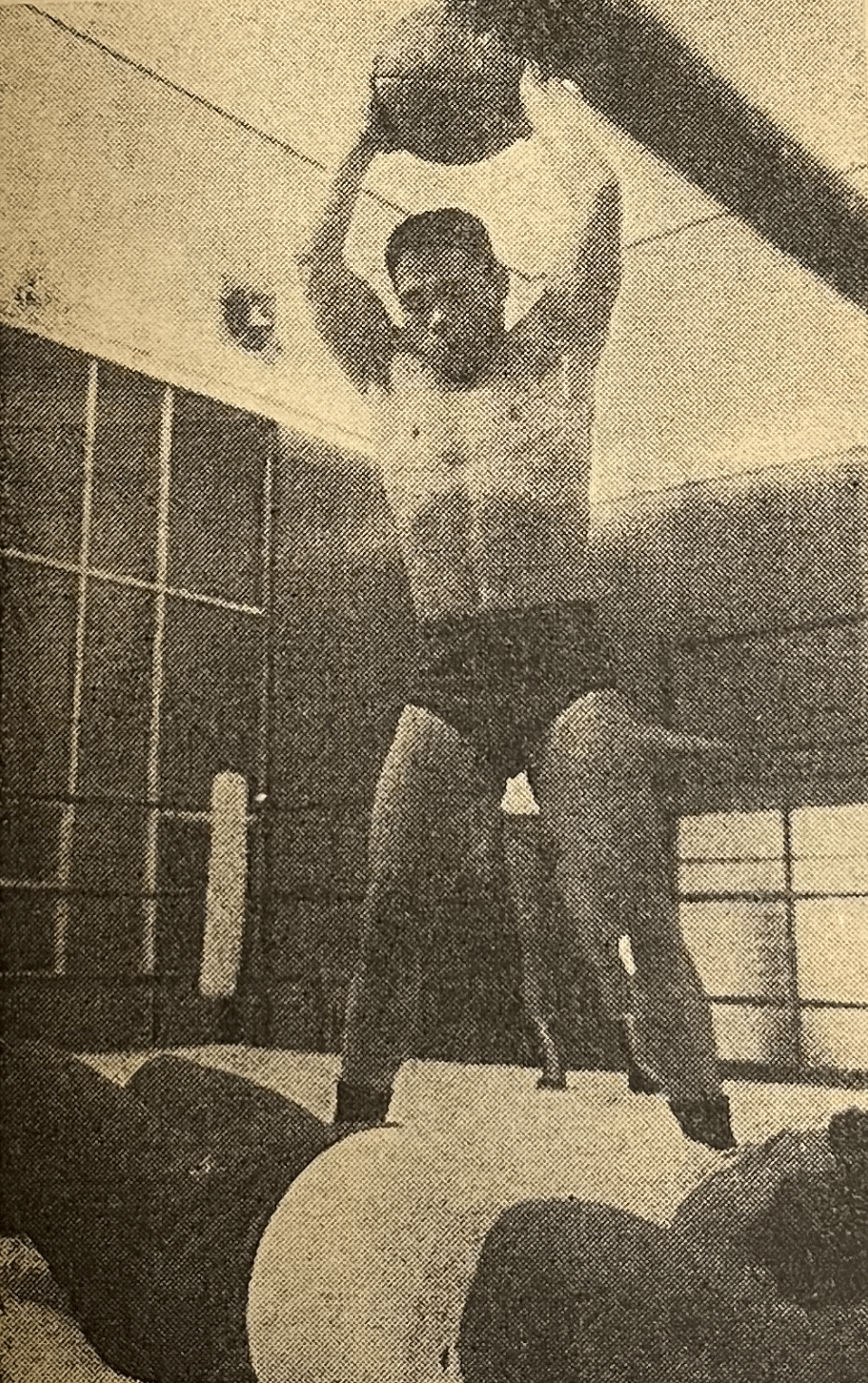
⑨ご家族の方からの情報
この記事のコメント欄でご家族の方が大坪さんについての情報を教えて下さいました。
ありがとうございます!
その情報は既にこの記事に追加しているので、気になった方は見てみて下さい。
以上が、大坪さんの数々の興味深いエピソードです。
多くの方が初めて知った内容ばかりだと思います。また、猪木さんや北沢さんたち若手を指導していたときのエピソードもありますが、字数が多いので、この記事に後ほど追記するか、また別の記事にするかと思います。
最後に
どうでしたか?
かなり詳しく大坪清隆(飛車角)さんについてまとめてみました。
そのため、字数は13000字を超えています笑。
大坪さんのエピソードに関してはもう少しあるので、少しずつ追加していく予定です(ミスター珍さんの記事を先につくる可能性が高いため時期は未定)。
今回の記事を読んで、少しでも大坪さんのことを知ってもらい、興味が出て下されば幸いです。
また、この記事に載せた内容以外にも大坪さんについて知っておられる方がいましたら、この記事のコメント欄か私のX(旧Twitter)のDMにてメッセージをお願い致します。
長くなりましたが、ここまで読んで下さりありがとうございました。
では、また次の記事で。

参考文献(書籍・サイト)
書籍
・プロレス&ボクシング
・月刊ファイト
・月刊ゴング
・別冊ゴング
・木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか
・プロレス オール強豪名鑑 日本編
・日本プロレス風雲録
・力道山以前の力道山たち
・1954 史論―日出ずる国のプロレス
・最強の系譜 プロレス史 百花繚乱
・永久保存版 アントニオ猪木全試合 パーフェクトデータブック
・Gスピリッツ vol.56
・日本プロレス70年史 昭和編
・日本プロレス全史
・WRESTLING of JAPAN No.1
サイト
・ミック博士の昭和プロレス研究室
・昭和プロレス激闘史
・BIGLOBE
・週刊ファイト
・レスリングデータ
・プロレス.com
