
2021年によく聞いた音楽
25. Kraus「View No Country」

サウンドの軸がリズム隊寄りに設定されている骨太なサウンドは、かつてのMy Vitriolを彷彿とさせる。DIIV『Deceiver』をよりシューゲイズ方面に寄せたような印象も受ける(歌のメロディにもかなり近いエッセンス)。ベースの音が締まって聞こえるシューゲイザーは良い。上方で鳴っているノイズの質感もかなり良く、あらゆるシューゲイザー好きの琴線に触れるであろう隙のない一枚。
24. ミツメ「Ⅵ」

前作から一転したバンドサウンドへの回帰によって、よりミニマルでストイックな響きを獲得している不思議な手触りの作品。今作はリモートで制作され、アレンジにかなり時間がかけられたとのこと。前作に引き続き、川辺素の詩感覚は感情を安易に断定させない余白を保っている。楽曲タイトルもどこか無機質で不穏な物が多い。最終曲「トニック・ラブ」以外はシンセ等の入らないバンド四人のアンサンブル。2本のギターが絡み合うインディロック的な快楽が獲得できる。
23. Kings of Convinience「Peace Or Love」

2021年になって「Kings of Convinienceというどえらい素敵なデュオがいまして…」という話をする必要があるのか、というところから葛藤してしまうが、このユニットは完成度の高い音源を出すことが「もはや自明の出来事」であるかのように扱われすぎている。メディアの年間ベストに載るかどうかは知ったこっちゃない、けれども、自分の家のレコード棚にはこの作品があって、休日の朝に「なんか今日も良い1日になればいいな」と思いながらこのレコードを流す、そういう真の意味で生活に根差した音楽が、本当の年間ベストなんだと私は思います(なんの話?)。
22. James Blake「Friends That Break Your Heart」

このアルバムがリリースされた当初「James Blakeも普通のSSWになっちゃった」みたいな感想をチラホラ見た(それ以上にジャケットに対する拒否反応が目に入ったが…)。この感想が出てくること自体が、逆説的に彼の偉大さを物語っていると感じた。冷静に聴いたら変な音ばっかりのこのアルバムが普通に聴こえるのは、「この10年間でアリじゃなかったことをJames Blakeがアリにしてきた」からであって、決して彼が安全地帯に回帰したからじゃないのでは?今までの挑戦や野心がかなり高度なレベルで結実している、集大成的なアルバムなのではないかと思う。『Before』あたりからシンガーとしてのアプローチが多彩になり、単純に良いメロディが乗るようになっているのも死角無しという感じがする。
21. 岡田拓郎「Guitar Solos」

森は生きている解散以降、様々な場で活躍している岡田拓郎によるギターインプロヴィゼーション集。使用された機材はTURNでの岡村詩野さんの記事によると「マイク2本、アコースティック・ギター、12弦アコースティック・ギターに加え、鉛筆、菜箸、木片」とのこと。冒頭の琴のような旋律を皮切りに、独創的な音色の連続に驚かされる。ギターという楽器に対する固定観念を覆される、鮮烈な体験をもたらす作品。音楽とは「作品」以前に「行為」なのだということを思わされる。
20. Lucy Dacus「Home Video」
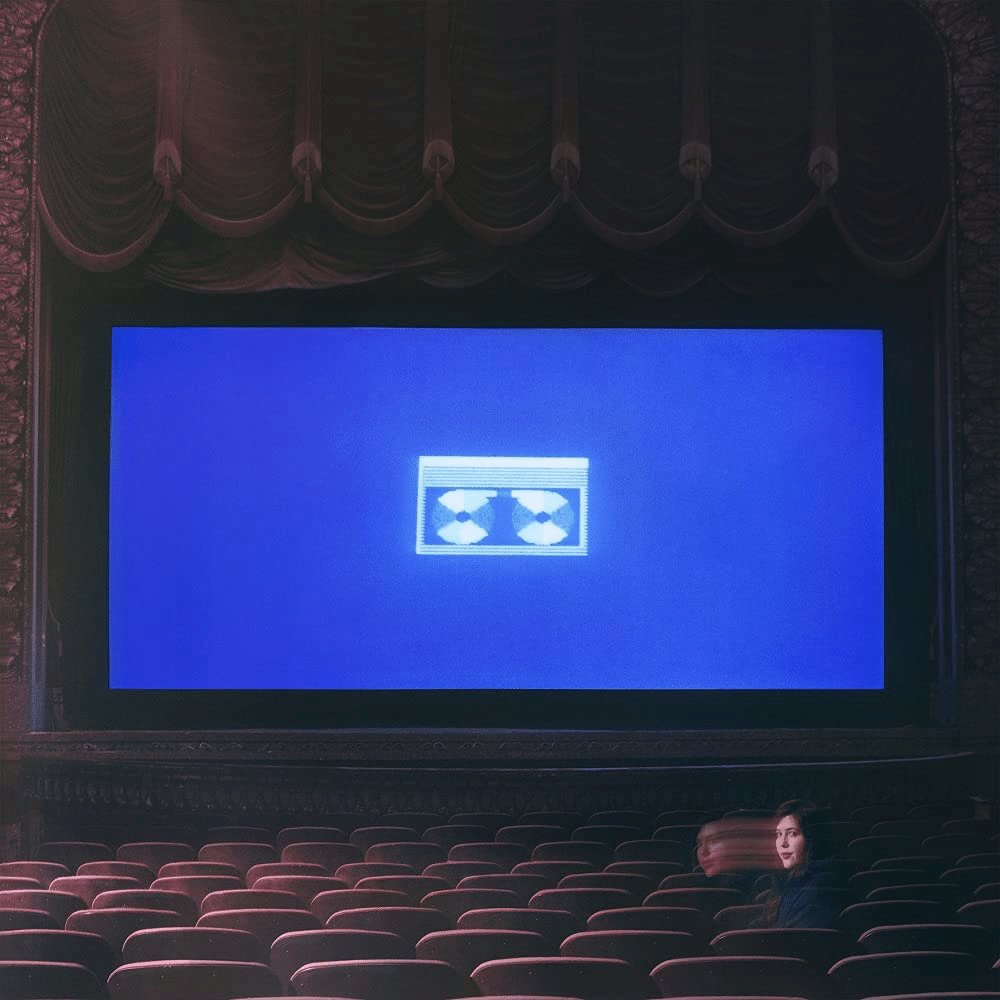
Boygeniusの一角、Lucy Dacusの2ndソロ作。ストリングス等の味付けを加えつつもインディロックの一番美味しいところは活かしたままの音像や、優れたVo.のメロディラインで今作は一気に飛躍を遂げた。影響源に『フェリーニのアマルコルド』が挙げられているように、本作は自身の記憶を辿るような楽曲が並ぶ。本人の体験に根ざしたユニークな歌詞もさることながら、歌メロの良さが際立つ。特に1曲目のHot & Heavyの3分を迎えるあたりの歌メロ、凄い良くない?なんつうかここまで踏み込んでいって霧が晴れるような感覚をもたらすインディロックって珍しい。
19. Turnstile「GLOW ON」

ハードコアバンド然としない佇まいと、ジャンルの常識に囚われない発想(普通のハードコアバンドはBlood Orangeを客演に呼ばない)が、新鮮な面白さとなって一枚に纏まった名盤。ポップなジャケットとルックスでバンドのイメージを親しみやすいものに統一している反面、ハードコアの音響として一番美味しい部分は全く疎かにしていないところに好感を覚える。ハードコアとして聴くとかなり不思議な感覚だが、シーンに閉じこもらずにマスに対して訴えかける意志をVo.の音処理等から強く感じる。とにかくライブが楽しそう。
18. Fuubutsushi「Natsukashii」

アンビエント作家M Sage.率いるカルテットFuubutsushiによるジャズ作品。ジャズ作品とはいえど、全体の音のトーンはポストロック然としており、どこかアメフトに通じるようなノスタルジックな雰囲気が貫かれている(そういえば表題も「なつかしい」だ。)Fuubutsushiとしては4枚目のアルバムで、今作含めて三作が2021年リリース。その全てがどこか温かみと懐かしさを感じさせる親密さに溢れた音楽。M sageはアンビエントでも今年何作か出してるけどその全てが好み。
17. Black Midi「Cavalcade」
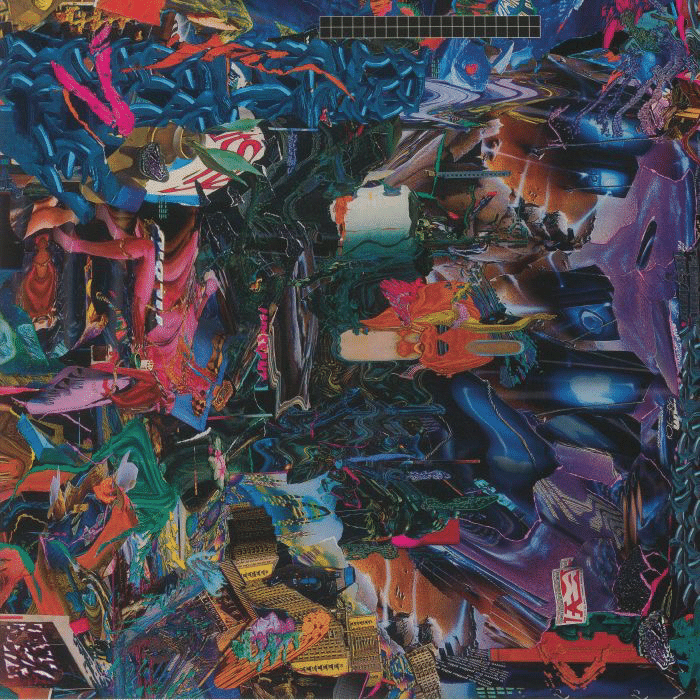
Black Midiの2ndは、セッションを経て楽曲が作られたことがうかがえる前作のアプローチとは変わって、より楽曲が構造的/理性的に制作された印象を受ける。「理性的に作られた楽曲の方が混沌を感じさせる」ということが、結果的にはこのバンドの底知れなさを証明する形となった。確か「John L」が先行トラックで公開されていたと思うが、日本のリスナーの反応が「これはザゼンでは?」「ザゼンだよな…?」みたいな感じなのも良かった。来日ツアーまだ待ってます。絶対来てくれ。
16. Julian Lage「Squint」

ジュリアン・レイジの名門ブルー・ノートからの第一作。ジャズ・ギタリストとしての名声を確立している彼が、ブルース/カントリー色の強い作品をこのタイミングでリリースすることが非常に興味深い。近年のビル・フリゼール作品と非常に近い肌触りを感じる本作では、音作りがかなりオーセンティックな分、彼のギタートーンの変幻自在さが堪能できる。生でジュリアン・レイジがギター弾いてるの観て、自然と泣いた時のことを思い出す。0と1の間に無数の段階を感じさせるギタープレイの解像度の高さ、トリオ編成ならではのバンドの呼吸の変化が楽しめる一枚。
15. カネコアヤノ「よすが」

Not Wonkとの対バンでの殺気あふれる演奏を見て、カネコアヤノの音源に対する印象もガラリと変わった。曖昧な日々に悩むものが、その悩みを振り切らんとして前向きな言葉を絞り出していると思った。『よすが』には移り変わっていく時代に正対しつつ、どのような時代にあっても変わらないものを希求する人間の言葉が並ぶ。優れたメロディに乗って、切実な言葉が歌われることの素晴らしさは失われない、そう言い切ってしまいたくなるような名盤。普遍的な良さがありすぎて、あまり年間ベストに入ってこない印象。弾き語り盤「よすが ひとりでに」も超良い。
14. Parannoul「To See the Next Part of The Dream」

リリィシュシュサンプリングからの、スネア連打からの、中低域ギター轟音。開始15秒で”ある特定の文脈”を辿ってきた人々の心臓を的確に射抜いたこのアルバムは、Rate Your Musicをきっかけに世界中で高い評価を受けている。「ディストーションとドラムのクラッシュが重なった時、めっちゃ音が潰れてもうてるよね」とか、色々音響的な弱さを感じる部分があるものの、その弱さこそがこのアルバムの圧倒的な魅力を形作っているということが何よりも素晴らしい。自我の肥大したセカイ系的なイメージとシューゲイザーの轟音ってこんなに相性良いんだという、灯台下暗し的な驚き。bandcampで公開されている、本アルバムに寄せられた文章もエモくて良い。
13. Black Country, New Road「For The First Time」

サウスロンドンから現れたBC,NRは、ポストパンクの美学と詩情の継承者足り得るのか。本人たちが、そんな問はどこ吹く風で好きなように音楽しているだけの佇まいが好きすぎる。一聴して覚えられる歌メロではないものの、どこか耳触りが良い良メロを量産している気もする。バンドとしてのまとまりや、ジャンルといった形式といった固定観念から逸脱し続けるという意味で、彼らは真のポストパンクバンドだと感じる。「人を食ったような態度をとってる暇があるほど、人に興味はありません」という感じのアティチュードがSonic Youthを彷彿とさせる。このままずっと生意気でかっこいい佇まいでいておくれ。
12. Clairo「Sling」

宅録系SSWの2nd。ベッドルーム・ポップの代表格として名を馳せた前作リリース以降、彼女はZ世代のアイコンとして人々に祭り上げられた。『Sling』は、ツアーによって摩耗する騒乱の日々から距離を取り、自身の内面と向き合うことを志向した作品である。近年さらにその傾向が加速した音楽産業の「使い捨て」によって、自身の精神が蝕まれる様子、その最中で自分にとって本当に大切なことを問い直す様などが、静かな言葉で綴られていく。本作の音楽性がフォークに接近したということが、安易な回帰や悲壮感の前景化に繋がらず、Vo.の多重録音やユニークな各楽器の音配置によって音楽制作の享楽を感じさせている点も、この作品の味わいをより豊かなものにしている。
11. Buck meek「Two Saviors」

Big Thiefのギタリストによるソロ作品。コロナの影響によるワールドツアー中断後、各メンバーの精力的なソロワークが目立つ。Big Thiefの音楽性において親密さの部分を担っているのは彼なのであろう、ということを顕著に示す良曲が続く。8トラックのレコーダー、7日間というレコーディング日数、レコーディング・テイクをメンバーには最終日まで聞かせないことなど、バンドの「全注意力をもった反応を引き出すこと」を目的として課されている多くの制約が、穏やかな曲調の中にメンバー同士の音楽上での会話を感じさせる。
10. 細野晴臣「あめりか / Hosono Haruomi Live in US 2019」

2019年6月に行ったアメリカ公演の模様を音源化した、ソロキャリア初のライブアルバム。これまでのスタジオ録音作品と同様に、まずはその驚異的な音の良さに驚かされる。しかしなによりも、細野晴臣という存在が海外でも熱狂的に受け入れられている、その事実をこのライブ盤はビビッドに伝えてくれる。海外における細野受容は(近年の環境音楽の再評価文脈を含んだ)オリエンタリズムと切り離せない様相を呈していると予感していたため、クラシカルなバンド編成を携えた細野晴臣がストレートに会場を湧かせている様子に、共感と喜びを感じた。というか、海外だとスタンディングで細野晴臣のライブ見られるのか、それはズルイ!
09. Little Simz「Sometimes I Might Be Introvert」

「個人的なことは政治的なことである」という言葉を引用するまでもなく、ラッパーとしてのオルターエゴとSIMBIとの間の格闘、家族への複雑な感情を吐露したLittle Simzの新作は、レイシズムの加速した現代への訴求力に富んだ作品である。サウンドや展開が多岐にわたるバラエティに富んだ作品の中でも、特に彼女と近しいルーツを持つobongjayarをゲストに迎えた「Point and Kill」、続いてそのままなだれ込む「Fear No Man」は白眉。彼女が自身に流れるアフリカ大陸のルーツを見事に消化し、自身のラップに取り込んでいる様に感動する。
08. NOT WONK「dimen」

ストレートなパンクナンバーが並ぶ1stから、このバンドの歩む道筋をいかにして想像できただろうか?前作Down The Valleyから意識的に形成されたサウンドの余白に、ソロワーク等を通じて表現力を増した加藤の歌唱が響く。その音楽性を何かのジャンルや何かの比喩に当てはめて安易に形容することは躊躇われる。dimenのアートワークに対して、加藤修平は「ありのままや等身大という言葉はどうも安っぽくて嫌いだけれど、ないまぜになったものをないまぜのまま形にしたかった。」との言葉を寄せている。このバンドのこういう姿勢から、多大な影響を受けている。
07. 君島大空「袖の汀」

SSW君島大空がリリースしたEP。全編に亘ってドラムレスで、君島の囁くような歌声とクラシックギターが際立つようなサウンドデザインになっている。このアルバムの魅力は、本人の感情と主張を可能な限り削ぎ落とした今にもほどけそうな歌声と、手数の多いテクニカルなギターが完全に調和し、あくまで音楽全体が一つの芸術として機能している点にある。このような音楽性で、これだけの音数のギターを弾いて、それが一切浮ついて響かない。弾き語りの形式をとるアルバムは数あれど、ここまで高いレベルでの歌とギターの両立は今までなかったのではないかと思わせる名作。
06. LI YILEI「之 / OF」

ロンドンを拠点に活動するアーティスト、LI YILEIがコロナによる影響を受け中国に帰国した際に制作されたアンビエント。アタックのない持続音をいくつも重ねてピークをもってくるアンビエントのクリシェが用いられず、ただただ縁側に座って庭を眺めているような錯覚を生じさせる空間的な音像。音を流れや展開の連続として捉えるというよりも、全体を空間として捉え、音をどこに配置するかということに意識が向けられているという意味で、どこか箱庭療法的なアプローチを思わせる。宋王朝の芸術にインスピレーションを受けたという本作は、失われた文化のエッセンスを汲み取る、という意味では冥丁の諸作品に共通する志向を感じさせるが、特定の時代を想起させない「環境音楽」の系譜にも連なる傑作に思える。
05. Japanese Breakfast「Jubilee」

今年出たアルバムで一番ジャケット好きかも。母に捧げた「Psychopomp」からSFをテーマにした2ndを経て、「時間の経過と共に甘い干し柿に変化していく」柿の実を今作のジャケットに選んでいるらしい。Wild Nothingのジャック・テイタムやらAlex Gが制作に関わっている。Wilcoのジェフがこのアルバム収録の「Kokomo, In」をカバーしている動画を見て一気にハマった。圧倒的にポップだがどこか引っ掛かりがある楽曲群は、全曲シングルカットできるのではというクオリティ。色々インタビューとか読んでいると、大学でウォン・カーウァイ研究してたり、今敏作品から曲名取ったり、Mount Eerieのタトゥー入れてたり、人柄にすごい興味湧いてくる。亡くなったお母さんとの想い出を綴った著書「Crying In H Mart」がアメリカでベストセラーになっているそうで、そちらも早く読みたい。
04. Cleo Sol「Mother」

コロナによって、人類は社会的距離を取ることを(半ば自発的に、半ば強制的に)余儀なくされた。今や人々はインターネットという空間を媒介して、物理的な距離を保ったままコミニケーションを取る。そこは自分にとって用がある人がポップアップしては消えていく不自然な空間である。Cleo Sol『Mother』は、そのような無機質な社会の中であっても、変わらぬ愛情があることを、過度な音響的装飾を廃して率直に歌い上げた作品である。Cleo Solが母親となった葛藤、子に対する愛情を、ストレートな言葉で歌うこの作品は、用もないのに一緒にいる/一緒にいなければならないという人間関係のもどかしさとその先にあるかけがえなさを思い出させる。
03. Floating Points Pharaoah Sanders & The London Symphoney Orchestra「Promises」

“若き才能“と“生ける伝説“の邂逅によって、強烈な化学反応が起きた名演。ele-kingのレビュー内で、野田努さんがこのアルバムを評した言葉が、まさに我意を得たりという感じなので引用。
じっくり聴くこと、ただ耳を傾けること、あたかも禅の教えのように、それによって何かが得られるとか、気持ち良くなれるとか、いっさいの見返りと考えずにただ聴きたいから聴くこと。そして、ただ聴きたいから聴くことがどれほど素晴らしいことかを『プロミセス』は教えてくれる。
このアルバムを聴いている間は、費用対効果や生産性、効率といった単語を忘れられる。遠くに導かれるような瞑想的な音楽である一方で、呼吸やサックスのキイが鳴る微かな音、呼吸音などが、自分の物凄く近くでなっていることが、これ以上なく温かく感じられる名盤である。
02. Grouper「Shade」

本作『Shade』でのLiz Harrisの歌声は、ギターの運指によって発生するノイズによってすらも消されてしまいそうなほど静かに響く。15年間の間に構想された楽曲集とのことだが、アルバムを通して不思議な統一感は保たれている。部屋でこのレコードを回す時、何か物音を立てると曲が壊れてしまう気がして、自然と動かずにそっとしてしまう。「聴く」や「耳を澄ませる」といった身体/精神的なレベルではなく、空間ごとその世界に引き寄せてしまうような孤高の音が鳴っている。
01. 折坂悠太「心理」

前作『平成』から更なる深化を遂げて、今や深い深い海の底に折坂悠太はいる。「光が揺れてる 例えを拒んでる」という言葉で表明されているように比喩で消化できない得体のしれなさを、この作品は孕んでいる。一聴してすぐにフェイバリットの作品となった『平成』と異なり、この作品からは未知の世界に触れる怖さを感じる。この感覚がすごい久しぶりで、怖いと同時にすごく興奮したし、嬉しくもなった。なんでもかんでも分かったふりができてしまうこの時代で、分からない状態でい続けられることの幸せを思う。音楽を通して、分かり合えるはずのない人間、その心理と向かい合っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
