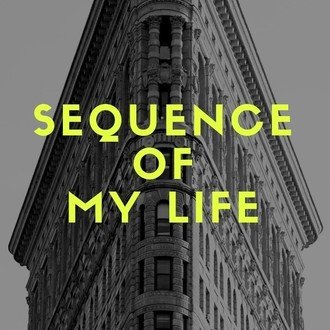セイント・ベリー・ツリー
レベッカ・ベルはオーブンに頭を突っ込んで死んでいた。オーブンからだらん、とぶら下がった足が左右に揺れている。何故こんなことになったのか、僕には良く分からない。狂ったと言えば話はそれまでだけど、じゃあ何が狂わせたかという話になる。それにイニスの目論見はこうなることじゃなかったはずだ。しかし、彼がいない今それを確かめる術は無い。
イニス・ノストは本当に奇妙な奴だった。背は小さくずんぐりとしていて洞窟のような目玉が特徴的だ。身体中毛むくじゃらで、皆から「コアラ」と呼ばれていた。僕が彼を心底おかしい奴だ、と思うようになったのは、そう、この前の電話がきっかけだった。その日は丁度レベッカ・ベルがこの町にやってきた日で、周囲の人々は彼女のことばかり話していた。こんな田舎町に移り住むひとなんて年に一人いればいい方だし、なにより彼女はとても魅力的だったのだ。見るものをはっとさせるような赤毛、意志の強そうな瞳、自信に満ちた動作、そしてそれらと相まって放たれている甘酸っぱい雰囲気。友達はまだ見てもいないのに彼女にすっかり惚れてしまっていた。どうやら僕の学校に来るらしいので、歓迎パーティをすることになり、一応僕も誘われたのだが丁重に断った。
家に帰り宿題を片付けていると電話が鳴った。リン、リン、リンの三回目で受話器を取る。
「もしもし」すると向こうからねちっこい、首筋がくすぐったくなるような声が聞こえてきた。
「テリー、テリーかい」
「君は、ええと」思い出すのに時間がかかった。確かにイニスはおかしな奴として認識されていたけど、自分から何か仕掛けてくるような奴ではない。基本的におとなしい性格なのだ。
「イニスだよ。イニス・ノスト」と若干間を空けて、「君はテリーなのかい」
「そうだよ」僕は正直早いところこの会話を終わらせたかった。どうもイニスの喋り方は苦手だ。
「ああ、それは良かった。電話をするなんて久しぶりでね。間違えていたらどうしようかと思った。」全く気にしていないかのように言った。
「用件があるなら早くしろよ。母さんが代われって言ってるんだ」
「おお、それはすまないね」
とイニスは大げさに謝った。
「率直に言うとだね相棒」たっぷりと楽しむかのように間を空け「君の夢を売って欲しい」と言った。
「夢だって?」
「そう、君の枕にこびりついているとびきり汚いやつを頼むよ」
彼は喉の奥で笑った後、黙り込んだ。僕の反応でも楽しんでいるのだろうか。だとしたらひどく腹の立つ奴だ。僕は指でジーンズを叩きながらそう思った。僕はジーンズが好きなんだ。ワイルドで、タフだ。
「いくらだい」
「そうだな、これでどうだろう」
彼が言った金額に思わず目を丸くした。
「だめかな。こちらとしては最大限の申し出だったんだけど」
どうやら僕の沈黙を否定的に受け取ったみたいで、イニスの声色は若干の不機嫌味を帯びていた。
「いや、それでいいよ。十分だ」
「そうこなくちゃ」
指をパチンと鳴らす音が聞こえる。
「だけどコアラ」
「なんだい」
さっきまで腿を叩いていた僕の手は汗ばんで、手の平を服にこすりつけてどうにかその気持ち悪さを拭おうとしていた。
「受け取りはどうするんだい」
「ああそんなことか」どうでも良さそうな調子で答えた。「そうだな、僕の家まで来てくれ」
「君の家?」
「そう、町外れのワザリング通りにあるから。来ればすぐに分かるよ」
ワザリング通りなんて、道はでこぼこしていて、湿った草原と生暖かい風しか無い所だ。夜になると野犬の唸り声や、得体の知れない何かが草を掻き分ける音がする。子供の頃、何か悪さをする度に親が僕を小突いて「ワザリング通りに放り出すよ!」と脅したものだ。そういうものを一番怖がる子供にとっちゃ、ワザリング通りなんて恐怖の象徴でしか無かった。「それとテリー」僕はつい息を呑んでしまった。「コアラは止めてくれ。その呼び名は気に入っていない。南半球は暑くて嫌いなんだ」
そう言ってイニスは電話を切った。外では犬が吼えていた。妹がこの前拾ってきたのだ。雨の晩、お気に入りの服に泥や毛をいっぱいくっ付けながら、子犬を大事そうに抱きかかえて玄関に妹が現れた時、母は気を失いそうになった。父が慌てて支えなければ大変なことになっていただろう。それ以来その犬は僕の家に居座っている。こいつと来たら食い意地がものすごくて、以前、僕のお気に入りのジーンズを食べ物だと勘違いしたらしく、僕がいざデートに穿いていこう、とした時にはもう手遅れだった。僕のジーンズはボロ雑巾のようになっていた。その時から僕とこいつはいい関係を築けていない。それとこいつには名前が無い。付けるのが面倒らしい。特に呼ぶようなこともないし、下手な名前を付けるより、無いほうがしっくりくる。なんだってそうだ。あるより無いほうが良い時がある。
次の日、僕はクラスの友人達とバーベキューをしていた。家の庭で犬が匂いに釣られて吼えまくっている。暑い日差しが照りつける中、内臓をすっぽりくり抜かれた豚が、鉄板の上で激しく身を焦がしている。リンゴや玉ねぎが添えられ、僕達はご馳走が出来上がるのを心待ちにしていた。手に持ったアイスクリームが溶け出してしまうくらいに暑かった。僕が溶けない内に一生懸命アイスを舐めている隣で、友達は道路を挟んで向こう側にいる女の子達と熱い視線を交換し合っていた。
その眼差しを遮るように、真っ黒い車が家の前に停まった。そしてレベッカ・ベルが中からゆっくりと姿を現した。白いスカートをふわりと風になびかせ、日傘を差している。白い歯を時折ちらつかせ、赤毛を傘の下で揺らしている。僕らは馬鹿みたいに口をぽかんと開いてそれを見ていた。誰かのアイスクリームが溶け落ちた。すかさず犬が走りよってきて、きれいに平らげてしまった。スズメバチが近寄ってきても誰も逃げ出さなかった。
「ごきげんよう皆さん」と彼女は芸能人みたいな気取った挨拶をした。
「どなたかパーキンソン夫妻をご存知ありませんか。借家の件についてお伺いしたいことがあるのですが」 焦げ付き始めた豚の匂いに顔をしかめながら言った。男の子はみんな身体をもじもじさせて、あっちだよ。いやあっちだよ、と口々に言った。視線を遮られた女の子が何人かこちら側に来ていた。それぞれカチューシャをなおしたり、スカートのしわを伸ばしたりしながらレベッカ・ベルに近付き、酷い顔で彼女を睨んだ。
「パーキンソン夫妻ならでかけておりますわよレディ」
とケイシー・ノーラがかみつくように言った。彼女は女の子のリーダー格で、いつも手下を引き連れている。「どうもありがとうお嬢さん」とレベッカ・ベルは微笑み、「あなたの髪飾り、とてもよく似合っているわよ」踵を返して車の中に消えて行った。ケイシーは皆の前で痛くプライドを傷つけられ、顔を真っ赤にしていた。豚はすっかり焦げてしまい、真っ黒な物体になっていた。僕達は落ち込み、ただ何も言わずに黙っていた。犬はどうにかして焦げた肉を食べようとぴょんぴょん跳ねていた。
レベッカ・ベルはちょっとした有名人になった。こんな寂れた田舎町じゃ彼女のような都会のご令嬢はいやでも目立つ。なんでも父親の転勤で引っ越してきたようだが、そんな素振りはまったく見せなかった。歩いているときは、背筋をぴんと伸ばし前を見据えて、全てを見届けようという気概が窺えた。もちろん、彼女はたちまち人気者になったが、それを良く思わない奴もいて、度々嫌がらせを受けていたけど、彼女はそれを流れるように受け流し気にもかけていなかった。その態度がますます連中の反感を買ったのは言うまでも無い。ある日、その日の授業が終わって僕が帰ろうとしていると、ケイシーがルドウィン・ベーカーになにやら耳打ちしている姿が目に留まった。ルドウィン・ベーカーはどんな最低な事も面白がってやれるような奴だ。彼が何人もの女の子を泣かし、動物を面白半分で殺してきたか、学校じゃ誰でも知っている。
ケイシーがルドウィンにウィンクすると、彼はイスから立ち上がり、レベッカ・ベルの背後に忍び寄り、彼女の尻を思い切り蹴飛ばした。ノートや、ボールペンがそこら中に散らばり、彼女は床に四つん這いになって突っ伏した。ケイシーは鼠のように歯をカタカタ鳴らしながら笑い、ルドウィンは足の感触を楽しんでいた。
普通の女の子ならそこで終わりだっただろう。逃げるようにトイレに走って行って、誰かが慰めに来るまで泣き腫らしていただろう。そうなるはずだ。でもレベッカ・ベルは違った。燃えるような赤毛を逆立て、唇をきゅっと真一文字に結び、汚れを払って立ち上がる。そして油断をしてケイシーと馬鹿笑いしているルドウィンの股間を思い切り蹴り上げた。つま先がめり込みルドウィンは白目を剥いて失神した。生暖かい液体が彼を中心に広がる。失禁したのだ。
「レディを蹴飛ばすなんて」レベッカ・ベルはうずくまるルドウィンを冷ややかに見つめ吐き捨てる。「あなたに男たる資格はないわ」彼女は何も片付けずに去っていった。そしてそれを何人かのクラスメイトが羨望の眼差しで見つめていた。もしかしたらレベッカ・ベルのファンサークルでも出来てしまうかもしれないな。ケイシーは真っ青になってルドウィンを介抱しようとしていたが、途中で躓いて小便の水溜りに突っ込んでしまった。彼女は引き裂くような悲鳴を上げて身をよじった。
家に戻ると、犬が僕の帰りを待っていた。やたらと飛びついてくるので頭を撫でてやるとよだれを垂らして尻尾を振った。部屋にまで入って来ようとしたのでしっしっと追い払った。ドアを閉め荷物を放り出しベッドに横になる。そして、棚に並べてある頭蓋骨のコレクションを眺めた。どれもこれも自慢の品だった。苦労したり、嬉しかったり、それぞれに僕の思い出が詰まっている。僕は棚に並んでいる内の一つを手に取った。その乾いた冷たい輪郭を指でなぞる。リスの頭蓋骨だ。これは僕が初めて手に入れたものだった。僕の父は狩猟が大好きで、良く狩に連れて行ってもらった。けもの道を踏み分けながら、父は若い頃に仲間と一緒に仕留めたグリズリーの話をする。S&W500を何発もぶち込んだんだが、まったく効かなくてな、と父は襟をくいっと引っ張り首に走る長く深い傷を僕に見せる。後数センチずれていたら動脈をやられていたそうだ、と誇らしげに自慢する。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?