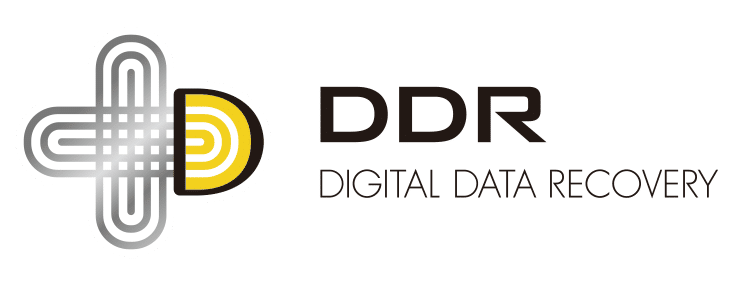SSD(ソリッドステートドライブ)の仕組みと種類
今回は、SSDの種類とデータが読み書きされる仕組みについてご紹介いたします。この記事を通して、SSDについて少し詳しくなりましょう!
1. SSDとは?
SSDとは、Solid State Drive(ソリッドステートドライブ)の略で、HDD(ハードディスク)と同様の記憶装置です。
HDDと異なるのは、「NAND型フラッシュメモリ」が用いられたドライブ(記憶媒体)であるという点です。ごく簡単に言えば、SSDはSDカードやUSBメモリと同類の記憶媒体に分類されます。
SSDの役割としてはHDDと同じですが、HDDに比べて衝撃に強く、読み書き速度が速いなどの利点があります。さらに近年は、低価格化と大容量化が進んだことから、急速に普及しています。
2. SSDの中はどうなっている
SSDはHDDと同様の用途で使用されるものの、その構造は全く異なります。
それでは、SSDの内部を、HDDと比較して少し覗いてみましょう。


HDDは磁気ヘッドやスピンドルモーターのような部品が動くことでデータの読み書きを行いますが、SSDの場合は、「物理的に駆動する部品」がありません。そのためSSDは、HDDに比べて振動に強く、物理的な損傷を起こしにくいとされています。
SSDの主要なパーツについて、以下に説明していきます。
(1)インターフェース
パソコンとSSDをつなぐ規格(接続口)のことです。SSDの接続規格には、大きく分けてSATA(Serial ATA)とNVMeがあります。
SATA:HDDと同じタイプの接続規格で2000年代以降急速に普及しました。
NVMe:SSDの使用を最適化するために新しく作られた接続規格です。SSDに搭載することが前提の規格なので、SATA接続よりもデータ転送を高速化できます。
(2)筐体
SSDの外装です。現在は2.5インチ(6.35cm)のサイズが主流で、1.8インチの製品も販売されています。
(3)NANDメモリコントローラ
データの読み込みを制御するパーツ。SSDの心臓部です。
(4)キャッシュメモリ
一時的にデータをキープする小容量で高速なメモリです。
(5)NAND型フラッシュメモリチップ
データはここに保存されていきます。
ちなみに、スマートフォンなど、私たちの身近な機器にも、同様のNAND型フラッシュメモリが使用されています。

(NAND型フラッシュメモリが使われている製品)
3. どういった種類があるの?
SSDは、筐体タイプ別では ①「内蔵タイプ」と、②「外付けタイプ」の2種類に分けられます。

①「内蔵タイプ」とは、文字通り「パソコンに内蔵されたSSD」のことです(ここにOSも入っています)。容量はMaxでも512GBほどと、そこまで大きくはなく、不足した容量は「外付けタイプ」で補われることが多いです。
なお、内蔵タイプは、容量が増えるほど、搭載PCなどの価格も上がっていくため、使用用途に適したタイプを選ぶことが大切となってきます。
②「外付けタイプ」とは「パソコンに外付けできるSSD」のことです。これはHDD同様に、電源ケーブルにつなぐ「据え置き型」と、電源ケーブルにつながず、持ち運びもできる「ポータブル型」に分けられます。
ただしSSDの外付けタイプにおいて「据え置き型」は、あまり普及しておらず、主流タイプは、小型サイズの「ポータブル型」となっています。
4. データはどう保存・消去されるの?
SSDではコントローラーを介して、メモリにデータを書き込んでいます。
なお、SSDのメモリは書き換え回数に制限があり、特定のメモリセル(メモリデータを記録する最小単位)にアクセスが集中すると劣化が早まります。
そのためSSDのコントローラは、同じエリアに書き込みが集中しないように、書き込みを行うセルを分散させることで、劣化を防ぎ、耐用年数を伸ばしています。これを「ウェアレベリング機能」といいます。

(SSDではHDDと異なり、データはバラバラに保存されます)
では、いったいどのようにデータがメモリに書き込まれるのでしょうか?
まず、SSDに搭載されている「NAND型フラッシュメモリ」は、内部の3層の間で電子を移動させることでデータの保存・消去を行っています。

(NAND型フラッシュメモリの断面。「絶縁膜」「浮遊ゲート」「トンネル酸化膜」の3層から構成されています)
3層の中間にあたる「浮遊ゲート」には「電子格納エリア」が存在しており、ここに格納された電子の数が「記録されるデータ」の正体になります。
なお「浮遊ゲート」の上下にある膜は通常時「絶縁」しており、電子を外に漏らすことはありませんが、浮遊ゲートの下にある「トンネル酸化膜」は、データを保存・削除するときだけ絶縁せず、電子を通過させられます。
データ保存の仕組み
高電圧をかけることで「トンネル酸化膜」が絶縁膜でなくなると「②保存時」のように電子が「浮遊ゲート」に格納され、データが書き込まれます。
データ消去の仕組み
データを保存する時とは「逆」に電圧をかけることで「③削除時」のように中心層の「浮遊ゲート」から電子が抜け、データは抹消されます。
5. まとめ
今回はSSDの種類や仕組みについて紹介しました。SSDがいかに精密で電子的に作られた機器であるか、少しでもイメージがわいたでしょうか?
なお、メモリの書き込み回数には上限があるため、SSDは突然故障する場合が多く、またこれだけ精密なSSDを安全に復旧するには、HDD以上に高度かつ特殊な技術が必要になります。
この技術についても、今後かいつまんでご紹介してまいりますね!
それではまた次回お会いしましょう!