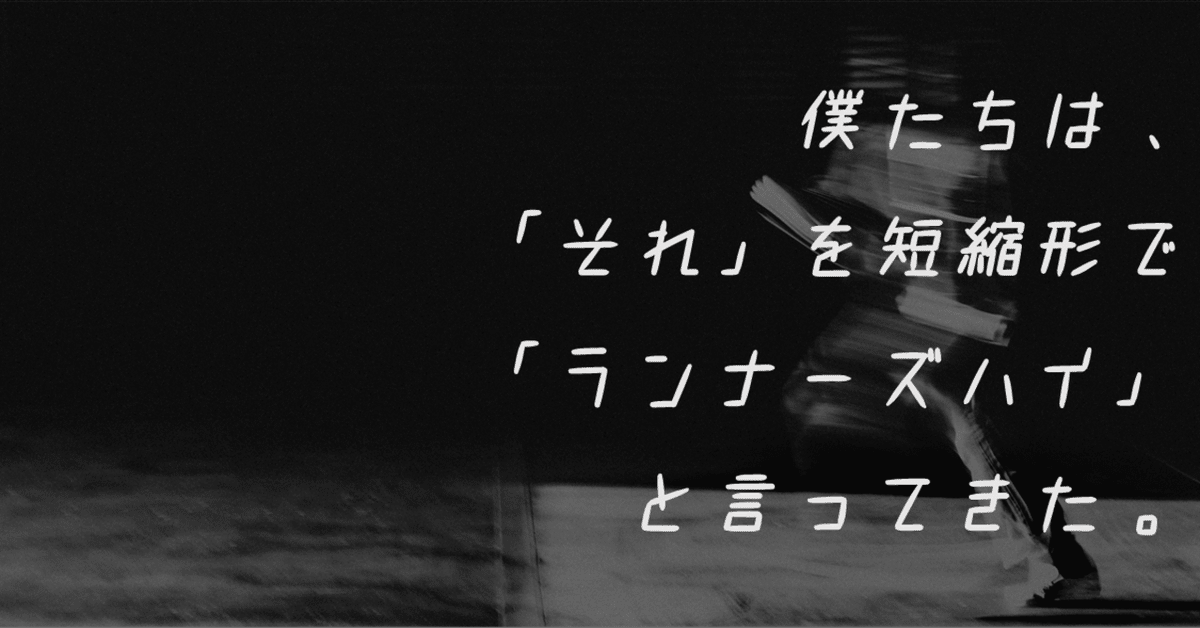
僕たちは、「それ」を短縮形で「ランナーズハイ」と言ってきた。
それが雑談の常ではあるのだけれど、話題にはたいがい持ち時間のようなものがある。皆が興味を持てる話題には何分、1人だけが好きな話題には何分、といった具合に。例えば僕が「ランニングが趣味です」と言うと、30秒くらいある。こよなく愛するランニングのことを文字通り一息に語る。それはそれは涙ぐましい30秒だ。
かといって話術があるわけではない。唐突にポンッとボールが転がってきて、誰かが話題を取り替えるまでの持ち時間。これを自在に使って、何十弾も打ち込める言葉の速筋のようなものを僕はたまに羨ましく思う。
そんな速筋を鍛え上げた彼らが、もし仮にレトロゲーマーだとしたら(?)バンダイナムコの「もじぴったん」は RTA になるのだろう。「もじぴったん」で延々と「れんさ」が最大になる言葉を選んでタイムオーバーしてしまう僕のような人間は、ラグと推敲が許される SNS のテキストメッセージに精魂を込めるしかない。
と、いうのは流石に冗談だが、その話題の持ち時間がとうに事切れたのに、30 分とか経ってから「さっきのことなのですが」と言って切り出すのも変な感じだ。だから大体話題の冷めないうちに、よく知れた短縮形のフレーズで場を持たせて処理してしまう。30秒の持ち時間で僕が喋れるのは「ランナーズ・ハイ」とかそれぐらいのもので、そういう時に「よろしければこれ読んでください」とサッと差し出すのに、note というのは便利だと思う。
と、考えていたところ、この漫画の描写にものすごく共感した。

漫画家はマンガの描写をツールにして編集とやり取りをする。じゃあ僕は文章で「ランニングが趣味です」を描けばいいのだ、と思ったわけだ。
とすると、この note の本題は「短縮形の『ランナーズ・ハイ』を、僕なりのランニングの全体像に向かって開く」という話になる。
であればまずは、この秋、僕は6歳になった。という話から始めたい。(そう、この note を書き始めた頃はまだ 2022 年の秋だった)
生まれる前、高校生活で唯一うまくいったのは、南関東大会出場の長距離ランナーと友達だったことだ。野球部を辞めた残りの高校生活の逃げ場が、その友達の居る陸上部だった。野球を辞めた高2の秋。17までのアイデンティティの殆どを立ち消えにしてしまって、陸上初心者になった高2の秋。僕はそこから生まれ直したんだと思う。今年で大学4年になる。この秋で僕は6歳である。
だからといっては変だけれど、「ランナーズ・ハイ」と聞いたときの普通の反応も凄くわかる。「そんなんドMじゃねーか」と皆そう言う。体育で長距離走を走る前の、嗚咽の出そうなあの感じは僕も苦手だった。もちろん、誰もが長距離走の楽しさを味わうとは思わないし、僕も無理に誰かに勧めたことはない。昔走っていたけど、辞めてしまった人も大勢知っている。それでも僕は、はじめて60分ジョグから帰ってきた、あの瞬間から生まれ直したのである。僕はいつかその感覚を文字に起こしてみたいと思っていたから、まあよかったら読んでほしい。いたって日常のランニング風景を、ゆっくりと、コマ送りで再生するように綴っていきたいと思う。



表情筋が沈殿したような顔つきをしている。



ただずっと、真下の地面を押し返している。

その〈醒めた〉感じに、「これだ、これだ、これだ!」と快さを感じている。

その各々が思い思いに T シャツを着ている。という話

1. ランニングコース概観
1 メートル 20 センチ。僕のストライドをそれ位だとする。これを 250 万回繰り返すと、3000 キロになる。この 3 年半で、僕が走ってきた距離だ。行き詰ったとき、偏頭痛がするとき、腹を括りたいとき、「えいやっ」といつものランニングコースに出て行った。多摩川沿いをぐーっと東京湾まで走る、直線のサイクリングロードである。

信号で止まらなくていい、進路を変えなくていい、パタパタとひっくり返る前髪を気にする必要もない。暇や、偏頭痛や、不安定な感情を、夜風に溶かしながら、ひとり深夜の川沿いをトツトツと走った。
やるべきことは次から次へと降ってくるし、Slack から飛んでくる通知音は鳴りやまなかった。それでもランニングから帰ってくると、言い様のない〈空白感〉に浸ることができた。それがこの世で一番好きだった。
カラオケでシャウトして得られる熱っぽさや、あっつい温泉に浸かったりして得られる安寧を、僕はランニングのなかに見付けてきた。ひとり深夜の川沿いをトツトツと往く。この2時間が、他では替えの効かない向精神薬として機能するのだ。
2. 常夜灯の点いた住宅街を抜けて

走り出す45分程前、おもむろに椅子を引いて伸脚を始める。何も考えずに、伸脚からアキレス腱、肩回りと首回り、体を前後に曲げて、回す、もう一度伸脚。整理体操とランニングの試行をN回してきて、痛くならなかった最低限のものをこなしていくので、いたって作業的である。し、決まり切っているがゆえに端折るべきものもなく、時間が掛かる。だからいつも、机の上に開いたままの PC から、今見ていた動画の続きを聞いている。
玄関先でアシックスのピンク地の厚底シューズに足を通すに至るまでは、油断がならない。雨がしんしんと降り出しているかもしれないし、明後日〆切の中の下くらいの課題を思い出してしまうかもしれない。雨が降っていても家を出て数秒で気圧されるような大玉の雨粒でなければ走り出すし、中の下くらいなら〆切1時間前に始めたって終わるのだが、要は、頭を働かせてしまうと「走らないでおこうか」となってしまって、あまりよくない。
緑ラベルに巻かれた円柱型のボックスを「ポカッ」と開けて、ミント味のキシリトールガムを2個口に放り込み、気持ち大きめの音量にしたプレイリストが、興醒めな CM に差し掛かってしまう前にと、そそくさと階段を降りる。是非など介在させずに、諦念や焦燥やヤケといった混濁した感情にまかせて、ふらつくようにして体を運んでいる時が、自分を走らせるのに一番上手くいく。
だから玄関口の姿見に映る自分はいつも、表情筋が沈殿したような顔つきをしている。
速乾性の蛍光 T、タイツ地のロング T、アームウォーマーに白軍手、タイツ地のロングパンツと、滑り止めのパッチが付いた5本指のレース用ソックス。それが端的な贅肉であれ、音楽プレイヤーであれ、100g位のモノでも、走り始めるとずっしりくるので、基本的に何も携行しないが、鍵だけはゴム素材のリングチェーンにして握り込むようにして走る。衣服一式に鍵、玄関に着いてようやく全身の一揃いを確認する。乱心で来るので、何かを忘れて階段を上がることもままある。

そうしてようやっとシューズに足が通されると、もう幾分晴れやかな気分になっている。それは「走りたくない・だるい」が霧消するというより、反発性のあるソールを足底に感じると、「弾め!」と直感が降ってきて、否応なく組み伏せられてしまう感覚に近い ───。
足にフィットするランニングシューズを選ぶと、履く・歩く体験も幾分変わるが、ランナー的動作をすると尚のこと変わってくる。
靴底の弾性をもったランニングシューズというのは、地面に接地した時の衝撃を吸収する「ブレーキ」であり、かつ、地面を離れる時に遅筋のバネ運動の力を伝える「アクセル」でもある。「ゆったりと鷹揚に走っているように見えて、思ったよりも速い」ランニングフォームの芯であって、ランナーにとっては足よりも足らしく感じられる存在である。
靴底の弾性が甘いと、「足を振り下ろして地面を押」そうとするやいなや、骨と地面が「衝突」するような、ドンッという感触が返ってくる。
1km3分のペースで走れる長距離ランナーと聞いたら、どんな TPO でも走れるように思えるが、クロックスやスニーカーや革靴で300mもダッシュすると、骨がじんじんと響いてとても走れなくなる。バッティング手袋がなければフルスイングできないように、バッグで肩回りが制約され、ジーパンで股関節周りが固定され、シューズの靴底が硬ければ、全くと言っていいほど持久できず、すぐに息が上がる。特定のランニングフォームを纏えなければ、満足に長距離も走れず、当然気持ちよくもならない。
─── 虫除けのスプレーをくるぶしと、首筋に吹きかけて、顔を除けばそれ以外に肌の露出している部分はない。
もうここまで来たら、走ることなくして踵を返した記憶がない。あとは川沿いへ歩を進めるのみである。

常夜灯の点いた駐輪場を抜けて、ややもすると、開けた1本道に出る。25人乗りほどの市営バスが乗用車と擦れ違うことができるから、その程度の幅はある。突き当たりまではざっと 200m はあって、住宅街に挟まれているけれど、走りに出る時間帯にはほとんど人が出歩いていないから、割に清々しい1本道である。
この1本道の入り口に立つと、「これから 15km 走りますよ」と、そういう雰囲気がしてくる。
ランニングの要衝たる足首や腱の類がそれとなくこわばる。ハムストリングに太めの弦のようなものが、ピンと通っているのを確かに感じる。足を地面に着くたびに、じりっと遊離していて、足首が ”座って” いない嫌な感じがする。
「ちょっとこのまま走るとやばいんじゃね」と言いたげな控えめな警告を、都度受け取って、路上で一時停止しては座り込んだり、ひねったり、伸びをしたり、回したり、うねうねとしながら 5 分ほどかけて渡り終える。
といっても、15km を積むことのしんどさへの予期的な緊張は、「ここ」まで縮まってきてしまったという方が正しい。高校の陸上部に中途入部した頃の、「きょうは 4km × 3 のペース走やります」と平板なトーンで告げられたときの反射的な嗚咽とか、「段々慣れるよ」と諭されながら 60 分ジョグに走り出したときの武者震いとか、そういうものを今の自分が追体験できるとしたら、フルマラソンを申し込む位のことをしないといけない。

突き当たりを右曲がりに、細い住宅街路の交差した三叉路に入る。そのうちの一本が、土手下の車道に向かってまっすぐ抜けている。ほんの 50m 先を 2tトラックや乗用車が 50, 60 km/h のスピードでびゅんと左右に通り過ぎ、ヘッドライトがふぁんふぁんと瞬いて、背の高い雑草が生い茂った 3m ほどの斜面を断続的に照らしている。
住宅街路の出口に面する所には、路傍の歩道を覆う植木レールの分け目が開けていて、そこから直に車道へ接続している。
一定の間隔で途切れる車列を、横目に見遣りながら、「ここだ」とあてを付けるようにしてスルスルと車道に出て行って、土手の端っこに足を掛けてひょいと飛び乗る。
川沿いのしかるべき位置には、しかるべき石階段もあるのだけれど、川へ続く全ての住宅街路の出口に横断歩道を設置してはいられないのだろう、こういう「非正規」な箇所には、住民が必要のために斜面の雑草を踏み倒した轍がそれとなく開けているので、そこを使って土手のサイクリングロードに上がっていく。
轍に左右から横垂れる高草の累々や、そのあいだに網を掛けるクモの巣が顔周りを撫でようものなら、ここから1時間強、何らか顔周りの付着感を拭いながら走るはめになるので、長袖ランニンググローブで防備した腕を前にやって漕ぐようにして轍を抜ける。

雑草に撫でられた衣服を手でパッパッとはたきながら、舗装されたゴム質の路面に出ると、目前に多摩川を望むパノラマが開ける。右手に常夜灯を連綿と灯した橙色の四谷橋が向こう岸に向かってぐーっと走り、河川敷の木立や一年草の合間にドォーッと小さく唸る一級河川の水流が覗けている。いま渡ってきた土手下の車道にも、土手に沿うようにして白色の常夜灯が続いている。

一見して「開け」た、立体感のある景観にあてられて、パァーッと晴れそうなものだが、実を言えば、上ってきた当の本人はそうでもない。
脇腹の隙を突かれて「ざぶぅぅ」と夜風に震えながら、「今日も来たぞ」なのか「おぉ久々だ」なのか、そういう淡泊な感がざばっと流れて、大方の感情は、「さっさ走り出して、ばーっとやって、5km 過ぎまでトリップしたい」という思いに支配されてくすぶっている。
3. 予定不調和な身体

ストレッチしたとはいえ、この時点ではまだ、身体は全く「ランニング」できる状態にはなっていない。45 分前からここまで掛かった労力は、「含み損」として実感されていて、気分は「現時点で着実にこなすべき、予定調和なウォーミングアップ」に向いている。
あたまでは、数十分後には揚々としていることを「記憶」から知っていても、そんなこと言ったって動画をスキップするみたく時間を飛ばすことができるわけではない。
「気分」と付き合いながら、ゴム質の路面の端っこで着々と動き始める。
不定期に横切る、ライトを灯した自転車や、腕にミニ蛍光板を巻いた市民ランナー、スマホ片手に悠々と歩くサラリーマンの様な風貌の通行人を見送りながら、動的なストレッチを流れるようにこなしていく。伸脚から肩甲骨周りの旋回、ランジ、股関節周りの 90° 回旋、上方への蹴り出し、最後にしずしずと足首を入念にこねくり回す。
こうしたことを入念に行ったうえで、摺り足の様に慎重に、全く大胆さのない雰囲気で、体重を覚えさせる / 思い出させるようにして、3m ほど走り出す。走り出したそばから、右足甲に硬さを感じては止まり、右踝が沈み込んだときに痛みを感じては止まる。
首の右後ろに引っ掛かりを感じて左手で引っ張るようにして押し込み、ゆっくり回すと小さくパキポキと鳴って収まる。肩甲骨を体の後ろ半分だけでくるっと回して、胸骨の辺りがパキッと音を立てて開く。膝裏からハムストリングにかけてが緊張してうまくバネ感をもって機能しないので座り込み、伸脚を 2 往復する。上体が脚の回転とうまく連動しないので、股関節を 15° ずつ回旋する ── 。

こうして関節たちが徐々に滑らかに動き始めてくる。とはいえ、心臓とか内臓の方がエンジンが掛かってこないので、250m ほど走った所ですぐ左胸の辺りがぐーっとキツくなってきて止まる。だらだらと 3 分歩く。「ほんとうに君は長距離ランナーなのか」と情けなくなりがちな時間帯である。こんなときは「わたしの筋肉は、お前たち一般人とは、ものが違う …」と呟いて乗り切っている。

ともかくも、ちまとした小走りと、ぐずぐずと立ち止まって行う整理運動による調整を、徐々に大きくしていく。
3m、7m、3m、30m、40m、25m、100m、250m、450m、600m ... 。
足掛け 2~3 km ほどこうして手塩にかけて育てていくと、「ぐねぐねとした歩行と、ギコギコとした小走りの混ざった様な徘徊」が、「ターンターンと小気味良く地面とシューズの底が噛み合った様な音を立てる、弾みのあるスムーズなランニングフォーム」に変換されていく / 移行していく。
この、ある種「ランナーの進化」とでも言うべき過程を、我慢強く通過することから、ようやく「ランニング」というものが始まってくる。

… あぁ、ようやく。
どのランナーにも多かれ少なかれ、持病のようなもので、相対的に筋量だとか柔軟性だとか故障癖だとかで「弱い部位」があると思うが、これらをひとまず〈違和感〉と括ってしまうと、ランニング体験はこの〈違和感〉によって汚染されるリスクにつねに曝されている。し、ここまで見てきたように、まずもってこの予防(起こってしまえばその対処)に少なくない時間が喰われる。15km であれ、3km であれ、〈違和感〉は同様の重みでそこに現れるので、「ちょこっと走るか」と思い立って、6 割の時間を整理体操に、残りの 4 割を走ると、何だかとても滑稽な思いがする。
4. 眠るようにして、走っている

差し当たり〈違和感〉と会話をしなくてよくなると、スペースが空く。
その空いたのを使って、随意とも不随意とも言えない「考え事」が始まる。
走っている最中は始終そうやって何か取り留めもないことを考えているのだけれど、思うに、その走りながらの「考え事」というのは、眠りにつくときの「それ」とよく似ている。
ふつう「寝る」という目的をうまく達成しようと我々が思うとき、「寝る」ことを考え過ぎるとかえって寝つけない。ので、なるべく遠回しに思いを巡らせようとすると、すとんと入眠できる。
その要領で、「走る」という目的をうまく達成しようと「走る」ことに注目し過ぎると、呼吸のリズムとかがやけに気になってかえって走りがぎこちなくなる。ので、なるべく頭の中はそこから離れていく。すると、すとんと「入眠」できる。持続的な振り子運動に打ち解けていく。
そうすると 30 分でも 40 分でもスムーズに走り続けられる。
とはいえ、安静時と違って、全身運動をしながらだと一握りのことしか考えていられない。
スペースがキュッと絞られていて、あんまりひとつの考えがそこに長く留まっていられず、その小さな部屋を次から次へといろんなものが入っては出て行く。
核心的なフレーズだけは何とか覚えていようとするのだけれど、大方あまり何を考えたか覚えていないのも、寝たあとに夢を思い返そうとしても思い出せないのと似ているといえば似ている。
どちらも脈絡というものがまるでないのだろう。あるときは、歌のフレーズが Aサビの一節だけ浮かんで、それが誰の何て曲だったかを思い出そうとしていた。かと思えば、昼と夜と地球の自転のことについて考え出し、40秒後には、財布の残金の計算を始めた。

しかし、この脈絡のなさが、効いてくる。
よく、「何も終わらない」という遣る瀬がない気分になる。
これも、走らないと治癒できないもののひとつだ。
星野源は『化物』のなかで、何気ない日々は何気ないままゆっくり僕らを殺す、と唄う。そういう感じだ。「次は某日までに云々」と期限を複線的に走らせていると、誰かとの口約束の負債感を背負っていると、脳梁がじわじわ凝り固まってくる。
それが走っていると、まともに物を考えられなくなって、しっかり肺に酸素が入って、ただただどうでもいいことで頭が一杯に満たされてくるものだから、減速を挟みながら波状的にそんな境地に留まっていると、なんだか思考の荷が下りてくる。バカになってくる。
バカになってくるというと語弊含みなのでどうにか言葉を探すと、明後日とか来週とかがちらつかない、何もない日の何の気なしの、夏休み初日みたいな地平というか、そんなところだ。
ただはっきりしているのは、5 - 9キロ地点に着いている頃には、何か「答え」が出ている。それは端的に「ああしよう」と当座で振り出す方角が定まるということでもあるし、「悩んでいたそれはくそどうでもいいことだった」と出来事の分別、処理のめど、やり場の整理がつくということでもある。
そうやって、遣る瀬がない気分が、治るのである。
5. 最速区間を運ばれていく身体

何かを標的に、「連れていかれるように」して走るとき、ランナーは最も理想的な走りをすることがある。ひとり川沿いを行くとき、その標的は大体の場合、自転車である。
ランとランのあいだ、繋ぎの徒歩を消化し、ようよう走り出そうかという段になって、1 度や 2 度そういうタイミングが訪れる。背中越しに、ポワンと分散したヘッドライトがあたって、近づくにつれて焦点をとって明度を上げてくる。「シャー」。左に 2 m 程の距離をとって、時速 15-20 km のスピードで自転車が追い抜いていく。
つかの間、つけるかつけないか(市民ランナーに優しい速度なのかどうか)目測する。「ついていける」となれば、十分に距離がとれた所で、25m 先を行った赤色灯をぼんやりとターゲットにして、追い始める。大体こちらのトップスピードと同じなので、実際には付きつ離れつしてまともな追走にはならないことが多い。が、この、ひとつ気を抜くたびに赤色灯に引き離され、目標が闇に霞んでいく、というのがいい張り合いになって、脚の動きをいい方向に働かせる。

ゆるゆるとモチつきの様にぺったぺったと地面をなめだした靴底が、ダンッダンッと踏み付ける様な音になったあと、ある地点から、足首、膝周り、ハム、股関節が「くっついて」、ふっと地面を撫でるように動き始める。回転がスムーズになって速度が上がり、脚から憑き物が落ちるように〈違和感〉が外れていく。
あの感覚を何と言ったらよいのだろう。ここだけは思案しあぐねてきた。だから、今からランニングにあてる形容に合点がいかないこともあるだろう。
はっと、するのだ。「前に進んでいる」んじゃ、ない。
ただずっと、真下の地面を押し返している。
空間認識としては、周囲 2m を包み込む半球のなかで、足踏みをしているのだけれど、景色は着々と流れていて、自分がいま「移動して」いることを不断に物語っている。
加えて、下半身はただ振り子のように、また、上下運動を繰り返す "ふいご" のように、そして勝手に、繰り出されている。

というのも、関節と筋と腱とは 1 本の統率で結ばれたようになって、地面を捉え、骨伝導で伝わってくる振動が、確かに股関節の付け根辺りまでのぼってきて、そこでフワッと霧消する。地面を弾いた 1 本の統率は直前の 1 歩を弾み馬にして、また地面を捉える。これが帰納的に続くのである。
上半身の側からしたら、まるで他人事のように、その乗り物を俯瞰で見下ろせるのだから、奇妙な感覚だ。よく箱根駅伝で脱水症状などによって大ブレーキしたランナーを指して、「足に力が入らない」感じと説明されることがある。それとは少し違って、「足に力が入らない」訳ではないが、「浮き足立って」いるとは言える。
ほとんどエネルギーを使わないまま、水にあてられた眼のようにちらつく常夜灯が着々と流れ、60kg 170数cm の体躯が確からしく運ばれていく。トップスピードの最中に居るにも拘らず、「ああ、俺はいま、走っている」と一歩引く余裕が、どこまでも進んでいける感が、そこにはある。
「思い切り走っていないのに、進む」わけで、「ゆったりと鷹揚に走っているように見えて、思ったよりも速い」をランナーの側から地でいく感覚なのだ。
あれを掌握して、そのうえ 1-2 時間ものあいだ身を委ねていられるのがトップランナーなのだと確信しているが、とても 20 分も持たないのが市民ランナーの実際である。
6. 酩酊から空白へ

あそこだ、あそこで、止まる、止まる!───。
止まれ!なのか止まりたいなのか、どっちつかずの停止信号が駆け巡り、関節と筋と腱とを結んでいた 1 本の統率が、ふっとほどける。
瞬間、慣性で振られた上半身が前のめり、ダンッと膝に手を落としてうなだれた。
ヒィヒィフウゥーー、ヒィヒィフウゥーー。
全部が、熱い。額とも脳天ともとれない辺りからジュワァと 40 ℃ 位の大粒の汗が湧き出て、ゴム質の地面にぽたっぽたっと球状の染みを作る。浸透圧が変化したかのように、身体の内側に押し込めていたものがどっと外へ溢れ出て行き、意識はただただそれを経験する入れ物になってしまったかのように為す術を失う。
頭がぐらつく。
ガンガン揺れる。
ヒィヒィフウゥーー、ヒィヒィフウゥーー。
何もしたくない。ハァーヒィッ、ハァハァー。
ただ息だけをする機械になりたい ───。

40秒はそうしていただろうか。
気が付くと、視界がボワァーっと湯けむりのように滲んでいた。涙みたいなものが出ていたらしい。
ハッ、ハッ、はっ、はっ。
網膜がやっとのことで焦点をみつけて、ギューっと解像度を取り戻してくる。足元の雑草が、こちらを見上げていた。
はっ、はっ、フゥー。すこし、楽になった。
ぐっぐっと冷凍保存から動き出すように腰を起こす。といっても、むわっと熱気がこもったようなのが体の表面を包んでいて、それでいて絶えず外の冷気に向かって逃げていく。呆っとしたあたまで、その熱と冷との境界が僕の表面なのだと、逆向きに理解していた ───。
本当に苦しそうに見えるのだろう、一度、携帯で誰かと話し込んでいた20代ほどの男性がタタタと歩み寄ってきて、「大丈夫ですか?具合、わるいですか?」と話しかけてくれたことがある。
その実、当の本人は、「これだ、これだ、これだ!」と快さを感じている。
たしか、ざばっと顔をあげて「あ、走ってるだけなんで」とくそみたいな返答をしていた。
「お気遣いありがとうございます」と付け加えればよかった。
─── これを経験したあと、身体は急激に重たくなる。速乾性 T の背筋にじわっと汗が染み込んで、少しつめたい。ハムストリングの20%位が肉塊に変わったようにバネ感を失って硬くなる。ここからのちは、遅筋と腱を徐々に機能不全にしていきながら、心地の良い消化試合が履行されていく。2km 走っては小さく酩酊し、3-5分の休憩のあいだに意識を取り戻しながら物思いにふける。

酩酊状態と、意識を取り戻してくる局面とを往還する。そうして、ぐらつく感覚器の最中から〈還ってきたもの〉として、俄かに〈自分〉を掴みかける。その一握の、〈醒めた〉感覚が、尊い。
虫の鳴き声が聞こえてくるのは、いつもこんな時間だ。
すぐそこに夜の一級河川が迫る土手道を走っているのだから、そう驚くことでもないと言えばそうなのだが、走り始めの自分はいつも何かと急いていて、耳の機能が大味になっているのか、虫の鳴き声をはたと聞いた覚えがないのである。
べつに「走ると、聴覚が研ぎ澄まされるのである」などということを言うつもりはない。ただ、荒い呼吸が治まったあと、ふっと落ち着いた気持ちになる。虫の鳴き声が聞こえるというのは、その〈醒めた〉感じをなんとなく表している。

こと感情の側面からぱきっと形容してしまえば、ランニングは乱高下する波の様なもので、それを乗りこなしてしまうと、気怠さ混じりの〈空白感〉に行き着く。
さながらそれは、嵐のあとの静けさに包まれた海原である。
が、しかしながら「水平線が見渡せるほど晴れ渡った昼下がり」ではなく、
「真夜中の快晴」とでも言うべきものである。
空が高く、月が明るい。
二百数十メートル隔てた対岸で、酔っ払いが独り謳っているのが、「チチチ」と飛んでいる河原の鳥のさえずりと同じ音量で、微かに聴こえる。
冷えた汗の滲んだタイツ地のロング T が、ぴたっと背中に張り付いて肌寒い。

もはや行きの半分以下のスピードで、ゆるゆると残り千五百メートル程のコースを帰っていく。河川敷に別れを告げるように、最後少し速度を上げて、「だああ」と声を上げながらスタート地点へ帰り着いた。
はっ、はっ。息を整えて、一級河川の一帯に開けた景色を見遣った。

これは、実は「走り切った僕」が見る景色だ。「走り出す前の僕」ではない。
行きの時に見たのとはちがって、心なしか気持ちが立体的になる。吹き去った靄の代わりに、余白が吹き込んできた様な気分である。
暫くそうしているか、あるいは路面に寝転んだかと思えば、スッと気が済んで、余韻を抱えたまま土手の斜面を駆け下り、車道をタタと駆け抜けて、路地へ入る。土手下の車道に向かってまっすぐ抜けた、件の住宅街路である。「ナイスラン。」夜道にうつむく影に、ぼそっとつぶやいた。
7. Things we said today

ボーっと暗街路をふらつきながら、手に持った鍵をチャラチャラとしている。ただ風景だけが家路へ向かっていく。真夜中のしんとした住宅街を歩いているから、走り終えたあとの〈空白感〉も相まって、心なしかしんみりしてくる。
しんみりしていると、普段は目に付かないものが、何か意味ありげに映ってくるものだ。例えば、行きに来たのとは逆回しに件の1本道を帰っていると、ある住宅の脇辺りに、1 m 20 cm ほどの庭木が、3本並んでいて、その各々が思い思いに T シャツを着ている。
そう、1 m 20 cm ほどの庭木が、3本並んでいて、その各々が思い思いに T シャツを着ている、のである。
何を言っているのか、という感じだが、実際そう、なのだ。たぶん、住人が「裸の庭木じゃあ寂しいだろう」ということで着せているのだと思う。
ともあれ、その真ん中のやつが胸の辺りに大きく「Things we said today」とプリントしてあるのだが、何といっても真夜中なので、ヒト型に映るものが道に居ると、どうしても脳が反応してしまうのだろう、それが毎回目に入る。
でもなんだか、「深い」ことを言っている気がするだろう、含蓄がある、というか。だから大体いつもそれを読んで、次の曲がり角まで少し考え込んでしまう。昼下がりに通っても全く気にならないのだから、不思議だ。

そうやってひとつ考えることには、僕はいつからか、「なんともないこと」が、平穏無事が、許せなくなっている。
普通に変哲もない日々を送っていると、僕のなかに、「なんともない負債」が掃き溜めになって堆積してくる。それをそのたびごとに「当座のなにか」でやり過ごしてきたんだとおもう。
その役回りが、あるときから、「走る」ことにまとめられていくようになった。「走り」さえすれば、じぶんを保てるように、矯正してきた。
「走り」ながら、「なんともないことのエントロピー」が、溶解して、押し流されていく。そのような形容が、「くそだるくて走り出し、ぐわーっとむしゃくしゃして、目が覚めてくる」、あの感覚にちかい。
そういうことをざばっと考えていると、家に着いている。
大した距離を走ったのでなければ、全身を大雑把にはたいて、異物の付着感を振り落としてから、ずっと握っていた鍵を静かに差し込んで玄関に入る。
15-20 kmを走った日には、やはりそのままでは何がしか「無理を言わせている箇所」というものがあるので、「それ」を探すようにして 5 分ほど玄関先の駐車場で整理体操を積んでから家に入る。何らかうまく色々なものが噛み合った日には、この整理体操の小休止に様々に観照が生まれたりする。そうでなければ、いたって何も起こらない。

とまあそうやって、ランニングが終わる。実際、ぼくにとってのランナーズハイは最速区間を運ばれる感覚でもあり、酩酊と意識を取り戻す局面の往還でもあり、走り終えたあとの気怠さ混じりの〈空白感〉でもあるし、なんともないことの解消でもあって、その全体像としてのランニング体験そのものでもある。これを1分の世間話として話すなら「ランナーズハイ」と短縮形で呼ぶし、もしも一から喋ってと言われたなら、こういうことを喋りたかったのである。
それがこの世で一番好きなのだ。

