
大河べらぼう鑑賞◆本作りの工程を書いた黄表紙を紹介
大河ドラマ「べらぼう」。
第3話は、「吉原細見」の改訂版を出したものの吉原の集客にはつながらず、蔦重は次の策として入銀(事前に費用を出資者から募ること)という手段で新たな吉原誘致の本を出そうとするお話でした。
その本は「一目千本」といい、各遊女を生け花に見立てて描いたもの。花の性質や名前で、遊女の個性まで伝えようという粋なアイデアでした。
※実際には、単純にそれぞれの遊女が活けた花を活写したという説もあるようですが、ドラマとしてはこちらの方が面白味があってよかったですね。
今回、私が注目したのは、その「一目千本」を蔦重たちが一生懸命手作りする「本の工程」の再現度の高さ!
実は、江戸の黄表紙の中には、この「本作りの工程」がしっかり描かれている貴重な作品が存在します。
それが、十返舎一九作の「的中地本問屋(あたりやしたじほんといや)」という作品。
享和2(1802)年の作品なので、おそらく今のドラマの時代<安永4(1774)年かな?>から30年近く後に書かれたものにはなりますが、およそこのような形で作っていたことには変わりないでしょう。
ドラマでもおそらくこの作品を参考のひとつとされたのではと思うほど、とてもよく似ていて、私は大興奮してしまいました笑

「的中地本問屋」に描かれた本作りの工程
彫師が彫る

本作りは、まずは作者に書いてもらった後、それを版木屋に持ち込んで職人の彫師さんに彫ってもらいます。
ドラマ内では、実際の彫師さんが彫師役を演じられていたそうですね。そこにも感激しました。
摺師が摺る

お次は摺師さん。
「早く仕事を終えて晩には遊びに行きたいなあ」
「それよりスッポン煮で飲むのがいいよ」
なんて職人さんたちの会話もリアルに書かれています。
丁合を取る

摺りあがった紙を順番どおりに一枚ずつそろえることを「丁合」といいます(右ページ)。
左ページの一番の左側の人は紙を半分に折っているところ。まだ若いと見えて、
「早く晩にならないかな、そしたら烏飴(からすあめ)を買って食べるのに」
なんてぼやいているのがかわいいですね。
裁ち作業

丁合を取ったら、小口や天地をそろえて紙を裁ちそろえます(右側)。これが非常に難しく時間がかかる作業だったとのこと。
表紙がけ

今度は表紙づくり。台紙に表紙用の紙を貼って表紙を作っていきます。この作品では、おそらく奉公人の少年たちが担当しています。表紙掛けは基本的にそれほど力もいらないので、子供でもやりやすかったのかもしれませんね。
綴じ作業

最後は針と糸を使って、本を綴じていきます。行燈のまわりに女性たちが集まって、せっせと縫い綴じています。
「この本はとんでもなく面白いよ」
なんておしゃべりもしていますよ。
今でいうパートの主婦、近所のおかみさんたちが集まっているのかもしれません。
おわりに
ドラマの中で、本を作った蔦重が「楽しい~」と本作りに目覚めていく瞬間が見ているほうにも伝わる映像、演出、演技が素晴らしかった。実際に私も豆本を作ってみたことがありますが、慣れるまでなかなか綺麗に作るのは骨の折れるものです。
でも「楽しい」。わかるよ~蔦重。
しかし実際に黄表紙に描かれた職人さんたちの呟きを見ていると、まぎれもない「仕事」「労働」でもあって楽しいだけでは語れない。それはそれでとても共感できます笑
実際にこの「的中地本問屋」を読んでみたいという方は、当時のレイアウトそのままに現代語訳した「黄表紙のぞき」という作品を通販中ですので、よかったらご覧になってください。
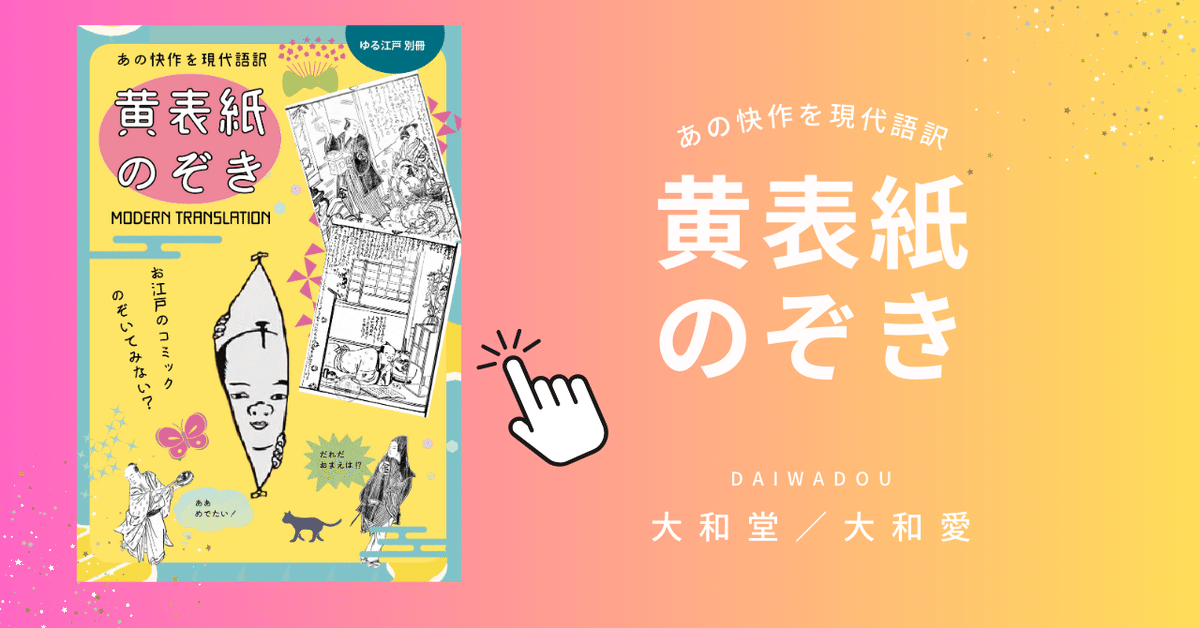
大和堂通販ページ(外部・アリスブックス)
それではまた~。
