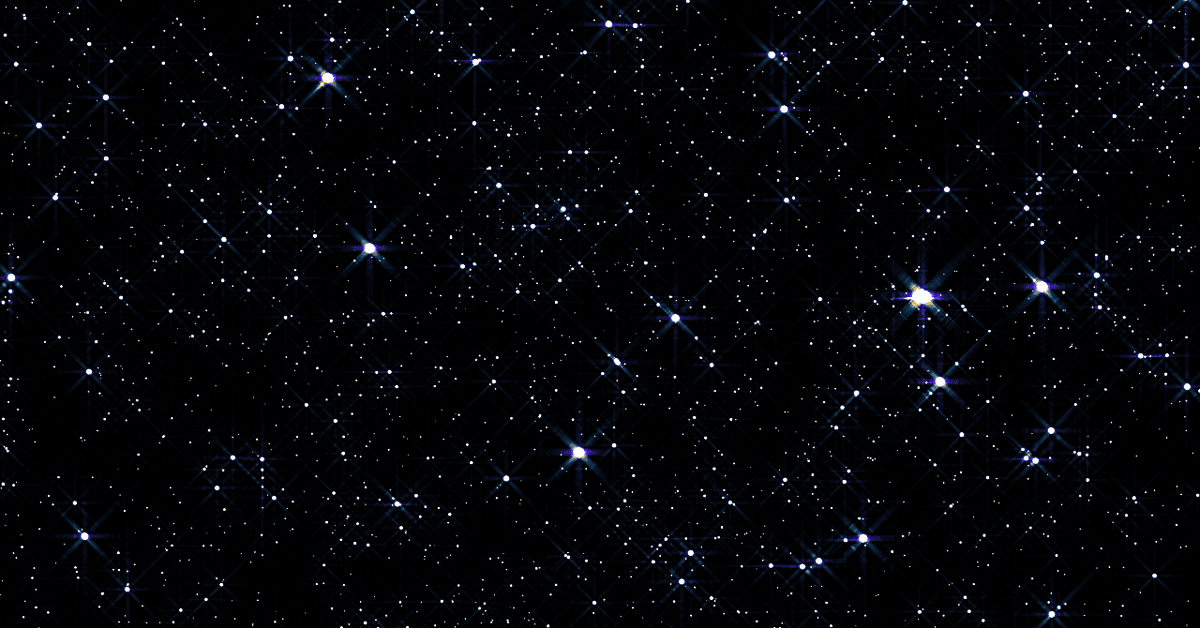
リアル巨人の星
星飛雄馬って実名の人がいてびっくりしたけれど
よくある話だけど、意外と少数派だった
昭和のスポ根ものの代表作、巨人の星。
僕は成人してからページをめくったのだけれど
フィクションとして読めなかったのには理由がある。
親子関係の描写がとてもリアルだったから。
あまりいい家庭像とはいえない。
そのくらいは書いてもいいだろうと思う。
家から出た後、一回り以上歳上の親友や、カウンセラー、
仲の良かった知人に少年時代の境遇について聞いてみた。
「それはあまり一般的ではないかもしれない」
そのような答えだった。
人ではなくて、作品
「世間様に顔向けできるような作品に仕上げる」
それが養育者のゴールだった。
成人してからそれを聞いてそうだろうなと。
人ではなくて、モノ、私有物扱いだった。
言葉の勢いだったにしても、あまりにも弱い人間が
そこにいた。
僕の中で崩れたもの。
「愛されたかった」
飛雄馬が社会に躓き、脆さを露呈したように
僕も歳を重ねるにつれ、周囲に適応できなくなっていった。
少年期に人とのつながり方や親密さの深め方を学習できなかったのは
若い頃は不幸だと思っていた。
すでに自分が何をしているのか、何がしたいのか
感情すらどう感じれば良いのか成人を迎えたあたりで
わからなくなっていた。
もちろん、人と親密さを築くことも不可能だった。
機能不全家庭の宿痾
最近は親ガチャとライトに言葉を変えているが
子供は親を選べない。
親と子とはいえ、一個の個性を持った命であり他人である。
では養育者は子供以外の他人に暴力を振るったのか。
配偶者を除いてないはず…
そこに機能不全家庭の宿痾がある、と思う。
外からは見えない。見てくれは仲の良い家族だから。
子供が養育者の世話をしたり、大人の役割を担っていた。
「いい子だね」は当然褒め言葉ではなかった。
酔い潰れた養育者に上着をかけて、お金を払い、タクシーに押し込む。
怒声や暴力を受けながら家に運ぶ。
そんな子供がいい子なわけがない。
後で気がついたこと
学生時代も、僕と同じような環境で育った人はいた。
ごく少数。知りうる限り。
育ちがよく、高校までガリ勉だらけだった少年少女が
新しい環境に伸びやかに逞しく適応していくのとは対照的だった。
そして、機能不全家庭で育った子供同士は惹かれ合う。
これは後で気がついた。
出会ってしまう引力を持っている。
自分にないものと、お互いの共感に惹かれる。
あまり健全とはいえない、けれども分かり合えてしまうから。
でも最後まで健全な人間関係を築けず、ひどい終わり方をする。
親密になるのが怖い。
本当の自分を知られたら、と思うと気が気じゃない。
そんな不安と緊張の中で親密さなど深められない。
これまでと今とこれから
約10年の介護期間を経て両養育者がそれぞれ鬼籍に入った。
僕は40間近になっていた。
それが僕の人生の第一歩だった。
自分で責任を取り、誰でもない自分で生きる。
どんな境遇でも自分が選ぶ。
気に入らなかったらやめればいいし、ハマったら飽きるまで続ければいい。
たどり着くのに7年かかった。
それだけ大人の影響は強く、また大人の力が自分にもあることも知った。
それでもまだ人が怖い。
と同時に人間はそのようなものだと理解も進んでいる。
ようやく苦労のない日々が訪れた。
成し遂げた全てが何の証明にもなることなく、
僕がただ生きている事実のみ語れるように。
自分で風向きを変えながら進んでいく。
