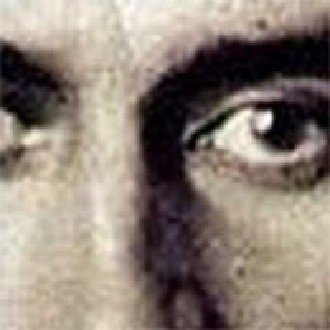なぜ「愛される厄介者」が存在するのか
「愛される厄介者」とでも言うべき人がいる。
実例をフィクションに絞れば、たとえば『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の両津勘吉であるとか、『男はつらいよ』の車寅次郎、『天才バカボン』のバカボンのパパなどが挙げられる。
彼らはみな自分勝手、欲望に素直で、周囲に迷惑ばかりかけている。なのに、人々に愛されているように見える。事実、読者には愛されている。
「どうしてあんな迷惑なやつが愛されているのかわからない」という人もいるが、それはむしろ基本的に彼らが愛されているから出てくる言葉だろう。ふつうに考えれば、厄介者は迷惑だから嫌われるはずだ。なぜ、彼らは逆に好ましく思われるのか。
それは「愛される厄介者」に自己投影しているからではないか。
人はみな多かれ少なかれ内面では「好きに生きたい」という欲望を抑え込んで社会生活を送っている。両さんや寅さん、バカボンのパパのように奔放に、自分に嘘をつかず、やりたいようにやっている姿は羨望の対象になっても不思議ではない。
ここまでは「そりゃそうだ」という当たり前な話。ここからもう少しだけ踏み込んで考えてみる。
なぜ、人は他人に自己投影するのか?
両さんも寅さんもバカボンのパパも、キャラクターであり、他人であって、どうころんでも自分ではないんである。なのになぜ、彼らに自分を重ねるなどという芸当ができるのか。これは物語全般に対していえる疑問だ。なぜ存在しないキャラの命運に手に汗握り、あこがれることができるのか。
ひとつの解答は、人間がそのような生き物だから、という単純なものだろう。進化論的に説明すれば、他人を自分自身と同一視(混同)する生き物は「人に優しく」を実現することができる。これはコミュニティを維持するために必要なシステムだ。人が困っていたら、自分が困っているかのように感じ、どうにかしてやりたいと思う。そのようになっていれば相互扶助が成り立って、生き物としての強度が増す。
自分と他人をまちがえる能力が人間にはあらかじめ備わっており、それがあるから親切することができるし、応用してフィクションの人物に自分を重ねることもできる。これは「愛情」の本質にも近いものであると思う。
もちろん、それだけが人間の全てではない。犬に噛まれて本当に痛いのは自分だけである以上、真の意味で自分と他人を間違えることはないし、その強烈な自己愛を自他混同能力(≒他者愛)が凌ぐことはほとんどない。「人を助けよう」とか「人が嫌がることはしない」というような倫理的スローガンは、自他混同の傾向をより大きくして社会維持に役立てようというものだ。
こう考えた上で最初の話に戻ってみると、構造のおもしろさに気づかないだろうか。こち亀の両さんを愛することができるのは、わたしたちが他人に自己を重ねるという他者愛を持っているがゆえのことだ。しかし、その感情移入先の両さんはまさに「自分さえ良ければ良い」という自己中心主義、エゴイズムの体現者なのである。他者愛があるからこそ、自己愛しかない他人を自分のように愛せる!
「どうしてあんな迷惑なやつが愛されているのかわからない」という人は、一見すると良識ある社会的人間のように見える。しかし、その「迷惑」とはどういう意味か。もし「ほかならぬ自分にとって迷惑だ」というのであれば、それは「自分さえ良ければ良い」というエゴイズムが導く感想だといえる。実際、両津勘吉は極端なエゴイストであるがゆえに「両津勘吉のような他人」をよく思わないだろう。
両さんや寅さんやバカボンのパパのような「愛される厄介者」の良さを理解しない人を想定するのはたやすい。利己主義者にとっては単に自分にとって迷惑な他人でしかないし、利他主義者にとっても社会にとって迷惑な者でしかない。
彼らを愛せるのは、自己愛と他者愛を適切な順番で積み上げられる者だけなのだ。にもかかわらず、多くの人が彼らに親しみを持っているという事実は、じつは驚くべきことではないか。
いいなと思ったら応援しよう!