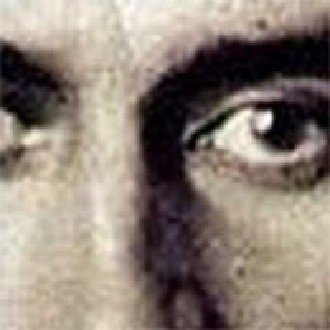社会と芸術の間には相互詐欺関係がある
芸能人が薬物使用で逮捕され、携わってきた作品が次々と回収されている。やめてよ。
やめてよと思うと同時に、作品の権利元である企業の立場を想像すると、そりゃ自粛したくもなるよな、とも思う。「犯罪者が関わった作品を販売することで、間接的に裏社会に寄与している」という指摘は、たしかに正しい。問われるとすれば指摘の真偽ではなく、それを踏まえた上で容認し作品を販売し続けるべきなのか否かだろう。
企業が自粛を選ぶ動機はとても単純明快だ。社会の中で商売をするうえでわざわざリスクを取りたくはないという、それだけの理由である。
一方、そういった自粛ムードを非難する消費者側の動機は、そう単純ではない。もちろん、第一には「好きな芸能人のコンテンツが見られなくなるのはいやだ」という単純な要求がある。しかし、それだけではない。彼らは当然、企業側が抱えるリスクに比べたらそんな要求が矮小であることを理解している。そのうえで「だとしても権利元は芸能人を守るべきだ」と言っているのだ。何を根拠にそんなことがいえるのか。
この背景には、芸能というジャンルの特殊性がある。芸能は単にみなを楽しませる職業というだけでなく、芸術の要素をも含んでいる。そして芸術は本質的に無制限なものであるから、規範からの逸脱の可能性を必ずどこかに宿している。表現の限界を規定する枠組みを内側から食い破り、拡張しようとする運動。そんな破壊的なエネルギーこそが芸術を芸術たらしめているといえる。
直感的にわかるように、これは「社会」というシステムと真っ向から対立しうるものだ。言い古されてもはや誰も言わなくなってしまった「ロックは危険だ、不良の音楽だ」という頭の固い老人たちの言葉は、実は正しかったのだ。そこには確かに、社会を破壊しようとするエネルギーがたぎっているのだから。
にもかかわらず、なぜ今、そういった言葉は言い古されてしまったのか。それは「社会」という巨大な枠組みが芸術を排除するのではなく、自らの内部に芸術を取り込むというかたちでコントロール下に置こうとしたからだ。
無制限で危険な芸術に理解を示し、あえて居場所を作ってやる。しかしその目的は、芸術の核である破壊的エネルギーだけを巧妙に取り除くことなのである。
芸術に対する社会の詐欺性は、この関係に表れている。
国営放送の情報バラエティ番組などを見ると、サブカル系の芸能人が番組の堅苦しい雰囲気を和らげている光景を目にすることができる。彼らの「奇抜」「個性的」「非常識」「ワル」「不謹慎」…な特色は、社会のガス抜きのためにうまく役立てられているのだ。
しかし、芸術サイドの人間もまた詐欺的でありうる。彼らは生存を確保するため、まず社会にすり寄っていく。そして「個性的で奇抜だけど、本当はちゃんとした社会人なんですよ」という顔をして居場所を作り、社会のコントロール下に置かれたフリをして、悪徳に手を染めるのだ。つまり、隠れて本当の芸術をしてしまうのである。
もとを正せば彼らは「悪人」なのだから、「悪人のふりをする善人」のふりだってできるのだ。社会が巧みに芸術家を制御しようとしても、芸術家は常にそのような形で社会をひそかに裏切ることができる。
社会に対する芸術の詐欺性は、この関係に表れている。
だから、これは芸能というジャンルを社会が認める過程で必然的に生じる相互詐欺的な関係なのではないか。社会は芸術を騙し、芸術は社会を裏切る。
芸能人が不祥事で逮捕された時にだけ聞こえてくる、独特の優しいエールがある。あれは、この関係性が気づかれているからこそ生じるのだろう。芸能人を無慈悲に見限る企業は、そもそも芸術の破壊的性質を知っていながら無毒化し骨抜きにして利用しようとしていたという点で欺瞞的なのだ。だからファンは「彼らを守ってくれ」と叫び、社会の不誠実を告発しようとする。
あなたたち社会は、自由でワルっぽくてメチャクチャな連中を認め、居場所を作ってくれたじゃないか。多少なりともそこに価値を与えてきたのに、いざ本当の悪が顕現したら排除するのか?
しかし、「悪を容認しない」という、社会の「不誠実」の告発は、社会の内部では全く力をもたない。なぜならその告発の形式自体、社会が作り出してきたものであるからだ。
芸術家は、黙って「裏切り」という形式で復讐を果たすしかない。たとえば、出所してからテレビの前で深々と頭を下げて陳謝し、再び社会にポジションを作ってから、当たり前のように薬物を摂取し続ける、というような形で。
いいなと思ったら応援しよう!