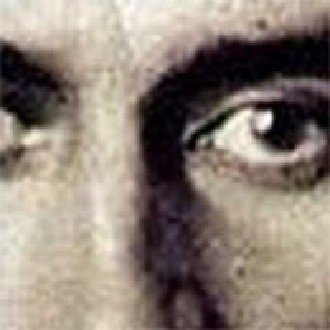【習作短編】最後の静寂
使用機材:Claude 3.5 Sonnet(一部)
「はぁ…」
自宅のデスクで溜め息をつきながら、朝倉はるかは動画サイトをスクロールしていた。
締切に追われる毎日は、決して楽ではない。特にオカルト系のウェブメディアで記事を書くはるかにとって、ネタ探しは永遠の課題だった。世の中には心霊スポットや都市伝説は無数にあるものの、大手メディアが扱っていないような、しかも事実確認ができる題材となると、その数は途端に少なくなる。
すでに23時を回っている。「不思議体験」や「怪奇現象」といったキーワードで検索をかけても、出てくるのは既出ネタばかり。編集長からは「みんなが知ってるような話はNG」と口酸っぱく言われていたから、使い物にならない。
「あと1本…今月の記事ノルマまで、あと1本なのに…」
スマートフォンを手に取り、SNSのタイムラインを眺める。するとそこに、気になる投稿が流れてきた。
「心霊か? 図書館のポルターガイスト現象!」
リンクをタップすると、30秒ほどの動画が表示された。投稿されたのは6日前。しかし再生回数はすでに3万を超えていた。
画面には、図書館の内部が映っている。タイムスタンプは午前2時37分。夜の闇に包まれた館内で、書架に並ぶ本の背表紙が浮かび上がっていた。
最初は何も起こらない。しかし15秒ほど経過したところで、一冊の本が、まるで見えない手に引かれるかのように、ゆっくりと棚から滑り出してきた。画質は粗いが、本の背表紙はかろうじて視認できる。動き出した本の背表紙には『呪い大全』と書かれている。そして──
「──落ちた」
はるかは思わず声を出していた。映像の中で、本は重力に従って床に落下する。その瞬間、かすかなノイズが走り、動画は終わった。
「これは…」
説明文には「XX区の某図書館で撮影された心霊現象」とある。投稿者の他の動画を見ると、同様のアングルで撮影された怪奇現象が数日おきに投稿されている。内容は似たりよったりだ。本棚から一冊の本だけが抜き取られるように動き出し、床に落ちる数十秒の映像。映像は合計で5つあった。コメント欄はそれなりに盛り上がっている。
「マジモンのポルターガイスト?」 「ヤラセでしょ」「霊現象としては地味すぎて怖くない」「地味だから逆にリアルじゃね?」
はるかは思わず背筋を伸ばした。これは、間違いなく良いネタになる。すぐに関連するSNSの投稿を探してみると、大手メディアが取り上げている様子はない。いままとまった記事に仕上げることができれば、一番乗りになれるに違いない。
「よし、まずは図書館を特定しないと」
しかし、動画の映像は暗すぎて、建物の特徴を掴むのは難しい。かといって、XX区内の図書館を片っ端から当たっていくのは効率が悪すぎる。
そこではるかは、ふと思い当たることがあった。
「そうだ、澪先輩なら…!」
篠原澪──XX区、中央図書館の司書で、はるかの大学時代の先輩。自他ともに認める本の虫で、収入の8割を本に費やしているとか、本の重量でアパートの床が抜けて弁償したとか、まことしやかな噂をいくつも耳にした。はるかは個人的に澪の世話になっていた時期がある。彼女なら、この映像から図書館を特定できるかもしれない。
「明日、会いに行ってみよう」
スマートフォンを握りしめて頷いた。はるかの記者としての第六感が告げていた。これは、ただの怪奇現象以上の何かがある──そんな予感を。
翌日の午後、はるかは中央図書館を訪れていた。
閲覧室の隅で、カウンター越しに澪の姿を目で追う。相変わらず青白い肌に疲れた表情を浮かべながら、淡々と返却された本を整理している。制服のワイシャツは几帳面にアイロンがかけられ、黒縁メガネの奥の目は本の背表紙を追って小刻みに動いていた。
「あと30分…」
はるかは時計を確認する。澪の勤務終了までもう少しだ。待ち合わせは休憩室と決めていたが、この30分が妙に長く感じられた。スマートフォンを取り出し、例の動画を何度も再生する。暗がりの中で本が滑り出す映像は、何度見ても不気味だった。
「朝倉くん、早かったね」
気がつくと、澪が目の前に立っていた。170cmの長身が逆光に照らされ、はるかを黒い影で覆う。
「お疲れ様です、澪先輩」
休憩室に移動する二人。小さな部屋の窓からは、夕暮れの空が見えていた。
「それで?」澪は紙コップに注いだコーヒーを啜りながら言う。「何か面白い話でもあるのかな」
はるかは即座にスマートフォンを取り出し、例の動画を見せる。暗い図書館の書架。静かに滑り出す一冊の本。その映像に、いつも気だるげな澪は珍しく興味深そうな目を向けた。
「ふむ…」
動画を三度ほど繰り返し再生し終えると、澪は背もたれに深く身を預けた。
「あの、実は知りたいことがあって……」
「東図書館だ」
「え?えっ、どうしてわかるんですか?」
「書架の配置と天井の照明の具合」澪は目を細める。「それに、あの本──『呪い大全』が置かれている棚の位置からして。私、県内の図書館は全部行ったことがあるから」
「さすが澪先輩…」
はるかは感心しながらメモを取る。
「撮影は図書館の外からされたみたいだね」
「えっ、どうやって?」
「この書架の前は全面ガラス張りだからね。日光で本が痛みやすいから、見栄えばかり先行させるのは勘弁してほしいものだけれど」
「おしゃれなほうが人が来てくれますもんね」
「私にはよくわからない感覚だけれどね。図書館は静かに本を読む場所じゃないのかな。ただ、非営利の公共事業とはいえ、来館者が少ないと助成金がカットされ、本の購入にも制限がかかる。どこの馬の骨ともしれないコンサルタントが口を出してくるし、図書館はどこも必死だよ……おっと、つい愚痴っぽくなってしまった。それで、用事は済んだかな」
立ち上がろうとする澪をはるかは慌てて引き止めた。
「あの。せっかくだから力を貸してください。私、このポルターガイスト現象の取材をするつもりなんですけど、先輩ならこの謎が解ける気がするんです」
「朝倉くんは、この映像が本当の心霊現象だと思うのかな?」
はるかは首を傾げる。
「さあ……あ、でも、よくできたCGとかかもしれないですよね」
「なら、確認しよう」澪はペンを取り出し、メモ用紙に何かを書き始めた。「東図書館の司書に聞けばいい。朝の時点で本が落ちていたかどうか」
そう言って、澪は書き終えたメモをはるかに手渡した。はるかはそれを読んで、首を傾げる。
「えっと、これって…」
「指示に素直に従えばいい」澪は意味ありげな微笑みを浮かべる。「場合によっては、面白いことがわかるよ」
東図書館は、街の喧騒から少し外れた場所にあった。バス停からも遠く、最寄り駅からも徒歩15分。スマートフォンの地図アプリを開いたはるかは、思わずため息をついた。
画面には、古墳群や神社の地図記号が点々と並んでいる。かつてこの辺りは由緒ある地域だったらしい。古墳時代の遺跡も多く、地元の歴史研究家が熱心に保護を訴えているという記事を読んだことがある。神社の境内には樹齢300年を超える御神木もあるそうだ。
「歴史のある街なのは分かるけど……」
周辺には古びたアパートが点在するばかりで、人通りはまばらだった。空き家も目立つ。地図上で緑地に見える場所も、実際は雑草が生い茂るだけの空き地だ。曇り空の下、街全体がどんよりとした空気に包まれている。もうすぐ開通するという新駅によってアクセスは格段によくなるらしいが。
「ここなら幽霊が出ても、おかしくないかも…」
閑散とした雰囲気に不釣り合いなガラス造りのモダン建築は、なんだか滑稽に感じられる。税金の無駄遣いではないのか。はるかは図書館を見上げながら、澪の言葉を思い出した。「場所も建築もちぐはぐで冴えないけれど、蔵書のセンスはかなり良い」と。しかし、その良い本も読む人がいなければ意味がない。
近くの古墳から吹いてきた冷たい風に、はるかは思わず身震いした。
自動ドアをくぐると、館内は静寂に包まれていた。平日の午後とはいえ、利用者は片手で数えられるほどしかいない。机に向かう高齢の男性が一人、児童コーナーで絵本を読む親子連れが一組。そして、雑誌コーナーでうつらうつらしている学生らしき若者が一人。
「あの、中村さんはいらっしゃいますか?」
カウンターで声をかけると、奥から30代くらいの女性が姿を現した。茶色のカーディガンを羽織った温和な印象の司書だ。
「はい、私が中村ですが」
メモ用紙を横目で見てから、はるかは切り出した。
「メールを差し上げました、怪スポマガジンの朝倉と申します。先週起こったポルターガイスト事件について、お話を聞かせていただけませんか?」
「はい、構いませんよ」中村は特に警戒心を示すこともなく応じた。「確かに、朝の開館時に本が落ちていることがありましたね」
「具体的にはどんな……?」
「そうですね。『呪い大全』という本が床に落ちていて。最初は誰かが乱暴に扱ったのかと思ったんですが、何日も続いたので変だなあと」
中村は首を傾げる。
「閉館後の蔵書チェックでは、棚にしっかり戻しているんですよ」
はるかはメモを取りながら、さらに質問を重ねた。
「何か、それ以外にその……心霊現象めいたものは?」
「ええ」
中村は少し声を落として続けた。
「誰もいないとき、たまに人の気配を感じることがあって。書架の向こうに人影が見えたような…それに、青白い光が浮かんでいるのを見たスタッフもいます」
はるかはごくりと唾を飲み込む。
「霊……でしょうか」
「どうでしょうね。こういうことには詳しくないんですが、あまり嫌な雰囲気はなかったので、悪霊とかではない気がします。読書家の幽霊なのかしらね」
中村は上品に笑い、はるかもそれに合わせた。
「動画のことは、ご存知でしたか?」
「ええ、見ました。誰が撮影したのかまでは分からないんですけど。実はSNSで見かけて、私も驚いているんです」
「ちなみに、館内にある正規の監視カメラ映像を見せていただくことは」
「それは、さすがに」
中村は苦笑し、ですよねとはるかもヘラヘラ笑う。しかし中村の話では監視カメラにも同様の映像が収録されていたという話だった。ひとりでに本が落ちたのだ。
「もし良ければ、現場……書棚も見せていただけますか?」
「もちろんです」中村は笑顔で応じた。「写真を撮られるなら、許可証をお書きいただけますか」
事務的な手続きを済ませ、はるかは例の本棚へと案内された。動画に映っていた場所は、確かにここに違いない。窓際の書架。オカルトや超常現象関連の本が並ぶ「精神世界」エリアだ。
中村の親切な案内を受けながら、はるかは考えていた。これは本当に、単なる心霊現象なのだろうか──。
「ちょっと、調べさせていただいてもいいですか?」
はるかは中村司書に許可を求めると、さっそく書架に近づいた。動画に映っていた『呪い大全』は、確かにそこにあった。黒い背表紙に金文字で刻まれたタイトルは、薄暗い書架の中でも存在感を放っている。
手に取ってみても、特に変わったところは見当たらない。本の重さも普通だし、背の高さも隣の本とほぼ同じ。むしろ、触ってみると安っぽい印象だ。ぱらぱらとめくってみたが、ネットのどこかで見たような話が列挙されているオカルト雑学本という感じだった。中村に了承を得て、スマートフォンで写真を撮りながら、書架の構造もチェックした。
「あ、これ…」
書架の奥側に、わずかな傾斜がついている。本がちょっとした拍子に落ちない工夫が施されているようだった。指で触れてみても、その傾斜は確かに感じられた。
「これじゃますます、勝手に本が落ちるのは難しいかも……」
やっぱりポルターガイスト現象なのだろうか。呟きながら周辺を見回し、今度はカメラの位置を特定しようとする。
図書館の外に出る。ガラス張りの外壁を見ると、確かにそこからさっきまでいた書架が見えた。近くには街路樹が数本植えられている。そのどれかに小型カメラを仕掛ければ、十分に撮影は可能だろう。
「でも、どうやって……」
撮影方法はわかったとして、ポルターガイスト現象のことは謎のままだ。そこではっと閃く。
「地震、とか?」
スマートフォンを取り出し、最近の地震情報を検索する。しかし、この地域で大きな地震があったという記録は見当たらない。仮に地震だとしても、傾斜のついた書架から、なぜ『呪い大全』だけが落ちるのだろうという疑問も残る。
冷たい風が吹き抜ける中、はるかは首を傾げた。謎は深まるばかりだった。そこで再び、彼女は澪の顔を思い浮かべた。
街路樹の葉が風に揺れる音は、まるで誰かの忍び笑いのようにも聞こえた。
「もう、わかりません!」
はるかは中央図書館の休憩室で、机に突っ伏した。窓の外では夕日が沈みかけており、オレンジ色の光が疲れ切った彼女の横顔を照らしていた。
「ふう」
対面に座る澪は涼しい表情のまま、紙コップのコーヒーを啜っていた。目の前のカフェイン中毒者は、友人の苦悩を眺めて楽しんでいるようにも見える。
「結局、何もわからなかったのかい?」
「いいえ」はるかは顔を上げ、スマートフォンを取り出した。「いろいろわかったことはあるんです。でも、それがかえって……」
彼女は写真をスワイプして見せながら調査結果を説明した。書架の傾斜構造、外からの撮影可能性、地震の可能性の否定——すべての事実が、謎を深めるばかりだった。
「なるほどね」
澪は黒縁メガネの奥の目を細める。その表情には、いつもの倦怠感とは違う、何か別の色が混じっているように見えた。
「じゃあ、状況を整理してみようか」
「整理、ですか?」
「そう」
澪はコーヒーを置き、姿勢を正した。
「まず、この現象が単なる映像の合成である可能性は?」
「それはないと思います」はるかは即答した。「中村さんも、確かに本が落ちていたって証言してましたから」
「なるほど。それに、もし合成なら、もっと派手な演出をしたくなりそうだよね。いくつも動画が投稿されていて、全て同じ本が落ちるだけというのは、つくりものにしては芸がない」
「確かにそうですね」
「次に、誰かが糸でも使って引っ張った可能性は?」
はるかは首を横に振る。
「警備員さんもいるし、ガラスに隙間はないし、そんなことできないと思います」
「そうだね。私もそう思う。では、地震の揺れで落ちた可能性は?」
「それは私も考えて調べましたけど、最近は特に大きい地震はなかったですよ」
「そうか。でもね」澪は急に口調を変えた。その声には、何かを見抜いた者特有の冴えが宿っていた。「その『最近』って、いつのことかな?」
「えっと、動画が投稿された先週……」
「本当にその時期に撮影されたのだろうか」
はるかは目を見開いた。確かに見たのは投稿された日付だけだ。投稿された日付の付近が撮影時期だと無意識に思い込んでいた自分に気づく。
「これを見てごらん」
澪はスマートフォンの画面を指差す。動画の一場面で、問題の本の右隣に紫がかった背表紙の本があった。
「背表紙のデザインと位置から推測すると、これは『悪魔の紋章辞典』だろう。20年ほど前に出版されたニッチな学術書なんだけれど、今や貸出予約が殺到してるんだ。『デビルクラッカー』っていうアニメの影響だ。中央図書館だと半年待ちだよ」
「ああ、あの人気作ですね。私も観てます。少年マンガだけど、けっこう宗教学の蘊蓄がマニアックなんですよね」
「そう。でもそのアニメが始まって本格的に人気が高まりだしたのは3ヶ月前なんだ」
「はあ……」
「わからない? いくら人の少ない図書館でも、そんな人気の本が何日にもわたって書架に挿さったままなんて考えにくいんだ。他館からの取り寄せだってできるんだし。現に、朝倉くんが撮ってくれた本棚の写真に『悪魔の紋章辞典』は写っていない。だから、この動画が撮影されたのは、少なくとも3ヶ月は前ってことだよ」
「なるほど、たしかにそうですね」
「それと、左側にあるオレンジ色の本。これは『アフリカの奇面』だと思われるが、今年発売の本で発売時期は約5ヶ月前だ。つまりこの動画が撮影されたのは、5ヶ月前から3ヶ月前の間ということになる」
「そんなに前だったんだ!」
はるかは色めき立って、その時期の地震の記録を掘り返した。しかし予想に反して収穫はまったくなかった。
「先輩、この時期にも地震なんて起きてないじゃないですか」
澪は意味ありげな微笑みを浮かべる。
「地面が揺れるのは、地震だけじゃないんだよ」
「地震だけじゃない?」
はるかは首を傾げた。澪の言葉の意味がすぐには理解できなかったのだ。
「朝倉くんは、東図書館にはどうやって行ったんだい?」
「電車ですけど……」
「駅からずいぶん歩いただろう。あそこはどこからも遠いからね」
「そうなんですよ先輩。周りもお墓とか古墳とか、なんとなくどんよりした雰囲気の場所ばっかりで……」
その瞬間、はるかの目が大きく見開かれた。そうだ。来年から新駅が開通すると聞いたではないか――地下鉄の。
「トンネルの延伸工事は深夜に行われている。施工マップを確認してみると、トンネルは東図書館の真下を一部かすめるように掘られている。その場所が、『精神世界』エリアとぴったり重なるんだよ」
「工事の振動で本が落ちた……というわけですか!」
澪は頷く。
「あのあたりは旧跡が多く、ちょっと掘るだけで骨や壺なんかがゴロゴロ出てくる。比較的影響が少なかろうと選ばれたのが図書館周辺だったんだろうね。かなりの振動を伴う工事だったはずさ。本が落ちてもおかしくはない」
なるほど。分かってしまえば単純な理屈だ……しかし、はるかはすぐに首を横に振った。
「でも、それはおかしいです! 本棚には奥に傾斜がついていました。工事の揺れくらいじゃ本は落ちないと思います。それに唯一『呪い大全』だけが落ちるのも不自然です」
「だから『呪い大全』だけが落ちるように細工をしたんだよ」
「細工、ですか?」
工事の揺れで全ての説明がつくと思っていたはるかはオウム返しをする。澪は、まるで当然のことを説明するような口調で続けた。
「方法は実に簡単さ。本棚の奥に何か小さなものを挟んで、傾斜を逆につければいい。折りたたんだ紙とかね。本を少し手前に傾けるだけで、振動によって少しずつ前に進み、落ちる」
はるかは息を呑んだ。
「つまり、誰かが地下鉄工事を利用して、人為的にポルターガイスト現象を起こしていた?」
「おそらく。閉館直前に『呪い大全』の入る隙間の奥に仕掛けを施したんだろう。撮影された時期とSNSに投稿された時期がズレているのは、撮影時期を誤認させることで、鉄道工事という単純な答えから気を逸らさせるためだ」
そこではるかは、ある重要な点に気づいた。
「でも、そんなことができるのは図書館の内部の人間しかいませんよね?」
「よく気づいたね」澪は満足げに頷いた。「このトリックには、決定的な弱点があるんだ。それは、本棚の奥に傾斜をつける機構が残ってしまうこと。朝、床に落ちている本を戻そうとした司書がその機構に気づいたら不審に思われるだろう」
「という事は……」
「犯人は中村という司書に違いない」
「そんな……中村さん、すごく良い人だったのに」
そこで澪は、あのメモの話を持ち出した。
「私が渡したメモのことを覚えているよね。『先週起こったポルターガイスト事件についてお話を聞かせてください、と言え』と書かれていたはずだよ」
「はい、その通りに……あっ!」
「もしも司書が何も知らないなら、ポルターガイスト現象は5~3ヶ月前に起こっていたと認識しているはずだ。『先週起こった』という聴き方に違和感を示さなかったのは、どう考えても変なんだよ。そうしなかったのは、中村司書が犯人であるという決定的な証拠さ」
「でも、どうして中村さんがそんなことを……」
はるかは背を丸め、困惑した表情を浮かべた。取材時の中村司書の親切な態度が、まだ頭から離れない。澪はゆっくりと言葉を紡いだ。
「朝倉くんのような人を呼び寄せるため——というのが答えだろう」
「え?」
「東図書館は来館者不足に悩まされているんだ。その状況を何とかしたいと思った中村さんは、苦肉の策としてこの方法を思いついたんじゃないかな」
言われてみれば、と思い返す。確かに取材の際、中村は不自然なほど協力的だった。まるで、記事になるのを待ちわびているかのように。澪は推理を続けた。
「おそらく最初は偶然だったはずさ。たまたま、棚にきちんと刺さっていなかった本が、深夜の工事の振動で落ちた。今まさに地下で長期にわたる工事が行われていることを知っている司書なら、その原因に気づくのは難しくない。しかし、真下の工事が通り過ぎていったあとならその可能性に気づくだろうか? そう考えたんだろう」
「でも先輩」はるかは首を傾げた。「もうすぐ近くに新駅ができて賑わうのに、わざわざオカルトネタで人を呼び寄せる必要なんてないんじゃ……」
「考えてみてほしい」
澪の声には、意外な重みが宿っていた。
「地下鉄の新駅が開通したらこの図書館はどうなる? 日中、絶え間なく電車が地下を通る。その振動や音は、少なからず響くはずだ」
「あ……」
「便利にはなるかもしれない。けれど、落ち着ける憩いの空間としての図書館は、決定的に失われる。ならばいっそのこと——騒々しい霊を呼び寄せ、それを売りにすることはできないか……。彼女はそう考えたのかもしれないね」
なるほど、と納得しつつも、はるかは少し憤慨せずにはいられなかった。
「でも、中村さんは図書司書なのに、故意に本を床に落とすなんて……職業倫理はどうなってるんですか」
すると澪は、不意にくすっと笑う。
「確かにね。でも私は、彼女にもある種の倫理観が備わっている気がするんだ」
そう言って、澪ははるかが撮った本棚の写真を指差した。
「この棚に『ポルターガイスト図版集』という写真集があるだろう? A4サイズの横倒しという変わった判型で、きちんと挿さないと本棚から飛び出してしまう。たぶん最初に偶然落ちたのは、この本だったんじゃないかな。ほら、テープで破れを修復した跡が見えるだろう?」
「なるほど……って、あれ?」はるかは写真を覗き込んだ。「それなら、その本を使えば良かったんじゃないですか? まさにポルターガイストのごとく落ちたわけですし」
「素直に考えれば当然そうなんだ。でも、彼女にはそれができない理由があった」
「理由って……?」
澪の顔に微笑みが広がる。
「この『ポルターガイスト図版集』はね、滅多に手に入らない稀覯本なんだよ。XX区では、この図書館にしか所蔵されていない。彼女はそれを考えて、使う本を変えたんだろう」
「それで『呪い大全』を?」
「その本、実は私も読んだことがあるんだけど」澪は少し顔をしかめた。「見かけは立派だが、ネット記事の切り貼りで構成された、粗製乱造本さ」
静かすぎるほど静かな休憩室で、はるかは考え込んだ。貴重な本は大切に守り、代わりに質の低い本を利用した中村司書。その選択には確かに、歪んではいるが一つの倫理が宿っていたのかもしれない。
「もちろん、これは私の想像にすぎない」
コーヒーを一口飲んだ澪の横顔に、オレンジ色の夕陽が差し込んでいた。図書館の外では、新たな駅の工事が粛々と進められているに違いない。やがてそれは、この街に賑わいをもたらすだろう。そして同時に、あの静かな図書館の在り方を永遠に変えてしまうのかもしれない。
その時、はるかの携帯電話が震えた。おそらく編集長からの催促メールだろう。彼女は溜息をつきながら、心霊図書館の記事をどう書こうか、考え始めていた。
いいなと思ったら応援しよう!