
青春小説|『彼女の味方』
<ChatGPTによる紹介文>
『彼女の味方』は、数学研究部(数研)という部活動を舞台にした青春小説です。数研は、一般的な数学部活動とは異なり、部活動の中心はゲームで遊ぶことで、特に「毛獣のジャングル」というゲームが話題になっています。
物語は、主人公の斉木が新入生歓迎会で部活動の紹介を行う場面から始まります。数研は、ゲームを通じて新しい仲間との絆を築くことを目指し、今年こそ女子部員を迎え入れたいという熱意が感じられます。
ーー中略
作品は、数研という変わった部活動の雰囲気や登場人物たちの成長と関係性の発展に焦点を当てており、学園生活や友情、恋愛をテーマにした青春小説として読者を惹きつけます。登場人物たちの人間味あふれる描写や、彼らが抱える心の葛藤に共感しながら、物語の展開に胸を躍らせることができるでしょう。『彼女の味方』は、読み手に感情豊かな青春の物語を提供する作品と言えます。
ーーChatGPT
◇
◇
◇
ここから本編がはじまります
『彼女の味方』
作:元樹伸

第一話 新入生
新入生歓迎会で部活動の紹介が始まり、数学研究部の代表を務めることになった僕は、体育館のステージに登壇して慣れない熱弁をふるった。
「みなさん、僕たちと一緒に毛獣のジャングルで遊びませんか? 数研に入れば学校に携帯ゲームを持ってきても先生に没収されません!」

数学研究部。すなわち数研と言えば、数学の知識を深めるアカデミックな部活だと思う人がいるだろう。
だけど本校の場合はだいぶ違っていて、放課後になると、みんなでゲームをして時間を潰すのが部活動の中心となっていた。さらに今の数研には女子部員が一人も在籍していなかった。だから今年こそ数研の華を獲得したい我が部は、この日のためにある作戦を練っていた。
「いいか、新歓は”毛獣のジャングル”を話題の中心にするんだ」
第二校舎にある狭い部室の中で、部長の安城がニヤリとして言った。
”毛獣のジャングル”は、巷で話題の携帯ゲーム機用のゲームソフトだ。毛獣というモンスターが住むジャングルで狩りや釣りを楽しみながら、通信機能を使って世界中の人と一緒に遊ぶことができる。登場するモンスターたちも個性的で可愛らしく、発売当初から女性ユーザーたちの心を掴んでいた。

「たしかにあれなら、女子受けがいい」
他の部員たちも頷いて安城に賛同した。数研の部員は、僕を含めて二年生の男子が五人。ちなみに三年の先輩は、受験にむけてすでに引退していた。
元々が倉庫だったこの部室には、換気扇どころか、小さい窓がひとつしかない。したがって運動部の着替え部屋のように、いつも男臭かった。だから繰り返しになるが、今年こそは女子部員を招き入れ、殺伐とした数研に潤いと癒しをもたらしたかったのである。
僕が壇上で”毛獣のジャングル”の名前を口にすると、整列していた一年生がざわつき始めた。手ごたえを感じたのか、舞台袖では安城がガッツポーズを決めている。だけど正直なところ、僕はこの程度の餌で女子の新入生が来てくれるとは思っていなかった。
「言っておくが、部活以外で使えば遠慮なく没収するからな」
体育館の隅にいた教頭先生がマイクを手にして断言した。ドスが効いたその声に恐れをなしたのか、騒いでいた新入生が瞬く間に鎮まり返る。

思わぬところからの営業妨害。どうやら本校の教頭先生は、ゲームで遊んでいるだけの数研に、あまり良い印象を持っていないようだった。
放課後になって部室に行くと、珍しく数研の部員が全員集まっていた。おそらくは、新しい女子部員が集まることを期待して待っているのだろう。
「教頭のせいで新入生が怖がっていたじゃないか。あれじゃ逆効果だ」
部室に入って開口一番に文句を言った。けれど安城は、鞄から携帯ゲーム機を取り出す僕を見てニヤリとした。
「そう言う斉木も期待しているんだろ。その”毛ジャン”が何よりの証拠だ」
「悪いけどこれ、”毛ジャン”じゃないから」
”毛ジャン”とは、”毛獣のジャングル”の略称だ。でも僕がこの時に遊んでいたのは別のゲームソフトで、彼の発言は完全に的外れだった。
「だったら早く買えよ。さもないと女子部員が来た時に後悔するぞ」
そんなことはわかっている。だけどお小遣いがなかった。少なくともこれから数ケ月間は無駄遣いを控えてコツコツとお金を貯めない限り、新しいゲームを買う余裕などなかったのである。
「いくら待っても、女子の新入部員なんて来やしないさ」
憎まれ口を叩きながら、やりかけのゲームを再開した。するとその時、部室のドアがギギィッと軋みながら開いて、女子生徒が顔を覗かせた。
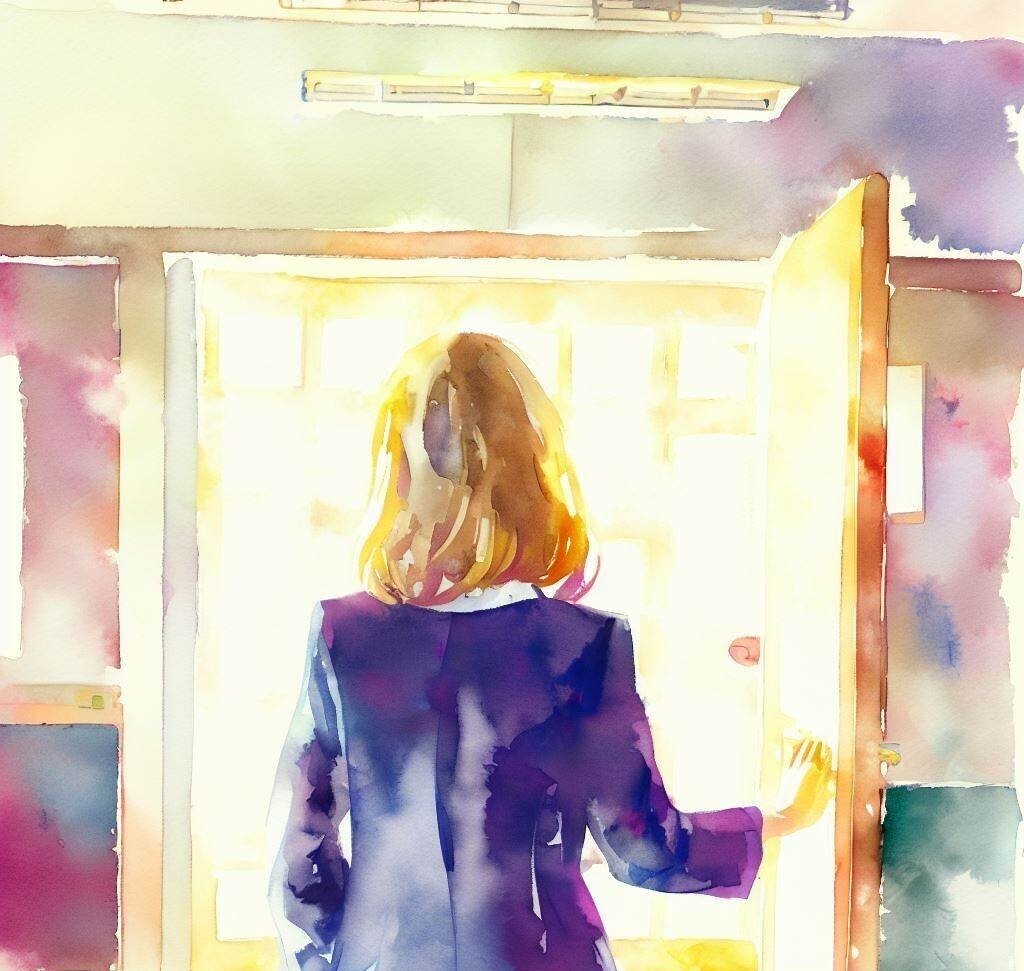
「あ……新入生歓迎会で登壇していた先輩ですよね。えっと、ここが数学研究部で合ってますか?」
女子生徒はドアの近くにいた僕にむかって尋ねた。少し大きめの制服に着せられたような姿が初々しく見えた。
「ゲームが好きで入部しました。私と一緒に”毛ジャン”で遊んでください」
入部希望の新入生の名は松田郁子。人を魅了する丸っこい顔立ち。アヒル口でぷっくりとした愛嬌のある唇。肩まである艶やかな黒髪。松田さんの自己紹介に男子部員たちが色めき立ち、僕は“毛ジャン”を買っていなかったことをすでに後悔していた。
第二話 気まずい出来事
どうせ松田さんはすぐに飽きて、数研をやめてしまうだろう。
僕を含めた部員たちのそんな予想を裏切り、彼女は入部から三ヶ月経った今も数研に通い続けていた。ただ部室に染み付いた臭いはどうしても慣れないらしく、来るとすぐに窓を開けるのが彼女の日課になっていた。
だから七月に入って冷房で窓を閉め切るようになると、数研の部室は松田さんにとって過酷な環境になりつつあった。
男子部員たちは、「ここが臭くて松田さんがそのうち来なくなるのではないか」という不安から毎日窓を開け放つようになり、数研はさながらサウナ風呂のような蒸し暑さに蝕まれていた。

そして天気予報が「今年一番の暑さ」と告げたその日。松田さんはいつも通りみんなと”毛ジャン”を楽しんでいた。だけど僕は今でも彼女たちの仲間に入ることができず、部屋の片隅で別のゲームをして時間を潰していた。
松田さんは以前から「斉木先輩はやらないんですか?」と、僕を”毛ジャン”に誘ってくれていた。だけどプライドが邪魔をして買えないことを正直に打ち明けられず、「興味がないんだ」と意地を張ってしまったのである。
そのせいで僕は、この時すでに”毛ジャン”を持っていたにも関わらず本当のことが言えないまま、松田さんとの接点を完全に失っていた。
室温は三十度を越していて、頭から汗が滴り落ちて目に沁みた。集中力が切れて賑やかな方を見てみると、松田さんに驚くべき異変が起きていた。なんと彼女のブラウスが汗ばんだ肌に貼りついてしまい、その奥の青い下着がうっすらと透けて見えていたのである。

見てはいけないものを見てしまった罪悪感。僕はすぐに彼女の胸から視線を逸らした。だけど本人はその事態に気づいてないようで、このままだとあの禁断のシルエットが部員たちの目に晒されるのは時間の問題に思えた。
「松田さん、ちょっといい?」
思いきって声をかけると、松田さんはゲームを中断して顔をあげた。
「何ですか?」
「悪いんだけど……少し外で話せないかな?」
伝えるべきか迷ったけど、知ってしまった以上は黙っておけないと、僕は彼女を廊下に連れ出した。

「廊下の方が涼しいですね。お話って何ですか?」
切り出し方がわからず、単刀直入に事実を伝えることにした。
「じつはその……君の下着がシャツから透けて見えてるっていうか……」
「はい?」
彼女は凍りついたような表情で自分の胸元を確認するやいなや、透けた下着の部分を両腕でさっと覆い隠した。
「こ、これっていつから?」
「気がついたのは、ついさっきだけど……」
「あ、あの……わざわざ教えてくれて、ありがとうございました!」
彼女はしどろもどろになって頭を下げると、逃げるように去って行った。
その日以降、僕たちは気まずいまま一言も交わさずに数週間が過ぎ去り、世の中は長い夏休みへと突入した。
第三話 駅にて
八月。夏休みが来て猛暑真っ只中になっても、数研は週に二日のペースで活動を続けていた。
部活終わりの帰り道、田舎駅で電車を待つ僕の隣に松田さんが立った。その間隔、およそ五十センチ。部活中はずっと部屋の隅でゲームをしていたので、彼女とこんなに接近したのはあの日以来だった。
「斉木先輩も下り方面の電車ですか?」
「あ、うん」
「こうして同じ電車に乗るのははじめてですね」
「そういえば、初めてかもね」
松田さんが自分から話しかけてくれた。ただそれだけのことが嬉しくて、目頭が熱くなった。

その後はお互い沈黙のまま、電車が来るまではしばらく時間があった。僕は緊張で喉がカラカラになり、自動販売機で飲み物を買うことにした。
「奢るよ」
仲直りの印に何かしたくて、自販機の前から松田さんに声をかけた。
「ありがとうございます。でもさっき買ったばかりなので」
彼女が鞄から飲みかけのペットボトルを出して見せた。中身は珍しいスイカ味のソーダ。きっと夏限定の商品だろう。
「果汁ゼロパーセントなのに皮の香りまで再現されているんですよ。よかったら先輩も飲んでみませんか?」
松田さんが水滴のついたペットボトルを差し出した。だけどそれをもらって飲むということは、彼女と間接キスをすることに他ならなかった。

「本当にいいの?」
後ろめたさが手伝って、余計な一言が口をついた。案の定、「先輩がイヤじゃなければですけど」と彼女が畏まってしまったので、これはマズイと思った僕は覚悟を決めた。
「じゃあ、お言葉に甘えていただきます!」
松田さんが差し出したソーダは本当にスイカの皮の味がして、同時に彼女の唇を想起させるような不思議な口当たりがした。
やがて電車が到着し、先に松田さんが乗り込んだ。彼女がふり返ると同時にドアが閉まって、電車はホームにいる僕を残して動き出した。

「斉木先輩?」
電車の中から松田さんの声がかすかに聞こえた。けれど僕は夢見心地のまま、電車が見えなくなっても、ただその場に茫然と立ちつくしていた。
第四話 出馬宣言
夏休みが終わり、移動教室にむかう途中の廊下で松田さんを見かけた。彼女は他の男子と一緒にいて、すれ違いざまにそれが二年の平多勝だとわかった。
平多は別のクラスだけど、同学年では有名な男子だ。剣道部で全国大会に出場した経験があり、しかもハンサムで女子に人気があった。次の生徒会選挙では生徒会長として立候補するという噂もあり、僕にとっては別次元レベルの存在といえた。
平多は松田さんと楽しそうに話していた。剣道部のエリートと女神の松田さん。どんな共通点があるのか知らないけど、とてもお似合いのカップルに見えた。
あくる日、朝の当番でいつもより早い電車に乗りこむと、同じ車両に松田さんがいた。

彼女は老人に席を譲ろうとしているところだった。しかし老人は「大丈夫ですから」と断っていた。近くにいた学生たちがその様子を見て、「断られてるし」「余計なお世話じゃね?」とコソコソ話しているのが聞こえた。
ふたたび座るタイミングを失ったのか、松田さんは吊り革に掴まっていた。僕はその姿を見て、彼女はあまり器用な性格ではないのかもしれないと思った。
「松田さん、おはよう」
思いきって声をかけるとむこうも気がついて、「おはようございます」と笑顔で答えてくれた。
「いつもこの時間に乗ってるの?」
「はい。でも生徒会に入ったら今より早くなるのかな」
「生徒会って?」
「じつは次の生徒会選挙で書記に立候補したいと思っているんです」
「選挙に出るって、松田さんが?」
突然舞い込んだ松田さんの出馬宣言。この出来事は数研にとって一大事といえた。

安城は彼女を数研の次期部長にしたがっている。だけどこの学校では、生徒会員が部長を兼任することができない。だから彼女が生徒会に入った場合、松田さん以外に一年生がいない数研は部長候補を失うことになる。
つまり来年度に新入生が来なければ、数学研究部は廃部に追い込まれる運命だったのである。
間もなく生徒会委員選挙の受付が始まり、松田さんは安城に要望書を提出した。
「書記に当選したら、数研と生徒会をかけ持ちさせてください」
「待てよ。松田が生徒会に入ったら誰が数研の部長になるんだ?」
「来年は新入生が入ってきます。私が呼び込みするので大丈夫です」
「俺はずっと松田が部長になるものだと信じていたんだぞ?」
「そ、それはちょっと……」
安城が反対の姿勢を貫き、松田さんの声が小さくなった。
「選挙に出るのは彼女の自由だろ?」
僕は心配になって、彼女の後ろから援護射撃をした。
「じゃあ新入生が来なかったらどうすんだよ?」
「廃部さ。それとも松田さんだけで数研続けろっていうのか?」
「誰もそんなこと言ってないだろうが!」
「でもそういうことになるじゃないか!」

「二人ともやめてください!」
僕と部長の言い争いを見かねたのか、松田さんが間に入って叫んだ。
「急にこんなことをお願いした私が悪いんです。少し考えたいので時間をください」
彼女が頭を下げて出て行くと、安城の不満が爆発した。
「松田が生徒会に入ったら数研に来なくなるぞ?」
「どうしてそんなことが言いきれるんだよ?」
「次の生徒会長は平多だ。きっと松田はあのイケメンに篭絡されて、こんな野郎臭い部室になんか寄りつかなくなるに決まってんじゃねぇか!」
安城の発言は自虐的だったけど、平多の件に関しては否定できなかった。それでも僕は安城を説得したくて、最終手段に打って出た。
「でも松田さんは立候補できないなら、数研をやめるって言ってたぞ」
「ちょっと待て、嘘だろ?」
もちろん嘘だ。松田さんがそんなことを言うわけがない。だけど彼女の意思がそれだけ固いと知れば、安城もこれ以上の反対はできないと思った。だから後で自分が大嘘つきの悪者になってでも、今ここで彼を説き伏せるつもりだった。
「選挙前に松田さんを失うことになる。それでもいいのか?」
「そんな殺生な……」
案の定、部長の心がポキリと折れる音が聞こえた。
「それに彼女の生徒会入りは、デメリットだけじゃないと思うんだ」
「なんでだよ?」
「生徒会に数研のスパイが侵入したと思えば、来年度の部活動予算を融通してもらえるかもしれないじゃないか」
口からのでまかせにふさわしく、悪代官のようにニヤリとしてみせた。

「なら気持ちよく彼女を送り出して、選挙を応援してあげなきゃだな」
「部長、理解してくれてありがとう」
「ふん、こんなときだけ部長呼ばわりしやがって」
見え透いた嘘をついてでも松田さんを庇う。そんな僕を相手にこれ以上の議論は無駄と感じたのか、安城が死んだ魚のような目で捨て台詞を吐いた。
下校中、改札をくぐって駅のホームに出ると、線路を挟んだむこう側に松田さんと平多の姿が見えた。
松田さんが部室を出たのは一時間以上も前のこと。ということはずっとその間、彼女は平多と一緒だったのだろうか。以前から二人の関係が気になっていたので、肩を並べているあの姿を見ただけで、胃のあたりがキリキリと痛くなった。
ガタンゴトン、ガタンゴトン……。
松田さんがいるホームに電車が入ってくるのが見えた。このままだと彼女は平多と一緒に乗って行ってしまうだろう。

今から向かっても間に合わないかもしれない。それでも部長を説得したことを伝えたくて駆けだしていた。案の定、階段を下って反対側のホームに着くと、電車はすでに走り去った後だった。
「くそっ」
間に合わなかったのは運動不足だけのせいじゃない。平多が一緒にいたので、ふてくされて躊躇した自分がどこかにいたのだ。
とにかく悶々としていた。地面を睨んだまま肩で息をしていると、人影が僕の前に立った。
「お疲れさまです。私に用があった、で合ってますか?」
見上げると目の前に松田さんがいた。
「はい……君に用がありました」
「なら電車に乗らなくてよかったです」
「松田さん……待っててくれて、ありがとう」
サラサラサラ……。
涼やかな風がホームを駆けぬけた。火照った身体の熱が冷めていくのを感じながら、僕は勝ち取ったばかりの朗報を彼女に報告した。
第五話 生徒会選挙
十一月。
寒い冬が訪れ、生徒会の役員を決める選挙戦が始まった。生徒会長の候補者リストには予想通り平多勝の名前もあり、僕の心はざわついていた。
書記に立候補した松田さんは、数研の後押しを受けて選挙活動を展開し、まずまずの予想票を集めていた。一方の僕は彼女からのご指名で、生徒会選挙演説で行われる質疑応答の質疑役を任されていた。

質疑応答は、立候補者が有権者の質問や疑問に回答して、いかに自分が有能であるかをアピールする場である。しかしほとんどの生徒は選挙に興味がなく、質疑をとったところで誰も手を挙げない。そこで質問者は立候補者の方で事前に決めておくのが通例となっていた。
「斉木先輩、くれぐれも質問の内容を間違えないようにお願いしますね」
荷が重すぎて不安だらけだけど、「新歓の時の先輩、すごくかっこよかったです」と言ってくれた松田さんの頼みとなれば、断れるはずがなかった。
「では書記候補の松田郁子さんに対する質疑応答を行います。疑問やご意見のある方は挙手をお願いします」
司会進行役の三年生が、こちらにアイコンタクトを送りながらアナウンスした。予定通りに手を挙げて当てられたので、予め用意していた原稿を読み始めた。
演説の質問や疑問なのに原稿があるなんておかしな話だが、周りの生徒は誰も気にしていない。それに日本の国会も似たことをしていると聞いたので、とちるよりはましだと思った。

ただこの日、僕は季節の変わり目で風邪を引いており、止まらない鼻水に苦しんでいた。だから原稿を読む最中にズズッと鼻を啜る音もマイクが拾ってしまい、聞いていた生徒たちがこぞって笑い出した。それでも鼻水は容赦なく垂れ続け、松田さんの重要なプレゼンの場を笑いの渦に巻き込んだ。
「えっと、ただいまの質問に対する回答ですが……」
グダグダな質疑が終わって松田さんが答えようとした時、「それよりよく効く風邪薬を教えてやれよ!」と野次が飛んで、体育館にふたたび笑いが起こった。
選挙演説が終わった後、「風邪なんですから仕方ないですよ」と松田さんは優しい言葉をかけてくれたけど、僕は彼女に合わせる顔がなかった。
「斉木くん、ちょっといいかな」
落胆して教室に戻ろうとした時、選挙演説も質疑応答も威風堂々とこなした平多に呼び止められた。
「何だよ?」
「今日の質疑応答だけど。あれじゃ松田くんが可哀想じゃないか」
初めて話す平多の第一声は、僕へのクレームだった。
「風邪だったんだから仕方ないだろ」
もちろん悪いとは思っているけど、彼と楽しそうに話していた松田さんの姿を思い出すと無性に腹が立って、素直になれなかった。
「とにかく選挙はまだ続くんだ。彼女の足を引っ張るような真似は止めて欲しい。用はそれだけだよ」
平多がいなくなってすぐにクラスの女子たちが寄って来て、「斉木くんって彼と仲がいいの?」と興味津々の様子で聞いてきた。
「ぜんぜんよくないけど」
きっぱりそう否定した後も、彼女たちは平多の情報を根掘り葉掘り聞き出そうとしてきた。だから僕はうんざりした気分で「後輩の子と付き合っているみたいだよ」とだけ答えて、早々にその場から立ち去った。

最終話 彼女の味方
激しい選挙戦の末、松田さんは書記に当選した。平多も生徒会長に選ばれて、ここに新しい生徒会が発足した。
「もうダメだ。松田は生徒会に奪われちまった」
安城の心配が的中して、松田さんが数研に顔を出す機会は少しずつ減っていった。他の部員たちもそんな状況に白けてしまったのか、最近も毎日部室に来るのは、僕と安城の二人だけになっていた。
今になって考えてみれば、僕があの選挙戦でしていたことは、松田さんと平多を生徒会という愛の巣に送り込む手助けだったのかもしれない。そう思うとむなしくなった。
「おい、ここは剣道部の着替え部屋より臭いな」
ある日、ひとりで部室にいると平多がやって来て、僕の顔を見るなり文句を言った。
「部長ならいませんけど。生徒会長がこんな所になんの用ですか?」
失礼な登場の仕方にカチンときて冷たくあしらったけど、彼は気に留める様子もなく椅子に座って、目の前のパソコン画面を覗き込んだ。
「数研の機材はこの程度のスペックなのか。これなら生徒会の方が快適にゲームを楽しめるんじゃないかな」
彼とは住む世界が違うのは承知していたものの、話せば話すほどイヤな奴のように思えた。
「何しにきたんだよ?」
「じつはね、松田くんが数研をやめたいらしいんだ」
「なんだって?」
彼の爆弾発言に驚きを隠せなかった。平多は満足そうな笑顔を浮かべてこう続けた。
「ところが彼女には君に選挙戦を一緒に戦ってもらった恩義があって、たったそれだけのことを言い出せないらしい。でも実際のところ、君は彼女の足を引っ張っていただけだろ? だからそんなことを気にするのは馬鹿げていると思うんだ。それで是非、君から彼女に直接言って欲しいのさ。今すぐ数研をやめて生徒会に集中した方がいいってね」

ショックで言葉が出ない。僕が彼女の足を引っ張ったのは事実だけど、数研をやめたがっているなんて知らなかったからだ。
「それに気づいてないみたいだから教えるけど、もう松田くんは生徒会のものだ。いつまでも数研の部員だと思って気安くしないで欲しいな」
平多が椅子にふんぞり返って偉そうな態度で言い放った。すると、うしろでドアの開く音がした。
「平多先輩、ここで何をしてるんですか?」
振り返って見た先には、松田さんが立っていた。
「君こそ何でこんなところに?」
平多が聞き返すと松田さんは「数研の部員だからです」と答えた。僕は堪らず二人の間に割り込んで、「数研をやめたいって本当なの?」と彼女に詰め寄った。
「そんなわけないじゃないですか。それと平多先輩。廊下まで聞こえてましたけど、私は生徒会の持ち物じゃありませんから」
――もう松田くんは生徒会のものだ。
あの暴言を聞かれて居心地が悪くなったのか、平多はバツが悪そうに彼女から視線を逸らした。
「斉木先輩、行きましょう」
松田さんは怒ったまま僕の手を掴むと、部室の外へと連れ出した。
黄昏時。僕たちは駅のホームのベンチに座っていた。
「冷めないうちに食べて」
「ありがとうございます」
何も考えずに隣同士で腰かけてしまったものの、女の子とこんな風に座るのは初めてだったので、僕はすっかり緊張していた。

「無理やり連れ出した上に、御馳走になっちゃって。すみませんでした」
彼女はため息をつき、コンビニの肉まんを口に運んだ。
「せめてもの罪滅ぼしだよ。選挙で君の足を引っ張っちゃったからね」
「そんな。先輩にはたくさん協力してもらってすごく感謝しています」
「選挙の質疑応答で鼻水を垂らしていたのに?」
過去の失敗を話したら、彼女はクスクスと笑った。
「あれでみんなに私の名前を覚えてもらえました。だから当選できたのは斉木先輩のおかげだと思います」
情けない先輩の自虐を優しく受け止めてくれる松田さん。そんな彼女だからこそ、数研と生徒会で奪い合いになったのだろう。僕だって本音を言えば、彼女を独り占めにしたかった。
「でも生徒会長は今も怒っているみたいだ。君と関わるなって言われたよ」
「ごめんなさい。平多先輩が数研に押しかけたのは私のせいなんです」
「どういうこと?」
「じつは昨日、平多先輩に生徒会活動の妨げになるから数研をやめるように言われてしまって。断っても納得してもらえなかったので、つい斉木先輩のお世話になっているからやめられないって口走っちゃったんです」
なるほど、そんなことがあったのか。でも松田さんが数研をやめたいと思っていないなら、僕が彼になんと思われようと問題はなかった。

「それで松田さんは、これからどうしたいの?」
さっきまでコーヒーが入っていた紙コップを見つめたまま、僕は聞いた。
「生徒会は忙しいけど、私は数研を諦めたくないです。ただこのままだと皆さんに迷惑をかけてしまう気がして。やっぱり両方続けるのは無理なんでしょうか」
食べかけの肉まんを見つめたまま、松田さんが弱音を吐いた。僕は彼女のことを励ましたくて、今思っていることを口にすることにした。
「僕は君がどんな結論を出したとしても応援するよ。だから自分の思う通りにやってみたらいいんじゃないかな」
もちろん数研をやめて欲しくないけど、もし彼女がそれを選んだとしても支持するつもりだった。僕は結局、松田さんにどんな事情があったとしても、最後まで彼女の味方でいたかった。
「やっぱり先輩は優しいですね。あ~あ、またみんなと一緒に”毛ジャン”したいな」
松田さんが悔しそうに夜空を見上げて呟いた。
「数研に来ればいつだってできるさ。それとね」
僕は上着のポケットからゲーム機をとり出して電源を入れた。液晶モニターに”毛ジャン”のタイトル画面が表示されるのを見て、松田さんが言った。
「先輩も”毛ジャン”持ってたんですか?」
「うん。だからまたみんなと遊ぶ時は、僕も仲間に入れてくれないかな。本当は前から一緒に遊びたかったんだ」
「だったら今から始めませんか?」
「えっ、ここで?」
「はい。いつでも正々堂々とゲームできちゃうのが数研の特権ですから」
笑顔で自分のゲーム機を取り出す松田さん。教頭先生がこの状況を部活として認めてくれるかは疑問だったけど、僕は素直に彼女の提案を受け入れることにした。

暗闇の中にもうひとつのゲーム画面が浮かび上がり、僕たちは同時にスタートボタンを押して”毛ジャン”を始めた。
「寒っ……」
やがて闇と共に訪れた冬の冷気が辺りを包み、二人はどちらともなく寄り添った。そしてやってくる電車の明かりの帯を何本も見送りながら、数研の特権を心ゆくまで楽しんだ。
おわり
最後まで読んで頂きまして、ありがとうございました。

