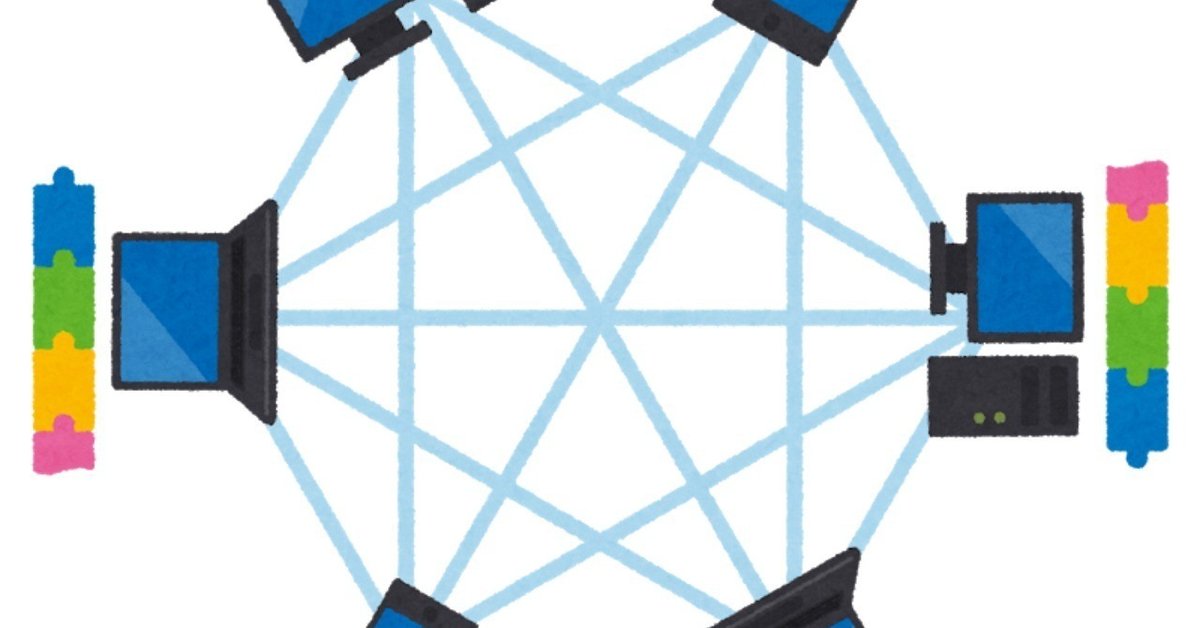
日本発のブロックチェーンアプリを殺しかけているのは誰か?
日本発のWeb検索エンジンを殺したのは誰か?
まず外堀から埋めていきます。
上に引用したツイートのような言説は、よく言われていることと思います。
しかしながら、実際のところ、史実は異なります。日本発のWeb検索エンジンは1990 年代中盤には複数存在し、Google は後発です。むしろ経営的・技術的な判断ミスで、日本発の検索エンジンは衰退していったと考えるのが順当でしょう。
...
ところで、なぜ「著作権法のせいで日本発のWeb検索エンジン立ち上がらなかった」という、史実と異なる話になっているのでしょうか。専門家による、興味深いツイートがあります。
行政がどうこうしたのではなくて、一介の弁護士から話がねじ曲がってしまった、その可能性が指摘されています。
...
関連して、2009 年著作権法改正に関与した方によるツイートも、興味深いものがあります。
法律は絶対ではなく、社会的に有益なものであれば適法にするだけの柔軟さも持ち合わせているわけです。そのために国会はあるわけですし。
また、法(というか法解釈の揺れ)が、サービス提供に対して萎縮効果をもたらしうることが示唆されています。
...
ここまでは、識者の軒先を借りてきました。ここから先は、当業者BOTの中の人の記憶に基づく私見です。
2009年改正著作権法が成立する前にも、日本発のWeb検索エンジンは存在したものの、改正が必要だと法曹のプロが判断する程度にはグレーな要素は存在し、…本稿において、ここが大事なのですが…、「グレーだからダメだいつか規制がかかる」「法改正を前に事業を続けるのはコンプライアンス的にどうなのか」と執拗に主張し続ける論者が居たように思います。いわゆるノイジー・マイノリティ、ってやつです。
失敗の本質は技術力や経営力の無さだと、認めるとして。背中から弾を打ってくる日本国内のノイジー・マイノリティが、検索エンジン技術者や経営層に何らの影響も与えなかったというのは、おそらく誤りでしょう。
日本発のブロックチェーンアプリを殺しかけているのは誰か?
さて、本題。
仮想通貨交換業以外のブロックチェーン・アプリケーションの開発者にとって、資金決済法は、技術的諸問題が理解されないまま作られた「悪法」かもしれません。
ただし、合法なアプリケーションを一切作れないかというとそうでもなさそうです。既に、前払式支払手段という合法な手を使った、LCNEM が登場しています。Monaparty も資金決済法に沿えるプラットフォームとしての、機能拡張が予定されています。
一方で、「現行法の下では、ブロックチェーン・アプリケーションは実質作れない」という悲観論に暮れる方々もいらっしゃるようです。中には法曹関係者も。単に悲観するだけでなく「あらゆるトークン発行は ICO に相当するから、登録仮想通貨交換業と手を組め」と迫ったりとか。
...
日本発のWeb検索エンジンが実質死に絶えた理由は、おそらく複合的な要因でした。技術の問題、経営の問題、そしてコンプライアンスの問題。コンプライアンスを盾に諸々を捻じ曲げる方々の存在。
日本の暗号通貨界隈は、自国のブロックチェーン・アプリケーションに対し、Web 検索エンジンの轍を踏ませるのでしょうか。
当業者BOTのなかのひとには、既に踏ませかけているように見えています。
