
【CREAMコラム 第3回】下北沢モラトリアム
初回ぶりです。タマです。
CREAMの最寄駅である下北沢駅。
近々どうやら駅前にロータリーができるそうです。
路線バスも乗り入れるとの話で、これでやっと「下北沢駅前」のバス停がホントの"駅前"に。

かつての駅前は線路と踏切のだいぶ大きな存在感で、クラブスタッフ時代は外販に苦戦した思い出があります。
南口を出ると駅に沿ってTSUTAYAとドトールがあり、小田急線で通学していた大学生時代にはよく利用したものです。先ほどTSUTAYAがなくなったのが18年前と知って震えましたけど。

小田急線と井の頭線の私鉄が二路線、それも新宿・渋谷という大繁華街へ数分で繋がるという利便性。
一方で、先述の踏切問題とともに主要幹線道路から置き去りに取り囲む細い路地という不自由さ。
1960~70年代の下宿屋が転じた一人暮らし向けアパートの発生という地域性も相まって、「若者の街」さらには「音楽・演劇の街」になっていったそう。諸説あり。

私見ながら、「若者の街」「音楽・演劇の街」に感じられる懐の深さというか心の広さというか、興味深くも雑な部分がこの街らしさであり魅力なのかな、と思っています。
そして、なんとなく近代化にしばらく取り残されていたこれを「モラトリアム」という表現をしている本がありまして、たまたま流し読んだことがあったので今回改めてKindleで購入して流し読みしてます。
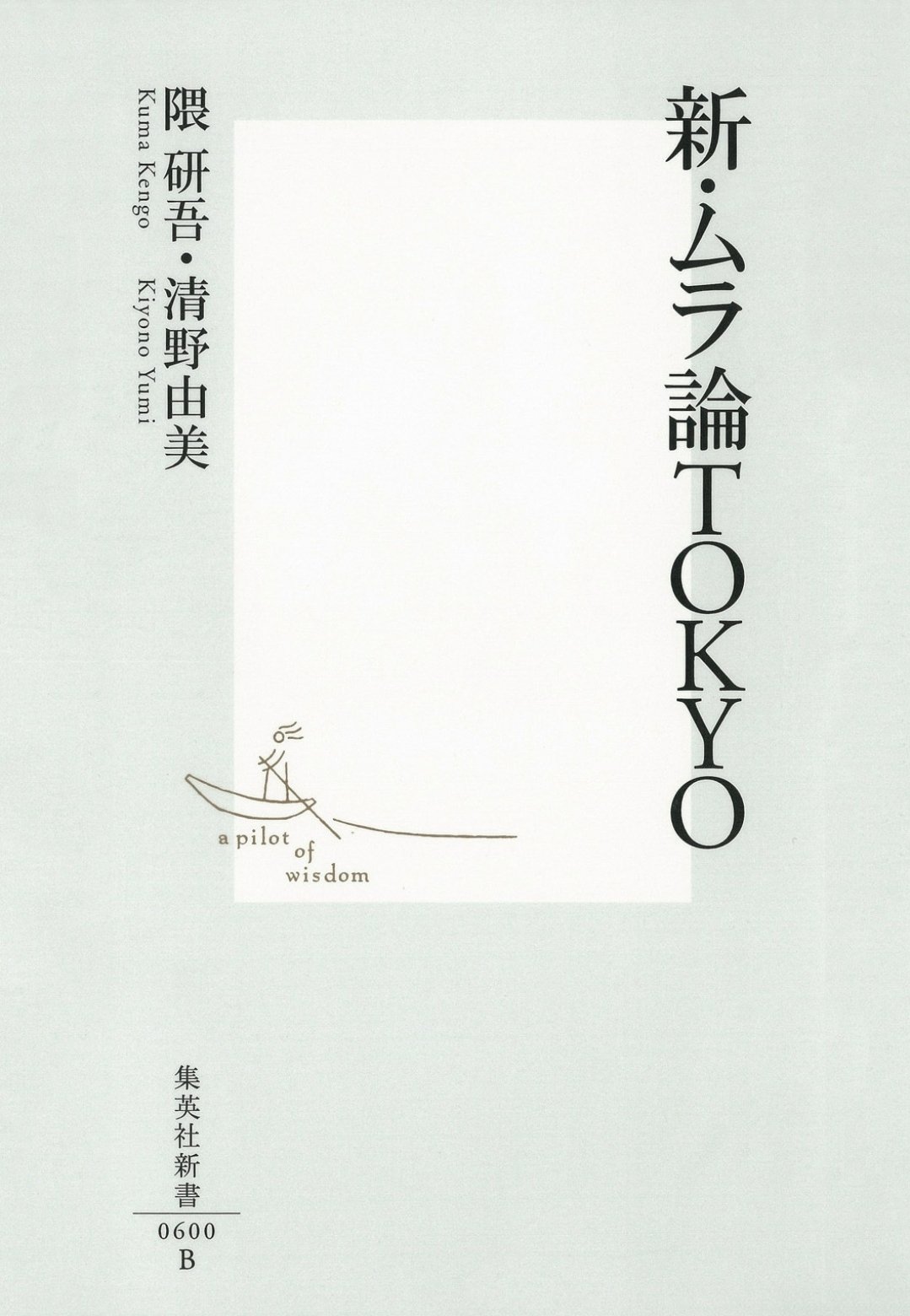
こちらは隈研吾さんによる建築家の観点からの、都市以前の「村」と都市以後の「ムラ」=その場所と密着した暮らしがある場所をそう呼んでおり… という具合の地域経済学とか好きだったら絶対おもしろい本なのでご興味あればぜひ。
話を戻して。
そんな「若者の街」に進みつつある"都市計画"は、踏切の消失や駅前ロータリーの出現など日常のあちらこちらに感じ取ることができ、懐古主義者ならずとも惜しむ声をたまに耳にします。
まさに「モラトリアム」とその終焉、みたいな状態に感じたのですよね。私は。全く卑屈なニュアンスはなく。
---
モラトリアム (moratorium)とは、一時的な猶予や一時停止、猶予期間を意味する言葉です。金融や心理学などの分野で用いられます。
---AIによる。
とりわけ心理学における「大人の領域に踏み込めずにうろうろしている状態」を指してネガティブな意味で使われることが多いのですが、先の本にも『すべての創造はモラトリアムから出発する。』とありますからね。
そして更に思うのです。
モラトリアムが終わりを迎えつつある下北沢で、遺されたモラトリアムの居場所になり得るのは、CREAMなのではないか?と。諸説あり。

嘘か真か?モラトリアムとは?
CREAMは今年2月に5周年を迎えます。
未体験の方はぜひ一度その目で確かめにいらしてください。
