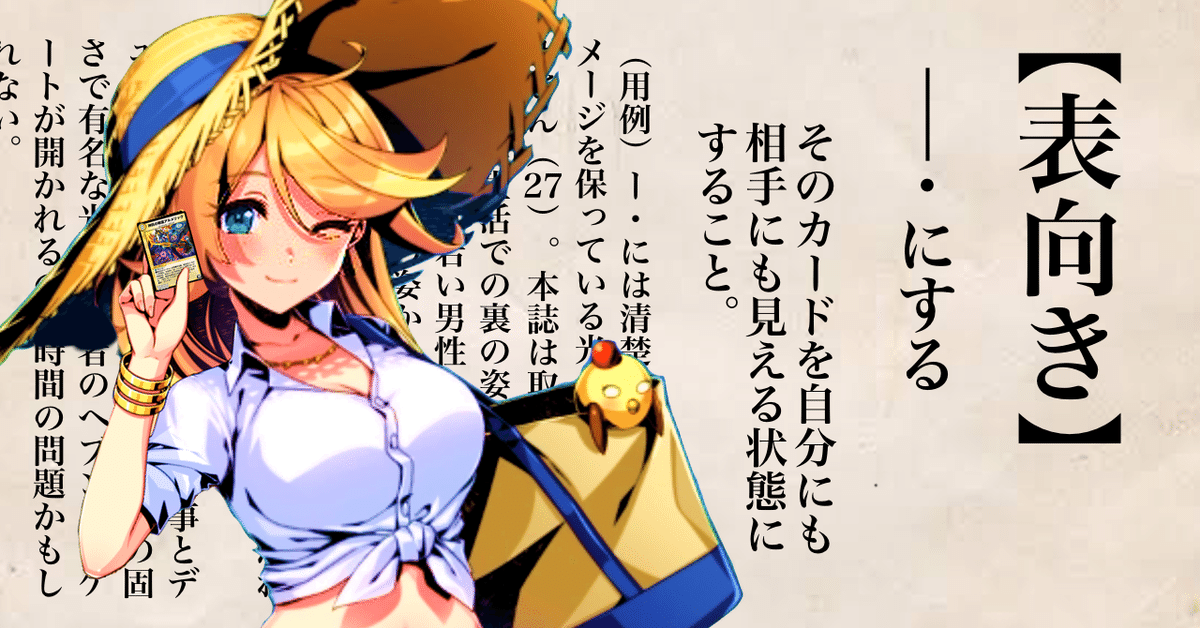
【デュエプレ】なんで見せる必要があるんですか?【表向き】
『バルカディアス・チャージャー』 というデュエプレオリジナルカードがあります。

筆者はエンジェルコマンド推しなので、このカードの実装が発表されたときは、それはもうウキウキでした。
が、実際に使ってみた結果、思ったよりイマイチということが判明。
というのも、
多色チャージャー特有の不器用さ
ドローが条件付きで不安定
デッキ構築に縛りがかかる
などなど、マイナスポイントが多かったためです。
似たようなドロー効果を持つチャージャー呪文には、1コスト高いブレインチャージャーがあります。こちらのほうが遥かに使いやすく、また汎用性
があります。上にあげたマイナスポイントの全てをブレイン・チャージャーは持っていませんからね。
さらにもう一つ、ブレイン・チャージャーに無く、バルカディアスチャージャーだけが持っているマイナス効果があります。
それは、カードを表向きにすること。バルカディアス・チャージャーで引いたカードの内容は、相手に公開されます。
なんで表向きにする必要があるんですか?
今回はこの『表向き』について深堀りしつつ、ついでにバルカディアス・チャージャーの悪いところ、バカチャ加減についても語り尽くしたいと思います。
※先日のDEVIL DIABOLUS ZETA CUPにて、バルカディアス・チャージャーを採用し、最終100位に残った方の構築解説記事がこちら。
バルカディアス・チャージャーが環境一線級のデッキに採用され得ることが証明されました。こちらの記事も要チェック!
『表向き』にする必要性
表向きにするカードといえば数多くありますが、代表的なのはこちらではないでしょうか。

紅神龍バルガゲイザーです。
山札の上から1枚をめくり、それがドラゴンであれば無条件で場に出すことができます。
ここでバルガゲイザーを例に出して主張したいのは、紙版と違いDCG(デジタル版)のデュエプレでは、カードを表向きにする必要性が無いのではないか、ということです。
紙版デュエル・マスターズは、基本的には第三者による審判を必要としないゲームです。対戦しているプレイヤー同士が、ルールに従い、互いに処理の確認を行いながら進めていきます。
バルガゲイザーを使うときも、めくったカードを表にすることで、そのカードがドラゴンかどうかを両者が確認した上でゲームが進行します。
丁寧に描写するなら、
プレイヤーA「バルガゲイザーで攻撃します」
プレイヤーA「山札から1枚目をめくります」
プレイヤーA「う〜んこれはドラゴン!w」
プレイヤーB「たしかにドラゴン!w」
プレイヤーA「ドラゴンなので、バトルゾーンに出します」
とまあこんな感じに、両者確認のもとでゲームを進めていく必要があります。だからカードを表向きにする必要があったんですね。
一方で、DCGであるデュエプレでは、プレイヤーに代わってシステムがカードの処理を全て実行してくれます。上のように表現するなら、
プレイヤーA「バルカガイザーで攻撃します」
システム「山札の上から表向きにします」
システム「う〜んこれはドラゴンじゃない!w」
システム「墓地に送ります」
こんな感じ。攻撃することを決めて以降、そこからプレイヤーが介入する余地はありません。
極端な話、プレイヤーAとプレイヤーBがともにカードが表向きになったシーンを見逃したとしても、何事もなくゲームは進みます。
つまり、紙版にはあった『カードを表向きにし、プレイヤー同士が互いにカードの内容を確認するという過程』の必要性が、システムの存在によって失われています。
では、表向きにするという処理が完全に意味のないものなのか?ということについて考えていきます。
バルガゲイザーの能力は、それがドラゴンであればバトルゾーンへ、そうでない場合は墓地に送られます。
バトルゾーンも墓地も、双方のプレイヤーが常に確認できるゾーン(公開領域)です。バルガゲイザーの場合は、能力が発動後、成功失敗を問わずカードの内容が露わになります。
一連の処理の終了時には、必ずカードの内容が相手の知るところになるため、バルガゲイザーに関しては山札の上から1枚目を表向きにする行為に意味はありません。テキストからまるまる一文抜いても問題ないと思われます。
(でもめくるときに特殊演出あるし、あとあのドキドキ感がいいんだよな…)
ここで話を戻して、バルカディアス・チャージャーの場合を考えます。
バルカディアス・チャージャーはバルガゲイザーと違い、カードを表向きにするという処理に対戦上での意味があります。
バルカディアス・チャージャーは、めくったカードがエンコマデモコマかどうかの判定に成功すれば手札に、失敗すれば山札の下に送られます。
手札、山札の下はどちらも非公開領域であり、カードを表向きにするという処理さえ無ければ、カードの内容を相手に知られることはありません。
表向きにするという行為によって、相手にカードの内容が知られる、というわけですね。
どうして表向きにするんですか?
表向きにすることで相手の納得感を得られますが、不正ができないのはシステム的に明らかのはず!
紙版からテキストまるまる持ってきたならまだしも、デュエプレのオリカでなんでこんなことをする必要があるんですか?
ここからは、同じような処理を行う他のカードと比較して考えていきましょう。
『表向き』の事例
筆者のバカチャ理想のテキストとしては、
山札の上から1枚目を見る。それがエンジェル・コマンド、もしくはデーモンコマンドであれば手札に加え、そうでなければ山札の一番下に置く。
こんな感じです。
チャージャー呪文ということもあって、百歩譲って他の効果は据え置きにしても、せめて『表向き』にはせず『自分だけが見る』ようにしたい。相手にカードを知られないようにしてほしい。
これを一般化すると、
山札の上から【n】枚を見る。それが【特定のカテゴリー】であれば【成功処理】、そうでなければ【失敗処理】。
こういう風に表現できます。これに該当するカードの例をカードリストから探してみます。
探した結果、ありませんでした(無能サイト風)。

似たような効果を持つアクア・ハルフォートも、最初にカードを表向きにします。
失敗の場合は公開領域(墓地)に晒し上げられますが、成功の場合は非公開領域(手札)に加えられます。ただし、一度表向きにしているため、行き先が非公開領域であってもカードの内容はバレています。

フェニコーラーは、めくった5枚全てを相手に見せた上で、1枚を手札に加えます。
成功の場合(手札)も失敗の場合(山札)も非公開領域行きですが、最初に表向きにしたことでやはりバレています。
(山札に戻した後にシャッフルするので、デッキの中の5枚を公開する以上の意味はないんですけども)
ということで、紙版デュエル・マスターズよろしく、デュエプレも『成功失敗を問う場合は相手の確認を要する』ということになっているみたいです。
見せなくていい代表例としては、スペース・クロウラーやオリジナル・ブレインなどです。

これらは、見たカードの中から手札に加えるカードを自由に選ぶというもので、成功失敗といった概念はありません。この場合はカードを見せなくてもよいみたいです。
じゃあバルカディアス・チャージャーも『成功失敗が問われるときは相手に確認を要する』の法則に従っていただけなのか…。
そういうもんだってことで、この記事は終わり…?
~ここまでで本記事の6割~
特殊な例
調べている最中に変なカード(能力)を見つけたので、それらも一応紹介しておきます。

ポジトロン・サインです。
山札から4枚を見て、Sトリガー呪文を唱える呪文です。
見た4枚のうち、唱えた呪文は、まあ唱えるわけなので相手にも公開されますが、唱えなかったカードは相手に公開することなく非公開領域(山札の下)に戻します。
バルカディアス・チャージャーらは必ず公開、オリジナルブレインらは全てのカードが必ず非公開のまま終わります。
一方でポジトロンサインは、成功(?)の場合のみ公開、失敗(?)の場合は非公開となります。
4枚のうちにSトリガー呪文があった場合に、それを唱えるかどうかは任意のため、失敗処理が行われたとしても、それが本当に失敗しているかは相手からはわかりません。
ちょっと珍しい処理だと思います。
次にランブルです。

俗にランブルクイズと呼ばれる覚醒の際の処理ですが、その過程が公開されないため、なにをやっているか相手からは一切わかりません。
これは、『成功失敗が問われるときは相手の確認を要する』の法則に反しています。
が、そもそもやってる本人さえ『選んだカードが本当に山札の一番下にあるカードなのか』の答え合わせをゲーム中で行うことができないため、これはノーカンとします。
あくまで『う〜んこれはドラゴン!w』のように、プレイヤーがゲーム中で成功したかどうか、自力で確認が取れるものだけに法則は当てはまるようです。
次に連鎖です。

連鎖は、成功すれば場に出し、失敗すれば山札の下に戻す、というギミックです。
失敗の場合は相手に見せずに山札の下に戻します。
は?
それ、相手に見せなくていいのか!?本当に失敗してるのかどうかわからなくない!?
『成功失敗が問われるときは相手の確認を要する』の法則はどうした。
なんだこれは…。
ちなみにこれ、一見すると紙版ならブチギレ案件のように思えます。クリーチャーを場に出したくないときに、連鎖が成功しているにも関わらずあえて失敗を主張し、連鎖の失敗を偽装することが可能になってしまっているからです。
しかし、紙版ではちょっとだけ効果が異なり、成功の場合のクリーチャー踏み倒しが任意になっています。そのため、あえてクリーチャーを出さないというプレイングが仕様で可能と、先ほどのポジトロン式になっており、その辺りの処理に矛盾が起きなくなっています。
デュエプレでは成功の場合は強制のためにおかしなことになっていますが、紙版の処理に沿えば問題はありませんね。
このコーナーで最後に紹介するのはアルメリックです。

このクリーチャーが干渉するのは山札ではなくシールドなのですが、非公開領域をイジるという点で今までのカードと同様のものとして扱います。
このカードの効果をわかりやすく書くと、攻撃時にシールドを見て、それがSトリガーであれば使うか手札に戻すかを選択し、Sトリガーでなければそのままシールドゾーンに戻す、というもの。
相手にカードを公開せずに処理が進行し、Sトリガーであっても使わなければ、特に公開することなく手札に加えることができます。
ん?
呪文を使うならまだいい。結果的にカードの内容が公開されるわけだから。
でも手札に加えたら、お前それが本当にSトリガーかどうか相手からはわかんなくない?
なにかおかしなことになっている気がします。ここで一旦紙版の確認をしましょう。

自分のクリーチャーが攻撃する時、カード名をひとつ選んで言う。その後、自分のシールドを1枚見る。そのシールドの中に選んだカードがあれば、相手に見せ、そのシールドを手札に加えてもよい。そうした場合、自分の山札の上から2枚を裏向きのまま、それぞれ新しいシールドとして自分のシールドゾーンに加える。
紙版ではガッツリ相手に見せてるじゃねえか!
他と違って見るのが山札ではなくシールドだからなのか、厳密にテキスト通りだと呪文を使用することがおまけとなっているからか。
アルメリックお前…どうなってるんだ…?
『表向き』の良いところ
アルメリックのことは一旦忘れて。
最後に、表向きにすることをデメリット効果と捉えた上で、『表向き』を持つ自分が好きなカードについて語ろうと思います。
それは、アクアンとプリズム・ブレインです。

4コストで最大3枚ドローが可能という強烈なドローソースで、かつて5Cコントロールが環境を跋扈した際に採用されていたカードです。
もはや語る必要もないほどに強力なカードですが、これがなかなかよくできていて。
2つのカードは共通して、引いたカードを相手に公開しなければならないという特徴があります。
当時は、ゲキメツやアガピトス全盛期(よく知らない方は、とんでもないバランスブレイカーがいたと思ってください)。
彼らを上手く使うということは、同時に彼らに対する除去札関連の読み合いを制するということでもありました。
アクアンとプリズムブレインは引いたカードを相手に公開するため、使われた側はそれらのカードによって大量のドローを許したとしても、手札の中のゲキメツや除去札の有無をある程度把握することができました。この情報とその後の展開を基に、プレイングの判断をしていました。
特にプリズムブレインは、最後に追加で引く1枚は非公開になります。3枚中2枚は公開、でも1枚は非公開。これが個人的にとても面白かったのです。
システムが処理してくれる以上、『カードを表向きにする』ことの必要性はありませんが、表向きの処理があることで、読み合いの面白さが格段に増していたと思います。
筆者は表向きにする効果はデメリット効果の意味しかないと考えています。しかし、アクアンとプリズムブレインの例から、表向きにすることはゲーム性の要素の一つになり得るという肯定的な捉え方もしています。
終わりに
ということで、バルカディアスチャージャーの不満点と、カードを表向きにするという処理の考察?でした。
『表向き』を、みなさんはどのように感じましたか?
デュエプレ特有の処理である『探索』が考察されているシーンはよく見かけますが、この『表向き』に関する考察ももっと盛り上がるといいな~と思っています。
特に今弾ではアルメリックとかいうわけのわからんカードも実装されました。
もしかしたら、『表向き』という処理を運営が既にデメリット効果として認識していて、アルメリックはそれゆえの8コストという重さ・・・なんて考えると楽しいです。
今後の『表向き』界の動向には要注目ですね。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
バカチャ上方修正運動の署名の方も忘れずにお願いします(嘘です)。
