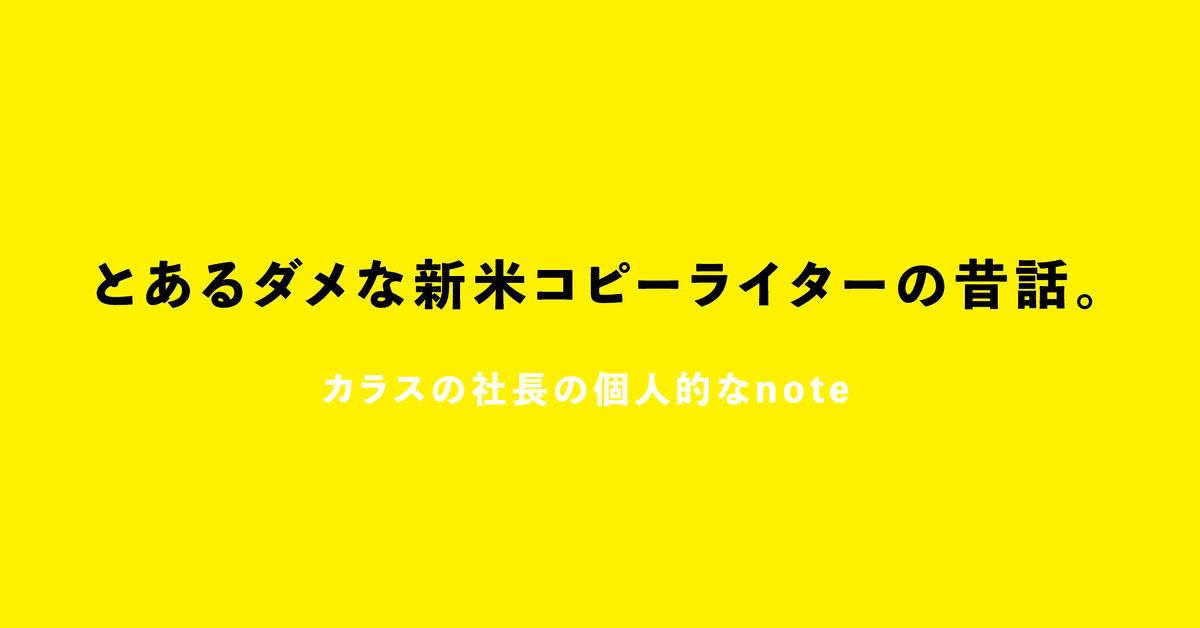
とあるダメな新米コピーライターの昔話。
先日、博報堂の先輩と飲みながら「昔話」をした。とある「コピーのかけないコピーライターの話」だ。
そのコピーライターは、本当にダメなコピーライターだった。広告のイロハもわからず、きちんとした文章を書く訓練もされていない。出身が理系だったからか「間違ってはいないが、おもしろくもない」そういうやつだ。
そんな中、新規プロジェクトが始まった。上司のCDが言った。「この仕事はお前がメインのコピーライターをやれ」まだ入社2年目のそのコピーライターにとって、始めてメインをつとめる仕事だった。そいつはとても喜んだ。半人前から、一人前になったような気がしたのだろう。その仕事に全身全霊でとりくんだ。実際に眠る時間も家に帰る時間も惜しんで、コピーを書いた。
彼には何も書けなかった。気の利いたキャッチコピーも、深みのあるボディコピーも書けなかった。PCと紙とを交互に向かい合って書いたりしていたけど、しっくりくる何かを書くことができなかった。しかし書けなかろうが、締め切りはきちんとやってくる。いくら努力をしても時間は待ってはくれない。
そしてクライアントにコピーを提案する日が来ても、社内のみんな(営業、CD、アートディレクターの方々)が、納得するものを書くことはできなかった。
提案の日時になってもコピーはない。営業の人たちは、何も持たずにクライアントへ行き「うちのコピーライターが頑張っているから、もう少し待ってほしい」と言いに行ってくれた。しかもそれが2,3回つづいた。いつまでも、そのコピーライターがコピーを書けないがために、営業はただただ謝るためだけにクライアントへ足を運んでくれた。
でも広告の出稿の時期だけは絶対にズラすわけにはいかない。営業の人たちは「二年目のあいつだけじゃ足りない。もっと経験のあるコピーライターをいれるべきだ」とCD(クリエイティブ・ディレクター)に掛け合った。博報堂の営業はプロジェクトマネジメントが仕事だから当たり前の判断だった。しかし上司であるCDは首を縦にはふらない。「大丈夫、あいつならできるからこのメンバーでやる」と最後まで言っていた。
コピーライターは締め切りの直前まで、コピーを書きつづけた。しかし終ぞ、みんなが納得するコピーを書くことはできなかった。結局、締め切りの直前に、上司のCDやADが書き直しをして、それをデザインに反映させて提案した。上司が書き直したボディコピーは、新米コピーライターがつくるより格段によくなっていた。
広告は無事に完成し、世の中にもきちんと出た。それはとてもいい広告だったと思うけど、僕はその広告をみて「自分がやった仕事だ」なんてことは決して思えないものだった。この仕事で、初めて泣いた。悔しくて泣いたのなんて、高校の部活の試合で負けたとき以来だったかもしれない。
そんな昔話を、営業の先輩と二人で飲みながら話をしたら、また泣きそうになった。
あるところにコピーの書けないコピーライターがいた。それでもできると信じて、成長を見込んで、仕事を任せてくれた上司がいて、クライアントに迷惑をかけても謝りにだけいってくれた営業の人たちがいた。本当に、本当にかっこいい上司たちだった。
実はいま、その頃の上司と僕はほぼ同い年になっている。
本当にすばらしい場所にいたんだな、と最近になってつくづく思う。
あの頃の恩を、今も返せていない。それをいつか返せるようにがんばろうと思うけれど、まだその見通しもない。だけど、今もあのときの背中を追いかけて、仕事をしています。
ありがとうございました。本当に。
