
THE NEW COOL NOTER賞~小説講座 第4回「文章のリズムと、言葉の統一について」
THE NEW COOL NOTERコンテストに参加いただいている皆様。
ならびにみこちゃん出版を応援いただいている皆様。
赤星先生の「小説作法(文章作法)」について、第4回「文章のリズムと、言葉の統一について」をおくらせていただきます。
文章のリズム~改行の活用
昔、特命リサーチだったか、トリビアの泉だったか、実験系・調査系のテレビ番組で、こんな話を聞いたことを覚えています。
曰く、バイキングにおいて、一度に大量の食事を机に持ってきすぎてしまうと、人間の脳はそれを「見ているだけでお腹いっぱいになってしまう」とのこと。
元を取るぞ! などと意気込みすぎてしまうと、そういうところにまで、気が回らなくなってしまう。机の上が料理でいっぱいで、さらにそれを食べなきゃという義務感を自ら生じさせてしまうと、げんなり感をこえて苦痛すら生じさせえます。
なので、バイキングなどで楽しく食べるコツは、
「次は何を食べようかな」
という期待をしながら、少しずつ小分けで取ってくること……だそうです。
小説や、文章による表現もまた同じと考えます。
一度に、目の前に巨大な塊のような文章が、ずでどどん、と現れたら、まず読んでみようと思う前にそれだけで読者は「お腹がいっぱい」になってしまう。
それを避けるために、「文章作法」として、段落の冒頭は一マス開けるだとか、改行を活用する――というものがあります。
すべては、少しでも読者にとって読みやすくさせるための工夫。
読者の、
「次はどんな文章が続くのか?」
という期待を維持しながら、読み進めさせ、あなたの文章の中身や物語の流れ、キャラクターの心象などにストレスと違和感なく入っていかせるためのものとなります。
過去の講座で、一奥が各種の記号を「無意識レベルで読者に働きかける標識」と言ったのは、この意味においてです。
すると、この記事の文章でも当たり前に扱われている「改行」について、さらにKindle版を今お読みであれば、「行間」について、工夫が見えてくると思います。
noteで記事を執筆したことがある方は、わかるかと思いますが、他のブログ等と異なりデフォルトの設定では、Enterキーを押した時の改行幅が、かなり広く取られています。(ほとんど1行分)
同じ「幅」つまり「余白」を、Wordなどの文章ソフトで取ろうとしたら、まるまる1行追加で「改行」しないといけないでしょう。
そしてKindle版の本記事を読んでいる場合は、一奥が「Google Document」によって、この改行や行間の余白のテイストを、note記事版に近づけるために行間の設定を行っている……ということが想像できようかと思います。
たかが改行。
然れど、改行。
他の読者にとっての標識となる記号達と同じく、そして時にはその記号達以上に、まるで息を吸って吐く呼吸のように、意識しなければあまりにも当たり前に行う自然な身体動作であるかのように。
改行は、最も基本的なレベルで文章の読みやすさを左右します。
基本にして奥義、と言い換えても過言ではないかもしれません。
みこちゃんが赤星先生の長編小説をKindle化する際に、重点的に力を入れた箇所もまた、改行(空行)入れなのです。
以下、2作の著作が、その、実践となります。
是非、お読みいただく際には、空行(行間)に込められた精密な計算を、意識して読んでみると、書く者として心がけるべき参考が、いくつも潜んでいることでしょう。

文章のリズム~言葉の統一(ゆらぎの統一)
読者が読み進めながら、違和感が生じないように、スムーズに内容の理解を導くのが文章の役割です。
そして、その文章の読み進め方に無意識レベルで、まるで標識のように働きかけるものに、記号などがあり、そして「言葉の統一」というものがあります。
これは、いうなれば「その文章(小説)におけるマイナールール」のようなものです。
たとえば、1つの小説の中で、主人公が食事をする場面が何度か出てきたとしましょう。
それが場面ごとに、次のようになっていたとしたらどうでしょうか。
例)
① あの店のカツ丼は美味かった。
② 昨日食べたそばは旨かった。
③ 妻がビールのつまみに出してくれた枝豆がとてもうまかった。
ちょっと固い文章を書く仕事の方でしたら、他の例として「および」と「及び」や、「また」と「又」が混在するような文章も、イメージしていただければと思います。
同じ「(味が)美味い」という表現に対して、1つの小説の中で、3種類の表現が使われています。確かに、どれも日本語的に間違ってはいません。
しかし、読者にとって無意識レベルでの混乱を、わずかではありますが引き起こします。文章全体でそのわずかが積み重なれば、それは大きな違和感につながりかねません。
どういうことかというと、上の例文で言うならば、①の段階で読者は無意識に「この小説の作者は、料理などの味がよかったことを<美味い>と書く」ということを無意識に刷り込まれている。
ところが、読み進めていって②や③が出てくると、その前提が崩れてしまいます。
そこに混乱が起きるわけです。
日本語の標識を見ながら旅をしていたと思ったら、突然、英語や中国語の標識が出てきた(たとえ意味が同じものであったとしても)ようなものです。
確かに、文法や漢字表現として間違っているものではないとしても、①~③に法則性もなにもなく、その場の感覚だけで書かれている場合は、読者が混乱することは必至。
ちなみに、これは「表記の揺れ」と呼ばれるもので、Wordなどの文章ソフトでは、統一のための校正機能もあるぐらい、メジャーな文章作法の一つです。
一奥の経験で言えば、「なに」と「何」も、油断すると混ぜがちですね。
あと、何気ないものとしては、算用数字と漢数字の使い分け、もあるでしょう。
明らかに算用数字で表現しなければならないもの、漢数字で表現しなければならないものを除いて、たとえば同じ小説内に、
「一番目」
という表記と、
「1番目」
という表記が混在している場合、読者には統一感が無い印象を与えかねません。
それをあえてそうしている、明確な理由、つまりその小説における「読み方のルール」として、その言葉をちゃんとわけて使う理由があるならばともかく……。
いえ。
仮に理由があったとしても、その「理由」なるものについて、読者にまさか、小説を読む前に「この言葉はこういう意味であーる」といった用語集を延々読ませるわけには、いきますまい。
(そういうのは、製品説明書や法律の条文で「お腹いっぱい」です)
ひとたび、そう書いてしまえば、読者は「そういうもの」としてすでに読む頭になっている。
あとから修正するのであれば、最初から、表記を統一することを意識して書くか、または最後に全体を校正する際に、しっかりと潰していかなければなりません。
……といっても、プロの「校正」のお仕事が存在しているぐらい、これは、プロの小説家の方々であってもつきまとう、悩ましい問題ではあります。

文章のリズム~同音語
前項のリズムが「同意義語」として、つまり同じ意味を表す複数の言葉の”表記の仕方”であるならば――つまり視覚的な混乱――この項で述べるのは、聴覚的な混乱についてです。
例文を出しましょう。
例)
「カフェに着いたら、君に憑いている霊について教えるから、ついてきて」
いかがでしょうか。
「ついて(た)」という、確かに意味は異なりますが、同じ”音”が連続してしますが……読みにくいですね。
なので、読む側からすると「視覚的」には、そこまで違和感はぱっと見無いのですが――頭の中で「音」として認識した時に、どうも、できの悪いラップを聞かされているような違和感を覚えます。
わざと、韻や平仄を意識して計算して作った文章とも違います。
これもまた、無意識レベルで読者にとっての「スムーズな読み進め」を阻害してしまう要素なので、気付き次第、潰していきたいところです。
主には、異なる表現(同義語)を駆使することとなるでしょう。
上の例文では、たとえばこんな改稿が考えられます。
例)
「カフェに着いたら、君を悩ませている霊の正体を教えるから、一緒にきて」
文意はほとんど同じです。
しかし、連続する「ついて(た)」が解消され、音としては違和感がなくなったかと思います。
また、場合によっては、思い切って音が重複しているものをカットしてしまうのも手です。
例)
「カフェに着いたら、その霊について教えるから」
目的は、あくまでも読者がスムーズに読めるように。
その意味で「音」という要素もあることは、意外な盲点となっているかもしれないので、時折、自分の文章を声に出して読んでみることもおすすめです。
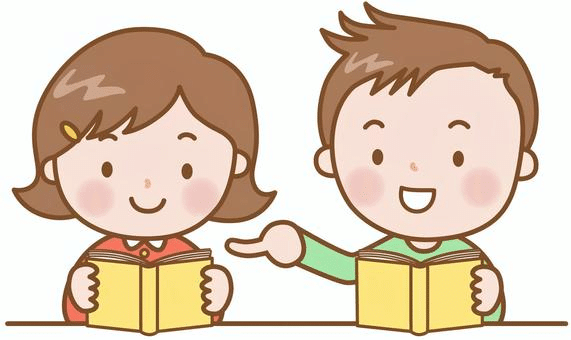
文章のリズム~文章表現を変えるということ
いきなりですが、一奥は「類語辞典」が大好きです。
それはもう、一度見だしたら止まらず、いつまでも読んでいられるぐらい、大好きです。
ネット上でも調べられますが――例えば「成長する」という言葉を、類語辞典で調べてみましょう。(Weblioより)

これだけの意味が出てきましたね。
――つまり、逆に言えば「成長する」という言葉を聞いて、これだけのものを連想する人がいるということです。
上の中からいうと、「発展する」と「円熟味が出る」とでは、まるっきり別の表現に思えます。
しかし実は「成長する」という語を仲立ちとして、言葉の意味として、はっきりと重なっている部分が、ある。
言い換えれば、言葉の意味として、重なっていない部分もある。
”同じ”と”違う”。
一見すると同じような表現であっても、そこにはわずかなニュアンスの違いが現れています。
一口に「○○は成長したのだ」という文章を書こうとしても、その背景や、前後の文脈や経緯、物語全体の流れの中から、その「成長した」で表したい万感は、まったく異なってくるはずです。
こういう時に、類義語に意識を向ける感性が、小説家として最も大切な部分の一つに資することに気づくことができます。
……また別の例を出しましょう。
欧米人は虹を「3~4色」でしか認識していないそうです。
他方、我々日本人は「7色」であると当たり前に認識しています――特に「青」に関する感性が、我々は鋭いようですね。
……さらに別の例を出しましょう。
北米先住民であるイヌイット達には、「雪」を表す言葉が、我々の何十倍も存在するようです。
いずれも、一奥が言いたいのは、同じように見えてそこに細かな差異があり、そしてその細かな差異を表現する、異なる言葉がある、ということです。
小説はキャラクターを描くものなので、喜怒哀楽といった感情を描くことも多いでしょう。
ですが、ことあるごとに「○○は笑った」と繰り返し表現した場合、本稿で前述した「ゆらぎ」と「同音語」の問題が同時に出てきてしまいますね?
――読者の中で「笑った」がゲシュタルト崩壊してしまうのです。
主人公が、よろこびのあまり笑ったのか。
ヒロインが、感動のあまり涙を流しながら笑ったのか。
悪役が、思惑が当たりそうで興奮のあまり笑ったのか。
それぞれ「同じ」笑ったという状況ですが、その文脈が全く異なっている。
小説って、そういう細かな違い、機微を描き分けるものなのではないでしょうか。
本講座は、文章作法の観点から論じさせていただいているので、表現論には立ち入りません。
しかし、読者にとって読みやすく、違和感なく、スムーズに読み進めさせる「標識」という意味では、それぞれまったく背後の異なるものであるはずの「笑った」を、ことあるごとに「○○は笑った」と繰り返すことは――端的に、読みにくい文章となります。
よく語彙力と言われますが、実は、語彙力が求められるのはこういう理由です。必ずしも、難しい表現を知っていればよい、というものではない。
7色としなければ表現できない、我々の眼(まなこ)に映る、虹という自然現象の中での細かな違いが確かにあって、そこには、
「red、yellow、green、blue!」
という単純な4色表現では、決して表し得ないなにかが込められているのです。
「同じもの」を「違う表現」で表すということ。
たとえば上の例で言えば、次のように書くことが考えられます。
主人公は、よろこびのあまり歓声をあげた。
ヒロインは、囚われの身から解放された感激のあまり、泣き笑うように嗚咽をもらしていた。
悪役は、全てがうまくいっていることに口の端を歪め、低い声で満足気にうなった。
ここに、小説の神髄の一つがあると一奥は考えます。
ぱっと上手く表現できない、なんだかもやっとした、しかし、なんとか表現したいと若干の焦燥感すら覚えるような、そういう、もどかしい感情。
それを表す言葉を見つけるために、その間隔を読者に伝えんと紡ぐ、そんな表現を編みだすために、古の文豪達は、命を削って言葉を探求してきたのだと思うのです。
その”感覚”は、作者本人にとってはあえて言葉で無理に表現する必要なく、今この瞬間自分自身の身体の中にあるので、自分にだけわかるようにするならば、別に同じ言葉を繰り返してもよい。
同じ言葉を使っているように見えて、それを書いた時の感覚、その微細な違いは、作者自身にとっては、思い出されやすい身体感覚ですから。
でも、読者は違う。
あなたの小説や文章を初めて読んだ読者には、その”感覚”は、まだ、ありません。
読者のために書く、というのは実はこういう意味です。
まだ、書いている最中では、あなた以外に誰も知らない、その”感覚”を、言葉の力によって読者に伝えなければならない。
ゆえに、読みにくさをいろいろな手立てで排除するのは当然のこととして、それすらも大前提として。
その物語を通して、読者に伝えねばならないものがあって――それを、丁寧に、全力で描こうと思えばこそ、同じように見えて実は違う、そんなものを表現する「言葉」を欲する。
一奥が類語辞典が好きなのは、それが理由です。
「成長する」「笑う」「虹」「雪」という、知っていたはずの言葉の、それぞれのまた異なる側面を知る。
それは、知識欲ではありません。
類語を通して「そんな一面があったのか!」と驚く感覚が、実は、書く者として常に書き表したいと思う、この「もやもや」したものに、うまい表現が見つかった時の、あの爽快感にとても近いからです。
「神は細部に宿れり」という言葉がありますが、そこに、作者として作品と、そして作品を通して読者と向き合うということの中での、とても大切なものがあると考えます。
以上。
次回で文章作法講座は、最後となります。

