
其ノ11「豊幡神社のおサンキンの疣(いぼ)ン神様」鳥居⛩めぐる
近道をしようといつも通る道のひとつ手前で曲がったら、見事に道に迷ってしまった。
キョロキョロしていると、目の前にハッとする一軒家があった。
屋根がとんがり帽子を平たくした形で、窓がとても大きい。
芝生は青々として、それらを取り囲む植物が生き生きとしている。
ヘアーサロンだった。

それから13年ずっとお世話になっている。
だいたい月一回。
しかし予約がとれないときもある。
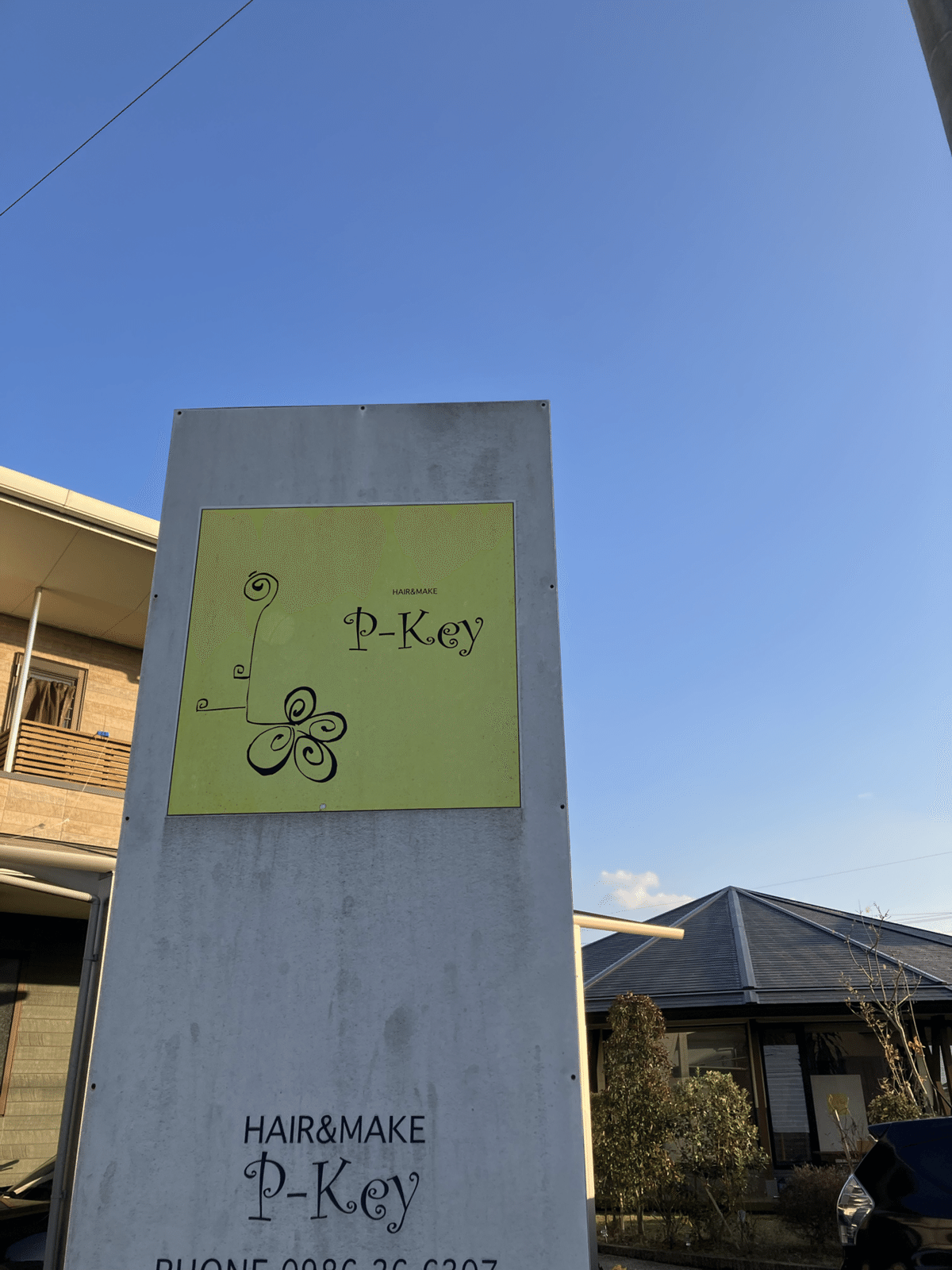
この看板と口コミ、紹介、道に迷って出会う人のみ。しかし、いつも予約でいっぱいだ。
高い天井、13年前からある観葉植物が、太陽をめざしてまっすぐとのびる。

その時から天に向かっている。
今年は龍神といっしょに向かう🐉
大きな窓から光が入り、太陽の光の粒子に乗って、妖精が楽しそうにクルクル踊る。
キラキラ光って解放感で満ちている。

この空間にこころが落ち着く。
そして、五感のすべてが癒される。
月1回の貴重な時間になる。

右は姉のミケさん(仮名)


ここは、居心地が良いため、あらゆる分野の情報と、いろいろなものがひ引き寄せられてくる。

突然道に迷ったのか、イボの神様が来られた。
美容師のミケさんの長男南くん(仮名)の足にできたイボを見事に取ったおサンキンの疣(いぼ)ン神様だった。

宮崎県都城市庄内町にある豊幡(とよはた)神社。同じ敷地には山久院跡(さんきゅういんあと)がある。

山九院跡 北郷資忠夫妻の墓と伝わる五重塔
文和元年(1352年)北郷資忠(ほんごうすけただ:島津本宗家四代島津忠宗の六男)は、観応2年の筑前国金隈合戦(ちくぜんのくにかねのくまかっせん)での軍功によって、足利尊氏から北郷三百町の地(現在の都城市の西部)が与えられた。そして、資忠は薩摩迫(都城市山田町)を居城として、北郷氏を名乗ることなった。のちの都城島津家の誕生となる。山九院は臨済宗で、二厳寺(にごんじ)の末寺であった。北郷氏初代の菩提寺として山田町の薩摩迫に建てられ、後に現在地に移された。
廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)によって廃寺となった跡地に豊幡神社が建てられた。
宮崎県西南部に位置する都城市は、東に鰐塚(わにづか)山系、北西に高千穂の峰を仰ぐ盆地であり、南は鹿児島県に隣接している。
盆地のほぼ中央を約126本の支流からなる大淀川(九州で4番目に長い川)が南から北に流れており、日向灘(ひゅうがなだ)に注いでいる。



産業は、畜産が盛んで、牛、豚、鶏の合計算出額は日本一である。
また、米、サトイモ、サツマイモ、茶などの栽培も盛んである。
国の伝統的工芸品に指定されている「都城大弓」は、200を超す竹弓作りの工程を一人の弓師が手作りで仕上げていく。
江戸時代初期にはその製法が確立されたとされていて、その技は現在に受け継がれている。
県の伝統的工芸品に指定されている「都城木刀」は明治時代から本格化され、霧島山麓に自生しているカシ、イスノキを材料に数十種類のカンナで一刀一刀入念に仕上げていくのが特徴である。
両者とも全国生産量の大半を占めている。
また、日本一の焼酎メーカーもある都城。大地の恵みと霧島裂罅水(きりしまれっかすい)を使用した焼酎は有名である。

「豊幡神社」の祭神は応神天皇である。別名、八幡大神(はちまんおおかみ)。[古事記:品陀和氣命(ほむだわけのみこと) 日本書紀:誉田別尊(ほんだわけのみこと)]
日本各地で親しまれる八幡信仰は、全国に約2万4000社以上はあると言われている。
総本宮は大分県の宇佐神宮である。

第十四代仲哀(ちゅうあい)天皇と神功(じんぐう)皇后の御子である。
古事記によると頻繁に巡行し、領地の視察や婚姻による新たな氏族と繋がるなどの伝説が多く、出世や成功、家運隆昌の象徴として、源氏の氏神にもなっている。


豊幡神社の入口、鳥居を上がる右側にある石塔がおサンキンの疣(いぼ)ン神様である。
「日向の国 諸県の伝説」によると、
「もし手足のイボに悩む者がお参りして自分の年齢と同数の大豆をお供えして祈願すれば、必ずイボは治るという。だが、祈るとき人に見られると治らぬという。」
とある。

豊幡神社の宮司、荒川内福一さんによると、いつ頃、誰によって祀られたのかは不明だという。
しかし、荒川内さんの亡くなられたお母様が、若い頃はあったという。
荒川内さんのお母様は99歳で9年前に亡くなられた。
若い頃を20歳とすると、約80〜90年前から疣ン神様はこの地に祀られていると考えられる。
おサンキンの疣(いぼ)ン神様は、この場所の山九院(さんきゅういん)と疣(いぼ)の神様が、丁寧語と方言と話し言葉で熟成された、地元の人たちに親しまれている呼び名である。

南九州ではところどころに疣(いぼ)の神様が祀られている。
疣(いぼ)は、はるか昔から人類と共存して、ひとびとを悩ませた。
疣(いぼ)の殆どが、ウイルス性である。
生き延びるためにあらゆる手段をつかう。
そして変異を繰り返し強くなる。

疣(いぼ)に感染すると、根治までに時間がかかる。
美容師のミケさんの長男南くんが幼少期のころ、足にできてしまった疣(いぼ)。
その頃、南くんは、毎日のように境内に遊びにきていた。
近くに住む南くんのおじいちゃんとおばあちゃんは、南くんの疣(いぼ)に心を痛めていた。
何とかしなければと決心し、立ち上がる。
疣ン神様へのお祈りは、ほぼ毎日おじいちゃんかおばあちゃんが付き添い、行われた。
多分、人目をさけて、こっそりと。
そして、祈りは疣ン神様を経由して宇宙に届く。
ひとの思いとウイルスの戦いは宇宙レベルに発展する。

豊幡神社の六月灯(夏祭りのことで南九州の神社や寺院でおこなわれる)は、この数年開催されていない。
境内で遊ぶ子どもたちも減ってきた。
時の流れとともに、人々の生活や環境は変わる。
しかし、疣ン神様がこの地に必要とされ、頼られ活躍されていることは変わらない。
そこには、疣ン神様と人々をつなぐ祈りと感謝の気持ちが宇宙の法則でつながっている。

イボは宇宙の彼方に消えた
疣(いぼ)がこの世にある限り、疣ン神様の多忙な日々は続く。

豊幡神社 宮崎県都城市庄内町13933-1
都城市役所より約8.8キロ 車で18分
参考文献
都城市史
都城盆地神社史料集 前田瑞行
南九州の地域形成と境界性 地方史研究協議会
都城市の文化財 都城教育委員会
庄内歴史読本 庄内地区まちづくり協議会
日向の国 諸県の伝説 瀬戸山計佐儀
続 神々の系図 川口謙二 東京美術選書 その他
