
連載 ひのたにの森から~救護の日々⑩人生は出会いとタイミング
御代田太一(社会福祉法人グロー)
遅れてやってきた思春期
高校を卒業した時、福祉のことはこれっぽっちも知らなかった。関心もなかった。
胸を張れるほどの充実した中高時代を過ごしたと思うし、現役で東大に合格できた。身体は丈夫だし、自分の能力次第でこれからどこまでも勝ち上がることができる、そんな自信と上昇志向に満ちていた。
福祉の側に身を置くと多くの人が「いつ自分が障害者になるかなんて誰にも分らない」「親や自分だっていずれ介護が必要な体になる」「だから、福祉はみんなが関心を持ってしかるべきだ」と語るけれど、当時の僕にそんな言葉は全く届かなかったと思う。障害のある人はもちろん、福祉や介護の世界で働く人も別の世界の人だと思っていた。本当だ。
大学に入って1年目は、国際交流系の学生団体の代表も務めた。他のメンバーとオンラインで予定をシェアし、Googleドライブで資料を作りこみ、スーツを着て協賛企業を回った。ハーバード大学を訪れたときは、世界中からやってきた学生たちとボストン市街を歩き、講義を受け、パーティーを楽しんだ。学内では、目立つ方の学生だったかもしれない。

東京大学駒場キャンパス
2年目を迎え、そんな日々もひと段落したころ、予定が丸一か月すっぽりと空いた。そこに偶然、遅れてやってきた思春期がぶつかった。学部を選択する時期である2年生の夏を前に、「あれ、そもそもなんで生きているんだろう?」と考え込んでしまったのだ。
それは普通の人なら、中2くらいの時にぶつかって、中高生活の中で折り合いを付けていくものかもしれない。けれど、そんな悩みがこの世にあることも知らずにハッピーな中高生活を送っていた僕のところに、5~6年遅れてそいつはやってきた。
これまでは自然と与えられた役割を全うして、望まれたように努力すれば、自然と充実した日々が降ってきた。受験勉強もゲーム感覚で楽しめた。
なんとなく理系科目の方が肌に合っていたから理系を選び、理科一類で入学したものの、それだけの理由で工学部や理学部に行くのは違和感があった。数学や物理の講義を何の力みもなく楽しんでいて、授業の後も黒板の前に集まって数式を書いている同級生を見ると「こいつらと勝負しても無駄だ。絶対かなわない」とも思ってしまう。
そういう意味で、学部選択が自分にとって、はじめて自分で何かを選ぶ瞬間だったのかもしれない。それまでは誰かが決めてくれたレールの上を思い切り走っていればよかったし、そのことを意識する必要すらなかった。しかし気付けば、レールの横で立ちすくんでいる自分がいた。
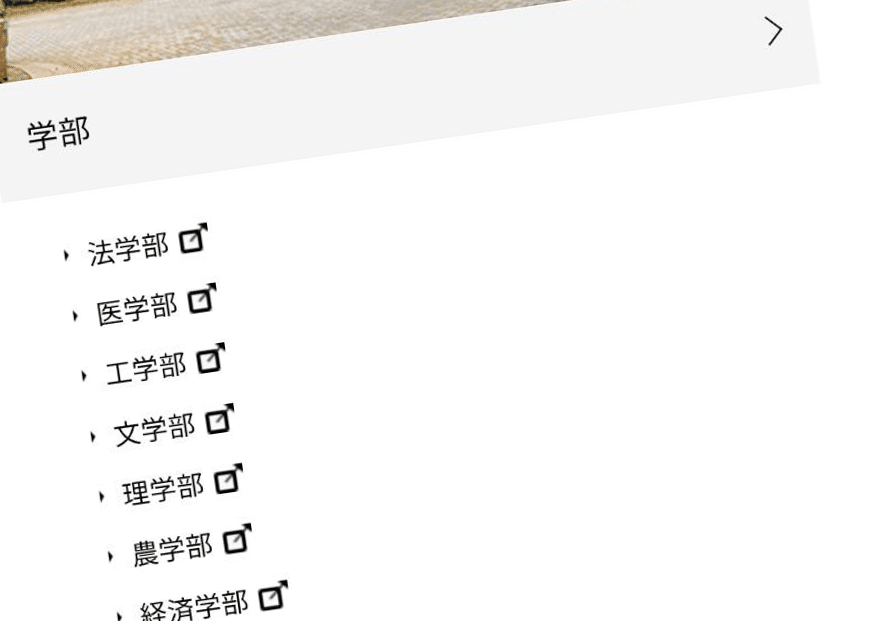
東大の学部の一覧
どの学部に行くべきか。今、どんなことを勉強しておく必要があるのか。それらは就活やキャリア形成においてどんな意味を持つのか。これからの時代は、どんな人材が重宝されるのか。社会の事を全く知らない状態で、あれこれ理屈をこねてみたが、すべて「何かのための何か」だと気づいてしまった。その先を最後までたどっていくと死しかない。
「自分の人生は意味を失ったまま、予定調和的に進むのか…」
「いったい自分は何のために生きているんだろう…」
そんな疑問が湧き上がってくると、全ての理屈が宙に浮いてしまう。レールから外れた途端、走り方さえ分からなくなってしまった。
“障害者”からのボディーブロー
そんな頃、シラバスをめくっていると「障害者のリアルに迫るゼミ」という授業を見つけた。ちょうど木曜日の5時間目は空いていたから、既に何度か講義を終えていていたが、「障害者の話でも聞けば、今の悩みのヒントが見つかるかもしれない。つまらなかったら途中で帰ろう」、そんな気軽な気持ちで講義を覗いた。
壁全面がホワイトボードになっていて、可動式の丸テーブルが並ぶ、新しいタイプの教室だった。
2回目の授業、全盲ろうの福島智さんの授業を強烈に覚えている。
全盲ろうということはつまり、目が全く見えず、耳も全く聞こえない。そんな福島さんが通訳者に手を引かれて、教室に入ってくる。「今教室には何人くらいいますか~?」「最初僕が1時間喋って、そのあと質疑応答ですね~」。授業が始まる前、授業の段取りを運営学生に尋ねる福島先生の甲高い声が教室に響く。
「この人はいったい誰なんだ。目は閉じているけど、耳は聞こえているのか…?」
理解が追い付かない。大学の講義ではあまり感じることのない、座りの悪さがあった。司会の学生が福島さんについて紹介してくれて、どういう障害かは分かった。それでも、やっぱりよく分からない。
福島先生が、少しずつしゃべり始める。
「僕は、3歳の時に目が見えなくなって、18歳の時に耳が聞こえなくなりました。今はこうして喋ることは出来ますが、周りの状況や、皆さんの質問は、通訳者を通じて1文字ずつ指先で伝えてもらわないと分かりません」
ようやく福島さんの置かれている状況が理解できた。音も視界も何もない真っ暗闇の中、指先の振動だけが外部の情報源ということか。「そんなの、生きていると言えるのか」。これが初めて福島さんを前にしたときの正直な感想だ。でも、現に目の前に生きている人がいる。

福島智さん。横に座る通訳者が「指点字」という方法で、福島さんに周囲の会話や状況を1文字ずつ伝える。
福島さんはこれまでの人生や、社会について思うことなど話してくれた。最後に、おもむろに人生の意味について語りだした。
「地球は、暗い宇宙という虚無の空間にただ一つ存在しています。地球が生まれて46億年、175万種類もの生命に溢れている。こう考えると、私たちがいま生きていて、世界や他人を認識していること自体が理屈を超えた奇跡的なことに思えるんですね。」
「人間が存在する『意味がある』とするなら、その意味はまさに存在自体にあるのではないでしょうか。もしそうなら、障害の有無や人種、男女などの差はほとんど無意味なほど、私たちの存在はそれ自体で完結した価値を持っているはずです。」
淡々と語る福島さんと、何事もないかのように時間が過ぎる教室の中で、1人静かな衝撃を受けていた。僕がまさに囚われていた悩みに対する答えを、「障害者」と呼ばれる人が目の前で淡々と語っているのだ。手足が痺れるほどのボディーブローだった。
その後も、様々な障害の当事者が教室にやってきた。
ある回では、知的障害のある若い男性が2人、支援者の牧野賢一さんとともにやってきた。
2人は、支援者のサポートを受けて、これまでの自分の人生をまとめた「自分史」を読み上げてくれた。親との関係が悪かったこと、中学時代から悪さをしていたこと、最近刑務所から出てきたこと、知的障害があると知ったこと、今は支援を受けて充実した毎日を送っている事、1文字ずつ追うように、ゆっくりと読み上げられた。
それを聞く僕たち東大生は、2人と同世代だ。教室の中で、小学校まで同じ学校に通っていたかもしれないような同世代が「知的障害のある人」として話している。妙な居心地の悪さがあった。

牧野賢一さんと若者2人が来た回の教室
その後、ゼミを企画する側に回って活動をつづけた。障害のある人や支援者、家族と、視線がかち合うような距離で対峙する。場を共にすることでこそ生まれる緊張感があった。
透明な檻から抜け出すために
学部は結局、教養学部を選び、哲学や文化人類学、社会学を横断的に勉強する学科に進んだ。入学したときには全く想定していなかった進路だが、納得のいく教授陣と講義だった。
そして人文科学を学べば学ぶほど、ゼミで現れた障害のある人は、不思議と輝いて見えた。人のサポートを受けながら、支援者と様々な関係性を築き、新しい人生観・生活観を獲得しながら、教授や学生が理屈の上で語っている様々な生き方や思想、社会の在り方を、具体的に実現している。当時の僕の目には、そんな風に映ったのだ。
「この人たちは自分より多くの制約の中、力をみなぎらせて生きている。自分の言葉を持っている。自分の足で人生を歩いている。では、お前はどう生きるのか。」
そう自分自身が問われている感覚にもなった。
しかし、就活の波は僕のところにもお構いなしにやってくる。友達の背中を見ながら、憂鬱な気分で就職活動をはじめた。試しに合同説明会(いわゆる“合説”)に行ってみると、大量の企業パンフレットを渡される。カラフルなデザインに横文字が並ぶパンフレットを読めば読むほど、透明な檻に閉じ込められたような、自分の人生がどこか狭い場所に閉ざされてしまったような無力感に包まれた。
そんな虚ろな気分もゼミの講義を受けると晴らすことが出来た。色んな障害のある人が困難を抱えながら、ハッピーとは言えないまでも、自分の言葉で自分の人生を語りながら、自分の足で歩いている。
「生きることは可能性と多様性に満ちている」
「この世界には、学歴社会の物差しでは測れない価値をもつ場所や生き方が確かにある」
「人は本来、力に満ちた存在なんだ。どんな風に生きたってイイ」
そんな風に、ホッとする自分がいた。
社会という大きな存在に飲み込まれてしまうのではないか、という不安もあり1年大学を休学して、福祉の現場を回った。どの現場を訪れても、そこにちゃんと人が生きていた。透明な檻に閉じこめられそうになっている自分の人生を、もう一度自由にするためのカギがあるような気がした。
だから、福祉の現場で働くことを決めた。
もう知ってしまった僕らの時代に
生活費の心配をしたことのない坊ちゃんの悠長な選択と言われてしまえばそれまでだが、やりたいこともないまま大企業に所属して、選択を先延ばししながら、ひとまず競争の中で自分の能力の高さを証明することに心血を注ぐ人生に、勢いよく飛び込むことは出来なかった。
この感覚は、人それぞれ多少の違いはあれども、今の時代の多くの学生に共有されたものだと思う。
バブルと高度経済成長のなかで、大企業を選んできた親の世代とは、恐らく見えているものが違う。もう世の中にフロンティアはないし、劇的な成長もない。大きな会社に入ったからと言ってものすごく幸せになれるわけではないことを、僕らはもう知ってしまっている。
そして、就職の偏差値表だけでは就くべき仕事の順位を決められない時代でもある。起業、スタートアップへの参画、早期の転職、周りの友達を見ても、働き方や稼ぎ方は様々だ。
そんな時代に、学生たちが就職活動の評価軸でしか社会と出会うことが出来ないとすれば、それはあまりに貧しいし勿体ない。
人生は出会いとタイミング
「人生は出会いとタイミング。」
ゼミの顧問をしてくれていた野沢和弘さんがよく言っていた言葉だ。
最初聞いたときは「他人や偶然に身をゆだねるなんて、なんか受け身な生き方じゃないか」と思ったけれど、今なら少しわかる。僕は障害のある人と、あのタイミングで出会ってしまったから、今がある。出会ってなかったなら、想像もつかない別の人生があったんだろう。タイミングが違えば、福島さんの言葉も、斜に構えて受け流せたかもしれない。でもあのタイミングで、出会ってしまった。
期せずしてやってきたこの人生線を生きるしかないけれど、悪くない出会いだった。今はそう思っている。

就職先の滋賀県の施設の近くの風景
つづく
これまでの連載はこちらから!

みよだ たいち
1994年神奈川県横浜市生まれ。東京大学教養学部卒。在学中、「障害者のリアルに迫る」ゼミの運営や、障害者支援の現場実習、高齢者の訪問介護などを体験する。卒業後、滋賀県の社会福祉法人グローに就職し、救護施設「ひのたに園」にて勤務。
