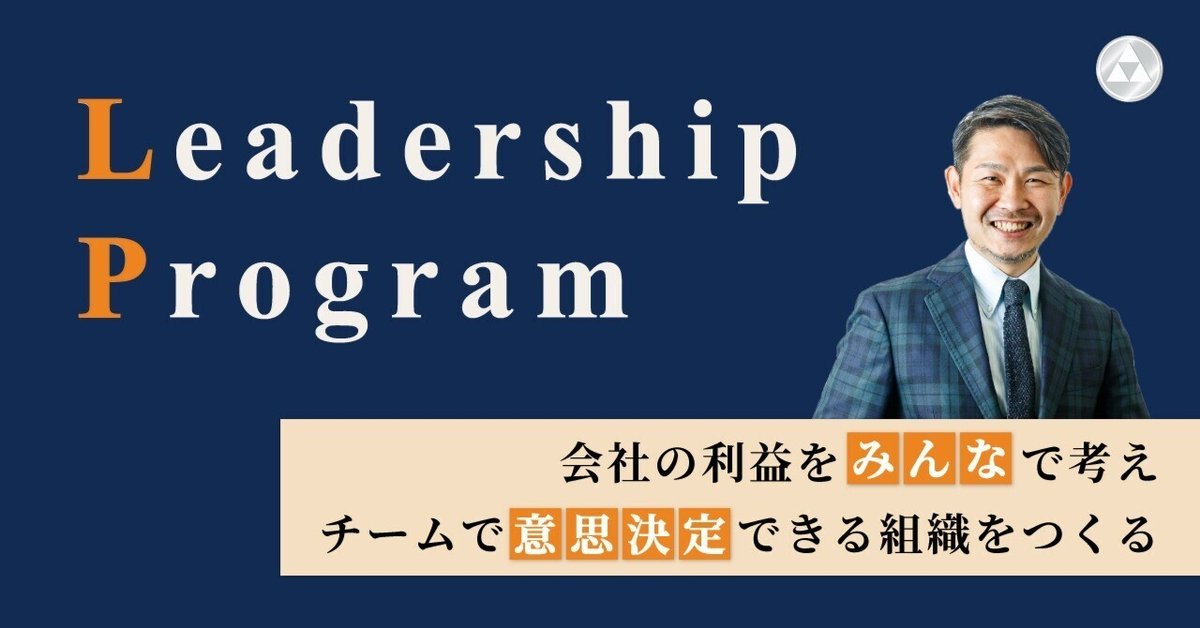
引っ張るだけがリーダーじゃない!?最高のチームづくりとリーダーシップ
ビジネスパーソンの"r5メートル"を対話のある世界に!
対話の専門 田口淳之介です。
いきなりですが…会社で起こる問題はすべてリーダーシップの欠如が原因です。
では、リーダーシップとは何なのか?
この「リーダーシップ」という言葉、ボクはかなり曲者だと感じている。というのも、あまりにも定義が曖昧。また使用される範囲の広さが半端ない。
小学校でも「班のリーダー」なんて使われ方をしますよね。アルバイト先にはバイトリーダーなるものが。業界を牽引するような経営者もリーダーと呼ばれたりする。
リーダーという言葉は「〇〇力」と同じくらい曖昧で、それでいてプレッシャーを感じさせる言葉だと思いませんか?
リーダーという言葉から醸し出されるプレッシャーはどこからやってくるのか?
それは「リーダーは人をまとめなくてはいけない」という、なんとなく漂う意味合いからやってきます。これがリーダーシップという言葉にまとわりつく、世間一般の共通認識ではないかと思うのです。ちなみに、リーダーシップを広辞苑で調べると次のように記載されていました。
①指導者としての地位または任務
②指導者としての資質・能力・力量、統率力 となっている。
広辞苑を読むかぎり、ある意味でどんな使い方も間違ってはいないと言えそうです。(このへんが解釈に幅が生まれる理由なのでしょう。)
リーダーシップとはいったい何なのか?
前置きが長くなりましたが、ズバリ「リーダーシップとは何なのか?」
ボクがこれまで聞いた中で一番しっくりきている言葉は「リーダーシップとは助けの声に反応する力」というもの。
ボクがこの言葉に出会ったのは2017年です。人材育成やチームマネジメントをさらに前進させるために、いつもとは違うアプローチの学習を求めていたボクは、セラピーの学習に取り組みました。
その学びの場で出会った言葉が「リーダーシップとは助けの声に反応する力」という言葉です。
助けの声に反応する力には葛藤を癒やす力があった

「助けの声に反応する力」という言葉に衝撃を受けた最大の理由は「とりこぼしがない」と感じたからです。
「とりこぼしがない」とは、次のような意味です。
一般的にリーダーシップという言葉からは「前進」という意味合いがイメージできると思います。たしかにビジネスシーンにおいて、前進していくその力はとても重要です。
困難にぶつかっても諦めずに進み続けるパワーがなくては、組織ひいてはビジネスそのものが立ち行かなくなってしまいます。
しかし、ボクは経験上知っていました。前進だけを掲げると、必ず「ついていけない」という人が多く出てくることを。
経験したことのある方ならわかると思います。
明るい未来を描き、顧客や仲間の笑顔を胸に抱いて前進し続けていく最中で、大切な人が次々と去っていくあの哀しみがどれほどキツイものか。
キツイのは当然です。なぜなら本末転倒だから。
こうなっては、自分がなんのために仕事しているのかわからなくなります。
「助けの声に反応する力」という言葉を聞いたとき、「前進」という意味と同じくらい「寄り添う」という意味も含まれていると直感で理解できました。
しかし、ボクは次のことも経験上知っていました。リーダーが「寄り添う」ことだけをしていては、組織はとてもヌルい状態になって活力を失うことを。
意欲のある人はヌルい組織を去ります。当然ですよね。低い基準に合わせて働いていても、自分の成長を感じることはできません。
前進のみを掲げれば「ついていけない」という人が。
寄り添うのみを掲げれば「やっていられない」という人が。
この葛藤をクリアにしてくれたのが「助けの声に反応する力」という言葉です。
「助けの声に反応する力」という言葉に出会って「前進する」と「寄り添う」は一つの言葉なのだと考えるようになりました。と、同時にとりこぼしのないこのアイデアをボクは大好きになりました。
そこからさまざまな組織のリーダーを、「助けの声に反応しているのか?していないのか?」という視点で見ると、どんどん気づきが深まっていきました。
そして、人と人は寄り添うからみんなで前進できると考えるようになったのです。
ビジネスシーンにおいてのリーダーシップの発揮
「助けの声に反応する力」とはビジネスにおいて、市場・顧客・上司・部下・ビジネスパートナーに活用できます。
サービスや顧客に向けて、助けの声に反応する力を発揮できれば、売れる新サービスやフォローアップの仕組みを開発できます。
上司や仲間に向けて、助けの声に反応する力を発揮できれば、ビジョンの共有をベースとした人材を育成できます。またチームマネジメントにおいては、心理的安全性を確保し生産性の高いチームを創造することも可能。
ビジネスパートナーとは対等性をもった関係性を構築し、助け合うことが可能になります。
状況や時代で望まれるリーダーシップが異なる理由
リーダーシップには、さまざまな意味合いがあります。
読者の中には「とはいえ、やっぱりリーダーは強くてみんなを鼓舞するのだ」と思う方もいらっしゃると思います。
また「助けの声に反応する力をもつ」という意味がいまいち「ピン!」とこない方も少なからずいらっしゃると思うのです。
ボクは、そう思われている方がいても当然だと思います。
というのも「リーダー」というのは状況が生み出すものだと思うからです。
もしくは状況を「時代」と言い換えてもいいかもしれません。
たとえば戦後すぐの日本であがった「助けての声」と、令和の時代に聞こえてくる「助けての声」は異なるからです。つまり、リーダーシップとは助けの声によってつくられるものとも言えます。
ビジネスパーソンは実務の中で生きている
「リーダーシップとは助けの声に反応する力」という言葉、あなたはどう感じましたか?
こんな記事を書いておいてなんですが、ボクはリーダー論にたいして興味はありません。いや、さらに正確に言うならば、論じることに興味がないのだと思います。
「リーダとは〇〇だ」なんていくら論じても、仲間や顧客が笑顔になっていないなら。そして、なによりもリーダー自身が笑顔になっていないのなら、そこに意味を感じることができないのです。
ビジネスパーソンはみんな、実務の中に生きている。
ボクはこう思っています。
そして、実務の中には耳をすまさなければ聞こえない、助けの声がたくさんあります。
「声になっていない声を聴く」
そんな力を身につけていくことが、リーダーに求められていると感じています。
まとめ

経営層がリーダーシップを発揮するための研修、【リーダーシップ・プログラム】を全国の中小企業様に提供しています。
助けの声に反応できる力をビジネスシーンにおいて発揮する経営層が一人でも増えたら、ボクはとても嬉しい。なぜなら、経営層が組織を起点に業界や地域に与えるポジティブな影響は、それは大きなものだから。
リーダーシップの発揮を目指す経営層と、さらなる出会いを楽しみにしています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
対話の専門家 公式LINEでは
さらに深い情報提供&コミュニケーションがとれます。
ぜひご登録を🙌


\絶賛発売中!こちらもよろしくお願い致します🙌/
\楽天でもご購入いただけます👇/
\リーダーシップ・プログラムが目指す組織のあり方・オススメ書籍/
#対話の専門家
#リーダーのための対話の方程式
#リーダーシッププログラム
#エンパワーメント
#経営者
#幹部
#中小企業
#対話
#コミュニケーション
#リーダーシップ
#幹部育成
#組織改革
#チームマネジメント
#中小企業の経営
#部下育成
