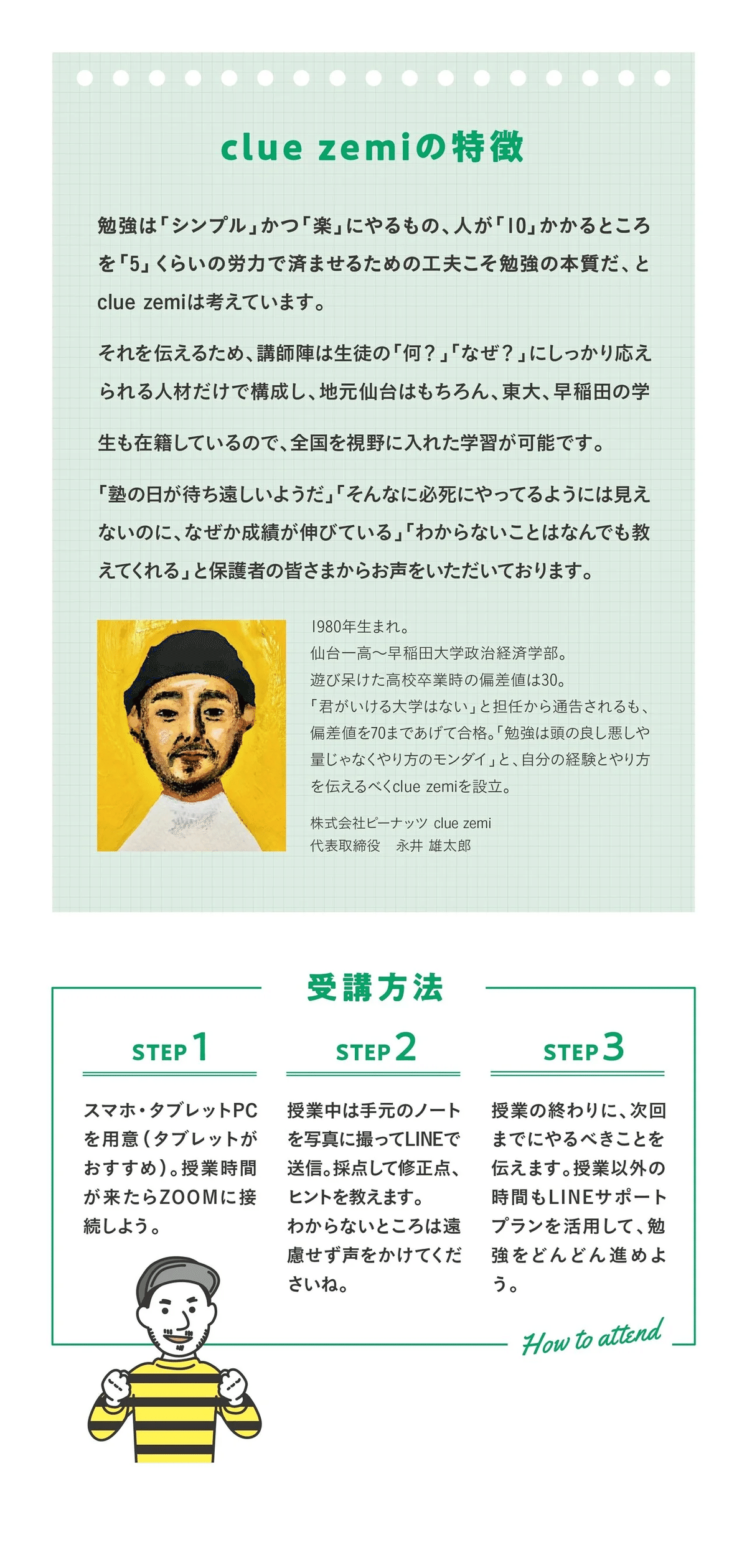理系上位校への道 演習書編(社会・国語・英語)
こんにちは。今回は社会、国語、英語の演習書についてです。
大前提として、社会と国語はセンター試験でしか使いませんでした。そのため、記述形式での勉強は…しました。特に、国語の古典はそもそもの内容が分かっていないからには選択肢を見ても何一つ分からないので、その分を詰めるために記述問題(特に文法書や単語帳にあるもの)をしました。実際の読解問題に関しては、現代文・古典どちらも演習書の問題を解くというよりは1,2年の時は学校の課題、3年に入ってからは過去問でやっていたので、特にこれといった演習書は買っていません。
社会はマーク中心だったものの苦手とはいえなかったので学校の課題以外はやっていなかった記憶があります。そのため、追加で演習書は買っていませんでした。
最後に英語です。これは演習書だけでは効果が分からない教科であった記憶があります。学校で渡されたものは、リスニングの冊子(センター用)、英作文の冊子、長文の冊子の3種という具合です。リスニングは過去問と模擬試験で伸ばした記憶があるので今回は飛ばします。英作文の冊子はそもそもの文構造の理解や単語帳・文法書で理解したことをきちんと組み立てられるか、というものなので、実際の試験で英作文をしない人でもやるべきではないかな、と個人的に思っています。また、長文はほとんどの入試でお世話になる形式なので(嫌悪感があっても)多くこなす必要があると思っています。とはいえ、突然1000語の文を読もうとすると頓挫するので最初は200語くらいのものから始めるのが(英弱なりのイチ意見として)適切なのではないかと考えられます。
具体的に英語のおすすめの問題集は何かと言われれば「そんなもの自分で読んで合うものを探して下さい」の一言につきますが、読解では旺文社の『基礎問題精講』が骨太でおすすめです。(筆者は『標準問題精講』を使いましたがマジで難しく意訳が多すぎるのでおすすめしません。)
と、ここまでが演習書の使い方についてでした。演習書マニアや多くの本を使った人ではないのでそんなに多くを紹介できるわけではありません。それではまた次回!過去問の使い方についてです!


clue zemi の詳細・お問い合わせはこちら↓